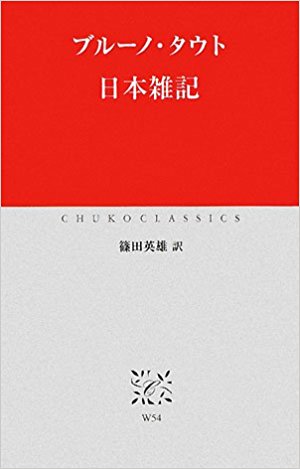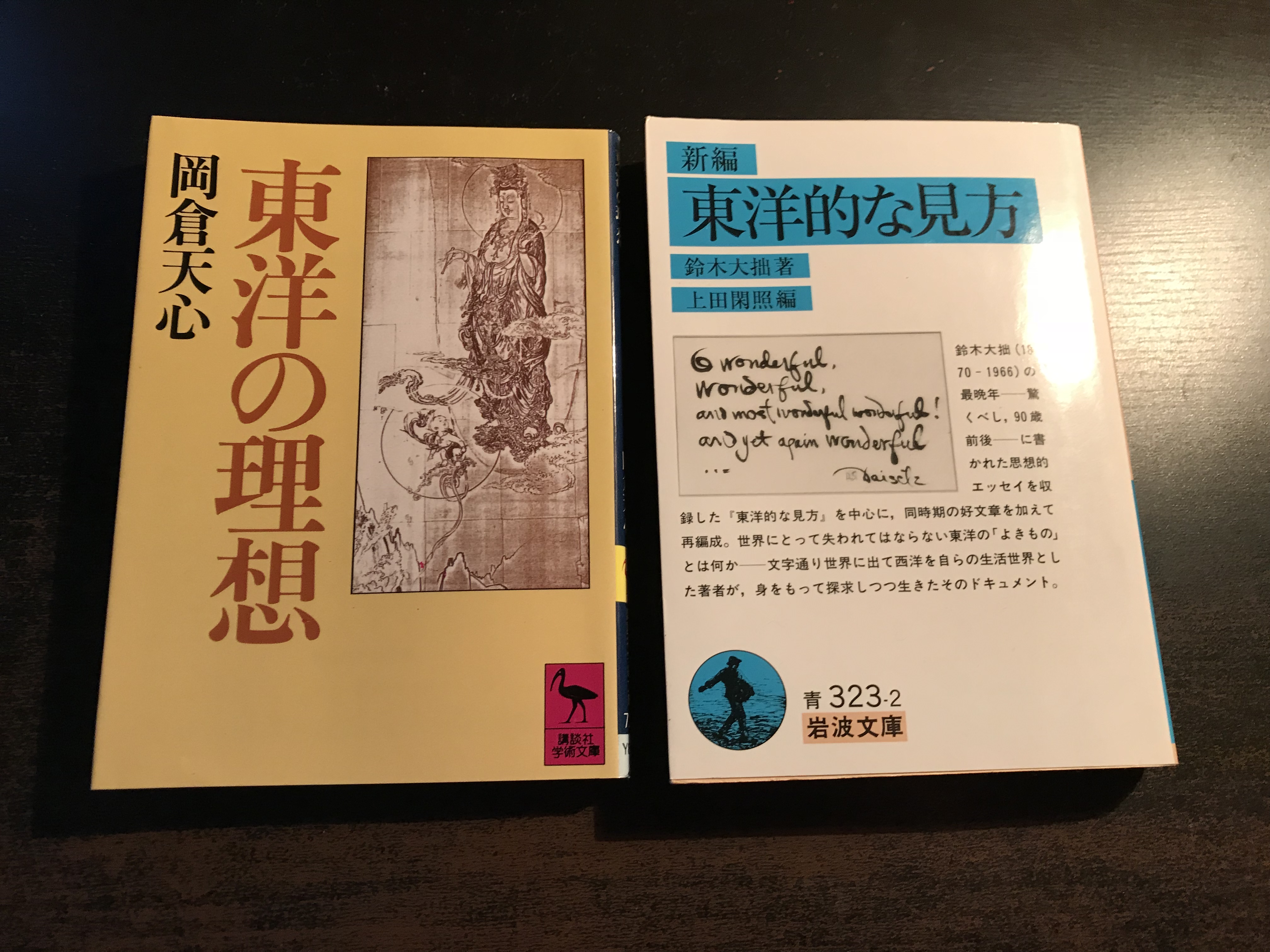最後に映画館に行ったのは、一体いつだったのか。
記憶がセピア色にもならないくらい、沈澱し忘却している。
テレビが普及する前の、映画館が生活の一部になっていた時代に生きていた人たちを、
時々羨ましく思うときがある。
それはなぜか。一言でいえば、その時代は日本映画の黄金期を迎えていたから。
代表的な映画監督を挙げれば、溝口、黒澤、小津。この三人はご存じの方も多いと思われる。
ぼくは昭和末期に生まれているのだけれど、その映画館世代の方は、感極まるものがあるだろ
うと予想する。
その代表的な三人の他にも、成瀬巳喜男、小林正樹、岡本喜八、鈴木清順、新藤兼人なども、
世代は違えど個性的で才能あふれ、すばらしい。
現在はどうだろうか?ご想像にお任せする。
本書は日経新聞の1968年から続く美術連載コラム「美の美」を加筆し、まとめた構成で、
日本映画黄金時代の代表的な監督三人を論じた良書。
文章も上手く、リズムが良く、読み応えがあり、綺麗にまとまっていて読みやすい。
映画とはフィルムに焼きつけられた一秒二十四コマ(トーキーの場合。サイレントは十六~
十八コマが主流)の写真の連続にすぎない。
『1秒24コマの美 黒澤明・小津安二郎・溝口健二』 古賀重樹
本書のタイトルはそういう意味。
ぼくが手にとって読んだ理由は、この御三方は何に興味を持ち、何を大切にしてきたのか、
その部分が知りたかった。映画の技法とかは二の次。
それぞれの評伝などもたくさん出版されているけれど、端的でわかりやすく、
浅すぎないものを探していた時に出会った。
最初に論じられているのは、黒澤明。
黒澤作品は全部観た。赤ひげまでのモノクロの作品が好きだけど、カラーはちょっと苦手。
ハリウッドの連中が黒澤を評価するのは、荒々しく大胆で、具体的ではっきりしていて、
ますらおに溢れているからだと思われる。
そんな黒澤明ですが、少年時代はいじめられ、青年時代は画家を目指し展覧会などにも
入選するが、挫折。
意外かもしれないが、「負」を背負っていた。それが映画に昇華したのかもしれない。
晩年の黒澤が描いた画コンテを見た、画家の横尾忠則は、
「自由奔放、力強い、生命力に満ちている」、
「みんな具体的に描いている。抽象的なところがなにもない」。
と、べた褒めしているくらいだから、腕は確かだったと思われる。
本書にも画コンテが載っているが、色使いが上手い。独特で引き込まれるし、
素人臭さがない。
「僕はね、ドストエフスキーと同時に芭蕉や蕪村が好きなんです。
ゴーグやロートレックやルオーが好きだと同じくらい、
宗達や玉堂や鉄斎が好きなんだよね」。
「日本人として、日本人が考えていることを、ただ一生懸命に言っているだけであって、
向こうの人の考えに合わせようなんてことは、一つもないんだよね。
国際性というのは、日本人は純粋に日本人の考えていることを、さらけ出せば
いいんですね。それを見て、お互いに理解しあうことが大事でね」。
『黒澤 明 全作品と全生涯』 都築政昭
骨董も好きで、中世の根来塗の漆器、信楽の種籾壺なども収集している。
小津安二郎
小津の映画全部は観ていないけれど、『晩春』、『東京物語』などのモノクロ、
そして、カラー作品を数本観た。
画面に赤が忍び込まれていて印象的だった。小津はやはり赤が好きだったみたい。
ヴィム・ヴェンダースが小津にオマージュを捧げた映画、『東京画』も観たことがあり、
印象的な作品だった。
小津は深川生まれで、関東大震災前の江戸情緒の残る、東京の下町育ち。
少年時代はやんちゃだった。
新しもの好きで、1930年~31年頃に、高額のカメラ、ライカを入手している。
ちなみにライカの名手と呼ばれた木村伊兵衛も、30年にライカA型を購入している。
しかもふたりは、38年に戦地の上海で偶然出会っているから驚きだ。
小津は映画人ということで許可されライカを持って出征し、
木村は従軍カメラマンとして戦地へ。
小津の座右の銘は、
「なんでもないことは流行に従う。重大なことは道徳に従う。芸術のことは自分に従う」。
口癖は、
「安物を粗末に使うな。良いものを大事に使え」。
生涯永井荷風を愛読し、浮世絵もたくさん所有していた。江戸趣味。
小林古径の鮒、岸田劉生の鵠沼風景、富岡鉄斎の掛け軸なども、好んでいた。
「名画の中で昼寝をするのが一番の喜びだ」と、
北鎌倉の自宅で闘病生活を送っている時に語っていたという。
溝口健二
溝口の映画は、
出世作の『滝の白糸』、『虞美人草』、『残菊物語』、『元禄忠臣蔵』、『西鶴一代女』、
『雨月物語』、『山椒大夫』、『近松物語』、『浪華悲歌』、『赤線地帯』。
カラー作品『新・平家物語』、『楊貴妃』を観た。
溝口健二は、湯島生まれ。父の事業が失敗し、姉の寿々は養女に出されて、芸妓に売られ、
家族の生活を支える。
虐げられ、したたかに生きる女性を描くのがうまいのは、姉のことが一因なのかと思われる。
少年時代は芝居や活動写真などを見てまわってすごし、青春時代は江戸趣味に凝り、
寄席にも通っていた。
ドストエフスキー、ゾラ、モーパッサンなどの外国文学、漱石、紅葉、鏡花、荷風なども
読み耽っていた。
『雨月物語』は上田秋成の原作の二編「蛇性の婬」と「浅茅ヶ宿」に、モーパッサンの
『勲章』を取りいれた構成。
四方田犬彦さんの『映画監督 溝口健二』に、詳しく記述されている。
ちなみに、芥川龍之介は小説を書く前に、上田秋成の『雨月物語』を読んでいた。
そんな溝口を、ヌーベルヴァーグの連中が好み、参考にしていたのは有名な話。
「溝口の映画には、各瞬間、各ショットに詩があらわれる」、
「溝口に私淑している。私にとってはバッハやラファエロのような芸術家なんだ」
と、ゴダールが言っている。
この御三方に共通することは、読書家で日本文化に精通し、その高貴な趣味がある。
それらが映画にもあらわれ、世界の巨匠といわれる人たちも、無意識にその部分に
惹かれるのではないのか。
技術云々という話以前に、このことを忘れているから、
映画がつまらなくなったのかもしれない。
と、個人的に思っている。
あらゆる芸術のうちでその動的な構成法において最も映画に接近するものは
俳諧連句であろうと思われる。
『寺田寅彦随筆集 第三巻』 寺田寅彦
人間は最速で一秒間に二四コマの情報を知覚する能力を備えている。
『脳はすごい』 クラーク・エリオット