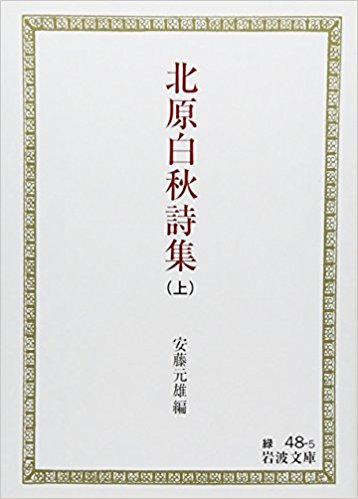

われは思ふ、
末世の邪宗、切支丹でうすの魔法。
黒船の加比丹を、紅毛の不可思議国を、
色赤きびいどろを、匂鋭きあんじやべいいる、
南蛮の桟留縞を、はた、阿剌吉(あらき)、珍酡(ちんた)の酒を。
『邪宗門』北原白秋
白秋二十四歳の時の代表作、第一詩集『邪宗門』の有名な一節。
九州人の白秋が綴ると妙に納得してしまう。
「私は北国人ではない。だから晴天の明朗を愛する。
愛するというよりも、晴天の明朗そのものゝ中に漲る透明な万有の寂しさを、
真の大自然の寂しさとして観る、さうして聴く。
枯淡は閑寂そのものゝ表の現われであるが、却つてこの私の奥に隠る閑寂性は、
かうした晴天の明朗をもつて若葉に映発する。
誰知らぬ私の魂の寂しさはこの光り輝くものゝ中にこそ慟哭(どうこく)してゐるのだ」。
白秋には「稲」や「土」の匂いがしない。
「潮」と「カステラ」と「いろごのみ」の匂いがする。

北原白秋 1885年(明治18)-1942年(昭和17) 享年57歳
そして、白秋は「赤い鳥小鳥」「ペチカ」「この道」「からたちの花」などの
童謡作家としてのイメージが強いが、
「いったい、この頃は芸術でも教育でも何でも彼でもあまりにも科学的分業的に
なり過ぎてゐる。で、いよいよ偏狭になり不統一になりやしないかと思ふね。
我々にしたところで、詩人とか、歌人とか、やれ民謡作家だとか、童謡作家だとか、
一面からばかり見て、手っ取り早く何かに片づけられて了ふが、
これは少々擽(くすぐ)つたいものだな。
何故一個の芸術家と見ないのかな、兎に角迷惑至極なものだよ。
人体から云っても解剖的にばかり見るのは近代医学の悪弊だな」。
と、大正十四、五年に述べている。なんだか、竹久夢二と印象が被る。
北原白秋は、明治十八(一八八五)年一月二十五日(戸籍上は二月二十五日)北九州・柳河に
生まれた。父長太郎、母しけ。長男はすでに亡くなっていたので、事実上長男として育つ。
本名は隆吉。
北原家は代々柳川藩御用達の海産問屋を営み、父の代で酒造産業を本業としている。
母方の祖父は、業隆(なりたか)といい、熊本の郷士で、横井小楠の弟子筋にあたる学者で、
大変な蔵書家でもあり、読書家でもあった。
江戸時代の町人文化そのままの受け継いできたような環境に育った白秋は、
幼い頃は病弱で、簡単にひびわれかねないということで、家族からは「びいどろ罎(びん)」と
仇名されていた。
そんな影響もあってか、出掛けるときには、人力車を使わず、わざわざ黒塗りの駕籠を
仕立てていた。後に白秋は「和蘭(オランダ)の舶来品扱ひされた」と書いている。
そんな病弱だった白秋は、近所の子供たちと遊ぶよりも、祖父の図書室に入り浸り、
「旧い蘭書の黒皮表紙や広重や北斎乃至草艸紙の見かへしの渋い手触り、黄表紙、雨月物語、
その他様々の稗史、物語、探偵奇談、仏蘭西革命小説、経国美談、三国志、西遊記」
などを読み耽る。この辺りも夢二と同じ香りがする。
叔父も変わった人で、夜になると家の欄干にでて、よく笛を吹き、アラビアンナイトの
挿話なども話してくれていた。後年に「アラビアンナイト物語」という詩も残している。
明治三〇(一八九七)年、十六歳のときに白秋と名乗る。
だが、その年の三月に、沖端の大火で生家、酒蔵が全焼し、生活が困窮していき、
白秋が上京してから五年後の、明治四十二年十二月下旬に破産する。
「私の郷里柳河は水郷である。さうして静かな廃市の一つである。
自然の風物は如何にも南国的であるが、既に柳河の街を貫通する数知れぬ溝ワリのにほひには
日に日に廃れてゆく旧い封建時代の白壁が今なお懐かしい影を写す」。
「私が十六の時、沖ノ端に大火があつた。
さうしてなつかしい多くの酒倉も、あらゆる桶に新しい金いろの日本酒を満たしたまま
真蒼に炎上した」。
二十六歳の時の第二詩集『思い出』の序文「わが生ひたち」に書いている。
序詩
思ひ出は首すぢの赤い蛍の
午後(ひるすぎ)のおぼつかない触覚(てざはり)のやうに、
ふうわりと青みを帯びた
光るとも見えぬ光?
あるひはほのかな穀物の花か、
落穂(おちぼ)ひろひの小唄か、
暖かい酒倉の南で、
ひき揉(む)しる鳩の毛の白いほめき?
音色ならば笛の類、
蟾蜍(ひきがへる)の啼く
医師の薬のなつかしい晩、
薄らあかりに吹いてるハーモニカ。
匂ならば天鵞絨(びらうど)、
骨牌(かるた)の女王(クイーン)の眼、
道化たピエローの面の
なにかしらさみしい感じ。
放埓の日のやうにつらからず、
熱病のあかるい痛みもないやうで、
それでゐて暮春のやうにやはらかい
思い出か、ただし、わが秋の中古伝説(レヂエンド)?
『思い出』北原白秋
陰影
なつかしき陰影をつくらんとて
雛罌粟(ひなげし)はひらき、
かなしき疲れを求めんとて
女は踊る。
晴れやかに鳴く鳥は日くれを思ひ、
蜥蜴(とかげ)は美しくふりかへり、
時計の針は薄らあかりをいそしむ……
捉へがたき過ぎし日の歓楽よ、
哀愁よ、
すべてみな、かはたれにうつしゆく
薄青きシネマのまたたき、
いそがしき不可思議のそのフィルム。
げにげにわかき日のキネオラマよ、
思ひ出はそのかげに伴奏(つれひ)くピアノ、
月と瓦斯との接吻(キス)、
瓏銀(ろうぎん)の水をゆく小舟。
雛罌粟は顫へ、
かなしき疲れを求めんとて
女は踊る。
『思い出』北原白秋
淡い粉雪
Tinka john作
淡い粉雪はブリツキの
薄い光に消えてゆく、
老嬢(オールドミス)のさみしさか、
青いその日も消えてゆく。
『思い出』
青いとんぼ
青いとんぼの眼を見れば
緑の、銀の、エメロウド、
青いとんぼの薄き翅
燈心草(とうしんそう)の穂に光る。
青いとんぼの飛びゆくは
魔法つかひの手練(てだれ)かな。
青いとんぼを捕ふれば
女役者の肌ざはり。
青いとんぼの奇麗さは
手に触るすら恐ろしく、
青いとんぼの落ちつきは
眼にねたきまで憎々し。
青いとんぼをきりきりと
夏の雪駄で蹈(ふ)みつぶす。
『思い出』北原白秋
少年の頃の複雑で残虐な内面も表している。
「私がこの『思い出』の編纂に着手し初めたのは、ちょうど郷家の旧い財宝はあの花火の
揚る、堀端のなつかしい柳のかげで無惨にも白日競売の辱しめを受けたといふ
母上の身も世もあられないやうな悲しい手紙に接した時であった」。
白秋の短歌の初作は十五歳の時で、本格的に作るようになったのは十七歳から。
島崎藤村と與謝野晶子から影響を受けていた。
明治三十九年から、白秋は『明星』の正式なメンバーにもなり、
與謝野鉄幹の新詩社に出入りしている。
脱退後は、明治四十一年十二月に、木下杢太郎、石井柏亭、吉井勇、森田恒友などの、
若い詩人や洋画家たちと『パンの会』を結成している。
まあ、恋多き白秋の正式な年譜は『白秋記念館』のホームページに掲載されているので、
そちらを参考にしてください。
個人的には、昭和五年(一九三〇)四十五歳の時に南満洲鉄道会社からの招きで、
四〇日満蒙に旅行をしているのが面白い。
あかい夕日に
あかい夕日につまされて、
酔うて珈琲店を出は出たが、
どうせわたしはなまけもの、
明日の墓場をなんで知ろう。
『東京景物詩 及其他』
深夜
月ほそく光りたり真の夜中に、懺悔せよとか
寸金本土の阿弥陀仏光るは海の真夜中
『真珠抄』
生命
光リカガヤク円キモノ
アタリマバユクフリカヘル。
光リカガヤク円キモノ
アタリマバユク目ヲツブル。
光リカガヤク円キモノ、
光リ澄ミツツ掌ヲ合ス。
『白金之独楽』
詩の香気と品位といふことを私はいつも考へる。
これを総じて気品と云ひ気韻といふのはそれである。
これは巧みて成るものではない。
詩人その人のおのづからな香気と品位とがそのままそれらをその詩に持ち来すのである。
『水墨集』(芸術の円光)
時雨
時雨は水墨のかをりがする。
燻んだ浮世絵の裏、
金梨地の漆器の気品もする。
わたしの感傷は時雨に追はれてゆく
遠い晩景の渡り鳥であるが、
つねに朝から透明な青空をのぞみながら、
どこへ落ちてもあまりに寒い雲の明かりである。
時にはちりぢりと乱れつつも、
いつのまにやら時雨の薄墨ににじんで了ふ。
『水墨集』
三木卓氏は『北原白秋』のなかで、
「白秋は士族でもなく農民でもない。
受け取ったカルチュアの質は、町人・商家のそれであった」とし、
大正・昭和に活躍した、日本を代表する民族学者の折口信夫は、
「元禄の作者たちの口癖に〈まれ男〉という語がある。
この人などを、今の世の〈まれ男〉といはねば、いふべき人はあるまい。
あて―上品―で、なまめい―はいから―て、
さうして一部いろごのみの味ひを備へた姿を文章の上に作る事の出来る人は、
この人をおいてさうさうはあるまい」
と評している。
ちなみに、明治四十一年の「文章世界」の「文界十傑」という人気投票で、
「詩人の部」の第一位に白秋が選ばれている。
第二位は蒲原有明、第三位は與謝野寛、第四位は三木露風。
白秋の詩には“何か”が降ってくるのが多い印象を抱く。
雨や雪、虫や花、日光や月光、かなしみやさみしさなど。
本書上巻は『邪宗門』(一九〇九)『思い出』(一九一一)。
下巻は『東京景物詩 及其他』(一九一三) 『真珠抄』(一九一四)『白金之独楽』(一九一四)
『畑の祭』(一九二〇)『水墨集』(一九二三)『海豹と雲』(一九二九)が収録されている。
飯島耕一氏は『白秋と茂吉』の中で、
「パンの会の白秋、キリシタン・バテレンの白秋は「雀の生活」の白秋となり、
ついに古神道となる」
と、巧みに白秋の生涯を言い表わしているのが印象に残るが、
それは白秋の詩にも顕著で、ただの西洋かぶれではなかった。
そして、一つ気になるのが、
白秋三十六歳の時に結婚した佐藤菊(大分市の奈良屋という時計商の娘)が、
国柱会の熱心な会員だったこと(菊の母親も)。
白秋の妹の旦那もそうだったので、その辺りのことが気になる。





