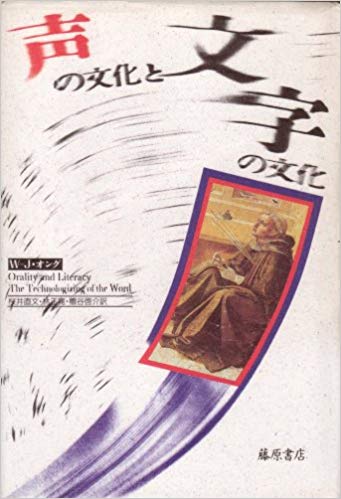
この何年かのあいだにわかってきたのは、一次的な声の文化 primary oral culture(つまり、ま
ったく書くことを知らない文化)と、書くことによって深く影響されている文化とのあいだに
は、知識がどのように取り扱われ、またどのようにことばに表されるかという点で、ある基本
的な違いがある、ということです。
この新しい発見からひきだされる帰結は驚くべきものです。
つまり、文学や哲学や科学の思考と表現において当然のものと思われてきた特徴の多くは、
あるいはまた、口頭での話であっても、それが文字に慣れた[読み書きができる]者たち
literates のあいだで行われるときに、そこで当然のものと思われてきた特徴の多くは、けっし
て人間存在自体に生まれつき直接に備わっているものではなくて、書くという技術が人間の意
識にもたらした手段によって生みだされたものだ、ということです。
『声の文化と文字の文化』ウォルター・J・オング
人間の社会はまず、口頭で話をするということによって形成されたのであって、文字社会とな
ったのは歴史上でもごく最近のことであり、はじめは、あるかぎられた集団のあいだのことに
すぎなかった。最初に「書かれたもの script」が現れたのは、たかだか六千年前のことにすぎ
ない。
本書の主題は、オラリティー(ことばの声としての性格と、ことばのそうした性格を中心に形成
されている文化=声の文化)とリテラシー(文字をつかいこなせる能力と、そうした能力を中心
に形成されている文化=文字の文化)の違いについて。
主に西欧世界のことばの声としての性格(オラリティー)と書くこと writing の関係であり、
そのあいだにある「心性 mentality」の違いについて。
その理解が開かれたのは、エレクトロニクスの時代になってからであり、それ以前ではなく、
電子メディアと印刷とを対照させることによって、それ以前にあった書くことと声の文化(オラ
リティー)の対照に気がついた。
エレクトロニクスの時代は、「二次的な声の文化」、電話、ラジオ、テレビによって形成され
る声の文化の時代でもある、とオングは指摘する(原著は八〇年代、日本語版は九一年の出版だ
が、現在では当然インターネットもその中に含まれるだろう)。
しかし「二次的な声の文化」は「一次的な声の文化」に純粋に回帰したというわけではなく、
その存立を、書くことと印刷することに負っている。
「ものを書いたり印刷したりということを全然知らない文化の声としてのことばにもとづく性
格を、わたしは「一次的な声の文化」と呼んでいる。
それがなぜ「一次的」なのかは、今日の高度技術文化の「二次的な声の文化」と比べてみれば
わかる。
後者の新しい声の文化は、電話やラジオ、テレビ、さらにそのほかのエレクトロニクス装置に
よってささえられている。
ところが、これらの装置はどれも、書くことや印刷に依存しないことには存在することも機能
することもできない。もはや今日、厳密な意味での一次的な声の文化はほとんど存在しない。
どの文化も書くことを知っており、それがもたらす効果を多少とも経験しているからである。
しかしそれでもやはり、多くの文化やサブカルチャ-が、高度技術文明につかりながらも、程
度の差はあれ一次的な声の文化の思考様式を相当に保っている」(本書)

ウォルター・J. オング Walter Jackson Ong (1912年11月30日~2003年8月12日)
文字と無縁の、声の文化に根ざした思考様式や表現様式と、文字に媒介されたそれらの様式と
の違いについてはっきりと気がついたのは、言語学者ではなく、文学研究であった。
なかでもさきがけだったのは、若くして世を去ったアメリカの古典学者ミルマン・パリーの『イ
リアス』と『オデュッセイア』のテクストに関する研究だった。
パリー以前には、『イリアス』と『オデュッセイア』は、すじだてがひどく、登場人物の性格
描写も貧弱で、倫理学的にも神学的にもいあやしむべきものだと攻撃し、ホメロスという人物
などまったく実在せず、彼の作とされる叙事詩は、他人の詩をつぎはぎしたものにすぎない、
などと論じられていた。
しかし、パリーは、ホメロスの詩に特有なほとんどすべての特徴は、口頭で組みたてられると
いう製作方法によって強いられるエコノミーによるものである、と発見した。
このような制作方法を再構成するには、詩行そのものを注意深く調べなければならいが、その
ためには、文字にもとづく文化に属する人々のこころの奥底に、いく世代にもわたってしみつ
いた、表現と思考過程についての諸仮定をひとまず棚上げにする必要があるとした。
「ミルマン・パリーが行ったような綿密な研究が明らかにしたところによれば、ホメロスは再三
にわたってきまり文句をくりかえし用いていた。
ギリシア語のラプソーデイン rhapsoidein の意味、すなわち、「歌を綴り合わせる」(ラプテ
イン rhaptein「縫い綴る」+オーデ oide「歌」)が、当時の詩の作りかたを暗示している。
ホメロスは、あらかじめ出来あいの部品を綴り合わせたのである。
そこにいたのは、創造者ではなく、むしろ、組み立てラインの労働者だった」(本書)
パリーの研究がすすみ、のちの学者たちによってさらにすすめられるにつれ、『イリアス』と
『オデュッセイア』に使われていることばのうち、きまり文句 formula の一部でないものは、
ほんのわずかにすぎないことが明らかになった。
さらには、ホメロスの詩の言語の全体は、アイオリスとイオニアの、初期および後期の方言の
特徴を混在させているという。
こうしたホメロス詩の特徴は、いくつかのテクストが塗り重ねられたものではなく、古い慣用
表現を用いる叙事詩人たちによって長い年月のあいだに生みだされた言語としてもっともよく
説明されるものだった。
つまりは、このような古い慣用表現を、詩人たちは保存し、もっぱら韻律上の必要からつくり
かえてきた。
ホメロスの二つの叙事詩は、それまでに何世紀もかけてかたちづくられ、手をくわえられてき
たすえに、紀元前七〇〇年から六五〇年にかけて、新しいギリシヤのアルファベットによって
書きとめられた。
そこで用いられている言語は、日々の生活のなかで話したことのあるギリシア語ではなく、
世代から世代へとそれを伝えてきた詩人たちの使用によって輪郭がかたちづくられてきた特別
なギリシア語だった。
慣用句やきまり文句などが、なぜ重んじられていたのかといえば、ことばがもっぱら声である
ような文化においては、いったん獲得した知識は、忘れないように絶えず反復していなくては
ならず、知恵をはたらかすためにも、そしてまた効果的にものごとを処理するためにも、
固定し、型にしたがった思考パターンがどうしても欠かせなかった。
しかし、プラトン(427?-347BC.)の時代までには、変化が起こっていた。
ギリシアのアルファベットが紀元前七二〇年から七〇〇年ころに作られてから数世紀がたった
ころ、このプラトンの時代までにギリシア人は、ようやく書くことを自分のうちに実効的に内
面化 interiorize した。
ちなみに、ホメロスの『イリアス』は文字誕生以前の文化からアルファベット文化への過渡期
に成立したとも言われている。(『メディア論』ヨッヘン・ヘーリッシュ)
そして、記憶をたすけるきまり文句のなかにではなく、書かれたテクストのなかに、知識をた
くわえる新しい道が開かれるようになった。
このようにして、精神は解き放たれて自由になり、より独創的で抽象的な思考をめざすことが
可能になった、とオングは指摘する。
「セム人の手になる最初のアルファベットは、子音字といくつかの半母音字だけからなりたっ
ていた。
ギリシア人は、母音字を導入することで、音声というとらえどころのない世界を、抽象的で分
析的な、それでいて視覚にうったえるかたちでコード化するという新しい段階に到達したの
だ」(本書)
だがしかし、プラトンは書くことに対しては深刻な留保を表明していた。『パイドロス』や
『第七書簡』などで。
書くことは、知識を処理する手段としては機械的で非人間的であり、書かれたものは尋ねられ
ても即座にこたえられず、記憶力をそこなわせるものだというように。
プラトンも書くことに全面的に依存していたのだが。
ようやく書かれはじめたころの詩は、世界のどこの詩であれ、まず必然的に、口頭での演じ語
りを文字に書き写したものになるように思われる、とオングは指摘する。
文字をすらすらと書きつらねてゆく才をはじめから備えているわけではなく、まず最初は、声
に出して語っている実際の場面を思い浮かべ、自分自身が朗々と発するはずのことばを、なに
かの表面に刻みつけていた。
「プラトンがかれの『国家』から詩人を排除したということは、ホメロスのなかにはくりかえ
しあらわれていた素朴で、累積的、並列的な、声にもとづくスタイルの思考を、プラトンがし
りぞけたということである。
かわりにプラトンが支持したのは、世界と思考そのもののするどい分析ないし解剖であり、そ
うしたことは、ギリシア人のこころにアルファベットが内面化されることによって可能になっ
たのだった」(本書)
プラトンは、書くことを外的でなじみのない技術と考えていたみたいだが、この時代の人々
は、まだそれを十分に自分の一部にはしていなかった。
自然な口頭での話とは対照的に、書くことは、完全に人工的なもの。
たえず、動いている音声を、静止した空間に還元し、話されることばがそこでしか存在できな
い生きた現在からことばを引き離すということで、印刷やコンピューターはその継続している
にすぎないと。
書くことは意識を高め、自然な環境からの離脱[疎外]は、われわれにとってよいことでもあ
り、多くの点で、人間生活を充実させるためには不可欠でさえある。
十分に生き、十分に理解するためには、近づくことだけではなく、離れることも必要である。
離れることこそ、書くことが、他のどんなものにもまして、意識にあたえるものなのであると
している。
「技術は人工的である。しかし、ここにも逆説があるのだが、人工的であることは、人間にと
って自然なのである。
技術も、適切なしかたで内面化されるならば、人間の生活の価値を低めはせず、反対に、それ
を高める」(本書)
技術とは、たんに外的なたすけになるだけのものではなく、意識を内的に変化させるものでも
ある。
書くことは、楽器による音楽演奏よりはるかに深く内面化された技術であり、話しを、声と音
の世界から新しい感覚の世界、つまり視覚の世界へと移動させることによって、話と思考をと
もに変化させる。
そして、書くことによって思考や表現におよぼされる影響は、印刷によって強化されると同時
に、変質もした。
勿論、印刷の影響がすべてだった、というように過大評価しているわけではないが、口頭での
話しから書かれた話しへの移行は、音から視覚空間への移行でもあった。
そして、書くここと印刷から、ある特殊な方言も生みだされた。
イギリスやドイツやイタリアでは、経済的、政治的、宗教的な理由、その他の理由から、書く
ことに結びつくことによって、一つの地域言語が他の方言からぬきんでて発展した。
その結果、それらの方言は、国民言語 national language になった。
イギリスではロンドンの上層階級の英語[の方言]、ドイツでは高地ドイツ語(南部の高地地方の
ドイツ語)、イタリアではトスカナ語。これらはすべて、地域方言ないし階級方言だった。
しかし、書くことを通して整序される国民言語としての地位をえることによって、他の諸方言
とは異なった種類の方言ないし言語となった。
またよくいわれていることだが、印刷は、イタリアのルネサンスを永続的なヨーロッパのルネ
サンスに変え、プロテスタントによる宗教改革を実現し、カトリックの宗教的慣行を方向転換
させた。近代資本主義の発展に影響を与え、西ヨーロッパによる地球の探検を実現し、家庭生
活と政治を変え、かつてなかったほど知識を広め、万人識字 universal literacy をまじめに検討
に値する目標に変え、近代科学の興隆を可能にし、その他さまざまなしかたで、人々の社会
的、知的な生活を変えた、ことも指摘している。
「ことばが、人間どうしの行動的なやりとりのなかではじめてその生を享けたときに宿ってい
た音の世界から、印刷は、ことばを引き離し、それを視覚的な平面に決定的に帰属させ、知識
の管理のために視覚的な空間を[これまでとは]違ったやりかたで活用しはじめた。
そうすることによって印刷は、人間が、みずからの内面の意識と無意識的な資源を、ますま
す、もののようなもの、非人格的なもの、宗教的に中立的なものとして考えるようにとうなが
した。
[つまり]印刷は、精神がますますつぎのような感覚をもつようにとうながしたのである。
つまり、その[精神の]所有物がいわば惰性的な心的空間のなかに保管されている、という感覚
である」(本書)
印刷文化においては、一つの作品は、「閉じられたもの」、他の作品から切りはなされ、
それ自身で一つの単位となったものとして感じられる傾きがあり、印刷文化が、「独自性」や
「創造性」というロマン主義的な概念を生みだしたのである、とオングは指摘する。
エレクトロニクス時代は、言語表現を変化させたが、その変化は、一方では、書くことかたは
じまり、印刷によって強化されたことばと空間とのかかわりをさらに深めるものであり、他方
では、二次的な声の文化という新しい時代の文化に意識を移行させているとする。
書くことによってはじまり、印刷によって新たな強度の段階にすすんだことばの逐次的処理
sequential processing とことばの空間化は、コンピューターによってさらに強化される。
コンピューターは、ことばと空間および(電子的な)位置運動との関わりを極大にし、[語の]分
析的な逐次的配列をほとんど瞬時に実現することによって、それをもっとも効果的におこなう
のである、と言及する。
「[ことばと空間との関わりを一方で強めると]同時に[他方では]、エレクトロニクスの技術
は、電話、ラジオ、テレビ、さまざまな録音テープによって、われわれを「二次的な声の文
化」の時代に引きずりこんだ。この新しい声の文化は、つぎの点で、かつての[一次的な]声の
文化と驚くほど似ている。
つまり、この二次的な声の文化は、そのなかに人びとが参加[して一体化]するという神秘性を
もち、共有的な感覚をはぐくみ、現在の瞬間を重んじ、さらには、きまり文句を用いさえする
のである」(本書)
しかし、この声の文化は、その本質においては、一次的な声の文化よりいっそう意図的で、み
ずからを意識している声の文化であり、書かれたものと印刷の使用のうえにたえず基礎をおい
ている声の文化。
二次的な声の文化は、一次的な声の文化と、きわめて似ているとともに、きわめて似ていな
い。一次的な声の文化と同様、二次的な声の文化は、強い集団意識を生み出したとオングは指
摘する。
それは、「新しいメディアは多くの人々を結びつけるが、それと同時に多くの、非常に多くの
人々を排除する」(『メディア論』ヨッヘン・ヘーリッシュ)ということでもあるだろう。
本書は上述のように、声の文化→文字文化→印刷→電子的コミュニケーションという移行が、
人々の精神、文学、社会にどのように影響を及ぼすか、を論じたものとなっている。今では
古典的名著といえるのかもしれない。マクルーハンは勿論のこと、ジュリアン・ジェインズの
「バイキャメラル・マインド」、「二分心」にも言及されている箇所もある。
ほぼ西欧について語られているが、他の地域での「声の文化と文字の文化」の過程も気にな
るところ。
どんな発明にもまして、書くことは、人間の意識をつくりかえてしまった。
『声の文化と文字の文化』ウォルター・J・オング
文字の発明とともにメディアの前史は終わり、技術メディアの歴史が始まるのである。
『メディア論』ヨッヘン・ヘーリッシュ
第三のメディア革命、すなわちデジタル・コンピュータ・メディアの登場によって、音と映像、
数字とアルファベットなど「すべて」が暗号化され、保存され、伝達されることが可能とな
る。
この第三のメディア革命がその予測可能な終末に近づくことになるのは、メディア機器が文字
どおり呼びかけに対して反応する、それゆえいつ何時ももれなく声を文字へ、文字を声へ変換
することができるようになった場合である。
『メディア論』ヨッヘン・ヘーリッシュ
ある言語が別の言語に変化する時には、常にその残余があるが、誰もそれが何かを思い出すこ
とはできない。
言語の中には話し手よりも多くの記憶が残っていて、それは生き物より古い歴史の痕跡を示す
地層に似ている。
それは必然的に、言語が通ってきた幾つもの時代の跡を残している。
『エコラリアス』ダニエル・ヘラー=ローゼン


