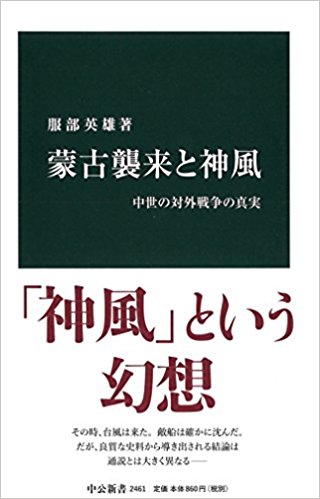
山川出版社から出版されているもうひとつの『蒙古襲来』は少し読みづらさがあったが、
本書は新書故にスッキリまとまっていて、一般人には読みやすい。
今現在でも蒙古襲来といえば、著者も指摘している、
「神風によって、蒙古が退散した。つまり、二度ともに神風が吹いて、元寇は決着がつく。
文永の役では敵は一日で引き返し、弘安の役では嵐によって肥前鷹島(たかしま)に集結した敵
船が沈み全滅した」
と、今でも教科書にはこのように書かれているものも複数あり、文部科学省の教科書検定でも
通過しているという、いわゆる神風史観によって解釈されている。
その「神風」なる言葉は、古文書では元亨(一三二一)七月に薩摩国分寺の関係者が、
老巧化した社殿の修理費用を国衙に対して要求した際に使った例が初見であろう、
と著者は指摘する。
そして、本書で批判の対象としている代表的な通説は、東京帝国大学教授であった東洋史家の
池内宏(ひろし)の『元寇の新研究』(一九三一年)で展開されている神風史観。
アカデミズムの場でも教育の場でも、一〇〇年近くにわたり君臨し、孫引きされ形成されてき
たと。しかし、その池内宏氏の説に対して、同時代にも科学的な学風、気概で批判的な学者が
いた。それは九州帝国大学医学部教授の中山平次郎。
本書は「中山視点を継承しつつ、飛躍的に発展させる」と著者が記しているが、それも狙いと
している。
クビライ(フビライ)の元は、何故日本に攻めてきたのか。
これも学校では習わないことなのかもしれない。
一二五七年、クビライの兄モンケ・ハーンは、ケルレン河畔のチンギス・ハーンの大オルドで大
会議を召集し、その席上で、華中・華南の南宋帝国に対する遠征計画を決定する。
モンゴル高原の政務を末弟のアリク・ブガにゆだね、モンケ・ハーンはみずからモンゴル軍の本
隊を率いて南下し、一二五八年の夏に、六盤山(りくばんざん・いまの寧夏回族自治区の南部)に
基地をおく。
秋、輜重(しちょう)を六盤山に留めて、南下して四川省の盆地に攻め込み、南宋の合州城(合川
県)を包囲した。
しかし、南宋軍の抵抗が強くて、城を落とせずにいるうちに、モンゴル軍の陣中で赤痢が流行
し、モンケ・ハーン自身も感染して、一二五九年八月十一日、合州城外の釣魚山で亡くなる。
クビライは、南モンゴルの本拠地から、南宋の鄂州城(がくしゅう・湖北省の武漢市)にむかって
進軍していたが、その途中で、兄のモンケ・ハーンが合州城外で亡くなったという知らせを受け
取る。しかしクビライは、すぐに引き返せなかった。
部下のウリャーンハダイが、雲南省からヴェトナムに進軍し、ヴェトナムからいまの広西チワ
ン族自治区の南宋領に侵入して、そこから湖南省を南から北へ縦断して、鄂州でクビライと合
流しようと北上をつづけていたからである。
クビライは鄂州の包囲をつづけながら南宋側と交渉し、和議を結んで、ウリャーンハダイの部
隊を収容してから北方に引き揚げた。
その後は、兄弟のあいだで内戦が勃発し(四年間)、クビライはそれに勝利し、モンゴル帝国の
筆頭のハーンとなる。
そして一二六八年、クビライは南宋に対する作戦を再開する。
モンゴル軍は、漢江のほとりの南宋の要塞、襄陽城(じょうよう・湖北省の襄樊市[じょうはん])
を包囲するが、南宋軍は勇敢に抵抗した。
五年間、包囲がつづいたのち、一二七三年になって、襄陽はようやく落城する。
これで南宋の臨時首都、臨安(りんあん・セッ江省の杭州市)への通路が開け、バーリン氏族出身
の将軍バヤンの指揮する元軍は、漢江を下る。
一二七五年、鄂州を占領し、ここから長江を下り、一二七六年、臨安を占領した。
バヤンは、南宋の最後の皇帝で当時六歳の瀛国公(えいこくこう)を捕らえ、クビライ・ハーンの
もとに連れていった。
こうして南宋帝国は滅亡し、元朝による中国統一が完成する。
ちなみに、「大元」という国号は、クビライが採用したもので、「大元」とは「天」を意味す
る。さらにクビライは、北京の地に大都という都市を新たに建設し、それは同時に漢人を統
治する行政センターにした。
モンゴル帝国の本拠地はあくまでモンゴル高原であり、元朝の歴代皇帝は、在位中、北京より
南の中国には、決して足を踏み入れなかったという。
以上、岡田英弘氏の『中国文明の歴史』(講談社現代新書)に詳しい。
上の背景の中で、「南宋に対する作戦の一環として、日本列島を占領して、背後から南宋を突
こうと考え、一二七四年(文永の役)、モンゴル・高麗連合軍を送って日本を攻め、北九州に上陸
を試みる」とも岡田氏は説明されている。
そして、服部氏は本書『蒙古襲来と神風』(中公新書)のなかで、
「敵国たる宋を支援し続ける国が日本だった。日本と宋の友好関係(通商関係)もまた三〇〇年
に及んでいた。
クビライは日本と南宋の同盟関係を認識していて、準備さえ整えば『或いは南宋、或いは日
本』に出兵すると、宋と日本を討つとしばしば発言している」(本書)
と記している。
その証に、交易と安全とスムーズな交渉を可能にするために、九州各地の海岸に宋人グループ
を各地に配置し、拠点(唐房)が張り巡らされていた。「唐房」は今でいうチャイナタウン。
その日宋貿易では、宋から日本への輸出品は、銅銭、陶磁器、医薬品などで、
日本から宋へは、中国では産出しないもので、木材であるヒノキ、スギ、そして硫黄であっ
た。
著者はそれらを踏まえて次のように説明している。
「火山列島である日本、特に九州には硫黄が豊富だった。日本は宋に火薬材料の硫黄を輸出し
続けた。硫黄は軍需物質だから、その供給はぜったいに阻止せねばならない。
クビライが宋を打倒するためには、まず日本を制圧し、支配下に置いて、硫黄つまり火薬を敵
から奪う必要があった」(本書)
「蒙古襲来は本質的に物質戦争であって、兵器製造に必要な硫黄を直接調達することを、
元が切実に欲くしたのである」(本書)
山川出版社の『蒙古襲来』のなかでは、
「日本を攻める前にモンゴルは親宋国だった高麗を事実上の属国とすることに成功し、宋に大
きな打撃を与えていた。
高麗は文班と武班の両班(ヤンバン)から政権が成っていたが、文班、つまり科挙合格者である
官僚文人グループが降伏派となり、武人グループが抗戦派となって対立し、文班が主導権を掌
握したことによってモンゴルに与した。モンゴルはつぎには日本を属国にする。
それができれば、宋は孤立し、火薬兵器の使用が困難になる」(『蒙古襲来』山川出版社)
としている。さらにモンゴルは高麗を属国にした方法を、日本にも仕掛けてきていた。
「大宰府を陥落し、九州の年貢供給ルートをわがものとする。
温泉岳(雲仙山)・阿蘇火山・九重火山・別府硫黄山の硫黄はむろん掌握する。日本は支配者が分裂
していた。
朝廷と鎌倉幕府が対立する政治状況を利用して、朝廷および反幕府・反得宗勢力と連合して鎌倉
幕府・北条政権を打倒する。親『大元』政権を樹立する。かつて高麗を味方につけた手法と同じ
である。朝廷内が文官派と武人派に分裂していることを利用する」(『蒙古襲来』山川出版社)
元についての情報は、宋から帰国した僧侶からの情報が主で、ほかは高麗経由で得る情報しか
なかったという。
そんな状況の中、来襲の三年前の文永八年に、鎌倉幕府は「蒙古人襲来すべきの由、その聞こ
えあり」として鎮西で迎撃態勢を整えるよう指示していたという。
翌文永九年には異国警固のため、御家人たちが博多津番役を、交代で一月ごとに勤番もしてい
る。
文永の役の一年前には、高麗南部や江華島、珍島などの島嶼部などで活動していた、反モンゴ
ル派の三別抄(さんべつしょう)が鎮圧されており、三別抄は高麗王朝と称して日本に救援を求
めてきていて、日本側は黙殺したが、大体の事情はわかっていたという。
文永十一年(一二七四)、高麗軍、そして高麗を支配する元の連合軍が、対馬・壱岐を経
て九州北部、博多湾岸に攻めてくる。文永の役。
日本側は善戦し、大宰府まで攻め込んできた蒙古・高麗軍を退けた。不首尾となった蒙古・高麗
軍は撤退を決める。
もともと蒙古・高麗軍は、大宰府陥落が不可能であれば、帰国してもよいとされていた。
通説の神風史観の骨格をなす、文永の役における「嵐によって一夜で殲滅」といわれている
が、著者は「俄かに逆風」「会(たまたま)、夜に大風雨」(『高麗史』)とあるように、嵐は吹
いているとして、この季節(十一月末)には例年、強い寒冷前線が通過し、漁船などが転覆する
こともある。嵐はそうした異常気象のことだろうともして、冬になれば北風が卓越し、日本海
交通も途絶えがちになって、補給が不安定になる。
悪くすれば退路を断たれて全滅である。嵐の通過が帰国を後押ししたと述べ、
「嵐によって一夜で殲滅」は幻想・虚像に過ぎないとしている。
「大宰府陥落を目標に、七日ほど合戦を続行したが、嵐があり、それを契機に二十七日頃、
北風が弱まった間に撤退、帰国した」(『蒙古襲来』山川出版社 )
第二回日本遠征の弘安の役は一二八一年に起こる。
一二七九年に南宋の残党の掃討作戦が完了し、クビライは、旧南宋の水軍を五島列島に回航さ
せ、これを中核部隊として、ふたたび北九州に上陸作戦を試みる。
一連の流れを通説(池内説)ではなく、著者は独自に推測・考察し、示している(服部説)。
東路軍(高麗軍)
五月三日合浦発→その日のうちに対馬到着・八日頃までに全島掌握→十五日頃に壱岐掌握
→二十六日に志賀島(「日本世界村大明浦」=志賀島)→六月六日に志賀島増派・日本側最初の大
反撃→その前後に蒙古・高麗軍が長門侵攻、対馬増派→この間、本隊は終戦まで志賀島駐留のま
ま、張成ら一部部隊が壱岐に移動(交替休養)→七月二十七日に張成ら一部部隊が鷹島に移動(連
絡補給)→閏七月一日(元暦では八月一日)暴風→閏七月五日博多湾で敗北
江南軍(旧南宋軍)
六月十八日舟山出発(一部は二十六日か)→二十一日頃済州島→二十五~二十九日に宇久島・小値
賀島→七月初め平戸島→七月十五日頃鷹島着→二十七日頃志賀島より張成ら一部連絡部隊が鷹
島へ→閏七月一日台風→閏七月七日鷹島(海上および陸上戦)で敗北
通説(池内説)では、台風が来て一夜で全滅状態になり敗走したとしているが、
著者は、その後も死闘をくりひろげていると指摘し、東路軍は志賀島に陸上にて嵐の難を逃
れ、海上合戦に敗れて帰国し、江南軍の将であった范文虎は真っ先に脱出している。
「神風史観の骨格は、文永の役における一夜での敗走と、弘安の役、鷹島における全軍殲滅で
ある。前者の誤りは指摘できたが、後者もまた、その誤りを明らかにできる。
鷹島で江南軍は台風被害を受けている。それはそのとおり。
しかし、台風で決着がついたのではなく、その後も志賀島および鷹島の両戦場で死闘をくりひ
ろげている。
帰還兵も多い。征日本軍の一翼をなす東路軍は、志賀島陸上にて嵐の難を逃れ得たが、
海上合戦に敗れて帰国したと考える」(本書)
「台風がこなければ日本は蒙古軍の上陸を許したであろう。しかし蒙古軍が日本征服まででき
たかどうか」(本書)
さらにこの先の章で、神風史観を構成してきた通説の論拠を、一点ずつ確認しながら掘り
下げて批判を展開し、後半の章では、御家人であった竹崎季長(すえなが)が指揮して絵師に描
かせた『蒙古襲来絵詞』を分析している。

蒙古襲来絵詞 (もうこしゅうらいえことば)
福沢諭吉が言うように、武家政権が外敵を追い払い、外国人に政権を奪われなかった
からこそ、国体が守られた、ということだろう。
多少細かすぎるきらいがあるが、本書はしっかりと分析しているので気になる方は是非。




