
「本書はビザンツ帝国の長い歴史を旅した、私なりの記録である」(本書)
「ビザンツ帝国は、人類が創った組織としてはもっとも長く存続したもののひとつである。
三三〇年のコンスタンティノープル開都を始まりとし、一四五三年のトルコ人によるこの町
の征服を滅亡とみなすならば、千年以上持ちこたえたことになる。
しかもきわめて厳しい環境のもとでなされただけに、その記録的な存続期間にはひとしお感慨
深いものがある」(本書)
「一九三〇年代にドイツで権力を握った体制は、千年続くと宣伝していたが、たった十二年し
か続かなかった。対照的にビザンツ帝国は千年の偉業を成し遂げた」(本書)
著者は、ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校ヘレニック・インスティテュート教授(ビザンツ
史)。ビザンツと西欧の関係、とくに十字軍、イタリア・ルネサンス、1453年以降のギリシャ
人ディアスポラを専門としている。
原題は『THE LOST WORLD OF BYZANTIUM』(失われた世界)。訳とあとがきは、多数のビ
ザンツ本を翻訳・出版している井上浩一氏。
ビザンツ(東ローマ)と聞いて、多くの日本人は、ヘレニズム文化を基調にギリシア・ローマの
古典文化とオリエント(西アジア)の文化を融合した独自の文化を形成した、ということについ
て関心を示される方が多いのかもしれない。
ぼくが本書を手にしたのは、戦略家で歴史家のエドワード・ルトワックが、その著作のなか
で、「ビザンツ帝国は、最も成功した「戦略」の実践者だった」という言葉を目にしてから興
味を持った。ちなみにルトワックは、ビザンツ帝国を二〇年以上研究しているみたいだ。
本書は、三三〇年のコンスタンティノープル開都から、一四五三年のトルコ人による征服まで
を「なぜ滅びたのではなく、このようなきわめて不利な条件のもとでなぜ存続できたのか、
なぜある時期には繁栄し、拡大さえしたのか、それこそが肝心かなめの問題なのである」(本
書)として、皇帝を中心に話が進められている(コンスタンティヌス一世~コンスタンティヌ
ス一一世まで)。
ここでは事細かな歴史的な背景などは取り上げないけれど、ビザンツ帝国の首都は、
コンスタンティノープル(クンスタンティニエ)で「コンスタンティヌスの町」という意味。
現在のイスタンブール。
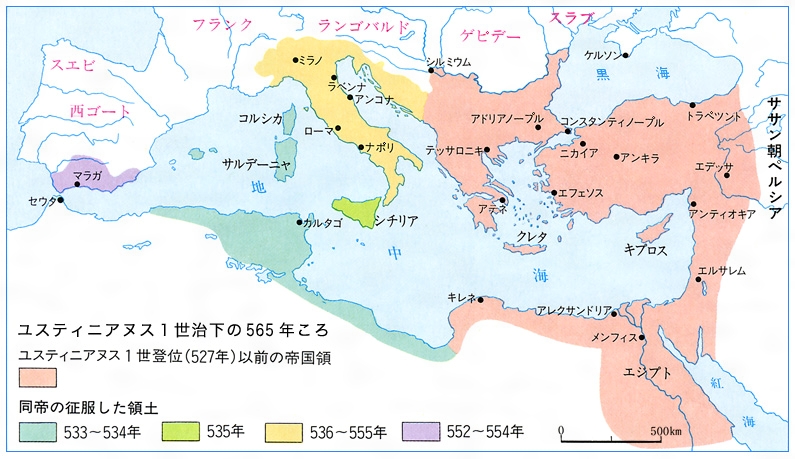
「ビザンツ文明に特徴的な要素が出そろうのがコンスタンティヌスの時代であった。
壮麗な難攻不落の都コンスタンティノープル、キリスト教の勝利、皇帝権を称えつつも制約を
課す政治理論、禁欲的な精神の称賛、霊的存在を具象化する芸術、国境への脅威に対する非軍
事的な対応」(本書)
地政学的に、アジアの草原地帯やアラビア半島から人の波が西へと流れてゆく「民族のボウリ
ング場」の端に位置していて、さらに、北にはブルガリア人やロシア人、その他の北方諸民
族もいて、この要因がビザンツ帝国のあり方を規定することになった、と著者は述べる。
「ビザンツ帝国の社会や精神の特徴は、国境へのきわめて強く、かつ絶え間ない圧力に対応す
るなかで形作られた。
外からの挑戦に立ち向かうのに、ここでは勇敢な軍隊だけでは充分ではなかった。
ある集団を軍事力で打ち破れば、代わって新たに三つの集団が現れるに違いないからである。
まったく新しい考え方を採用し、軍事以外の方法で脅威を取り除くよう努める必要があった。
外敵の同化や定住、買収や秘密工作、あるいは、もっとも特異な方法として、
壮麗なものを見せて敵を畏怖させ、友人ないし同盟者として囲い込むことなどが試みられた。
ビザンツ帝国は繰り返し危機に見舞われたが、そのつど切りぬけ、立ち直った。(中略)
実際のところビザンツ社会は、際限なく続く脅威に直面するなかで、絶えず革新と適応を繰り
返していた」(本書)
自国領土内で侵入者を撃退できない時は、帝国内に住まわせ、軍役と引き換えに土地を与え、
キリスト教の受容とビザンツへの同化を促した。
それらをビザンツ宮廷でまとめたものが、『戦術書』と通称されるレオン六世の著作であり、
次のように述べられている。
「策略、不意打ち、飢えによって敵を苦しめたり、波状攻撃などの作戦によって、時間をかけ
て打撃を与えるのがよい。決して正面戦争に誘いこまれないようにすべきである。
たいていの場合、勝利は勇敢さの証明ではなく、運に左右されることを我々は経験してきた。
…汝は、実際に戦うのではなく、金を使うことで、敵に対して多くの勝利を得るだろう。
もしその敵をどこかで待ち受ける別の敵があるのなら、金を提供してその民族に汝の敵を襲わ
せるよう説得すべきである」(『戦術書』)
皇帝やその取り巻きにとっては、敵対している周辺諸民族内部に友好勢力を育てることがきわ
めて重要であり、そのための最善の方法は、コンスタンティノープルに招き、盛大にもてなす
ことであった。
それらに加えて、千年の偉業を成し遂げられた要因を大きく四つ挙げている。
第一に、キリスト教は、政治的な指導権で宗教的な指導権を併せ持って国家の頂点に立つ支配
者、という概念をビザンツ帝国に持ち込み、これが政治的安定をもたらした。
第二に、キリスト教皇帝権は被支配者に対して、次々と現れる支配者を受容するよう促し、
支配者との驚くほど直接的な関係を提供するものであった。
第三に、キリスト教は、市民の生活必需品をまかなう公的な支援を提供し、市民の心情や精神
を捉える霊的な雰囲気を創り上げた。
最後に第四点として、非物質的なもの、精神的なものを目に見える形で表現しようとする、
新しい様式の芸術や建築を発展させた。
そして著者は、ローマ帝国と比較して次のように述べている。
「ローマ帝国が拡大したのは豊富な人的資源を用いて隣国を次々と圧倒できたからであった。
繁栄したのは、いったん帝国が成立してからは国境を襲う敵がめったに現れなかったからであ
る。これに対してビザンツ帝国は、千年を超える期間にわたって、ほぼ絶え間なく国境に圧力
がかかり、侵入・包囲・戦争が不断に続く、激動する不安定な世界の産物であった。
そのような時代に、周辺世界がすべて流動状態にあったなかで、ビザンツ帝国は存続し、みず
からの文化と存在を保持した」(本書)
ルトワックは、それを「ビザンツ帝国の七つの教訓」としてまとめている。(当初はアメリカの
ためにまとめたものだったらしい)
(1) 戦争は可能な限り避けよ。
ただし、いかなる時にも戦争が始められるように行動せよ。
訓練を怠ってはならず、常に戦闘準備を整えておくべきだが、実際に戦争そのものを望んでは
ならない。
戦争準備の最大の目的は、戦争開始を余儀なくされる確率を減らすことにある。
(2) 敵の情報を、心理面も含めて収集せよ。
また、敵の行動を継続的に監視せよ。
それは、生産的な活動ではないかもしれないが、無駄になることはまずない。
(3) 攻撃・防衛両面で軍事活動を活発に行え。
ただし戦闘、とくに大規模な戦闘は、よほど有利な状況でないかぎり避けよ。
敵の説得を武力行使のおまけ程度に思っていたローマ帝国と同じように考えてはならない。
武力行使を最小限に留めることは、説得に応じる可能性のある者を説得する助けになり、説得
に応じない者を弱体化させる助けになる。
(4) 消耗戦や他国の占領ではなく、詭動(機動)戦を実施せよ。
電撃戦や奇襲で敵をかき乱し、素早く撤退せよ。
目的は、敵を壊滅させることではない、なぜなら、彼らは、後にわれわれの味方になるのかも
しれないからだ。
敵が複数いる場合、互いに攻撃させるように仕向けられれば、単一の敵よりもかえって脅威は
小さくなる。
(5) 同盟国を得て、勢力バランスをシフトさせ、戦争を成功裏に終結させられるように努め
よ。
外交は、平時よりも戦時においてこそ重要である。
「銃口が開けば外交官は黙る」という馬鹿げた諺は、ビザンティンがそうしたように否定せ
よ。
最も有用な同盟国は、敵に最も近い国である。彼らは、その敵との戦い方を最も熟知している
からだ。
(6) 政権転覆は、勝利への最も安上がりな方法だ。
戦争の費用とリスクに比べれば、実に安上がりなので、不倶戴天の敵に対しても実行を試みる
べきである。
宗教的狂信者でさえ、買収可能であることを忘れるな。ビザンティンは、かなり早い時期から
このことに気付いていた。
狂信者は、もともとクリエイティブなので、自分の大義に背く行動でさえ正当化できるものな
のだ(「イスラムの最終的な勝利は、いずれにせよ明らかなのだから」云々)。
(7) 外交と政権転覆では目的を達成できず、戦争が不可避となった場合には、敵の弱点を衝く
手法と戦術を適用せよ。
消耗戦は避け、辛抱強く徐々に相手を弱体化させよ。時間がかかるかもしれないが、急ぐ必要
はない。
なぜなら、ある敵がいなくなっても、すぐに代わりの敵が必ず現れるからだ。
支配者は入れ替わり、国家は興亡を繰り返すが、帝国は永遠である。
もちろんこれは、自らが帝国を弱体化させなければ、という条件つきではある。
ビザンツ帝国が千年続いたのは、「勝利に真に必要なのは、戦争の勝利ではなく、外交と調略
である」という戦略的教訓を守ったからだ。
戦争が不可避になっても、「戦争をするのは、外交の開始を相手に強制するためである」とい
うことを忘れてはならない、ともルトワックは述べている。
著者は最後に、もしビザンツ帝国が後世に残した遺産をひとつだけ挙げるとすれば、
それはおそらく正教キリスト教でも、ギリシア古典を保持したことでもないだろう。
ビザンツ帝国の最大の遺産は、もっとも厳しい逆境にあっても、
他者をなじませ統合する能力にこそ、社会の強さがあるという教訓である、
で綴じられている。
その歴史を通じて、ビザンツ帝国は次から次へと難局に立ち向かってきた。
三七八年のアドリアノープル、ペルシャ人・アヴェール人・アラブ人の侵入、
九一七年のアンキアロス、一〇七一年のマンツィケルト、一二〇四年の第四回十字軍のコンス
タンティノープル占領。
ビザンツ帝国はこれらすべてから甦った。しかしここに至って、滅亡へ向かう坂道の舞台は整
った。
『ビザンツ帝国 生存戦略の一千年』ジョナサン・ハリス
著者には『ビザンツ帝国の最期』という著作もあるみたいだ。




