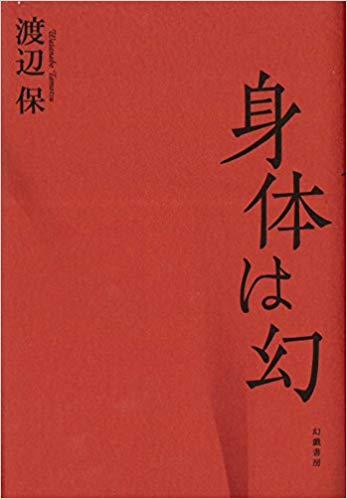
私が見るところ、日本人の身体観は古代から伝わってきたユニークなもので、
単に舞踊だけではなく、文化全体に及んでいるのだが、その独自の身体観が今日うしなわれつ
つある。
むろん必要がないものは失われてもいいが、私にはこの身体観こそ単に舞踊をささえて来たも
のであるばかりでなく、西欧近代の身体観をのりこえる、新しい視点になるものだと思う。
そう思うからこそ、いま、私たちは日本人の身体観について考えるべきだと思うのである。
『身体は幻』渡辺 保
今日うしなわれたものというのは、戦後になって畳と障子の生活を送っていた日本人が、椅子
とテーブルの生活に移り、そのことが日本人の体形も変え、体に対する考え方も変えさせた。
それに加えて近年の傾向である、踊り手も観客も、あまり舞踊について理解していないと思う
ことにしばしば出会うからである、としている。
そこには方法論に対する理解が欠けていること。
それらのことを理解できるような本を書きたいとし、さらにそのためには、方法論をささえて
いる日本文化の構造を解明しなければならい、としている。
著者が本書を著した理由は、この二点だとしている。
渡辺保氏は演劇評論家であり、NHKで放送されている『にっぽんの伝統』で古典芸能について
解説されているのをテレビで観たことがある。
少し前になるが、白洲正子を特集した番組にも出演されているのも観たことがあり、そこでは
白洲正子と一緒に行った、京都にある骨董屋でのエピソードを楽しそうに語られていたのも印
象に残っている。
伝統芸能を語らせたら右に出る者はいないと思うし、その穏やかな語り口から余計に聞き入っ
てしまう。
数多く出版されている著作の方も、『忠臣蔵』や『歌舞伎 型の真髄』、『明治演劇史』なども
眺めてはいるが、氏の代表作であろうと思われる大著『江戸演劇史』や読売文学賞を受賞した
『黙阿弥の明治維新』はまだ目にしていない。

渡辺 保
「踊り手のなかには三人の「私」がいる。これが舞踊の芸の、いやあらゆる日本の舞台芸術に
おける芸という方法論の基本である」(本書)
三人の私とは、本名、芸名、役名であり、芸の世界では、三人の私が舞台のうえに同時に存在
し、しかもこの三人の私は、わかれているようでいて、微妙につながっている。
さらには、この「芸」という方法論が、舞踊ばかりではなく、日本の古くからの芸能のあらゆ
る分野を通じて一貫しているという。
「古来の神楽や舞楽―それらは今日歴史的な資料としてしか見られないが―から、
能、狂言、文楽、歌舞伎の四つの古典劇はもとより、そこから発生した舞踊、音曲、すえは寄
席の人情噺や講談にいたるまで、およそ「芸」と名のつくものには、この方法論が通底してい
るのであって、決して舞踊だけの特殊なものではない。「芸」と名のつくものは全て、同じ方
法論を基本にしている」(本書)
そして、この方法論は明治維新後に導入された西欧近代のリアリズムの「演技」とは鋭く対立
しているとし、「三人の『私』」による方法論は、この混同から厳しく区別されなければなら
ない、と著者は警鐘を鳴らす。
さらに著者は、江戸時代に成立した三味線音楽の舞踊から「素」の思想を導きだす。
三味線音楽の舞踊には、二つの上演のかたちがあり、一つは、衣装付きと呼ばれるものであ
り、劇場で見られるような華やかな舞踊。
もう一つは、素踊りと呼ばれているものであり、簡素な舞踊。
著者は長い間、素踊りは、衣装付きの省略版だとおもっていたが、歌舞伎座の舞踊協会の公演
で、七代目坂東三津五郎の素踊りの「北州」を見たときにその考えが変わったという。
「素踊りはもう一つの別な芸であり、そこには素踊りでなければ味わえない魅力があり、その
ことが踊りばかりでなく、日本文化の底辺にひそんでいる「素」という形態に対する独自の考
え方にあるのではないか、そう思うようになった」(本書)
「素踊りの魅力は、いわば完成した建築の設計図なのである。
設計図は、これから完成する建築の美しさを見る者に想像させるが、それと同時に設計図その
ものの美しさをもっている。その美しさは虚構そのもののもつ美しさである」(本書)
そこから藤原定家の有名な歌に言及し、水墨画や文人画、随筆や私小説、茶の湯に触れなが
ら、「素」の思想の結論に至る。
「素踊りは一方で踊りの設計図であり、しかしその一方には、素顔の「私」と舞台に立つ人格
の「私」を見せながら、劇場とは違う日常現実につながる独自の心的世界をつくり上げた。
ここには水墨画のように色がない、しかし見る者の心には、色よりも深い色がうかび上がる」
(本書)
それを松岡正剛の言葉に直せば、引き算の美学であり、負の想像力ということであろう。
日本舞踊は、舞、踊り、振り、の三つの要素から成り立っているといわれているが、著者はそ
れらの関係性にも独自に紐解いている。
舞とは、能の舞のことで、ドラマ全体のなかに舞を取り入れた部分をいい(歌舞伎は能を土台に
しているので各所に舞が入っている)、宗教色の強い中世にでき、きびしい様式の規制によって
体ががんじがらめになっていて、様式的であり一定の型の繰り返しであると。
踊りは、近世に出雲のお国がはじめたものを歌舞伎踊りというように、歌舞伎の手足を自由に
動かす踊りをいい、様式から解放され、自由自在になっていると。
振りは、二つの意味があるという。
一つは、振付師が舞踊家に指示する動きが振りであり、舞踊家に振りを指示することを振り移
しという。もう一つは、歌舞伎の踊りに特殊な専門用語で、物真似のことをいう。
これらは並列的な関係ではなく、踊りは振りを含むことによって舞から独立し、その歴史的な
記憶から近世に向かって解放されたのである、と著者は指摘する。
舞と踊りを区別しているのは、振りであり、振りは踊りのなかにふくまれている、としてい
る。
「現代の人は観客も、あるいは演者でさえも、笛にかぎらず、日本古典の楽器を誤解してい
る」と指摘し、楽器にも話が及ぶ。
日本の楽器、笛や鼓や大鼓や三味線にしても楽器であって楽器ではない。能あるいは舞踊あっ
ての楽器であり、楽器あっての能でも舞踊でもないという。
笛は、他の楽器や言葉、ドラマと関係することによってはじめて、その独自の力を発揮すると
いう。しかもそれらは、一方通行ではなく、相互補完的に働いているものとなっていて、楽器
をこえた呪術的な力を発揮するものだとしている。
「笛は一節一節の連続音であるのに対して、大小の鼓は短音である。短音は連続音は連続音を
切断する。すなわち笛のつくる空間を鋭く切り裂く。この相交する力が作用して空間は笛だけ
がつくる平面的なものを立体的にする。この立体への転換の力が、魂を呼ぶ大きな呪術的なエ
ネルギーになる」(本書)
笛は抒情的に空間に流れ、大小の鼓は空間を切断するという。
「線としての笛、点として鼓。この二つが拮抗してくるものは、抽象的な空間である。
それに対して、この空間に入ってくるシテの身体は、具象的、日常的、現実的なものである。
この対立拮抗によってシテの身体は、抽象的な儀礼をうけ、日常的なものから抽象的な世界へ
転換する。これが音楽のつくる舞踊の身体であり、その身体から魂があらわれる」(本書)
そのため、能の音楽は単なる音楽ではなく、魂を呼び寄せるための呪術の道具としている。
三味線は、中国から琉球を経て、日本に伝えられたものだが、その課程で、歌の伴奏楽器であ
ったものが、物語を語る楽器になった。
琵琶法師の手に渡り、浄瑠璃語りに渡り、人形浄瑠璃(文楽)の手に渡った。
基本は何かを語る楽器であるが、その特質は、能の関係性と呪術性をそのまま受け継いでい
て、笛や鼓などの方法論が伝承されている。
しかしその一方で、三味線は能にない要素をつけ加えたという。
それは語られる登場人物が中世の亡霊ではなく、現世(近世)の人間の抑圧と解放の中にゆれう
ごく人間たちだったからだとしている。
そこに三味線のもう一つの側面が生まれたという。それは伝統と陶酔。
「近世の文楽や歌舞伎には、やはり人間の魂を呼び寄せたのである。
ただしその人間は過去の亡霊ではなく、現世の人間の内面に潜む魂であった。
その魂が現世の音楽を求めたから三味線が必要になり、そこに陶酔が生まれた。
亡霊と現実の魂との差はあっても、そのことを否定することはできない。
そして、笛と鼓によってつくられた能の舞の身体は、この三味線の陶酔によってつくられた踊
りの身体をつくった。
音楽によって舞踊の身体がつくられるという事実はかわりがないのである」(本書)
「間は魔だよ」と六代目尾上菊五郎が言った言葉から、西欧と対比させながら「間」について
次のように言及している。
「・・・日本の音楽や舞踊では考え方が逆なのである。
言葉と言葉、音と音の間にあるものこそもっとも重要なのであって、それは空白ではない。
逆に言葉や音は、その空白を彩る額ぶちにすぎない」(本書)
「言葉と言葉の間の、言葉のないところがもっとも大事なのである。
その一見空白に見えるところが空白ではないのは、そこに言葉をこえ、言葉ではいい表すこと
のできない無限の心情がつまっているからである。それが舞踊になった」(本書)
終章で「日本人の身体観」としてまとめているが、そこでは、山折哲雄の「日本では神像を人
間の身体に似せてつくることがなかった」や、福沢諭吉の少年の頃の有名なエピソードである
「神の実体を知りたくてわが家の神棚を開けてみた。なかにあったのはたった一枚の白紙。
ほかにはなにもなかった・・・」や、折口信夫の「からだ」の語源の解釈である、「「から」は本
来「殻」であって、空なる外面にすぎない。「だ」は接尾語である。そこに精神が入った状態
を「身」という。「身」が入った「殻」がすなわち人間の「からだ」」などに共通点を見出
し、「神のもっとも神的な本質はイメージにあり、そのイメージはまた人間の身体にも及ぶだ
ろうということである」、「日本人のもつ身体観は、身体をモノとしてとらえるよりも、イメ
ージ化している」として松岡正剛氏とほぼ同様の結論に至っている。
「このような日本人の身体観に立たなければ、日本の伝統的な文化は、どの分野においても理
解できない。伝統的な文化の深層には、この身体観が底流として流れているからである。
私がこれまでさまざまな角度からふれてきた、日本の舞踊の本質―その芸という方法論からは
じまって、変身、素、あるいは見えないものへの志向、イメージ化は、全て、この底流を前提
にしなければ、成立しえないだろう」(本書)
物真似や変身、身体が和服によって隠され、それによってイメージ化され、身体の輪郭が溶け
る、などには触れなかったけど、本書は、舞踊についての、読者の「考えるヒント」になれば
いい、としている、エッセイ風の断章となっている。
伝統舞踊を通して、日本人の身体観を眺めるのも新鮮であったし、政治や経済などを中心とし
て日本の歴史を語るのには限界があるとも感じている(結構前から)。
月今宵あるじの翁舞出でよ
蕪村
名月や院へ召さるゝ白拍子
井月


