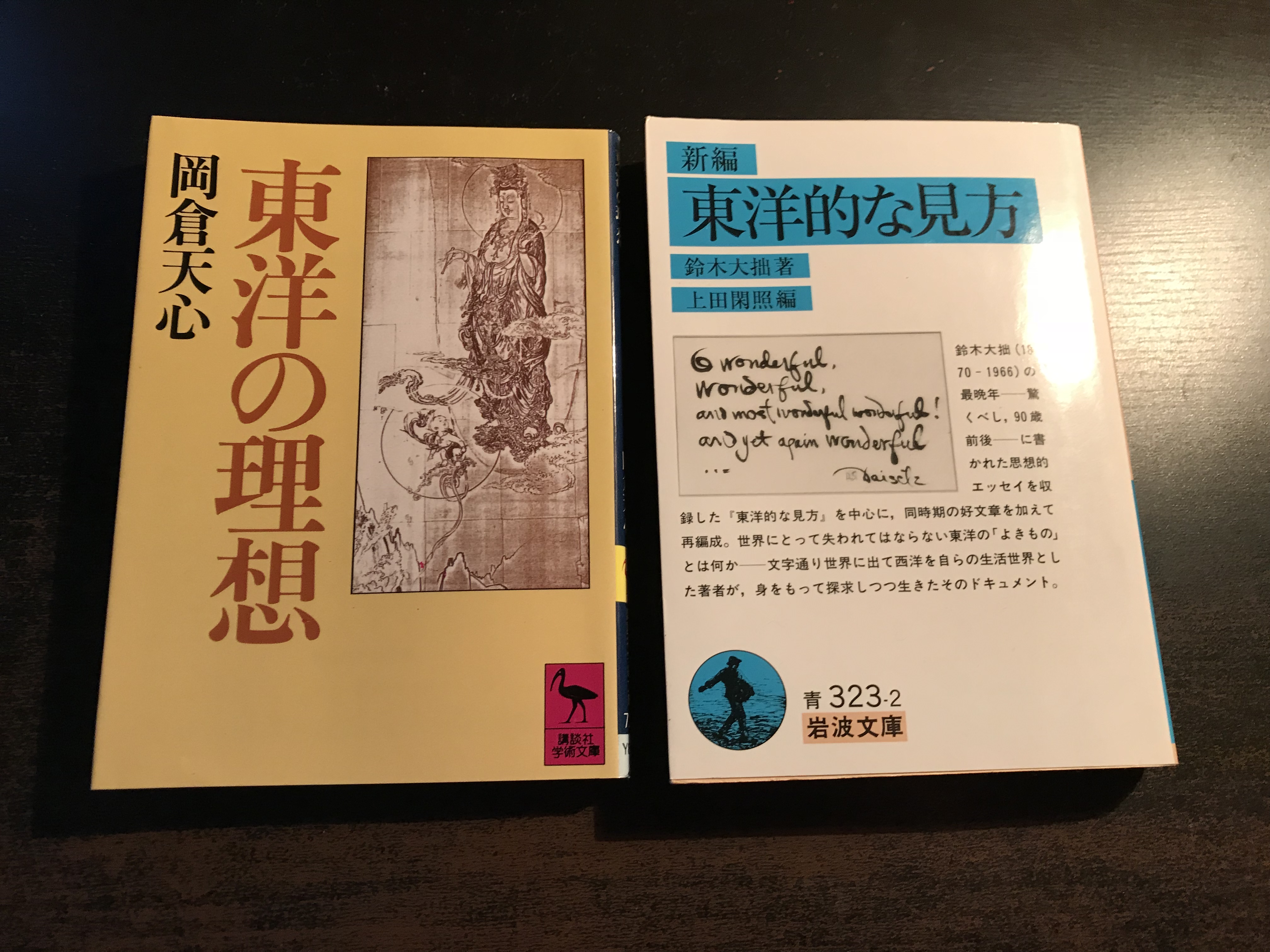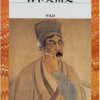副題がキーワード。なのでタイトルの冒頭に副題の「負」の想像力をもってきた。
松岡正剛の本を一冊選べといわれたら、間違いなく本書『山水思想』を選ぶ。
ぼくにとっては、現代に刊行された数ある書物のなかで“名著”的な位置づけ。
少し大袈裟に聞こえるかもしれないが。
でも、それぐらい言いたくなるような出来で、
近現代日本人の“忘れもの”を拾い届けてくれた感じ。もっと評価されてもよい。
(偉そうでごめんなさい)
禅僧で作庭家の枡野俊明氏が著した『禅と禅芸術としての庭』で、
参考文献としてもあげられている。中身が充実している証し。
さて、本題の中身の方ですが、
日本画家、横山操(みさお)の、「日本の水墨画を完成させないで死ぬのは無念だ。
ぼくはもう一度、雪舟から等伯への道程をたどってみたかった」。
松岡氏は「それから四半世紀、この言葉はいまだに問われつづけている」として、
それを継承し、難解な“水墨山水”の秘密に迫る。
これは膨大な東アジアの知識がないと迫れない。岡倉天心を見ればわかる。
松岡氏の叔父が横山操と同じ青龍社に所属していた画家で、松岡家にも遊びに来ていたらし
い。松岡氏の記憶にも残っている。
その横山操の遺言と思しき
“雪舟から等伯”(本書は与謝蕪村、浦上玉堂や富岡鉄斎も出てくる)に至る、
“和様化した水墨山水(「湿潤」と「余白」もしくは「影向」と「消息」)”の流れを、
本書で見事に書かれている。
特に凄いのは、中国で発生した山水の流れから説き起こしていること。
気の概念、北方の三遠(高遠・深遠・平遠)、南の辺角山水、
水暈墨章(すいうんぼくしょう)の誕生の過程、謝赫の「画の六法」、
禅がタオを食べた背景にも言及されているのは、目から鱗が落ちた。
それを一から十まで説明していたらきりがないので、中国山水は重要だが後日に譲るとして、
そのキーフレーズだけ引用しておく。
老荘思想がタオイズムの背景の倫理をつくり、
風水思想が景色の哲学をつくっていったのである。
この二つが歯車になって山水思想の原型がつくられたのだ。
『山水思想』 松岡正剛
話を日本に戻す。
その、日本山水の特徴を松岡氏が上手くまとめてくれている。
第一に、日本の山水は縮小されている。これは広大な中国の大地と比較すれば当然である。
第二に、浄土山水がそうであるように、それらの山水は彼岸の景色に同定された。
すなわちヴァーチャルな想像力の対象となった。
第三に、道元の山水一如の思想がそうなのだが、
そのような「而今(にこん)の山水」は「胸中の山水」にまで高められた。
第四に、その一方で想像力の対象としての山水に日本の実景が少しずつあてはめられた。
垂迹曼荼羅にその発想があらわれた。
ところが第五に、禅林に水墨山水が芽生えると、
その画境が庭園化して枯山水などのような消去的な「負の庭」としての山水の模型をつくりあげた。
しかしながら第六には、その枯山水をもういっぺん画境に戻したときに、
初めて日本の水墨山水が確立することになった。
その画面には、かつて枯山水に流れた見えない水流が飛沫をあげて潤った。
これが雪舟から等伯への道にあたる。
『山水思想』 松岡正剛
ここに「負の介在」があるとし、中国的山水と決定的に別のものにしたとしている。
そして更に踏み込む。
われわれは思い返してみるべきである。
横山大観の『生々流転』はなぜ近代日本を決する作品でありえたのか。
菱田春草が武蔵野を描いた『落葉』はどこが明治最高の作品だったのか。
そして長谷川等伯はなぜ『松林図屏風』を描けたのか。
そこに「負」が流れ、「負」がはたらいていたからであろう。
そういう「負の介在」が横山操が悩んだ日本画の出発点であり、確立点であったはずである。
また思い返すべきである。
『山水思想』 松岡正剛
日本人ならこの「負」の重要性に薄々気が付いているはず。
松岡氏には、『フラジャイル』という「弱さ」や「はかなさ」を題材にした著作もある。
しかも、それは画法ではなかったのだ。
日本人が知っている“方法の魂”とでもいうべきものなのだ。
たとえば定家の幽玄、道元の山水、心敬の冷え寂び、世阿弥の夢幻能、枯山水の庭、
等伯の墨絵、さらには遠州のきれい寂び、芭蕉の俳諧、秋成の物語、
宣長の「もののあはれ」、豊後節や清元の節まわし、良寛の書・・・。
こういうものはすべて「負の介在」によって成立してきた方法の魂だったとおもわれる。
これらは山水画ではないが、すべからく日本の山水だったのである。
『山水思想』 松岡正剛
界を破って、奥を限らない。
「負の介在」の無常の方法の魂。
これが日本を解く鍵でもあるのかな。
本書は、中国や韓国でも出版されたみたいだ。