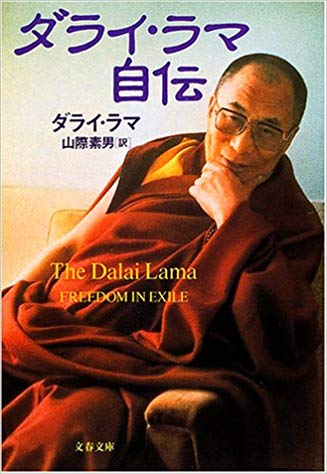
わたしは、チェンレシ(慈悲の観音菩薩)、すなわち“白蓮を持つ人”の生まれ変わりと信じられ
ている歴代十三人のダライ・ラマ(最初のダライ・ラマは西暦一三五一年に生まれた)たちの化身
と考えられている。
そしてまた、仏陀釈迦牟尼の時代に生きていたといわれるバラモンの少年にさかのぼること七
十四世代の観音菩薩と信じられている。
こんなことを本当に信じているのかとよく尋ねられるが、答えるのは容易ではない。
しかし五十六歳になった今日、過ぎし生涯を振り返ってみるとき、また己の仏教徒としての信
仰においても、過去十三人のダライ・ラマ、観音菩薩そして仏陀その人と精神的に結びついてい
るということを躊躇なく受け入れることができる。
『ダライ・ラマ自伝』ダライ・ラマ
「ダライ」とはモンゴル語で「大海」を意味し、「ラマ」とはチベット語で「上師」や「教
師」を意味する。モンゴルのゲルク派に帰依したアルタン・ハーンからたてまつったものであり
(十六世紀後半)、正式には「ヴァジュラダラ・ダライ・ラマ」の称号をたてまつっており、
「ヴァジュラダラ」とはサンスクリットで「金剛をもつもの」という意味。
本書は、世界一有名な仏教徒である十四世ダライ・ラマの誕生(一九三五年)から生い立ち、ダラ
イ・ラマとして即位、中国のチベット侵略やインドに亡命、長きにわたる亡命生活やノーベル平
和賞を受賞した一九八九年頃までを克明に綴った自伝。
今年は天安門事件から三十年でもあるが、中国共産党のチベット侵略から七十年でもある。

ダライ・ラマ14世(1935年7月6日~)
「チベットがまだ自由な国であったときに思いを馳せるにつけ、その頃のわたしの生涯で最良
の日々であったことにあらためて思いを深くする。
今、わたしははっきりと幸せだといえる。だが、今日の在り方は当然のことながら、わたしが
育ってきたものとはひどく異なっている。
ノスタルジアに耽っても仕方がないのはわかっていても、過去を振り返るとどうしても悲しみ
がこみあげてくる。
祖国に残された同胞のひどい苦しみようが浮かび上がってくる。もちろん昔のチベットが完璧
だったというのではない。
しかしわたしたちの生き方は、それなりに評価しうるものであったと信じている。
今日、永久に失われてしまったもののなかには保持しつづけるに足るものがいっぱいあったの
だ」(本書)
そのチベットの自由が奪われたのは、一九四九年から五〇年にかけての中国によるチベット侵
略によってであるが、先代の十三世ダライ・ラマは政治的洞察力も秀で、最後の遺書のなかで次
のように警告していた。
―チベットは、宗教、政府の両方が内外から攻撃を受けるであろう。
もしわれわれみずから自国を守らないなら、ダライとパンチェン・ラマ、父と子、すべての尊敬
すべき宗教的指導者たちはこの国から姿を消し、無名のものとなってしまうであろう。
僧も僧院も絶滅されるだろう。法の支配は弱まり、政府官僚の土地、財産は没収されるだろ
う。彼らは己の敵に奉仕させられ、物乞いのように国を彷徨うことになろう。
すべてのものが塗炭の苦しみに喘ぎ、恐怖にさらされ、昼も夜も苦悩に重い足を曳きずってゆ
くだろう。―
パンチェン・ラマは、ダライ・ラマに次ぐチベットの最高の精神的権威であり、第二の都市シガ
ツェのタシルンポ僧院を所在地にしていた。歴代のパンチェン・ラマは阿弥陀仏(無量光仏)
の化身と信じられている。
十三世ダライ・ラマはその生涯で二度亡命を余儀なくされたが、一度は一九〇三年のイギリス軍
による侵入であり、二度目は一九一〇年の清朝軍の侵略によってであった。
一度目のときは、イギリス軍が自ら撤兵し、二度目の清朝軍のときには、チベット軍の反撃で
退却した。
十三世ダライ・ラマは近代技術に大きな関心をもち、発電機設備や貨幣製造設備や三台の乗用車
を輸入し、四人のチベット少年をイギリスに留学させてもいる。
さらに、軍事力の強化が侵略防止の鍵であることを知り、チベット軍の改革を推し進めてい
た。しかし、十三世ダライ・ラマの死後、イギリスへの留学も軍事改革もいずれも中止されてし
まった。
この留学について十四世ダライ・ラマは嘆きながら「もしその留学が制度化され定期的に送られ
ていたらチベットの今日の状況は大いに異なっていたにちがいない」と語っている。
そして、その十三世ダライ・ラマの予見どおり、恐れていたことが現実のものとなってしまっ
た。
一九五〇年十月、チャムドの東、リチュ河を越えて八万人の人民解放軍がチベット領内に侵入
したという知らせがラサに届けられる。
その前年には、チベットを帝国主義侵略者の手から解放する、と称する中共軍と国境で小競り
合いが始まっていたが、チャムドにいるカム省の知事からの電報で、チベット駐屯地が中国兵
に襲撃され、責任者の将校が殺されたという報告もうけていた。
ラサにいるすべての中国国民党政府機関の官僚も追放していた。しかし、中国政府は中国解放
記念日に、チベットの“平和的解放”を開始したとラジオを通じて発表した。
ダライ・ラマの生まれ故郷であるアムド省のクムブムは中国に隣接しているが、クムブムの僧院
長はダライ・ラマの一番上の兄であった。
クムブムはたちまち中国軍に席巻され、僧侶の活動も禁止され、兄もただちに監視下に置か
れ、僧院に監禁状態となった。案の定、中国側は兄たちに中国の共産主義思想を吹きこみ、屈
服させようと試みた。
さらに中国政府は、もし兄がダライ・ラマを説得して中国支配を受け入れさせるならラサに行か
せてやろうと持ちかけ、ダライ・ラマが受け入れなければダライ・ラマを殺し、代わりに褒賞を
与える、という提案をする。
兄は中国側に同意したふりをしてラサに入り、チベットはどうすればいいのかをダライ・ラマと
政府に話した。その兄の話を聞いたダライ・ラマは絶句した。
「ずいぶんと風変わりな提案をしたものだ。第一、生物を殺すという思想は仏教徒には忌むべ
きことであり、個人的利益を得んがために兄が肉親のダライ・ラマを実際に暗殺するかもしれな
いなどと考えるのは、中国人がチベット人の性格をいかに理解していないかということを示す
以外になにものでもない」(本書)
兄は僧院の誓いを捨て、衣を脱ぎ密使としてアメリカに接触しようと試み、彼らが自由なチベ
ットという考えを支持してくれるだろうと思っていた。
ダライ・ラマはショックを受け、抗議しようとしたが、兄はその前にラサを一刻も早く脱出すべ
きだと主張して譲らず、危機は深刻であり、絶対にわたしが中国の手に陥ってはならぬと、断
固していい張ったという。
それから、首相や内閣に相談し、アメリカ、イギリス、インド、ネパールに使節を送り、また
別の代表団を、撤兵交渉のため中国へ派遣した。
そして、その使節団が出発してからまもなく、中共軍が東部で兵力を強化しているのを知り、
政府の主要メンバーのほとんどを引き連れ南チベットへ移る方針を固めた。
最終目的地は、三ニ〇キロ離れたシッキム(一九七五年インドの州になる)国境と目と鼻の先の
トロモだった。

しかし、トロモに着いてしばらくすると悪い知らせが届く。
ラサを離れる前に派遣していた外国使節団で、目的地に到着したのはわずか一つだけであり、
それは中国向け使節団だった。
これにはダライ・ラマも落胆し、チベットはたった独りで中国に対せねばならなくなった。
さらに、チャムド地区の大半は、すでに中国側の手に落ち、なんらかの解決点を見出さなくて
は、人民解放軍はラサにまもなく侵攻してくるだろう、という知らせも届いた。
ダライ・ラマは六ボルトの電池で聞ける古いラジオ受信機を持っていて、毎晩そのラジオで北京
のチベット語放送を聞いていた。
放送内容の大半は“偉大な祖国”の宣伝だったが、ある晩、一人で坐っていると、いつもとまっ
たく違った番組が流れてきた。
その内容は、中国政府代表と中国側のいうところの“チベット地区政府代表”との間に“チベット
解放十七箇条協定”が調印されたとの発表であった。
アナウンスはつづけて、「過去何百年間」帝国主義的侵略勢力がチベットに入り込み、「欺瞞
と挑発の限りを尽くしてきた」といい、「チベット人民は奴隷と苦痛の地獄に突き落とされて
きた」としていた。ちなみに、その“チベット解放十七箇条協定”は以下のようになっている。
チベット平和解放に関する協約(十七か条協定)─ 一九五一年五月二十三日
第一条
チベット人民は団結して、帝国主義侵略勢力をチベットから駆逐し、チベット人民は中華人民
共和国の祖国の大家族の中に戻る。
第二条
チベット地方政府は、人民解放軍がチベットに進駐して、国防を強化することに積極的に協力
援助する。
第三条
中国人民政治協商会議共同綱額の民族政策に基づき、中央人民政府の統一的指導のもと、チベ
ット人民は民族区域自治を実行する権利を有する。
第四条
チベットの現行政治制度に対しては、中央は変更を加えない。ダライ・ラマの固有の地位およ
び職権にも中央は変更を加えない。各級官吏は従来どおりの職に就く。
第五条
パンチェン・エルデニの固有の地位および職権は維持されるべきである。
第六条
ダライ・ラマ、およびパンチェン・エルデニの固有の地位および職権とは、十三世ダライ・ラ
マおよび九世パンチェン・エルデニが互いに友好関係にあった時期の地位および職権を指す。
第七条
中国人民政治協商会議共同綱領が規定する宗教信仰自由の政策を実行し、チベット人民の宗教
信仰と風俗習慣を尊重し、ラマ寺廟を保護する。寺廟の収入には中央は変更を加えない。
第八条
チベット軍は逐次人民解放軍に改編し、中華人民共和国国防武装兵力の一部とする。
第九条
チベットの実際状況に基づき、チベット民族の言語、文字およぴ学校教育を逐次発展させる。
第十条
チベットの実際状況に基づき、チベットの農・牧畜・商工業を逐次発展させ、人民の生活を改
善する。
第十一条
チベットに関する各種の改革は、中央は強制しない。チベット地方政府はみずから進んで改革
を進め、人民が改革の要求を提出した場合、チベットの指導者と協議する方法によってこれを
解決する。
第十二条
過去において帝国主義と親しかった官吏および国民党と親しかった官吏は、帝国主義および国
民党との関係を断固離脱し、破壊と反抗を行わない限り、そのまま職にあってよく、過去は問
わない。
第十三条
チベットに進駐する人民解放軍は、前記各項の政策を遵守する。同時に取引きは公正にし、人
民の針二今糸一本といえども取らない。
第十四条
中央人民政府は、チベット地区のいっさいの渉外事項を統一して処理し、かつ平等、互恵、お
よぴ領土主権の相互尊重という基礎の上に隣邦と平和な関係を保ち、公平な通商貿易関係を樹
立発展させる。
第十五条
本協約の施行を保証するため、中央人民政府はチベットに軍政委員会および軍区司令部を設立
する。中央人民政府が派遣する人員以外に、できるだけチベット地方の人員を吸収して工作に
参加させる。
軍政委員会に参加するチベット地方の人員には、チベット地方政府および各地区・各主要寺廟
の愛国分子を含むことができ、中央人民政府が指定する代表と関係各方面が協議して名簿を提
出し、中央人民政府に任命を申請する。
第十六条
軍政委員会、軍区司令部、およびチベット進駐人民解放軍の所要経費は、中央人民政府が支給
する。チベット人民政府は、人民解放軍の食糧およびその他、日用品の購買と運輸に協力する
ものとする。
第十七条
本協約は署名捺印ののち、直ちに効力を発する。
以上は、ダライ・ラマ法王日本代表部事務所 (チベットハウス・ジャパン)のホームページから
転載
これを聞いたダライ・ラマは吐気がしてきたという。
協定第一条に関しては、チベットに駐屯した外国勢力は、一九一二年に掃討された清朝軍をも
って最後とするし、その当時チベットには一握りのヨーロッパ人しか存在してなかった。
しかも「祖国に復帰する」というのはなんと恥知らずな作り話だろうと。
「チベットはかつて一度たりとも中国の一部であったことはない。(中略)
かつてチベットのほうが中国の広範な領土の領有権を主張したことがありこそすれ、だ。
なによりも、わが各民族は人種分類学的にも人種的にもはっきりしているし、言語も文字も中
国のそれとはまったく異なっている」(本書)
中国に送った使節団には、いかなる文書にも署名する権限を与えられておらず、単に交渉に赴
いただけであった。
後年になってから、このときの代表団のあるものが、回想録のなかで、北京で脅迫されて“協
定”にサインさせられ、中国側が偽りの国璽を使用したということなどを記述しているという。
しかし、当時のダライ・ラマにできることは、何が起こったのかを想像するしかなかった。
ただ一つわかったことは、新しいチベットの総督として張経武将軍がインド経由でトロモに来
ると通告してきたことだった。
長兄やハインリッヒ・ハーラーからの手紙には、インドに亡命したほうがいいとし、トロモに来
た大僧院大学学長などはラサに戻るよう主張した。
ダライ・ラマはジレンマに陥るが、ここは中国の将軍の到着を待つのが最上の道、という結論に
達した。彼もまた“人の子”ならん、という希望のもとに。
一九五一年七月十六日に、中国代表団はトロモに到着した。
張経武将軍は開口一番十七箇条“協定”のことを尋ね、さらには、中国が真摯な友情を抱いてや
ってきたことはすぐにわかるであろうといい、たとえ亡命しても自分の国にきっと戻ってきた
いと思うにちがいないと仄めかしていた。
そういうことになれば両手をひろげて歓迎されるだろうから、チベットを離れる意味がないと
もいい、張経武将軍はダライ・ラマがラサに帰るときに同行し、“象徴的”に一緒に町に入りたが
っているのは明らかだったと。
結局ダライ・ラマはラサに帰還するが、途中の村々では、中国は友好を唱えているが、 それは
侵略でしかないことを直接人々に訴えてまわった。
それと同時に宗教的教訓も付け加えることを忘れなかった。この方式は今日も変わらずつづけ
られている。
九ヵ月ぶりにラサに戻ると盛大な歓迎式が催された。
まるで国中の人がダライ・ラマを見に現れ、帰還を喜んでくれているようであった。
ダライ・ラマも深い感動を受け、同時にわが家に戻ったという大きな喜びを感じたという。
しかし、ダライ・ラマの留守中、ラサには、アムド、カム地区のチベット人虐待を告げる数々の
報告が届いていた。国民の多くはチベットの将来に大きな不安を抱いていた。
ダライ・ラマは伝統に従い、護衛兵の本部で張経武将軍を引見したが、張は突然怒りだし、なぜ
こんなところで会うのか、こんなつまらない場所でなくどこか別のところを選べないのかと詰
め寄ったという。
「彼の怒り方は、中国人の間ではどうも日常的な表現だということに気づいた。
これはきっとある人びとに、それも自分の感情を徹底的に抑える傾向のある
ヨーロッパ人やアメリカ人にきわめて慇懃に扱われているせいではなかろうかと思う」(本書)
それでもトロモからラサに帰還した最初の五、六週間は“蜜月”関係だったとダライ・ラマはい
う。しかし、それも一九五一年十月二十六日、三千の第一八歩兵部隊がラサに侵入したことで
終わりを告げた。さらに、二万にのぼる最後の派遣軍の到着により深刻な食糧難が発生した。
当初、中国側は、人民解放軍は公正な売買を守り、「人民から針一本、糸一本すら勝手に取り
上げない」と謳っている十七箇条“協定”を遵守するかにみえたが、この制度はまもなく崩れて
しまった。代価の支払いは中止され、中共軍は食糧を要求し、宿泊施設は彼らの権利として強
要された。
中国から役人が来れば来るほど、首相と中国当局者との間は険悪化する一方であり、
中国側は、十七箇条“協定”が規定しているように、チベットのことはチベット政府が処理する
という原則を認めるどころか、絶え間ない干渉を行った。
「ある意味で、仮想敵は友人より価値がある、なぜなら敵のほうが、自制心などといった友人
なら教えてくれないようなことをいろいろと教えてくれたからだ、という仏陀の教訓は、今も
大切に思っている。
さらにわたしは、いかに逆境が訪れようとも、いつかは好転に向かうという固い信念をこれに
付け加えている。
最後には、真実、正義、人間的理解といったものへのすべての人間に備わった生来的欲求が、
無明と絶望に打ち克つのだ。
中国がわれわれを押さえつければ押さえつけるほど、わたしたちは逞しくなってゆくのだ」
(本書)
一九五四年の初め、ダライ・ラマは中国に招待された。
多くの者が反対したが、家族や討論指導教師、閣僚、その他多勢の官僚を含む総勢五百人の随
行員を引き連れて出発した。
成都から西安に行き、そこから列車で北京に行き、北京駅では周恩来(首相)と朱徳(副主席)が
出迎えていた。

北京では毛沢東と会見するが、毛沢東は、十七箇条“協定”の条項すべてを実行に移すのは時期
尚早とし、とくにそのうちの一項目はしばらく不問に付すのが賢明だと思う、としていた。
さらに後日の会談では、中国がチベットに存在する目的はすべてチベットを援助するためのも
のであるといい、「チベットは偉大な国だ。素晴らしい歴史を有し、昔、中国の大きな部分を
征服しさえした。しかし今歴史に取り残されており、われわれはその遅れを取り戻す手伝いを
しようとしているのだ。だが、二十年もすればそちらのほうが進み、われわれを助ける番にま
わるだろう」ともいった。
ダライ・ラマは毛沢東と会談し、外交辞令でいっているようにはみえなく、中国との連携の可能
性を本気で考えはじめたという。

中央の毛沢東の右がダライ・ラマ
だが、帰国する前にも毛沢東と会見しているが、その時には、ぐっと身体を近づけて、
「あなたの態度はとてもいい、だが、宗教は毒だ。
第一に、人口を減少させる。なぜなら僧侶と尼僧は独身でいなくてはならないし、
第二に、宗教は物質的進歩を無視するからだ」
といった。これを聞いたダライ・ラマは突然非常なおそれを抱いたという。
一九五五年六月、ラサに帰還すると、何千という人びとの歓迎を受けた。
しかし、多くのチベット人はチベットの生活様式そのものが中国によって壊されるのを非常に
恐れていた。
チベットの外側世界もチベットに背を向けはじめ、インドはパーンチ・シーラ(平和五原則)とし
て知られる覚書を含む中国・インド条約を結び、それにより、インドと中国は相互の国内問題に
はいかなる場合でも干渉しないことを認めた。この条約に従えばチベットは中国の一部であっ
たと。
さらにチベット国内でも中国に近いカムとアムドにおける中国側の動きについて不吉な情報が
届きはじめた。
あらゆるかたちの“改革”を一方的に押しつけはじめ、家屋、土地、家畜に対する新しい課税が
強制され、僧院の内容物まで課税の対象とされた。
広大な土地が没収され、各地の中国人幹部によって再配分された。地主は公然と糾弾され、
“人民に対する罪”によって罰され、死刑に処される者まで出てきた。
また僧院の活動が全面的に妨げられ、地方住民が反宗教的思想を吹き込まれ、僧や尼僧はひど
いいやがらせを受け、公衆の前で辱めを受けている、という不吉な情報も入ってきた。
一九五五年末に向け、毛沢東は代案に従い、軍事委員会による統治の代わりに、チベット自治
区準備委員会(PCART)の発足が着手されていた。
そのPCARTの発足準備は着々と進み、わずか数カ月で、中国側はチベット人を使役し、三つの
大きな建物、中国人関係者の宿舎、大浴場、公会堂を建設した。
公会堂はポタラ宮殿の真ん前に建てられた。PCARTは、自治を目指す重要な方向に進むと約束
していたが、現実は逆であった。
チベットではカンパ/アムド自由解放同盟軍なるものも組織されるが、中国側は四万人の軍隊の
増強をした。これはダライ・ラマが恐れていたことであり、そのときの心境を次のように語って
いる。
「レジスタンスがいかに成功しようとも、相手側は、最終的に圧倒的な軍と火力によってそれ
を制圧するのは目に見えていたからだ。
だが、カムのリタン僧院を爆撃するとは予想だにしていなかった。その報に接したとき、声を
放って泣いた。人間がこんなに酷いことをやれるなどとは信じられなかった。
この爆撃につづいて、父や夫が抵抗運動に参加した家族の妻や子供たちが残酷な拷問と処刑に
さらされ、僧や尼僧にぞっとする凌辱が加えられた」(本書)
ダライ・ラマは毛沢東に手紙を書いた。何通か書いて送ったが返事はなかった。
この頃からダライ・ラマは、毛沢東の言葉は美しいが夢まぼろしにすぎないことに気づきはじめ
たという。
その後ダライ・ラマは中国側に許可をとりインドを訪れ、ネール首相と周恩来などと会談し、
ブッダガヤやサルナートなどを訪れるが、重い心を背負いラサに戻る。
「色彩豊かなチベットの祈願幟のなかに、中華人民共和国領を宣する一ダースほどの真っ赤な
血にも似た赤旗が風にはためいていた」(本書)
ラサに戻ると、すべてのチベット人は中国当局と正直で公正な応対をしなければならないと強
調し、だれがそれを犯そうと、人が罪を犯すのを見たらその過ちを匡さねばならない、そして
十七箇条“協定”の原則を厳しく守るよう人びとに説いた。
さらには、中国はチベット人を援助するためにチベットに入ってきたのだという中国側の言葉
を信じるとも述べている。
しかし、そのような楽観論は東チベットで広がる戦さのニュースで次々と打ち砕かれていっ
た。
カムとアムド全地域が戦闘状態に突入し、解放戦士は日に日に数を増し、中国側に対する襲撃
は大胆さを強めていった。
中国軍も容赦なく反撃し、町や村は爆撃、砲撃によって広い地域が廃墟と化した。そのため数
千にのぼる難民がラサに逃げこみ、市の外の空地にキャンプを張った。
人びとのもたらした恐ろしい話の数々は、あまりに残酷で何年も信じる気になれなかったほど
だったという。
磔、生体解剖、腹を裂き内臓を暴き出す、手足の切断などざらであり、打ち首、焙り殺し、撲
殺、生き埋め、馬で曳きずりまわして殺したり、逆さ吊り、手足を縛って氷った水に投げ込み
殺すといった残虐さは枚挙にいとまがなかった。処刑の最中に「ダライ・ラマ万歳」と叫べない
よう舌を引き抜いたりもしていた。
将来を考えれば考えるほど悲観的になり、ダライ・ラマたちがどうしようと、遅かれ早かれチベ
ットは宗教、文化の自由のない、ましてや言論の自由などまったくない、中国帝国の一属国に
成り下がるしかないように思えた。
ラサも中国の侵略以来かなり変化し、中国共産党官僚とその家族たちの暮らすまったく新しい
地区が出現していた。
彼らは病院や学校、いくつもの兵舎を新築したが、チベット人はほとんどその恩恵はこうむっ
ていなかった。
すでに、近代的中国人街が古い都をいつの日か埋没させるであろう兆しが始まっていた。
カム、アムドの全域の戦いは中央チベットに拡大していた。
中国側の残虐行為を逃れてきた数千の新たな難民がラサ市外で野宿生活を始め、すでにラサの
人口は以前の倍に膨れ上がっていた。
「毎朝早く、沈黙の祝福の中に小さな仏像が佇立する古い祭壇の前で祈りを捧げ、生きとし生
けるものへのいや増す憐愍の思いに沈潜し、敵はわが最大の教師であるという仏陀の教えにひ
たすら思いをいたすのであった。
そしてこの教えのむずかしさにぶつかるとき、その深遠な正しさを決して疑うことはなかっ
た」(本書)
ダライ・ラマの安否を気遣っていた市民は、ダライ・ラマを直接守ろうとし、あるものは一団と
なって離宮の入口を固め、あるものは周囲をパトロールしはじめ、その数はおよそ三万人にも
達していたという。
この報を聞いたダライ・ラマは背筋が寒くなったという。激情に駆られ、群衆は中国駐留軍を襲
うかもしないと考えた。
中国側も、チベット政府は中国に対する扇動をひそかに組織していると攻撃し、最後通牒を突
きつけてきた。
さらには、ラサの婦人たちまでもが中国側に異議を唱えるために大衆デモを組織した。

ダライ・ラマはお告げ師の“ネチュン”を呼び寄せ、留まるべきか、脱出するべきか、どうすれば
いいのか相談した。お告げ師は、ラサに留まり中国側との対決をつづけるべきだとはっきりい
った。今度ばかりは、それが最良の行動かどうか確信がもてなく、別のご宣託“モ”をやってみ
たが、結果は同じだった。
翌日ふたたびお告げ師の助けを求めた。
今度は「行け、今夜行くのだ!」と霊媒はそう叫び、憑依状態のままお告げ師は前方によろめ
き、紙とペンを取るや、ノルブリンカからインド国境の最終点の町までのルートを書き写し
た。そのとき、“お告げ”の言葉を確認するかのように、離宮の北門のほうから機銃掃射の音が
響きわたったという。
さらに、お告げ師の決定を確かめるために、“モ”占いをもう一度やり、答えは“イエス”だっ
た。
「わたしが宮殿にいさえしなければ、人びとは外で頑張り通す理由がなくなってしまう。
わたしは“お告げ”を受け入れることに決めた」(本書)
ダライ・ラマは最後に守護神であるマハーカラ(大黒天)を祠った寺院にお参りをし、宮殿を離れ
た。二週間後にルンツェゾンに到着し、十七箇条“協定”を公式に否認し、チベットの唯一正当
な行政機関であるダライ・ラマの新政府樹立を宣言するためにだけわずか二晩滞在した。
インド政府が亡命受け入れの意思があることを確認し、ラサから警護してくれた兵士や解放戦
士たちに別れを告げインドに向かった。
ダライ・ラマが脱出して四十八時間後に、中共軍が離宮を砲撃、現場に留まっていた無防備の群
衆に機銃の一斉射撃を浴びせたという。
「涙ながらに人びとに別れを告げ、ゾモの広い背に担ぎ上げられた。馬に乗るにはまだ無理な
状態だったのだ。かくて、わたしはこの不細工な乗物にわれとわが身、そして国民の運命を托
して祖国最後の地を離れたのである」(本書)
以上が本書前半部分であり、後半は長きにわたる亡命生活の苦悩や宗教指導者たちとの交流、
世界平和への願いなどが語られている。
そして、ダライ・ラマは本書の最後を次の言葉で締めくくっている。
世界が苦しみに耐え
生類が苦しみつづけているかぎり
この世の苦痛を取り除くために
願わくはわたしもまたそれまで
共にとどまらんことを
チベットに限らず、ウイグルや南モンゴルなどでも今現在行われていることは、明末清初(十七
世紀)の王夫之が主張していたことと一致する。
「中国人は蛮族に関して、彼らを虐殺することは無慈悲な行為ではなく、彼らを騙すのは不実
ではなく、彼らの土地や財産を盗むのは不正ではないと考えてよい」
『サンデー・テレグラフ』北京特派員を務めていたイギリスのジャーナリスト、デイヴィッド・
アイマーは数年前にチベットを訪れ、その様子を次のように語っている。
「ラサはすでに舵取りのないまま漂う都市で、過去と現在の間で板挟みとなり、寂れていく僧
院と広い空へとそびえる魅惑的な新しい集合住宅群のどちらを取るか厳しい選択を迫られてい
る」(『辺境中国』)
「消毒されて鎮圧され、チベットはテーマパークと化している。まもなく私はこう悟った。
観光客に踏みならされた道を避けなければ、もっと本物らしいラサは見つからない。
ポタラ宮のようにミイラ化されることもなく、中国全域を支配する物質主義的光景に呑み込ま
れていくこともないラサは―」(『辺境中国』)

チベットのどの僧院にも、ダライ・ラマが北インドのダラム・サラでの亡命生活から戻ってきた
ときに備えて玉座が残されているという。
[観音菩薩の]化身である偉大な護法王は
ちょうど七十年間王位を保ち
寺を建立して仏教を盛んにし
三宝に奉仕して仏法に則った政を行った。(中略)
衆生の利益のためにブッダが人に化身したお方
観音菩薩そのものであるお方
罪ある者を仏教に帰依させる慈悲を持つお方
あらゆる衆生にとってのただ一人の守護者
化身の護法王に帰命します。
私たちに観音菩薩の加持をお与えください。
『チベット仏教王伝』ソナム・ギェルツェン



