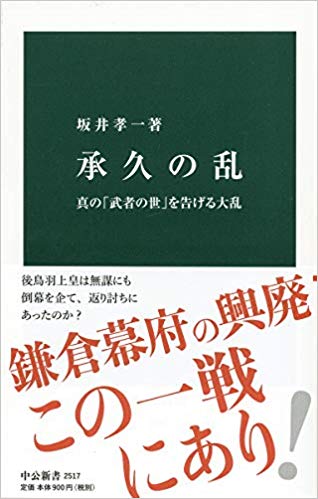
一二一九年、鎌倉幕府三代将軍・源実朝が暗殺された。
朝廷との協調に努めた実朝の死により公武関係は動揺。
二年後、承久の乱が勃発する・・・
『承久の乱-真の「武者の世」を告げる大乱』坂井 孝一
本書では、先入観に基づく一般的イメージを払拭し、研究の進展に即した「承久の乱」像を描
きたい、としている。
そして、その論述にあたっては二つの視座を重視している。
第一は、院政および鎌倉幕府の成立・発展という大きな歴史の流れの中に乱を位置づけること。
承久の乱は院が起こした兵乱であり、乱後には三人の院が流罪となった。
当時、朝廷政治の中心にいたのは院であり、院政という政治形態を抜きにして論じることはで
きない。
また、後鳥羽が意図したのは北条義時追討であったが、そもそも義時は鎌倉幕府の執権。
鎌倉幕府の成立と発展に目を配ることなくして乱を論じることはできない。
第二は、一般の読者にも理解しやすいよう、現代社会との比較、現代であればどのような事象
に相当するかといった点を意識しつつ歴史像を描き出すこと。
「「承久の乱」は、朝廷の最高権力者たる後鳥羽院(上皇)が鎌倉幕府を倒す目的で起こした兵
乱、というのが一般的なイメージであろう。
確かに、乱を境に朝廷と幕府の力関係は大きく変わった。この点だけを取り上げれば、朝廷が
幕府を倒そうとして失敗した事件ということになる。
ただ、そこには、朝廷と幕府を対立する存在とみなす先入観が働いているように思われる。
また、ほぼ百年後、倒幕を企てた後醍醐天皇が、後鳥羽の配流地である隠岐島に流されたとい
う事実も影響しているのかもしれない。
しかし、研究の進展によって、朝廷と幕府の関係は対立の構図だけで捉えられるものではな
く、後鳥羽が目指したのも執権北条義時の追討であって倒幕ではなかったことが明らかになっ
てきた」(本書)
上述のように、かつては、後鳥羽が目指したのは「倒幕」であったとする説が有力であった。
現在の学界にも、その説があるという。
しかし、承久元年(一二一九)から同三年に至る後鳥羽の動きや、承久の乱について記す鎌倉期
の史料から「倒幕」の二文字を読み取ることは難しいという。

(左)後鳥羽院像(伝藤原信実筆、水無瀬神宮蔵)(右)源実朝像
『新古今和歌集』を自ら主導し編纂した後鳥羽、『金槐和歌集』を自選した実朝。
折口信夫は、「後鳥羽院は歴代天子の中で、第一流の文学の天分を示して入らっしゃる。
歌人としては、勿論、第一位に捉えてよい方である。
定家・家隆をはじめ新古今同人の誰よりも、或は優れて居られたかも知れぬ。
唯、院躬(みずか)らそれを知り過ぎて居られた様に見える。
そのあまりとして院の好みが、多く新古今に現れ過ぎた。
この技巧は連歌から習得せられたものが多い様だ」
「こうした古今と万葉との対立の為に、当時の人は、万葉を読んでもその影響は、
自覚的にはうけ容れなかったもの、と見た方がよさそうだ。
実朝は、そうした間に、習得し、会得することもあったであろう。
又多少予期してもよかろうと思われる添刪(てんさく)を経て、ああした歌をこしらえ出したも
のであろう。(中略)
彼のよい方の歌には万葉の調子の外に、讃歌調があり、極、くだけた無心態度の自由さから、
世相を詠んだものなどが出て、それが融合しているのである。
単純に万葉一本の調子とは言えないようである」
と、後鳥羽と実朝の歌を評している。

鶴岡八幡宮境内
本書では、十一世紀末の応徳三年(一〇八六)、白河の譲位によって始まった院政「治天の君」
あたりから説き起こす(「序章 中世の幕開き」)。
白河の強烈な個性とあいまって公家政権の政治形態として定着、それが鳥羽・後白河に受け継が
れ発展した。
一方の武士らは、院政期に勢力を増大させ、「武者の世」の到来を告げる保元の乱を経て王権
を動揺させるまで成長する。
そして、十二世紀末には源頼朝が史上初の本格的武家政権、鎌倉幕府を樹立するまで力を得て
いた。
しかし、公家と武家との関係は、依然として公家である朝廷が優位を保っていた。
多芸多才な才能に恵まれ、日本全土を統治する正統な王たろうとした「治天の君」後鳥羽は、
三代将軍源実朝の幕府とも協調関係にあった。
十三世紀初頭は、朝廷の政治・文化の興隆期であり、公武関係の安定期であった。
ちなみに、本書では言及されていないが、仏師の運慶はこの頃に朝廷と幕府を行き来し、鎌倉
幕府の中枢を担った人物たちと関係を長くもっている。
こうした仏師は運慶以外にはいなかったという。(『運慶のまなざし』金子啓明)
そして、その絶頂期には、後鳥羽の新王を将軍に推戴し、右大臣に昇った実朝が補佐をすると
いう朝廷と幕府の合意であった。
後鳥羽は我が子や実朝を通じて幕府をコントロール下に置き、実朝は幕府を「東国の王権」と
して発展させる、という思惑があった。
しかし、建保七年(一二一九)一月、鶴岡八幡宮の境内で六十センチ余りの雪が降り積もる中、
実朝が甥の公暁に斬殺されてしまう。
幕府は九条道家の子三寅(のちの頼経)を将軍予定者に立て、北条政子・義時姉弟を中心とした新
たな体制を築いた。
京都では、承久七年(一二一九)七月、源頼茂の謀反により、王権の象徴たる大内裏が焼失する
という事件が起きる。
幕府との駆け引き、実朝の横死、などでストレスが蓄積されていたが、大内裏の焼失が決定打
となり、後鳥羽は一ヵ月以上も病床に伏している。
失意の中、後鳥羽は再建に着手するが、全国的な造内裏役に対する抵抗にあい、苛立ちを募ら
せる。
大内裏の焼失は幕府内の権力闘争が都に持ち込まれたことが原因、と考えた後鳥羽は、実朝の
横死後、幕府をコントロールすることができなくなった元凶、北条義時を排除する決意を固
め、大内裏の再建を中止し、北条義時追討の院宣・官宣旨を下す。
そして、承久の乱が勃発する。
「後鳥羽が目指したのは義時を排除して幕府をコントロール下に置くことであり、倒幕でも武
士の否定でもなかった。
それは、院宣に義時の「奉行の停止」し、すべて「叡襟に決す」と記していることから明らか
である」(本書)
「自ら武芸を練り、有力な在京御家人をも指揮下に置いた後鳥羽が目指したのは、
あくまで義時を追討して幕府をコントロール下に置くことであった。
しかし、幕府首脳部が義時追討の院宣・官宣旨を幕府全体への攻撃に読み替え、
存亡の危機感を煽ったことにより、鎌倉方の御家人たちは結果、大挙して進撃し、
後鳥羽の京方に圧倒的な勝利をおさめた。
後鳥羽をはじめとした三人の院が流罪となり、京方の貴族・僧侶・武士が多数処刑・配流された」
(本書)
巨大な存在であった後鳥羽を倒した幕府は、それ以降、存在感を増した。
治天の君・天皇の選定権を握り、京都に六波羅探題を設置、西国守護を京方の在京御家人から東
国の有力御家人に替え、没収地には新補地頭を補任した。
その結果、多数の東国御家人が西国に移住し、幕府の支配権、東国の秩序が京都・西国に浸透し
た。
「幕府による戦後処理の中で、人々が衝撃を受けたのはいうまでもなく後鳥羽の隠岐配流であ
った。
人並みはずれたマルチな才能を持った文化の巨人であり、誰もが認める強大な権力と権威によ
って君臨した帝王が、武家の力によって、都から遠く離れた孤島へと流されたのである。
人々の衝撃は現代の我々の想像を絶するものであったろう」(本書)
承久の乱は公家政権と武家政権の力関係を逆転させ、全国規模で社会的大変動を起こした。
乱に勝利した幕府は王権をコントロールする方向へと一歩踏み出した。
それ以降、後醍醐天皇による建武の新政はあったが(二年間)、幕末の大政奉還によって政権を
天皇に返上するまで、武家は自らの優位性を公家に渡すことはなかった。
「「武」の力によって「王権」の巨人後鳥羽が倒された承久の乱は、「武者の世」の到来を告
げた保元の乱から六十五年に及ぶ戦乱の世に終止符を打った。
と同時に人々を歴史の回顧、そして反省へと向かわせることにもなったのである」(本書)
この激動の時代を生きた人々の間には、崇徳院、安徳天皇、藤原頼長、信西、俊寛らの貴族や
僧侶、源義朝、為朝、義仲や平清盛、知盛、重衡らの源平の武将、などを追慕・鎮魂しようとす
る気運が高まっていった。
そうした背景に、一二三〇年代から四〇年代初めにかけて、『承久記』の原型の成立とほぼ時
を同じくして、保元の乱、平治の乱、治承・寿永の乱を活写した『保元物語』『平治物語』『平
家物語』の原型が作られていった。
これらの軍記物語は、敗れ去って死んでいった者への追慕・鎮魂という基盤の上に成立した。
しかし、それとは反対に「武」の力を認め、源義経などの英雄像を創出してもいる。
最近の研究結果で明らかだが、この時代(中世前期・十二~十四世紀)は他のどの時代よりも短命
だったことがわかっている。
乱後に幕府は、執権北条泰時が主導し、相次いで法令を出している。
その到達点が『御成敗式目』(一二三二年[貞永元年]/『貞永式目』とも)であり、十一人の評定
衆が連署した「起請文」に「相州(時房)・武州(泰時)」が「理非決断の職」として署判を加え、
形を整えて制定している。
山本七平は『御成敗式目』を高評価し、「それはまさに日本人によって制定された日本人の法
であった」「これは外国から輸入した継受法でなく、自らの規範を条文化した日本ではじめて
の固有法である」と述べている。
本書は新書とは思えないほど詳細に書かれており、複雑な時代を扱ってはいるが理路整然とし
て、かなり読みやすくなっている。
私見だが、何らかの賞を受賞されるのではないか、と感じさせるくらいの出来栄えになってい
る。
著者は中世史がご専門で、その他にも『源実朝』(講談社選書メチエ)や『人をあるく 源頼朝と
鎌倉』(吉川弘文館)などを著されている。
古代半ば、十世紀の延喜の聖代に軍事貴族として武士が誕生してから三百余年、
中世初頭、十一世紀に院政が始まってから百三十五年、「武者の世」が到来したと人々が感じ
た保元の乱から六十五年、「真の武者の世」は承久三年に始まったのである。
承久の乱とは、それほどまでに「画期的な大事件」であり、大きな意味を持つ歴史の転換点で
あった。
『承久の乱-真の「武者の世」を告げる大乱』坂井 孝一
「関ヶ原」はしばしば「天下分け目の戦い」と言われる。
しかし歴史的な分かれ道という意味では「承久の乱」こそ天下分け目の戦いであっただろう。
というのは関ヶ原はいずれが勝っても武家政権という体制の基本には変化はないが、
承久の乱は律令以来の天皇制に終止符を打ち、新しい法律の下に武家が政権を担当することを
決定づけた戦いであり、その勝敗は体制そのものに関連するからである。
『日本的革命の哲学』山本七平


