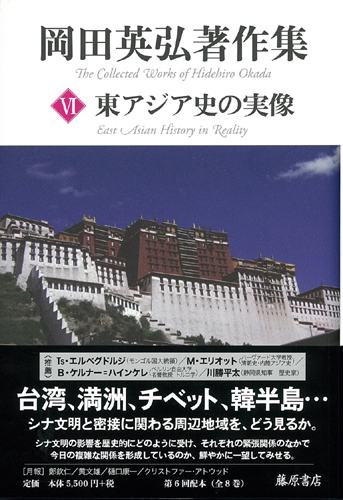
現代の中国は、清朝の実像を葬り去って、
清朝からの連続線上に新しい中国がある、としている。
『東アジア史の実像 Ⅵ』岡田英弘
ある意味においては、上の言葉が本書のあらましを示している。
通説では、清朝の連続として今の中国を位置づけて捉えているが、
本書ではその見方を否定されている。
清朝とういうのは、古代から現代まで繋がるシナの一時期である、
というのが通説になっているが、そうではない。清朝はシナとイコールではない。
清朝はモンゴルと不可分であり、分けてはならない。
元朝はモンゴル帝国の一部であり、清朝はその元朝を継承した。
『東アジア史の実像 Ⅵ』岡田英弘
以前紹介した、岡本隆司氏の『中国の論理』でも、次のように説明している。
20世紀の初めの漢人たちは、
nationたる「中国」を既存の清朝と重ね合わせて構想したから、
その範囲を主権が及ぶ「中国」の領土であり、
そこにすむ人々を「中国」の国民であるとみなした。
そして、そこにも「華」「夷」の上下関係・優劣意識が作用している。
つまり、清朝の範囲内に暮らすモンゴル人・チベット人は、
自分たち漢人より下位に属するので、その住地と一体化して同化すべきだ、
という論理になった。
たとえば、「五族共和」、「中華民族」をとなえた孫文は、
漢人への「同化」がその意味内容だと明言している。
現代の「中華民族」を定義する「多元一体」も、その言い換えにすぎず、
したがって習金平が「中国の夢」だと語る「中華民族の復興」も、
ほとんど意味はかわらない。
チベット人・ウイグル人が反撥するゆえんである。
かつて中華に属したことがあれば、そこに「中国」の領土主権がある、という論理は、
モンゴル・チベットという民族問題にも、尖閣・南沙という領土問題にも共通する。
『中国の論理』岡本隆司
としている。
『大清帝国と中華の混迷』のなかで平野聡氏も、
近現代中国が支配する地理的な範囲は、この儒学・漢字・漢人の広がりとは
まったくずれていて、一致していない。
したがって古来この領域の中で「中華」の文明世界が花開き、
さまざまな王朝が栄枯盛衰を繰り返した結果として
近現代中国が出来上がったと考えるのは間違っている。
認識は岡田氏とほぼ同じ。
ここでいう従属国とは中国の宗主国とする小さな独立国のことであり、
独立して国政を執りながらも中国の皇帝を君主と認め、
定期的に貢ぎ物をしたり、為政者が変わるたびに中国の承認を得たりする必要があった。
ヴェトナムと朝鮮のほかに、ネパール、ビルマ、ラオス、琉球が当時の中国の従属国だった。
李鴻章は新疆もそれらの国々と同列に扱うことを勧めた。
『西太后』ユン・チアン
上のユン・チアンの見方は、中国共産党政府の主張していることと同じだろう。
清朝の時代に朝貢していたのだから、そこは自国の領土だった、と。
しかし、岡田氏や平野氏は、
十九世紀以後、世界が国民国家の時代を迎えたとき、
清朝は、朝貢や冊封は近代的な概念で捉えれば保護領と宗主国との関係を示すものである。
と自分たちに都合よく解釈した。
朝貢していたのだからわれわれの領土の一部である、というわけである。
(中略)
その後も中国人は、一貫してこうした解釈を続けている。
かつてシナと友好関係にあった国は、すべて中国領であると主張しているのである。
したがって彼らの解釈では、ベトナムもタイもマレーシアもビルマも朝鮮も沖縄も、
すべて中国領である。
『東アジア史の実像 Ⅵ』岡田英弘
朝貢は、国王と清朝皇帝の個人的関係でしかない。
個人的な関係だったからこそ、
皇帝や国王の代替わりごとに朝貢し直さなければならなかった。
『東アジア史の実像 Ⅵ』岡田英弘
上の見方を粉砕している。先ほどの平野氏も、
近代国際法にもとづく秩序は、
ある特定の国家や地域が皇帝との関係の濃淡に応じて
朝貢国=属国という立場をとることに対して寛容ではない。
さまざまな経緯によって皇帝に定期的に朝貢をしながらも、
それがもはや皇帝の指図ではなく自発的な判断で行われおり、
諸外国との関係も自律的に処理しているのであれば、
その国は独立国であって属国ではないという判断がなされるであろう。
『大清帝国と中華の混迷』平野聡
としている。
現在の中国を見極める為にも、
清朝(満洲人)、その奥にいるモンゴル、ジュンガル帝国、チベットが、
鍵を握っているのは間違いない。
清朝では、マンジュ人(満洲人)、モンゴル人(蒙古人)、漢人、チベット人、
回人(いわゆるウイグル人)の五種族の住む範囲を区別して、それぞれ法典を用意した。
マンジュ人はすべて八旗と呼ばれる八集団に分属し、
それぞれの出自に従って満洲(マンジュ)・ 蒙古(モンゴ)・漢軍(ウジェン・ハーン)と名づけ、
旗人と総称された。その法典は「八旗則例」である。
また、モンゴル人は外藩蒙古(トゥレルギ・モンゴ)と呼ばれ、元代以来の封建制度を保った。
その法典は「蒙古例」である。
漢人(ニカン)は「大清律例」を適用され、明の旧制に従った。
仏教徒のチベット人(トゥベト)は「西蔵事例」を、
回人すなわちイスラム教徒のトルコ系トルキスタン人(ホイセ)は「回疆則例」を適用された。
全体としてマンジュ人とモンゴル人は協力して漢人を統治し、
これにチベット人とトルコ系イスラム教徒が服属するという形をとり、
オイラト人はモンゴル人の一部と見なされたのである。
『東アジア史の実像 Ⅵ』岡田英弘
清が内陸アジアの帝国であった頃、
チベットは騎馬民族がこぞって篤く信仰するチベット仏教のまばゆいばかりの中心であった。
加えて、朱子学・華夷思想原理主義に染まった漢人たちを牽制して、
非漢人であってもよき文化を持つことを示すうえで、
チベット仏教はその見本のようなものであった。
チベット仏教は、清という帝国をもっとも特徴づける存在のひとつであり、
安定の礎であった。
『大清帝国と中華の混迷』平野聡
いつも疑問に思っていたのだが、満洲の「洲」にさんずいが付くのと、
「州」にさんずが付かないのは、何故なんだろうと思っていたら、
本著作集では、満洲族の「洲」には、すべて「さんずい」が付いた「洲」の字を当てている。
近頃では「洲」ではなく、
「さんずい」を取った「州」を書くのが慣わしみたいになっているが、
「洲」が本来の表記である。
簡単に説明しておくと、満洲族がつくった王朝が清朝だが、
五行説では興起する王朝ごとに五行(木・火・金・水)の一つが当てられていて、
清朝は水の徳を持った王朝なのである。
それで、王朝の名である「清」にも「さんずい」が付くし、種族名である
「満洲」にも「さんずい」が付く。なお、水は同時に北方を表わす。
それで、満州族は北のほうから現われてシナを統一したという歴史が、
そこに反映されている、というふうに解釈してもいいかもしれない
(多少こじつけめいてはいるが)。
『東アジア史の実像 Ⅵ』岡田英弘
と、説明されていて、腑に落ちた。
本書は、満洲、台湾、チベット、韓国、東南アジアなどの、漢人の周辺で影響を受けながら
盛衰してきた国家、民族を扱っている。主に、清朝を建てた狩猟民族の満洲人がメイン。
端的に言えば、清朝が、今の政権とは関係ないことを示している。
清朝をもっと掘り下げて具体的に書こうと思ったが、まだそれは時期尚早だと判断した。
何故か。
生前に岡田英弘さんが監修された、
清朝史叢書シリーズ(藤原書店)に目を通していないから。
清朝史叢書
「大清帝国(1636-1912)から、今日の東アジアを見通す!
遊牧世界と農耕世界を統合した多元帝国の全貌!」
岡田英弘『康煕帝の手紙』
マーク・エリオット『乾隆帝』
岡 洋樹『大モンゴル国の遺産 清朝の「外藩」統治』
杉山清彦『八旗・ジャサク旗・緑旗 帝国の軍隊と戦争』
宮脇淳子『最後のモンゴル遊牧帝国 清の好敵手ジューンガル』
楠木賢道『江戸の清朝研究 荻生徂徠から内藤湖南へ』
豊岡康史『「海賊」と清朝 東南沿海の社会・経済・国際関係』
渡辺純成『明清の受容した西欧科学』
ちなみに、
豊岡康史『「海賊」と清朝 東南沿海の社会・経済・国際関係』は、
刊行されている。
清朝をここまで掘り下げたシリーズは、世界でも初なのではないかと、
個人的には思っている。
清朝史叢書シリーズは、その道の専門家や、
ぼくみたいな変わり者の一般人ぐらいしか、手に取らないと思われるが、
本書『東アジア史の実像 Ⅵ』は、
清朝史叢書シリーズの入門書としても捉えることが出来るし、
清朝の概観は掴めるので、一般人にはありがたい構成となっている。






