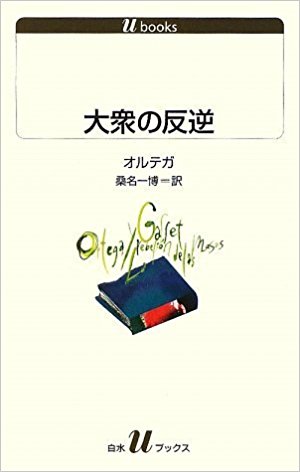
ホセ・オルテガ・イ・ガゼットは、一八八三年五月九日のスペインマドリード生まれ。
晩年は、フランス、オランダ、アルゼンチン、ポルトガルで亡命生活を送り、
一九五五年に七十二歳で亡くなっている。激動の時代を生きた。
本書は、一九二九年にマドリードの新聞『エル・ソル』で発表され、
その翌年に単行本として刊行されたもの。原題は『La rebelion de las masas』。

オルテガ・イ・ガゼット
オルテガ家は代々、新聞業を家業としており、
祖父のエドゥアルド・ガセット・イ・アルティメは、
「セビリアが生んだ世界に誇る二人の息子」の一人、
「詩人のなかの詩人」のグスターボ・アドルフォ・ベッケルと交流があり、
文化と文学を中心に据えた新しい雑誌『マドリッド画報』(La IIustracion de Madrid)
の創刊の提案を受け、ベッケルを文学担当の編集長として迎えて、
一八七〇年一月十二日に第一号を創刊させている、面白い人物。
(ちなみに、「セビリアが生んだ世界に誇る二人の息子」のもう一人は、画家のベラスケス。
ベッケルは、スペインでは勿論のこと、スペイン系文化圏でも『ドン・キホーテ』と並んで、
人々に広く読まれている詩人。)
そんな祖父の血筋を継いでかは知らないが、孫のオルテガ・イ・ガゼットも、
ボルヘスや同時代の「一九二七年の詩人」グループが、まだ無名詩人だった頃に、
自身が編集し発行する文化雑誌『オクシデンテ』に、活動の舞台を提供している。
さらには、その雑誌の中で、詩人たちは、オルテガの理論を詩作において、
実現しようとしていたらしい。面白い。
二〇〇八年にスペインの新聞『エル・パイス』紙が、
現代のスペイン系文化圏の百人の知識人に(日本で有名なのは、リョサやフエンテスなど)、
「あなたの人生を変えた十冊の本は何ですか?」というアンケートを実施したら、
セルバンテスは勿論のこと、ダンテ、ゴンゴラ、カフカ、ロルカ、ボードレール、
プルースト、ホメロス、マルケス、シェイクスピア、カミュ、紫式部などと一緒に、
オルテガの『大衆の反逆』が挙がっている。(『ベッケル詩集』[彩流社]の解説に詳しい)
ぼくの知る限り、日本では、惜しくも入水自殺された、
評論家の西部邁氏がオルテガを多く引用されていたのを、
著作や、ご自身の番組である『西部邁ゼミナール』で、見かけたことがある。
massを「大衆」ではなく、「大量」と訳すと言っていた。

2018年1月21日に亡くなられた、西部 邁さん
今日、ヨーロッパ大陸の全域において、均質性の一形式が勝利を収め、
それが西欧のこの宝を完全に食い尽くそうとしている。
つまりそれは、いたるところに出現した大衆人のことである。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
この大衆人とは、自分の歴史を持たない人間、つまり過去という内臓を欠いた人間であり、
したがって「国際的」と呼ばれるあらゆる規律に従順な連中である。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
大衆とは「平均人」のことである。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
として、オルテガは、いたるところに大衆人(平均人)を出現させた原理を三つあげている。
この新しい世界を可能にしたのは、
自由主義的デモクラシー、科学的実験、産業主義の三つである。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
さらには、
新しい科学と新しい科学が指導し代表している文明全体のなかで、
最大の利点であると同時に最大の危険ともなっているもの、つまり機械化にある。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
しかし私にとっては、平均人が科学から受ける恩恵と、平均人が科学に寄せる
― いや、寄せない ― 感謝の念との間にある不均衡こそが、
最も恐るべき野蛮の兆候だと感じられるのである。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
と述べていて、特にオートメーション(機械化)に対して、批判を展開してる。
面白いのが、ほぼ同時代を生きた鈴木大拙(一八七〇年~一九六六年)も、
晩年ではあったが、オルテガと同じことを述べている。
二元性を基底にもつ西洋思想には、もとより長所もあれば短所もある。
個個特殊の具体的事物を一般化し、概念化し、抽象化する、これが長所である。
これを日常生活の上に応用すると、すなわち工業化すると、大量生産となる。
大量生産はすべてを普遍化し、平均にする。……
すべて普遍化し、標準化するということは、
個個の特性を滅却し、創造欲を統制する意味になる。
(中略)
つまりは機械の奴隷となるにすぎない。
思想面でも一般化・論理化・原則化・抽象化などということも、
個性の特殊性、すなわち各自の創作欲を抑制することになる。
だれもかも一定の型にはまりこんでしまう。
どんぐりの背くらべは、古往今来、どこの国民の間にも見られるところだが、
知性一般化の結果は、凡人のデモクラシーにほかならぬ。
そして、「フランスの知性」と謳われ、上の二人と同時代人で、
詩人であり、批評家、評論家のポール・ヴァレリー(一八七一年~一九四五年)も、
同じことを述べている。
最も恐るべき機械は回ったり、走ったり、物質やエネルギーを輸送したり、
変形したりする機械ではない。
銅や鋼で作られたのとは別の、厳密に専門化した個人からなる機械が存在する。
すなわち諸々の組織、行政機構といったもので、
非人格的であることにおいて精神の存在様式に範を取って作られたものである。
『精神の危機(知性について)』 ポール・ヴァレリー
オルテガは、ヨーロッパが十九世紀に選択した、その形態(近代化〈三つの原理〉)によって、
「自己完成の努力をせずに風のままに浮かぶブイのように暮らす人びと」である、
無責任な大衆人(平均人)を、たくさん出現させ、そこかしこで幅を利かせ、政治をも動かし、
世の中を悪くし、生きづらくさせた、最新の“野蛮人”だと述べている。
それは、悲惨だった第一次世界大戦(一九一四年~一九一八年)をまねき、長期化させ、
ヨーロッパを退廃させたのは、この三つの原理によって出現した、
熱狂的な大衆人の影響を受けたからだ、としても受け取れるのかもしれない。
本書で直接は言及されていないが。(シュペングラーに触れている箇所はある)
大衆人は自分が国家であると信じており、なんらかの口実をつくっては国家を動かし、
それによって、国家の邪魔になる― 政治、思想、産業などいかなる面でも国家の邪魔になる ―
創造的な少数者をすべて押しつぶそうとする傾向をますます強めていくだろう。
この傾向がもたらす結果は致命的なものとなる。
社会の自発性は何度となく国家の介入によって暴力を受け、
どのような新しい種子も実を結ぶことができないだろう。
社会は国家のために生き、人間は政治という機械のために生きなければならなくなるだろう。
そして国家は結局のところ一つの機械にすぎず、
その存在と維持はその機械を維持する周囲の活力に依存しているわけだから、
国家は社会の髄まで吸いつくした後は痩せおとろえ、骨だけになり、
命ある有機体の死よりもはるかに気味悪い、あの錆びはてた機械の死を遂げるだろう。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
国家主義は、規範と化した暴力と直接行動でとる最高の形態である。
そして大衆は、国家という匿名の機械を通し、またそれを手段として自ら行動する。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
そんな時代を「満足しきったお坊ちゃんの時代」と呼んでいる。
あらゆる民族やあらゆる時代において貴族の特徴をなしていた性向の多くが、
大衆人のなかに芽ばえ始めているのを示すことができるだろう。
たとえば、賭事やスポーツを人生の主要な仕事にしたがる傾向とか、
自分の肉体への関心 ―衛星や衣服の美しさへの関心― とか、
女性との関係におけるロマンティズムの欠如、知識人を楽しみの相手にしながら、
心の底では尊重せず、召使や警官に彼らを鞭打つように命じたり、
議論によってことを進めるよりも絶対的な権威のもとでの生活を好むなどである。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
そして、その三つの原理の権化ともいうべき国が、アメリカ合衆国。
オルテガは辛辣に苦言を呈している。
私はかねてから、誇張になるのを恐れながらも、
アメリカは最新の発明品でカムフラージュされた原始民族であると主張してきた。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
アメリカはまだ苦しんだ経験がない。
したがって、支配者としての能力を持ちうるなどと考えることは夢にも等しいのである。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
私刑法(リンチ)がアメリカで生まれたのはまったく偶然ではない。
なぜなら、アメリカはある意味で大衆の天国だからだ。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
オルテガに限らず、ヨーロッパ人は、アメリカに対して手厳しいのが目に付く。
『欧州解体』のなかで、イギリス人エコノミストのロジャー・ブートルが、
「多くの人々にとって米国は美徳の鑑とはほど遠い」
と、述べていたことも思い出す。
オルテガの見方に従えば、
今は全世界に覆っていることでもあり、その成れの果て、といえるだろう。
その見方に立ち、オルテガを現代日本人の前に浮上させ、言論を展開されていたのが、
西部邁氏だったと感じている。
そして、「言葉」の解釈に於いて、ニュアンスの違いはあったが、二人は似ていた。
人は自分の考えていることをすべて言い得ると信じるがゆえに、話し始めるのである。
これが幻想なのだ。言葉というものはそれほど役立つものではない。
言葉は、程度の差はあるが、われわれの考えていることの一部を表現するだけであり、
しかもそうすることによって、他人との意思疎通に越えがたい障害を置くのである。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
西部邁氏は、生前に出演された、
最後の『西部邁ゼミナール』のなかで、次のように述べている。
「言論は虚しい」。
では、その無責任な大衆人(平均人、新しい野蛮人)にならない為には、どうすればよいのか。
具体的なことは示していないし、示す気などさらさらなかったと思われるが、
オルテガは次のように述べている。
生きるとは何かに向かって放たれていること、一つの目標に向かって歩むことである。
その目標は私の歩みそのもでもないし、私の生でもない。
それは、私が自分の生を賭けているもの、したがって生の外に、生の彼方にあるものである。
『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット
それは、その番組の終盤に、西部進氏が述べていたことでもある。
「どうせ死ぬのだからと、でたらめに生きるのか、
どうせ一回の人生なのだから、自分で納得できる人生を生きるのか」。
西部邁は、近代のオルテガであり、オルテガは、現代の西部邁であった。
と、2018年が明けたばかりの寒い日に思ったことだった。
西部邁氏のご冥福をお祈りします。



