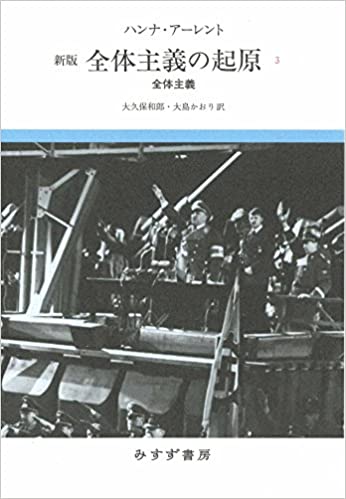
政治における目的と手段(1950年12月)
決定的なことは、政治が常に目的のための手段として考えられてきたことである。
政治ではすべてが許されていた、あるいはマキャヴェリ以来、政治ではすべてが許されるよう
になった。
なぜなら−善き生活という−非・政治的な目的が政治という手段を正当化したからである。
政治は常に非政治的なものの可能性の全体であった。全体主義者たちは、この手段を、このす
でに汚れきっていた手段を目的自体に祭り上げ、独特のやり方で目的・手段のナンセンスに終
止符を打ったのだ。
単数の人間−複数の人間(1951年1月)
全体主義体制では単数の人間の絶大な権力が、複数の人間の無用さと対応していることは明ら
かである。
すべては可能であるという考えから直接に、人々を人間としてある場合には殺害し一般的には
粛清することによって、人々を無用なものにしようとする実践が生まれるのはこのためであ
る・・・
『思索日記 I 1950-1953』ハンナ・アーレント
第一部、第二部では、全体主義へと結晶していくことになる諸要素である、反ユダヤ主義や種
族的ナショナリズムが検討されたが、それらに加えて最終巻では、階級社会の崩壊、全体主義
運動、全体的支配、が綴られている。その主役であるのは大衆(mass)である。
「全体主義的支配は大衆運動がなければ、そしてそのテロルに威嚇された大衆の支持がなけれ
ば、不可能である。
ヒトラーの政権掌握は民主的な憲法のすべての規定に照らして合法的であり、彼は絶対多数に
わずかしか欠けることのない最大の政党の指導者だった。
大衆の信頼なしにはヒトラーもスターリンも指導者として留まれなかっただろう。
−これなしには彼らが幾多の内外の危機を乗り切り、権力掌握後も続いた党内抗争を勝ち抜く
ことができなかったはずだという理由からだけでもそう言える」(本書)
「全体主義運動は大衆運動であり、それは今日までに現代の大衆が見出し自分たちにふさわし
いと考えた唯一の組織形態である」(本書)

ハンナ・アーレント(1906-1975)
大衆は、第一部のドレフュス事件や第二部の南アフリカの金鉱に殺到した「モッブ(mob)」(あ
らゆる階級の残滓を代表する集団)とは異なる。『精読 アレント『全体主義の起源』』の
「注」で牧野雅彦氏は「マスはモッブと対比され、政治的無関心、共通の利益を持たない未組
織の大量の人間の集積を指している」と書いてるが、「政治的に組織されていない巨大な人間
の集積」、これが大衆の定義。それは人口の少ない小国では全体主義は不可能であり、階級独
裁が精々のところだという。全体主義運動の特質は、大陸の国民国家の古い利益政党のように
階級ではなく、マスとしての大衆の組織を意図し、成功したところにある。
全体主義運動の指導者の多くはモッブから出てくるが、大衆は、国民国家の基盤としての階級
社会そのものの解体、大陸に顕著であった階級−政党のシステムの崩壊によって登場する。
国民国家の基盤としての階級と政党システムの崩壊は、政治的に無関心な市民、組織されない
巨大な個人の集積としての大衆を登場させることになった。アーレントは次のように書いてい
る。
「大衆はこのような「階級的基盤」すら持たず、彼らが反映し倒錯させているのは全人民の基
準とものの観方である。大衆が体現しているのは実際に「時代精神」以外の何ものでもない。
それゆえ、彼らに訴え彼らを動かし得るのは、もはや具体的な政治状況ではなく歴史的瞬間な
るもの一般にのみ対抗するきわめて概括的なスローガンだけである」(本書)
「全体主義運動はアトム化され孤立させられた個人の大衆組織であり、その成員からは他の政
党や運動と比べると前代未聞の献身と「忠誠」を要求し、しかもそれを手に入れることができ
る。
全面的な献身が大衆化した個人のメンタリティにいかにふさわしいかを最も明白に示している
のは、全体主義の指導者および運動が、権力を握り、全面的なテロルを組織するようになる以
前からすでに運動のメンバーの献身を確実に得られたという事実である」(本書)

アドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler, 1889-1945)とヨシフ・ヴィッサリオノヴィチ・スターリン(Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин, 1878–1953)
長くなるので詳細には書けないが、ボリシェヴィキ革命後のロシアではレーニンはあらゆる機
会を捉えて社会的な階層分化を強化することで革命を擁護しようとし、曲なりにも新階級も創
出していた。
国民国家の基盤となるはずのこれらの新階級は全体主義の展開には障害であり、スターリンは
これを解体していった。
すでに弱体化していたが国民的代表機関としてのソビエト権力を清算し、次にはイデオロギー
的理由から都市の新中産階級、農民階級が清算されていった。これは富農(クラーク)の廃絶と
農業集団化の促進を口実として進められた人為的飢饉や住民移動によって行われた。
その次に労働者階級の清算も進められていく。一九三〇年代に採用されたスタハノフ・システ
ム(労働生産性向上運動)は労働者からあらゆる連帯感と階級意識を奪っていった。
さらに一九三六−三八年の間、それまでの清算を進めていく担い手でもあった行政・軍事部門
の粛清が行われる。ほとんどすべての公務、工場、経済・文化団体、党と政府、軍の要員の交
替と粛清が行われた。
都市間のすべての移動を登録し規制する国内旅券制を再導入し、階級としての党官僚制の解体
が完了された。
ソビエトにおける大衆のアトム(原子)化は繰り返されるパージによって、あらゆる社会的紐
帯、家族的絆を破壊することによってもたらされた。そこでは自律的な存在はすべて否定さ
れ、固有の価値と論理をもつ存在は、自律的な論理をもつがゆえにそれ自体として全体主義に
とっては危険な存在となっていった。ボリシェビキ支配者たちは、いまだかつて例のない、ア
トム化されバラバラの個人に解体された社会を創造することに成功していった。
全体主義的支配者にとっては党綱領も邪魔になる。全体的な忠誠が可能になるためには、具体
的な内容を空白化することが必要となり、それによって生じうるいかなる変化にも対応した服
従を要求することができるからであるという。
ヒトラーは党の当初の綱領から運動を解放したが、それは綱領を変更したり公式に廃止したり
したのではなく、議論するのを拒否することによってであったという。
民主主義、共和政、独裁、君主制などの特定の統治形態を示すようなスローガンを用いること
を慎重に避けてもいる。
明確なマルクス主義の教義と共産党の綱領が存在していたロシアでは、スターリンはこのよう
な制約を分派の廃止、路線論争の禁止の後に行った絶えざる路線変更と再解釈によって事実上
廃棄してしまったという。
全体主義運動は、特定の綱領路線に縛られない自由、いつでも任意の目的と任務に構成員を拘
束する自由を獲得していった。党綱領の欠如や無視はムッソリーニのファシズム運動にも顕著
な傾向であったが、ファシスト独裁の究極目標が一党支配であるのに対して、全体主義にとっ
ては一党独裁そのものも過渡的な目的にすぎない。
大衆はアトム化されてバラバラの存在にされてしまうが、全体主義運動のリーダーの多くはモ
ッブから出ている。しかもそれらの担い手は前線世代であり、戦前の雰囲気の中で育ちながら
戦争による崩壊を経験した世代であった。
そのモッブと一時的に同盟を結ぶのがエリートであった。現状への募る不満や憎悪を爆発させ
る政治的表現主義、犯罪と紙一重の行動やテロルへの嗜好がモッブとエリートを結びつけてい
った。
モッブとエリートの「不穏な同盟」、野望の一致は、これらの階層が国民国家と階級社会の枠
組みから最初に除去された者たちであることに根ざしていた。アーレントによれば、知的エリ
ートがモッブと同じく全体主義のテロルに惹き寄せられたのは、「言葉の真の意味におけるテ
ロリズム、一種の哲学となったテロリズムがあったからである」と述べている。
しかし、大衆を全体主義へと組織することができたのは、社会的脱落者としてのモッブでも、
モッブに魅せられた知的エリートでもなかった。彼らは運動が自己展開を始める段階で、その
自己破壊的運動に順応できずに切り捨てられていくことになっていったという。
全体主義運動を推進していったのは、ゲッベルスのようなボヘミアンでもなかったし、シュト
ライヒャーのような性的犯罪者でもなく、ローゼンベルクのような変人でも、ヒトラーのよう
な狂信家でも、ゲーリングのような冒険家でもなかった。
一九三六年以降ドイツで最も権力ある人間であり、極めて「正常」な社会的俗物の典型として
のヒムラーであった。そのヒムラーもアトム化されて解体しているが、個人としてはごく普通
の生活人である大衆を組織できた。ここに大衆支配としての全体主義の特質があるという。
運動のもつ行動主義やテロルなどに惹かれてモッブとエリートが全体主義運動に自分から飛び
込んでいくのに対して、大衆は誰かが外から動員し、組織しなければならない。
そのための手段がプロパガンダであった。
アーレントのいう「行動主義」とは、「一切の考慮を「洗い流してしまった」純然たる行動
と、人間の理解を超えた純然たる必然性の圧倒的な力に対する信仰という、見かけだけは矛盾
しているように思える二つのものの融合」としている。
全体主義は特定のプロパガンダの技法や宣伝内容をみずから開発したわけではなかった。
それらは帝国主義の興隆と国民国家の崩壊に至る五〇年間に、モッブがヨーロッパ政治の舞台
に登場した時に準備されたものであり、全体主義はただそれを徹底して大衆に適用したに過ぎ
なかった。
大衆は目に見える世界の現実を信ぜず、自分たちのコントロールの可能な経験を頼りにせず、
自分の五感を信用していない。それゆえに彼らにはある種の想像力が発達していて、いかにも
宇宙的な意味と首尾一貫性を持つように見えるものならなんにでも動かされる、とアーレント
は指摘している。
階級社会の崩壊によって生活の基盤を根こそぎ奪われて「故郷喪失(homelessness)」の状態に
おかれ、バラバラに孤立した大衆の願望、もはや彼らが適応できなくなった世界から逃避する
一方で、何らかの一貫した拠り所を求める願望こそが、全体主義のプロパガンダを可能する前
提。(牧野氏による)
そのプロパガンダとして最大の効果を発揮したのが「ユダヤの陰謀」というフィクションであ
った。
第一次世界大戦による国民国家の解体とそれにともなうユダヤ人社会の解体は、一九世紀末の
繁栄とともに一時的に影を潜めた反ユダヤ主義をあらためて噴出させることになるが、ナチス
の反ユダヤ主義プロパガンダはこれを継承して発展させたものであった。そのスローガンの内
容自体はこれまでの反ユダヤ主義の焼き直しに過ぎない。
ナチスが付け加えたただ一つの新しい要素は、ナチ党員に非ユダヤ人の血統証明を要求したこ
とであった。
反ユダヤ主義は孤立した大衆に「自己規定と自己同一化」を与えて、彼らにある種の自尊心を
回復させて組織するための手段であった。ナチのプロパガンダは「反ユダヤ主義を自己規定の
原理に転換」したものであった。その反ユダヤ主義の特徴をよく示しているのが『シオン賢者
の議定書』についての応答であり、ナチスはこの偽書をユダヤ人の陰謀の証拠として攻撃の材
料に用いるだけでなく、自らの構想のプロパガンダの手段として用いた。
ナチスは『シオン賢者の議定書』に示されたユダヤ人の世界帝国の構想を逆手に取る形で、ユ
ダヤの世界支配の陰画としてドイツ民族の「民族共同体」による世界支配の構想を提示した。
(牧野氏による)
仮構のリアリティを持って大衆を組織する。そのためのプロパガンダの手段に対する嗅覚が、
全体主義の指導者の権力の基盤となる。その意味においては、ヒトラーの雄弁の才能さえ必要
なかったという。ただ、ヒトラーやスターリンなどの指導者個人の意義がまったく否定されて
いるわけではない。
全体主義の権力の核心は、「生ける組織」としての運動そのものの展開の内にあり、プロパガ
ンダのスローガンがひとたび「生ける組織」に具現されてしまえば、組織の全構造を破壊する
ことなしにそれを取り除くことはもはや不可能となるという。全体主義運動は、テロルとプロ
パガンダではなく、組織とプロパガンダこそが一つのメダルの両面であるとアーレントは見抜
いた。なので、全体主義プロパガンダの内在的な弱点が露呈するのは敗北の瞬間であり、運動
の力がなくなれば、構成員は直ちにそのドグマを信ずるのを止めてしまう。
全体主義の指導者たちに必要なのは、大衆的プロパガンダにおけるデマゴーグとしての能力で
も官僚的組織技術でもなく、多層的な運動の中心にあって構成員間の陰謀や闘争を操る才能で
あった。ヒトラーもスターリンも他に抜きんでていたのはこの能力であった。
全体主義運動の組織構造の特徴は、同伴者の前面(フロント)組織の創出にあった。
非全体主義的な外部の世界と、内部の仮構世界との間の媒介、内外に対する「ファサード」、
一種の緩衝装置としてフロント組織は機能した。
詳しくは書けないが、それは独特で流動的な階層構造を特徴としており、絶対的な命令と服従
義務に基づく軍事組織とは相容れなかった。SA突撃隊の指導者だったレームは、SAを国防軍に
編入することを夢見てヒトラーと交渉していたが殺されている。
全体主義運動の特質は社会学的に見れば、イニシエーションの程度によってヒエラルヒーが形
成されるという「秘密結社」のそれに類似しているという。牧野氏の言葉を借りるならば、
「奥義に通じた少数のサークルを、半ば通じたメンバーが取り囲むというかたちで階層が形成
され、これらが全体として、外の現実世界−運動から見れば敵対的な世界−に対する緩衝装置
として機能するのである。ここで重要なのはリーダーとエリート、一般党員、同伴者(シンパサ
イザー)の相違と相互の関連である」。外部の世界に対する嘘とシニシズムのような階層的構造
の中では、その中心にいるエリートはもはや運動のイデオロギーを信ずることを要求されな
い。みずからの運動のイデオロギーの内容そのものから自由であることが、全体主義運動のヒ
エラルヒーの最中心層の特徴であるという。
冒頭でアーレントの言葉も引用したが、全体主義の本質は運動であり、運動そのものにある。
その意味においては、国民国家という枠組みは、運動としての全体主義にある種のジレンマを
もたらすことになる。
ナチ体制もスターリン体制も憲法に対して「廃止しないが無視する」という態度をとっていた
が、全体主義運動がナチ党や共産党綱領に対してとった態度と軌を一にするものであり、その
ことは、全体主義がその本質において運動体であったことを示しているという。
運動そのものを規制するような規範を忌避すると同時に、公式の国家とその機構もあくまでも
運動のための手段として利用した。そのような態度が典型的に現れるのが、国家機構の「二重
化(duplication)」であったという。その具体的な過程は長くなるので割愛するが、公式の権力
と実質的な権力の二重化は、さらに多重化(multiplication)していくことになる。
権力を掌握した全体主義が国家を非全体主義世界に対して国を代表するファサードとして利用
するが、多重化した官職と錯綜した権限の背後に存在する唯一の権力核が秘密警察であった。
秘密警察は、全体主義の世界支配の野望の下で、自国と他国の区別なくあらゆる潜在的反抗を
鎮圧する中心機構でもあるが、その機能は、専制体制のもとでの古典的な任務とは異なってい
る。多くの専制体制は国内の政敵を鎮圧するために秘密警察を利用したが、全体主義体制にお
いても権力掌握当初の段階での秘密警察の役割は同様であった。しかし、全体主義体制下で
は、反対派を根絶するこの段階では、住民全体をフロント組織へと引き入れるとともに、旧来
の党員を再教育して彼らを自発的に監視させる過程と並行している。反対派などが根絶された
この第一段階はナチスでは一九三五年、ソビエトでは一九三〇年にほぼ完了したという。
専制支配においては、諜報機関は「国家の中の国家」として他の公的部門に対して優位を占め
ていたが、全体主義のもとではその指導者に完全に従属するようになる。逮捕すべき相手を定
めるのは警察ではなく、政府が特定のカテゴリーの住民の逮捕を決定する。
「容疑者」から「潜在的な敵」、「客観的な敵」への転換は全体主義体制における秘密警察の
地位そのものの変化と対応している。秘密警察は全体主義国における唯一の公然たる支配階級
となり、その価値基準が全体主義の社会全体に浸透することになる。犯罪者は刑罰によって処
罰されるが、運動から逸脱し存在自体が望ましからぬ特定のカテゴリーの人間は地上から抹消
される。その装置が強制収容所であった。
全体主義運動は秘密結社としての性格を有しているが、権力掌握後に秘密警察というかたち
で、真の秘密警察を作り出す。再び牧野氏の言葉を借りるならば、「まさに全体主義国におい
て唯一厳密に擁護された秘密、唯一秘教的な知識こそ、警察の機能と強制収容所に関するそれ
なのであった」。アーレントは「全体的支配は精鋭組織に対するイデオロギー教化と同時に収
容所における絶対的テロルによってこの結末に到達しようとする」と書いている。
「強制収容所および絶滅収容所の本当の恐ろしさは、被収容者がたとえ偶然に生き残っている
としても、死んだ人間以上に生者の世界から切り離されている−なぜならテロルによって忘却
が強いられているから−ということにある。
ここでは殺害はまったく無差別に行われる。まるで蚊をたたきつぶすようなものだ」(本書)
人々を強制収容所と人間そのものを絶滅へと導く過程の最初の段階では「法的人格」の剥奪。
次に行われるのが「道徳的な人格」の破壊。最終段階では人間の個性や個別性、固有のアイデ
ンティティが生きた人間から抹殺されること。
家畜用賃車で移送され、頭髪を刈られ、囚人服を着せられ、すぐには死なないよう周到に計画
された拷問などによって、個人の人格は完全に破壊される。「そこに創り出されたのは条件反
射的に事物に反応する動物のごとき人間である。(中略)パブロフの犬が自然のままの動物では
もはやないように、彼らは動物でも人間でもない、実際に「死体」になる以前にすでに「人間
としては死せる身体」となっているというのである。それはまさに全体主義のシステムの勝利
であった」(『精読 アレント『全体主義の起源』』牧野雅彦)
「全体主義体制にとって問題であるのは、人々を支配する専制的な体制を打ち建てることでは
なく、人間をまったく〈余計〉なものにするようなシステムを作ることなのだ。
完全にコントロールされ得る反応装置、一切の自発性を奪われた操り人形を相手にしてのみ、
全体的権力は行使され得、確立され得る。人間というものはこれほどまで強いものであるから
こそ、ヒト科の動物の一個体となってしまわないかぎり完全に支配されることはあり得ないの
だ」(本書)
全体主義の本質は運動にある。運動そのもののダイナミズムを喪失すれば、全体主義という現
象は消滅する。全体主義プロパガンダの本質的な弱点は敗北のときにはじめて露呈されるとし
て、アーレントは次のように書いている。
「いかなるものであれ、外的な原因によって運動が崩壊し「組織の暴力」が消失してしまう
と、支持者たちは昨日まで生命を捧げる覚悟でいたはずのドグマと虚構を一夜にして捨ててし
まう。大衆は彼らの虚構の故郷の壊滅とともにふたたび現実の世界へ、運動が彼らをその現実
から守り遠ざけてくれていた世界へと戻っていき、かつてと同じ大衆の中の孤立した人間に帰
り、そして変わってしまった世界の中で新たな仕事を引き受けるか、あるいは虚構が束の間の
解放をもたらす以前の絶望的な余計者としての存在にふたたび落ち込むかのいずれかとなる」
(本書)
最終章にはドイツ語版と英語版の「イデオロギーとテロル」が収録されている。英語版の方は
「エピローグ」と付けられている。そこでは本論を踏まえた上で、全体主義体制とはいかなる
体制なのか、として総論のようなものになっている。モンテスキューに触れながら、全体主義
を支える行動原理は専制のような恐怖ではなく、恐怖さえ必要ない段階でテロルは進行し、全
体主義体制においてモンテスキューのいう「行動原理」の代用品となるのがイデオロギーであ
り、人々がイデオロギーの強制に服するのは、そのイデオロギーから導出される「観念」の論
理的強制力のゆえであったと説明している。
「全体主義における動員とそこで生まれる力、バラバラに孤立化した人間集積と組織によって
生まれる力は、たんなる暴力装置による外面的な支配ではなく、内側からの強制による動員、
その結果として生まれるものであった。そこで行使される「テロル」は、恐怖による支配や脅
迫のための手段としての暴力というよりは、そうした動員と組織・画一化に大衆を巻き込んで
いく過程そのものということになるだろう」(『精読 アレント『全体主義の起源』』牧野雅彦)
アーレントは「エピローグ」の末尾の中で、「全体主義的支配は孤独(独りぼっち)であること
の上に、すなわち人間が持つ最も根本的で最も絶望的な経験の一つである、自分がこの世界に
まったく属していないという経験の上に成り立っている」ということを指摘している。
全体主義におけるアトム化された大衆とは、行動や思考や経験、人間的なすべての基盤やその
関係そのものが破壊されてしまう。『ハンナ・アーレント』を著している矢野久美子氏に言葉
に直すならば、「思考に動きがなくなり、疑いをいれない一つの世界観にのっとって自動的に
進む思考停止の精神状態を、アーレントはのちに「思考の欠如」と呼び、全体主義の特徴と見
なした」ということでもある。
アーレントはこの大著を反ユダヤ主義や帝国主義、全体主義の歴史を書いているわけではな
い。「反ユダヤ主義」の箇所でも引用したが、「精神科学における方法。因果律はすべて忘れ
ること。その代わりに、出来事の諸要素を分析すること。重要なのは、諸要素が急に結晶した
出来事である。私の著書の表題は根本的に誤っている。『全体主義の諸要素(The Elements of
Totalitarianism)」とすべきだった」と『思索日記』(1951年6月)に記している。
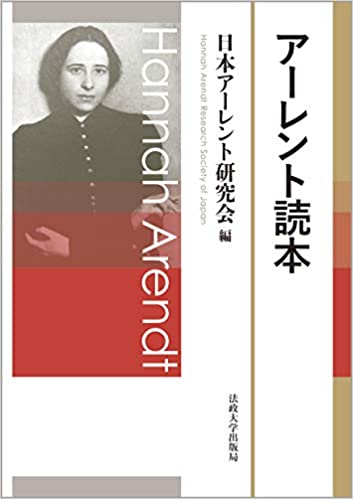
日本アーレント研究会が編集した『アーレント読本』(2020/7/21)
全巻を通して牧野雅彦氏(広島大学法学部教授)の『精読 アレント『全体主義の起源』』にお世
話になり、参考になった。もちろん、このブログの記事の中での不備や欠点はぼくの思慮不足
の結果である。ご了承ください。
そんな牧野氏ですら「読んでいく過程も、楽しいとは言い切れないところがあって、途中で投
げ出したくなることもしばしばであった」と書いている。それだけ難解で「気難しい友人」の
ような存在がアーレントの『全体主義の起源』なのである。最近では日本アーレント研究会 が
編集した『アーレント読本』(2020/7/21)が出版されたが、その第3章の「全体主義─アーレン
ト政治思想の基礎概念」は牧野氏が担当されている。
最後になるが、アーレントはアジアにおける全体主義体制について懸念も示している。それら
は冒頭に書かれてある。具体的な国名はインドと中国だが、その理由は、アジア的専制の遺産
や無尽蔵な人口資源、これらに加えて、一人一人の人間の生命の価値を重んずるヨーロッパ=
キリスト教的な伝統がなく、人間が余っているという大衆の感情が広く根付いていることをあ
げていた。本書の「まえがき」は一九六八年の英語版分冊のものが収録されているが、そこで
は主に、共産主義ロシアと共産主義中国を対比して書かれているが、結論付けてはいない。
共通世界の崩壊は、崩壊に巻き込まれた人々を極度に主観主義的な認識論の状況に投げ入れ
る。
誰しも現実には自分の知覚像しかもたず、見えているテーブルが実在するテーブルに対応して
いることを絶対的に確信することはできない。なぜなら、テーブルの実在性こそわれわれを共
同性のうちに確立させるものだからである。
こうなると、結合し分離させること〈間にあるもの〉としてのテーブルは脱け落ちて、バラバ
ラの個人の群が残ることになる。この群を結合するためには、しかもそれにもとづいて相互関
係が確かに結ばれる「テーブル」が再び世界のうちに存在するような形でこの群を結合するた
めには、感覚知覚を画一化して、どの視点から見てもすべては常に同じように同一の知覚対象
を再生し、そこには無限に反復可能な実験の確実性が伴っているとする以外に道はない。
物理学から借用された「群」という用語は、こういう意味で事態の特徴を非常によく表してい
る。
画一化によって、まさに常に異なりそれぞれに独自のものである感覚的知覚が統制される。
なぜなら、あらゆる差異のうちにあって同じもの、すなわちあらゆる共通の対象を認識させて
きた共通感覚が失われたからである。
その代わりに登場するのが科学的確実性であって、そこでは認識する者は、入れ替え可能でな
ければならない。
もはや共通ではない世界では、実在性を確信できるためには、人間は区別できないほど相互に
似たものになるほかない。
『思索日記II』(1954年10月)ハンナ・アーレント
【その他のハンナ・アーレント関連の記事】






