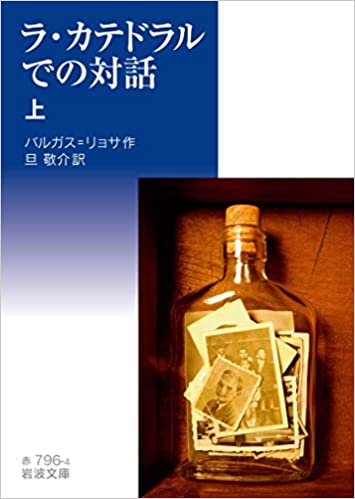

伝統的にペルーでは、ヨーロッパ系を祖先に持つ一部の人々に富が集中し、インディオやアフ
リカ系はほぼ例外なく貧困と窮乏の状態に置かれている。
白人や、富と出世によって「白人化」した人々から成る一部特権階級は、多人種・多文化のペ
ルー人への軽蔑を隠そうともせず、「インディオ」、「チョロ」、「ネグロ」、「サンボ」、
「チノ」といった表現は、彼らの口から発せられれば軽蔑の意味を伴う。
法として成文化されたことこそ一度もないが、歴史を通じて白人層は、人種の違うペルー人に
対して暗黙のうちに差別的な態度を取るのが常であり、時に醜聞を引き起こす。
『ラ・カテドラルでの対話』(一九六九)はマリオ・バルガス=リョサ(ジョサ)の最も野心的な作
品の一つであり、「作家が政治について考えるため、いかに文学を利用するかを示す最良の
例」であると評されてもいる。二〇一〇年のノーベル文学賞の受賞に際しては、「権力に抵抗
して挫折する個人の姿を鮮やかに描き出した」とする受賞理由であった。
バルガス=リョサ自身も、九三年にセイス・バラル社から発表された回想録である『水を得た
魚』で、「私の天職となった文学の最も重要な機能の一つは、権力への抵抗、権力のあり方を
根底から問い質し続けるところにあり、優れた文学作品は、生の不十分な側面、つまり、いか
なる権力も人間の欲求を満たすことはできない事実を浮き彫りにする」と書いている。
創作と文学論の支えとなる理念は、「世界は不完全であり、その不満を埋めるために小説が存
在する」というものである。
ビブリオテカ・ブレべ賞を受賞した処女長編である『都会と犬ども』(一九六二)は、父親に無
理強いされて中学二年間を過ごしたレオンシオ・プラド軍人学校を舞台としていた。
ロムロ・ガジェゴス賞を受賞した長編二作目の『緑の家』(一九六六)は、五八年のアマゾン探
検に着想を得ている。長編三作目にあたる『ラ・カテドラルでの対話』では、マヌエル・オド
リアの独裁時代を背景としている。一九四八年一〇月、オドリア将軍のクーデターで民主主義
的体制は崩壊し、そこから五六年までオドリアの独裁体制は続いた。バルガス=リョサの世代
にとってはその八年間は人格形成期でもあった。オドリアがクーデターを起こした時バルガス
=リョサは子供で、オドリアが権力を手放し、民主主義が到来した時には大人になっていた。
後年、『ラ・カテドラルでの対話』を執筆した動機についてバルガス=リョサは、「オドリア
の独裁政権が社会全体、つまり様々な社会階層の国民たちに及ぼした影響を明らかにするよう
な独裁小説を書きたいと思っていました」と語り、『水を得た魚』では、「ペルーの挫折を描
き出そうとして書いた」と綴っている。
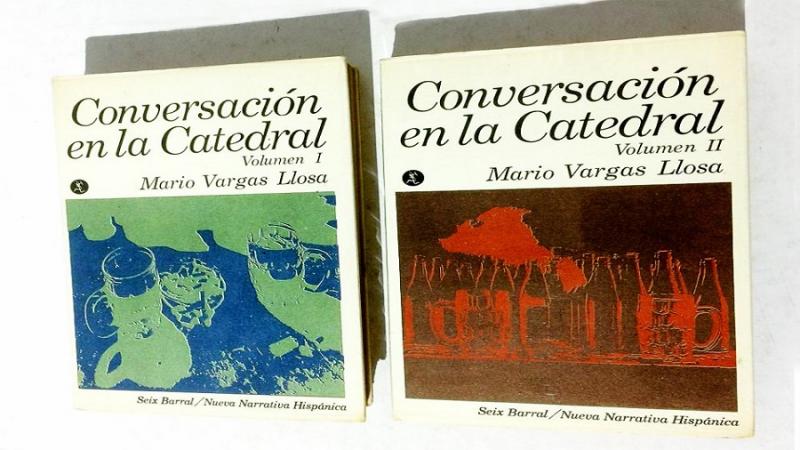
“Conversación en La Catedral”(1969)

マヌエル・オドリア(Manuel A. Odría)
主人公のサンティアーゴ・サバラ(サバリータ)は新聞社〈ラ・クロニカ〉で働くジャーナリス
トである。もともとはブルジョア階級出身で、サバラ家の住宅はリマの高級住宅街であるミラ
フローレスにあり、そこで育った。兄のチスパスは数ヶ月間海軍学校の士官候補生だったが、
そこを放校になると長いことブラブラし、ギャングを気取って賭博と酒以外には何もしていな
かった。後に父ドン・フェルミンのオフィスで働くようになり、真面目になっていった。
妹のテテは、サバリータの親友であり同じ階級のポパイ・アレバロと後に結婚し、二人の子ど
もを授かる。そんな兄妹からサバリータは「超秀才」と呼ばれている。サバリータの中等部二
年の時の成績はクラスで一番になったこともあり、学年末には賞を軒並み取っている。二人と
は真逆の性格である。
父親のドン・フェルミンは、製薬会社と建設会社などを経営するビジネスマンである。
しかし、大統領も手懐け、秘密警察や追放措置を駆使して国民を弾圧する内務局長であり、チ
ンチャ(リマから南方約二百キロにある都市)出身のカヨ・ベルムーデス(ドン・カヨ)と昼も夜も
べったりくっついて大儲けしているのが実態であり、ドン・カヨを引き立てたエスピーナ大佐
ともズブズブの関係だ。ドン・フェルミンはオドリアがブスタマンテに対して革命を起こすの
を手助けしていた。オドリアからは上院議員になるように促され、議会で与党のスポークスマ
ンになってくれると期待されたが断っている。ちなみに、オドリアは兵隊あがりのチョロ(先住
民との混血)である。ドン・フェルミンは政治は大嫌いだが仕方がないというのが本心であっ
た。ドン・フェルミンの製薬会社は軍養成学校への納入で、建設会社は国道と公立学校のおか
げで成り立っていた。ドン・フェルミンの妻であり、サバリータの母親であるソイラは貴婦人
である。
そんなサバラ家にはアンブローシオ・パルドというお抱えの運転手がいる。サンボ(黒人の混
血)であり、ネグロとも呼ばれている。チンチャ(リマから南方約二百キロにある都市)の外れに
ある集落に暮らしていたこともあり、チンチャでドン・カヨが乳搾り女トゥムラの娘ローサと
駆け落ちするが、その時に手を貸している。そんなアンブローシオはドン・カヨを頼りにリマ
に出てきて、はじめドン・カヨの運転手となり、次にサバラ家のお抱えの運転手となる。
ドン・カヨはリマでオルテンシア奥様と呼ばれている元歌手の愛人を抱えている。
そのオルテンシアにはセニョリータ・ケタという背が高くてきれいな脚をした、赤みがかった
髪のムラータ(混血の黒人女性)の娼婦と仲が良く、レズビアンな関係である。
ドン・カヨのもとで女中として仕えるのはチョラ(チョロの女性)のアマーリア・セルダであ
る。はじめサバラ家で女中として仕えていたが、その後ドン・フェルミンの製薬会社で働き、
ドン・カヨのもとで黒人のシムラとその娘のカルロータとともに仕える。
アマーリアの元恋人であり、サンボの風貌をしたトリニダーからは白人かかったチョリータと
呼ばれている。その後アマーリアはアンブローシオと結婚し、アマーリア・オルテンシアとい
う女の子を授かる。
ドン・カヨが内務局長から失墜され一時ブラジルに留まることになるが、その時にオルテンシ
アは見捨てられた状態になり、今まで以上に堕落した生活を送るようになり、ある時何者かに
殺害されてしまう。警察はアマーリアが何か知っていると思い捜し、新聞記者ベセリータはケ
タに取材に行き、ケタはドン・フェルミンが彼女を殺させ、殺したのはアンブローシオだと答
える。この証言は信頼されなかったみたいで、アンブローシオの耳にも入らなかった。
しかし、アンブローシオはサバラ家の運転手を突如として辞め、アマーリアと娘のアマーリ
ア・オルテンシアとともにジャングル地域であるプカルパに行く。プカルパではアマーリアが
二人目を身籠るが、出産時に子供もアマーリアも亡くなってしまう。失意の中アンブローシオ
は罪を犯し、プカルパにアマーリア・オルテンシアを残し、リマを出てわずか二年で戻ってく
る。リマではまともな仕事にありつけず、スラムを転々とし、給料の安い野犬収容所で働く。
サバリータの二人の兄弟とテテの旦那であるポパイ以外のすべての登場人物が精神的挫折をし
ている。敗北者たちである。
スペイン系ドミニカ人批評家のカルロス・エステバン・デイベは、『ラ・カテドラルでの対
話』の登場人物一覧を掲載した評論を書いているという。サバラ家や他のブルジョア階級の人
たちから始まって、登場人物を職業や社会階級によって分類。政府高官、新聞記者、警察官、
労働者から、ごろつき、売春婦に至るまでで、全部で七〇人にもなるという。
『ラ・カテドラルでの対話』の冒頭での街の描写は灰色で、「いったいどの瞬間からペルーは
ダメになってしまったのか?」という書き出しから始まる。サバリータが市の野犬収容施設に愛
犬パトゥーケを引き取りに行き、そこで、人生のどん底に落ちこんで野犬を処分している仕事
をしているアンブローシオと出会った場面から始まっている。アンブローシオは昔の名残りで
サバリータのことを「坊ちゃん」と呼んでいる。
そして、彼らは野犬収容施設の近くにある貧乏人向けのお店、食堂と飲み屋であるだけでな
く、連れ込み宿でもある〈ラ・カテドラル〉というバル(バー)でビールを飲みに出掛ける。
その二人の会話が『ラ・カテドラルの対話』の枠組みで物語の軸であり、二人の会話は時に長
い中断をはさみながらも、ずっと続いていく。

〈ラ・カテドラル〉でのバルガス=リョサ(1970)

〈ラ・カテドラル〉で従妹であり二番目の妻パトリシアと(1969)
この描写はバルガス=リョサ自身が実際に経験したものであり『水を得た魚』の中で綴られて
いる。
ある日、家に帰ると妻のフリアが泣き暮れていた。その理由は野犬捕獲人にパトゥーケが捕ま
ったという。トラックに乗ってやってきた連中が、フリアの腕からもぎ取るようにして愛犬を
連れ去った。バルガス=リョサは間髪入れずに飛び出し、野犬収容施設があったプエンテ・デ
ル・エヘルシトへ向かった。幸いパトゥーケはまだ殺されてはいなかった。しかし、そこで行
われていた屠殺の光景は身の毛もよだつものだった。
そこで働いていたサンボが、檻に閉じ込められた犬たちの目の前で、数日経過しても飼い主が
現れない犬を棒でなぶり殺していた。バルガス=リョサは、あまりのショックから立ち直れぬ
まま、パトゥーケとともに、最初に目に入ったみすぼらしいカフェ(バル)でへたり込んだ。
その名は〈ラ・カテドラル〉であった。
一九五六年には断末魔に喘いでいたオドリア独裁政権とその参謀エスパルサ・サニャルトゥに
まつわる小説をいつか書いてみたいと考えていたバルガス=リョサは、その時、作品の冒頭に
このシーンを持ってこようと思いついたという。
父親のドン・フェルミンから兄妹の中でも一番期待され愛されて育ったサバリータだったが、
家族の反対を押し切り、同じ階級が通うカトリカ(カトリック)大学ではなく、あらゆる階級に
開れているサン・マルコス大学に入学する。うろ覚えだがバルガス=リョサも同じような状況
でサン・マルコス大学に進学したかと思う。サン・マルコス大学では、コミュニストのアイー
ダやハコーボと友達になる。この頃のサバリータは隠れて詩を書きつけたノートを持って純真
だったが、ペルーの共産主義組織であるカウイデの大学分団と関わるようになる。
ある日、路面電車組合のストに連動し、党の大学分団ではこれはすごいチャンスだと考えた。
サバリータは反対していたが、スト支援が可決する。しかし、無期限ストに入ることを可決し
た十日後に捕まってしまう。多くの仲間と共に捕まったサバリータであったが、父のドン・フ
ェルミンがドン・カヨなどに頼み込むなどして一番最初に釈放される。逮捕も拘留も揉み消さ
れた。この件でドン・フェルミンとドン・カヨは仲が悪くなる。
バルガス=リョサ自身もサン・マルコス大学入学直後からカウイデに参加し、マルクス主義に
傾倒していた。独裁政権転覆運動にも加担し、「当時収監中の大学生は多く、治安維持法を盾
に政府は、「反体制分子」と目される者なら誰でも、裁判なしで無期限に拘束することができ
た」と『水を得た魚』の中で書いている。
ある日、内務府長官との面会に呼び出され、バルガス=リョサらはイタリア広場にある彼の執
務室へ向かった。執務室へ通されると、そこに独裁者の腹心であるエスパルサ・サニャルトゥ
がいた。この面会を終えた後、最終的に『ラ・カテドラルでの対話』となる小説をいつか書く
ことになるだろうとバルガス=リョサは直感したという。ドン・カヨのモデルがエスパルサ・
サニャルトゥであった。
その後のサバリータは家出をし、自分の力で生きていくことを決断する。
そして、クロドミーロ伯父の伝で新聞社〈ラ・クロニカ〉で働くことになる。大学や大学での
友人とも疎遠になり、ボヘミアン的な生活を送るようになっていく。
まだ十六歳にもなっていなかったバルガス=リョサは、中学四年と最終年の三ヵ月を〈ラ・ク
ロニカ〉で働いている。ジャーナリズムの何たるかを体で覚え、それまでまったく知らなかっ
たリマを体験し、人生で最初で最後のボヘミアン生活を送った。この期間はその後のバルガス
=リョサの進路を大きく左右することになったいう。『水を得た魚』では次のように書いてい
る。「私の小説『ラ・カテドラルでの対話』には、当然ながら粉飾が加えられているものの、
この時期の冒険が投影されている」

“La Crónica”と思われる場所で10代後半の頃のバルガス=リョサ
ジャーナリストとして道を歩むことを決断したサバリータではあったが、オルテンシアが何者
かに殺された現場に先輩記者と駆けつける。この事件について取材を敢行し、オルテンシアの
レズビアンの相手であったケタに取材をする。その取材中ケタから父ドン・フェルミンの秘密
を聞かされる。それはドン・フェルミンが「金の玉(ボーラ・デ・オーロ)」、つまりはホモセ
クシャルであったということだった。ドン・カヨもそのことを知っており、隠語として「金の
玉」と呼ばれていた。これはサバリータの耳には入っていないが、ドン・フェルミンは運転手
のアンブローシオともそういう行為に至っている。アンブローシオはそのような趣味はなく無
理矢理に愛人のようにさせられた。場所はリマから四〇キロほどの高級海水浴場であるアンコ
ン。アンブローシオはこのことについてソイラ夫人に手紙を書いている。
サバリータは取材先に向かう途中事故に巻き込まれ入院する。その病院で看護婦だったアナと
出会い結婚する。アナの父親はワンカーヨ出身の太った話し好きの男で、一生ずっと公立学校
で歴史とスペイン語の先生をし、母親は親切なムラータ(混血黒人)であった。
実家のミラフローレスには長らく帰っていなかったサバリータだったが、結婚を機にアナを連
れて実家のミラフローレスに行くと、母親のソイラは青ざめてしまう。アナを抱擁もせず、微
笑みすらしなかった。その理由はアナの人種に対してのものだった。サバリータは結婚を機に
ボヘミアン生活はしなくなっていった。
以上がかいつまんでのあらましである。サバリータは若き日のバルガス=リョサの分身のよう
な存在である。サバリータとアンブローシオの会話が幹のようなもので、そこからたくさんの
枝が伸びていき、最終的に様々な枝が物語の全体図である一本の木を描き出す。後年、バルガ
ス=リョサは「結晶化」という言葉も使っている。『チボの饗宴』では独裁者は物語の中心人
物だが、『ラ・カテドラルでの対話』では独裁者は登場しない。
バルガス=リョサはチリ人批評家ダビー・ガラハーが『ラ・カテドラルでの対話』について書
いた評論に、感銘を受けている。ガラハーはこの小説の意図が、権力は汚れており、社会の
隅々にまで及ぶ膿を生じさせるという点にあると、明らかにしようとした。ガラハーはそうし
た腐敗ぶりが小説の文章にまで影響をしていると、多くの例を挙げて示したという。
言葉は権力に近づくと汚くなり、より俗悪になり、卑劣さの直喩やシンボルが用いられる。
バルガス=リョサは執筆しているときの心の状態を示していると指摘している。
バルガス=リョサは『ラ・カテドラルでの対話』では「自由間接話法」を駆使している。
「直接話法」は登場人物の台詞を、ストーリーの中には登場しない語り手が紹介する。
「間接話法」は登場人物の視点はほとんど消えて、語り手が解釈した文言を紹介しているだけ
になるので語り手の存在がなおさら強く意識される。対して「自由間接話法」では、それが不
分明になる。曖昧になる。なので語り手の存在が薄まり、消えていくような感じになり、登場
人物の気持ちに直に触れているような感じになる。旦敬介氏の解説が詳しい。しかも時系列が
バラバラであり、ストーリーがジャンプし、ウェーブする。これはシカゴ大学で英語で講演し
た時にバルガス=リョサ自身も語っている。なので一回読んだだけでは内容が理解できない。
ぼくは二回読んだ。
バルガス=リョサはプリンストン大学で講義した時に、『ラ・カテドラルでの対話』の創作に
ついて次のように語っている。
「私は読者が大きなパズルに取り組むように、一人ひとりの登場人物をそれぞれの場所に当て
はめて行くにつれ、頭の中で物語が姿を現していくようにしたかったのです。私が書いた小説
すべての中で『ラ・カテドラル』は、おそらく一番苦労した作品です。これは『緑の家』の次
に書きましたが、『緑の家』はフォークナーの影響を強く受けており、言葉がまるで目立つ登
場人物のように、読者と物語の間に入り込んでいきます。『ラ・カテドラル』では同じような
ことが起きないようにと考え、おそらくそのために、物語が言葉を介さずそれ自身で成立して
いるかと思えるくらい、言葉は純粋に機能に徹し、無色透明であろうとしています。時間をか
けて何度も下書きを書き直し、物語を進めるだけの機能に徹していない言葉の使用はすべて排
除しました」(『プリンストン大学で文学/政治を語る バルガス=リョサ特別講義』)
『ラ・カテドラルでの対話』を書いた時、形式についてぼんやりとしたイメージしかなく、ど
うすればよいのか分からないまま、まったくの手探り状態で書き始め、柱となる会話が別の会
話を呼び寄せるというアイデアがひらめいたという。シカゴ大学での講演の最後でも述べてい
たが、「私の白髪は全部この小説を書いたせい」だとずっと言い続け、三年以上もかかり、苦
労して書いている。本書には三〇年後の九九年に書かれた「諸言」もついているが、そこでは
有名な「これまで書いたすべての作品の中から一冊だけ、火事場から救い出せるのだとした
ら、私はこの作品を救い出すだろう」と書いている。
そんな『ラ・カテドラルでの対話』は難解さのために最初は売れなかった。
しかし、時と共に読者が増え、再販され続けて、今では他の本よりも売れ行きがよいという。

廃墟となってしまった〈ラ・カテドラル〉
バルガス=リョサが『ラ・カテドラルでの対話』を書いた頃は非常に悲観的だった。
ペルーがどん底から抜け出せるという希望はほとんど持っていなかった。しかし、そうした捉
え方は時が経つうちに変化していき、最新作『つつましい英雄』や『シンコ・エスキーナス街
の罠』ではペルーについてそれほど悲観的な見方をしておらず、楽観的になっているという。
本書を訳された旦敬介氏は『ラ・カテドラルでの対話』を読んでリマに足を踏み下ろしたとい
う。大学の卒論にも本書を選んでいる。本書をガイドブックのように参照しながら街歩きをし
た。ぼくは本書に出会う前にリマの街を訪れたことがある。サバラ家のあるミラフローレスに
も滞在したことがあり、そこから太平洋を眺め、その先にある日本を憶ったことがある。
時代は違うが『ラ・カテドラルでの対話』を読んでその時のことを憶いだした。
ぼくにとっても思い入れのある作品でもある。
優れた書物は時の経過とともにそうした特質をいくらか失ってしまうかもしれませんが、同時
に得るものもあると、私は思います。だからこそ何世紀にもわたって読者を獲得し続けるので
す。こうした書物は独自性、特有性、あるいは民俗性といったローカルな色合いを超えて、な
んらかの人間の特質を示す力を有しており、そこに文化的背景の大きく異なる人々が共感を覚
えるのです。
マリオ・バルガス=リョサ







コメント
しかしその効果が発現するSLD-MAGICという材料を作るとき壮絶な苦労があったと聞きます。炭素の結晶ををうまくGIC化させるためにこの特殊鋼はCuとSが添加されていました。これは、教科書的には最もやってはいけない合金設計の組み合わせです。しかしひるむことなく久保田博士はそれを敢行し、巨大な不良の山を築いたらしい。それでもあきらめず、黒字に転嫁したのはなんと6年後であったという。これは赤熱脆性とよばれ鉄鋼技術者が真っ先に嫌う現象で、赤く焼けた巨大な鉄塊が圧延や鍛造中に真っ二つに割れてゆくことである。
この原因をしぶとく究明してこの材料は実用化されたのがその舞台裏である。