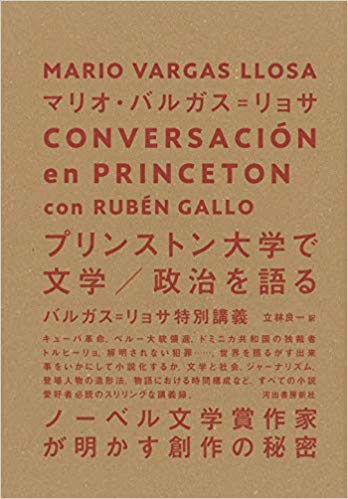
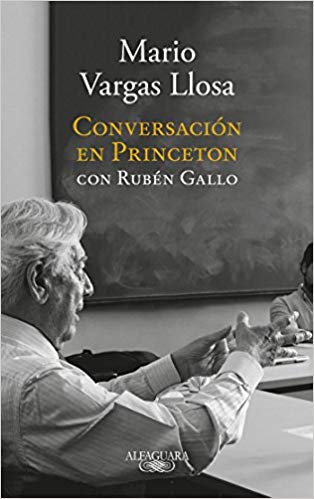
本書はマリオ・バルガス=リョサ(ジョサ)が二〇一五年にアメリカのプリンストン大学で一セ
メスター担当した講義録。
ラテンアメリカ研究講座の主任教授であるルベン・ガリョとの対話形式で講義は進められている
が、学生もそこに参加しているので積極的な議論が展開されている。
取り上げられているテーマは、ガリョの提案によってバルガス=リョサの作品の中から歴史的
出来事に基づき、政治的テーマを扱った五つの小説を中心に講義が行なわれている。
プリンストン大学といえば、アメリカの外交官で後に駐ソ、駐ユーゴ大使を務めたジョージ・ケ
ナンが、四九歳で早々と官界を引退し、思索と著作に没頭したのが母校プリンストン大学の高
等研究所だったことを思いだす。
同研究所にはアインシュタインら、世界的な頭脳を擁してきたことで知られているが、ケナン
を招請したのはロバート・オッペンハイマーだった。
もちろん「高等研究所」ではないが、バルガス=リョサはペルーで大統領選挙に出馬した直後
の九〇年代初頭に、プリンストン大学の客員教授を務めたことがある。
そのことと関係してか、プリンストン大学では、九〇年代にバルガス=リョサ関連の資料を収
集している。
大学図書館が彼の手紙や小説の下書き、その他の文書を大量に購入し、それは現在三六二の資
料ケースに収められて、世界中から大勢の研究者たちによって研究が行なわれ、今では重要な
拠点になっているという。
そんなバルガス=リョサも九〇年代初頭以降は、プリンストン大学とはご無沙汰な関係になっ
ていたが、ルベン・ガリョがラテンアメリカ研究講座の主任教授に任命されると、最初の企画と
してバルガス=リョサを招聘し、プリンストン大学で一セメスターを過ごしてもらうことを提
案した。バルガス=リョサは招聘を快く受け容れ、客員教授として三セメスターを担当した。
ノーベル文学賞受賞前のことだ。
ノーベル文学賞受賞後も多忙だったにもかかわらず、バルガス=リョサはプリンストン大学と
の協働を続けていた。
そして、二〇一四年七月に大学は名誉博士号を授与し、その一年後の二〇一五年には客員教授
として再びプリンストンに戻ってきた。その時の講義録が形となり、本書に結実した。
「プリンストン大学で友人のルベン・ガリョと一緒にこの科目を担当するのは、とりわけ楽しか
った。テーマは私自身の小説、とりわけ歴史に基づき、政治的要素を含む作品についてであっ
た」(本書)

マリオ・バルガス・リョサ(ジョサ)とルベン・ガリョ
その「政治的テーマを扱った五つの小説」というのは、『ラ・カテドラルでの対話』『マイタの
物語』『誰がパロミノ・モレーロを殺したか』『水を得た魚』『チボの狂宴』。
そしてその前後に「小説の理論」「ジャーナリズムと文学」「二十一世紀のテロの脅威」が語
られており、最終章には「歴史と文学」題して、本書の主旨や講義の回想、文学とは何か、小
説と歴史との関係性などが簡潔に綴られていて「あとがき」のような構成になっている。
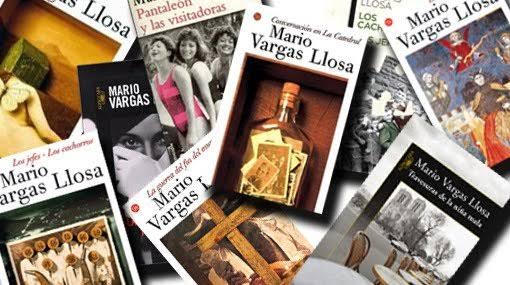
半世紀近く小説を書いてきたバルガス=リョサにとって、小説とはどのようなもので、その役
割は何なのか。第一章ではそのことをメインテーマとし、「〈ブーム〉とキューバ革命」や
「翻訳」についても話が及ぶ。
バルガス=リョサにとっての小説とは、生活の中心が農村から都市へ移ったときに生まれた、
と捉えている。農村生活は詩を生み出すが、都市は物語の発展を促す。それは世界中のどこで
も当てはまるが、もっぱら都会が生活の中心となったとき、小説というジャンルは大いに発展
する。都会とともに生まれたというわけではないが、物語が一般化し、多くの人に受け容れら
れるようになったのは、このときだった、と論じている。夏目漱石を想いだす。
バルガス=リョサが一九五〇年代に小説を書き始めとき、ロブ=グリエが「ヌーヴォー・ロマ
ン」という新しい考え方を打ち出して、リアリズムモデルを破壊し、新しい物語の手法を提起
していた。それに対して、実存主義のサルトルは政治色を帯びた物語という考え方を提起して
いた。
バルガス=リョサは大学時代にルーチョ・ロサイアという文学に精通していた友人に「勇敢な小
サルトル」という渾名をつけらていたぐらい、サルトルの愛読者で、サルトルの立場や政治姿
勢、美学のすべてに共感していたが、その辺りのことも語られている。
それは、後に一貫してリアリズムにこだわり続けたバルガス=リョサの“原点”みたいなものが
垣間見れる。
「二つの世界大戦をはさんで、きわめて政治色の強い文学が生まれました。
全ヨーロッパに及ぶ政治化現象というものがあり、そうした広範な政治化から生まれた文学
は、社会問題と密接に結びついていました。
ロブ=グリエのヌーヴォー・ロマンが生まれる前に、すでに二つの流れがありました。
一方に社会主義リアリズムがあり、文学を旧体制と戦う上での社会的武器、改革のための道
具、革命をもたらす手段と考えていました。
マルクス主義者、共産主義者は文学についてのこうした考え方を支持しており、リアリズムは
大衆を政治的に教育し、社会主義や革命的行動に彼らを駆り立てるべきものでした。
こうした一派に対し、サルトルや、カミュを始めとする他の大作家たちは、「そうした考え方
もあろうが、文学は教育的なものではありえないし、政治的プロパガンダの手段でもない、そ
んなことになれば創造性が失われてしまう。文学は単に政治的な枠にとどまらず、他の人間活
動もカバーしなければならない」と訴えていました。
このようにしてサルトルの理論が生まれ、それはヨーロッパからラテンアメリカまで、全世界
に多大なる影響を及ぼしたのです。
特に私の世代は、小説についてのサルトルの考え方に大きな刺激を受けています」(本書)
バルガス=リョサが共産主義に初めて触れたのは一九五三年のことだったが、党の支配してい
た閉鎖的な教条主義を強く批判し、その一年後には活動から身を引いている。
ところが、この最初の失望から数年後のキューバ革命の勝利がバルガス=リョサの政治活動へ
の情熱を再び呼び覚ますことになった。
しかし、キューバやソ連の負の側面が目に入ってくるようになると、マルクス主義や社会主義
に失望し幻滅している。『水を得た魚』ではそれらを激しく糾弾している。
ちなみに、バルガス=リョサの著作は、リョサがキューバ政府を批判してから発禁になってい
る。
バルガス=リョサの著作は世界各国に翻訳されているが、その翻訳に関して興味深く次のよう
に語っている。
「翻訳者が自身の言語でたくみに書く力を持っていることが重要なのです。
かりに外国語の作品を完璧に理解していたとしても、訳文がまずければ、翻訳としては失敗で
す。他方、翻訳が作品を十分理解しておらず、間違いを犯していたとしても、自分の母語でみ
ごとに書いているならば、その方が出来の良い本となります。言語にはそれぞれ特性がありま
す。
重要なのは、翻訳によって、翻訳調と感じられないように元の作品を作り直せるかどうかなの
です」(本書)
ジャーナリズムは『ラ・カテドラルでの対話』から『水を得た魚』に至るまで、バルガス=リョ
サの作品の中心テーマの一つ。
バルガス=リョサは十五歳で日刊紙『ラ・クロニカ』に足を踏み入れから(ボヘミアン的な生活
も送っていた)、『エル・パイス』紙にコラムを執筆している今日まで、半生にわたってジャー
ナリズムの世界を体験してもいる。
第二章ではそんな「ジャーナリズム」を取り上げているが、文学との違いを次のように語って
いる。
「私は、ジャーナリズムは文学と近いもので、作家として執筆しながら、ジャーナリズムで生
活していくことができると考えていました。
しかしジャーナリズムの言語の使い方は、作家とは完全に別物なのです。
熟達したジャーナリズムのプロは、表現よりもまず現実を伝えることを優先します。
言葉遣いが中立的で透明であるほど、ジャーナリズム的見地からは、優れたものと見なされま
す。
作家の言語の使い方はまったく逆で、言葉を通して自分の考え方を主張し、個性を表現しなけ
ればなりません」(本書)
日本に限らず世界的な傾向だと思うが、自身のイデオロギーに傾倒して書かれた記事を多く見
かける。バルガス=リョサが指摘するような熟達したジャーナリズムのプロが求められてい
る。
オルテガやジョージ・ケナンが明確に指摘し、トクヴィルが十九世紀のアメリカ社会を観察して
臭わせた「大衆化」についてだが、バルガス=リョサはその「大衆化」が今日の報道機関に浸
透し続けていると述べ、そうした変化は世界の文化の劣化に起因しており、民主的社会の基盤
を深く害するものだと喝破している。
さらに、コラムという一つのジャンルにも触れ、優れたコラムニストとは、ただ一つの考えを
展開することのできる書き手であり、ウォルター・リップマンを高く評価している。
「ウォルター・リップマンはずば抜けたコラムニストで、原稿用紙三、四枚で十全に考えを展開
していきます。彼のコラムは常に柱となる一つの考えを提示し、そこから記事全体が組み立て
られています」(本書)
『ラ・カテドラルでの対話』(一九六九)は、バルガス=リョサの最も野心的な作品の一つであ
り、作家が政治について考えるための、いかに文学を利用するかを示す最良の例であるといわ
れているが、第三章では『ラ・カテドラルでの対話』の創作秘話や枠組みなどが語られている。
バルガス=リョサが『ラ・カテドラルでの対話』の着想にたどり着いたのは、オドリアの独裁政
権が社会全体、様々な社会階層の国民たちに及ぼした影響を明らかにしうるような独裁小説を
書きたいと思っていたからだという。オドリア将軍の独裁は一九四八年から五六年まで続き、
リョサの世代にとってその八年は人格形成期だった。
『ラ・カテドラルでの対話』に出てくるリョサの思春期の思い出は、若者が政治活動を行なうに
は非合法活動に参加したり、法律で認められていない政党に加入して体制打倒の戦いを始める
しかないような国の状況だった。
『ラ・カテドラルでの対話』に痕跡を残している作家を挙げているが、それはフォークナーであ
り、現代都市の描き方を教えてくれたドス・パソスだったという。
武装蜂起を試みて失敗した、年老いた革命家の半生を語ったのが、第四章で論じられている
『マイタの物語』(一九八四)であり、革命を実現するために暴力的手段に訴えた左派活動家の
人物像を詳細に描き出したものといわれている。
着想の源となったのは、六〇年代にペルーで起きた小さな事件であり、その中心人物は年老い
たペルー人革命家で、アプラ党員から共産党員になり、結局セクト主義や教条主義に嫌気がさ
して、トロツキー主義になった。
この当時パリに暮らしていたリョサだったが、この事件を知って、非常に心を惹かれたとい
う。
マイタをホモセクシャルにしたいと思ったのは、そういう彼の性質が彼の同志たちとの間で引
き起こす葛藤を想像するためだったという。
『マイタの物語』は、リョサの著作の中で最も激しい批判を引き起こしたものであり、出版さ
れたとき一番厳しい批判は左派の人々たちから起こったという。
第五章の『誰がパロミノ・モレーロを殺したか』(一九八六)も『マイタの物語』と同様に、ペル
ーで起きた小さな事件の調査を行い、事実に基づいた小説。
拷問を受けた死体の発見の場面から始まり、広範な捜査が行なわれることになり、いかにして
真実を明らかにするか、というのがこの小説が提起する主要課題の一つであるとされている。
リョサの心にとても深く刻み込まれている、ペルー北部のエクアドルとの国境に近い都市ピウ
ラ地域を舞台とし、リョサの著作の中で、ヘミングウェイから受けた影響が見られるものがあ
るとしたら、間違いなく『誰がパロミノ・モレーロを殺したか』だという。
語られているところではなく、語られていないところがそうで、この物語には、伏せられてい
る要素が数多くあると指摘する。
足掛け三年にもおよぶ大統領選挙の記録と、リョサの幼少期の自伝を同時に綴られているの
が、以前に取り上げた『水を得た魚』(一九九三)であり、それが第六章で語られている。
リョサの掲げた理想と選挙運動を行なうのは、まったくの別物であり、大変な精力を注ぎ込ん
だ三年間だったが、酷く混乱もしていた。
それが終わった後、自身が経験したことをもっとよく理解し、もっと広い視点から見てみたく
なり、そう思ったときに『水を得た魚』を書こうと決めている。
『水を得た魚』では、ボラス・バレネチェア教授のもとで助手として働き、その時間のほうがサ
ン・マルコス大学の授業よりはるかに有益だったと綴っていたが、本書でもボラス・バレネチェ
ア教授を高く評価し、私の生涯で最良の教師であり、最良の講演者だった。
あれほど雄弁かつ上品に話す人には二度と会っていませんと述べ、バレネチェア教授の下で働
いた経験は私の歴史への興味に火をつけ、それは今でも続いていると嬉しそうに語っている。
そして、リョサが選挙運動で訴えた自由主義的改革の多くが、フジモリとアラン・ガルシアによ
って実行されたことにも触れている。結局、フジモリとアラン・ガルシアは悲惨な末路を迎えた
が。
ヨーロッパに旅立つ所で閉じられている『水を得た魚』だが、リョサ自身もこの本は不完全だ
と思っており、第二部の執筆を考えていないわけではないとも述べている。
『ラ・カテドラルでの対話』と同様に、独裁体制下の社会における様々な形での腐敗を描いた
『チボの狂宴』(二〇〇〇)。
トルヒーリョの支配下にあったドミニカ共和国が舞台で、ウラニア・カブラルという、ニューヨ
ークで人生を再出発させた一人の女性登場人物を通して当時のことが語られている。
ブラジルでの歴史的出来事を描いた『世界終末戦争』を除くと、もっぱらペルーに関してのも
のを描いてきたリョサだったが、何故、ドミニカ共和国という島国の小国について小説を書こ
うと思ったのか。
リョサは一九七四年か七五年にドキュメンタリーの資料収集のためにドミニカ共和国を訪れた
後にこの小説を書くことを決めている。
リョサはフランス・ラジオ・テレビ放送から、その番組に出演する人たちにインタビューを行な
ってシナリオを書くよう依頼を受け、一カ月近く島に滞在して、大勢の人たちにインタビュー
をした。そのときに、すでに亡くなって十年以上が過ぎていたトルヒーリョについて知ったこ
とが、印象に深く残ったという。
一九五〇年代のラテンアメリカは、とんでもない独裁者に事欠かなかったが、おそらくその派
手な振る舞いで一番目立ち、最も残忍だったのがトルヒーリョだった。
ラテンアメリカにおいて社会を完全に掌握できた独裁者はトルヒーリョだけであり、実際は小
説で描いたよりも、はるかにひどかったという。
『チボの狂宴』は基本的にはトルヒーリョを想定して書いているが、ラテンアメリカの多くの
共通項を持つあらゆる独裁者も頭に思い描いている。
リョサはこの章の最後に未来の独裁者にも触れているが、それは二十世紀に現れた、ベルトに
ピストルをぶら下げた将軍とは違い、かなり高度な科学技術を身につけた官僚で、個人の主権
を少しずつ剥奪していくことになると述べている。
「二十一世紀のテロの脅威」では、『シャルリー・エブド』襲撃事件についてが語られており、
その『シャルリー・エブド』襲撃の際に重傷を負った記者フィリップ・ランソンも参加し、表現
の自由とはなにかを論じられている。
リョサはこの事件の後に『シャルリー・エブド』の部数が増えたことに関して、フランス人側の
反応を高く評価している。これはまさに真の民主主義の精神だったと。
最後の「歴史と文学」は「あとがき」のようなものだが、歴史と文学の関係性について記され
ている。
よく日本でも歴史作家の司馬遼太郎のことを「司馬史観」などと揶揄して、「小説には真実が
反映されていない」という声が聞こえてくるが、その歴史と文学の関係に関して、リョサは素
晴らしい自論を展開している。何より本書を読んでいて一番参考になった。
「しばしば小説は感動を高めるために、実際に起きた事実から離れたり、それを省いたり、拡
大したりするが、そうした忠実さの欠如は、歴史的事実を歪曲するのではなく、その重要性や
意義を強調して、読者を主人公たちに感情移入させ、物語の中へ引き込んでいく。
「物語に引き込む」というのは、最も優れた歴史家だけがなしえるものではない。
彼らはしばしば大量の歴史資料を抱え込んでいて、それを用いて関係性や情報を詳述しなけれ
ばならない。
おそらくはそのために、ロシアのナポレオン戦争はトルストイが『戦争と平和』で、ワーテル
ローの戦いはヴィクトル・ユゴーが『レ・ミセラブル』で描いたときの方が、優れた歴史家が資
料的厳密さをもって描写したときより、私たちには本当らしく感じられるのだ。
歴史家がいなければ小説家は、空想をふくらませてくれるものとして歴史を利用することがで
きなかっただろう。
しかし小説家が歴史に加えた操作がなければ、人物や歴史的出来事は、それらの国の日常にお
いて有している鮮やかなイメージや存在感を持たないであろう」(本書)
トルストイは歴史と文学の違いは題名だけだと考え、歴史家は小説家と同じ手法で事実を再構
成していると主張していた。
リョサが指摘していたことは、日本近代が専門の評論家松本建一氏も生前に同じようなことを
いっていたのを想いだす。
バルガス=リョサとルベン・ガリョは、本書の出版を記念して何度か講演や会見も行なってい
る。上の動画は「Casa de América」が企画した会見の様子であり、ルベン・ガリョの態度や
話し片には上品で知的な印象を受ける。
本書で取り上げている作品の創作秘話や小説の技巧や枠組みなども参考になるが、それ以上
に、ジャーナリズムとは何か。歴史とは何か。文学とは何か。に関してのリョサの自論が展開
され、刺激的で大変参考になる。特に十五歳から叩き込まれたジャーナリスティックな洞察力
には驚かされる。
そして、バルガス=リョサはノーベル賞作家ではあるが、知識人として「知」に対する向き合
い方に感銘を覚えるし、目の前に提示された極端で短絡的な解に飛びつかない、その真摯な姿
勢には学ぶ必要があると感じている。特にぼくみたいな若い世代は。
ツイッターや動画だけを観て満足している連中には、“知的な香り”は出せないだろう。
その“知的な香り”は、ぼくが敬愛するジョージ・ケナンやオリヴァー・サックスにも感じられた
ことだ。
読書については、一日最低二時間とは言わぬまでも、その時間を毎日確認することができた
が、執筆、それもフィクションを書くという作業はまったく不可能だった。
これは単にその時間がないというだけではなく、精神を集中してファンタジーの世界に身を任
せ、周りの世界との繋がりを断ち切るという、小説や戯曲の執筆に欠かせない恍惚状態に入り
込むことができないからだ。
『水を得た魚』マリオ・バルガス・ジョサ







