
紛争解決とは矛盾の解消であり、平和構築とは矛盾の管理である。
しかし解決したり管理したりするためには、どのような矛盾が存在しているのかを分析しなけ
ればならないのである。
『国際紛争を読み解く五つの視座 現代世界の「戦争の構造」』篠田 英朗
冷戦直後の一九九一年、篠田氏は大学を卒業し、バブル時代末期の超売り手市場で就職してい
く友人たちを横目で見ながら、大学院に進んだ。
その二年ほど前には、中国で天安門事件、東欧では共産主義政権の崩壊、中東では湾岸戦争、
ユーラシア中央部ではソ連の崩壊の激震が走っていた。
一方の日本国内ではバブルを謳歌しており、冷戦時代の経済成長の最後の祭りのような空気感
が漂っていた。ぼくも十歳まで早稲田に住んでいたので、その光景は今でも目に焼きついてい
る。
当時の日本のODA(政府開発援助)は世界一であり、冷戦後の世界では日本が米国に挑戦すると
いった言説も真面目になされていた。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代だ。
篠田氏はそのような時代背景のなか、世界が大きく動いているという実感を抱きつつ、大学院
に進んだが、どこか現実離れしていた日本を離れ、海外で博士号を取得することを目指し、留
学する準備を始めてもいた。
その頃の篠田氏にとって、はたして世界はどこに向かって進んでいるのか、という問いは、非
常に切実なものだったという。
そんななか、篠田氏はNGO(非政府組織)「難民を助ける会」で国内のボランティアをしなが
ら、海外業務にも携わっていた。
イランでのクルド難民支援、ジブチでのソマリア難民支援、カンボジアでの帰還難民支援の現
場にも行き、一九九三年にはPKO法(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)にも
とづく派遣の最初の文民の一人として、カンボジアで選挙実務にあたってもいる。
そしてそれと同時に、篠田氏は時代の動向を大きく見据えようとするいくつかの理論的視座に
強い関心を抱いていた。それは、国際関係学の分野で研究者となっていくために必要な座標軸
のようなものに思えたのは当然のことであったが、その座標軸を見据えながら自分の生きる世
界の動向を把握していくことが、有益であり、また必要であったという。
篠田氏は平和構築という政策的分野を専門にした観点から、世界のさまざまな紛争に関係する
地域情勢の分析をされている。
特定の地域を専門にしているわけではないが、最大限に個々の地域事情についても調べ、地域
専門家と情報交換もおこない、なるべく頻繁に現地出張をおこない、多くの現地の方々と接触
し、状況把握に努めるようにしているという。その活動は端から見ていても窺い知れる。
しかし、長期にわたって同じ地域に滞在しつづけることは稀なので、自然に構造的な問題をと
らえる視点を大事にするようになったという。
そうすると、むしろ構造的な分析こそが、決定的な意味をもつと感じるときも少なくないと指
摘する。現場のことも熟知されている篠田氏のことばだからこそ重みがあり、説得力がある。
「細かな断片情報だけで、大きな流れをとらえることは、どちらもむずかしい。
国際社会の構造的な動きとは、鳥瞰的な視点によってはじめ議論の俎上に載せることができる
ものだ。そこには相当程度に、国際政治を分析するための理論的な視座が必要になる。
本書は、そうした理論的な視座を駆使して、現代世界の紛争を構造的に見るためのしくみにつ
いて論じてみようとする試みである」(本書)
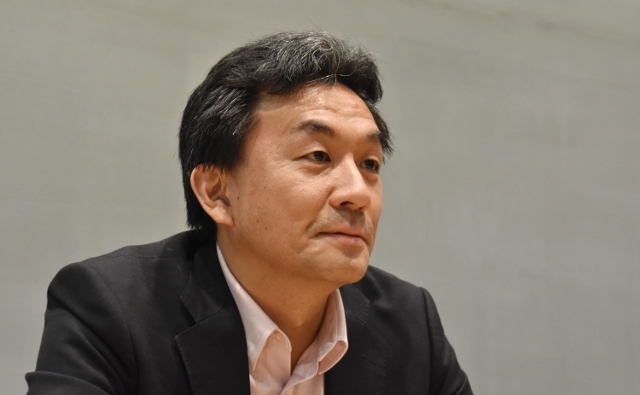
篠田英朗(ロンドン大学(LSE)で国際関係学取得Ph.D.取得。専攻は国際関係論・平和構築)
さて、表題に掲げられている「五つの視座」とは何か。
それは「勢力均衡」「地政学」「文明の衝突」「世界システム論」「成長の限界」である。
第一章では、十九世紀のヨーロッパのような伝統的な国際社会の秩序が、複数の勢力の相克関
係を基本的性格にしていたとすれば、冷戦終焉後の世界では、それとは異なる様相をもつ状況
が広まっていることなどを説明し、国際秩序への挑戦として紛争を捉えることが論じられてい
る。
第二章では、東アジアに焦点をあて、勢力均衡の理論的視座から、紛争構造を分析する。
第三章では、ヨーロッパに焦点をあて、地政学の理論的視座を用いた分析。
第四章では、文明の衝突という考え方を参照し、中東情勢が論じられている。
第五章では、世界システム論を手掛かりに、アフリカの格差社会としての国際社会の問題とし
て分析。
第六章では、アメリカによる対外的な軍事行動を、成長の限界を克服するための運動として捉
えている。
代表的な理論的視座を駆使して読み解いていくのは、第二章から第六章までとなっている。
そのなかでも一番ページ数を割いているのは、第三章の地政学の視座を用いて、ヨーロッパ情
勢を分析している箇所。
しかし、それらを読み解く上で大前提として、紛争とは何か、主権国家と何か、自由主義とは
どのように立ち上がってきたのか、十九世紀の国際秩序と二十世紀後半にできた現代の国際秩
序との違いは何か、などが第一章で論じられている。
本書は分量も多く中身も充実している大著なので、うまく説明できるとも思っていないが、以
下簡単に取り上げる。
一般人でいい加減に生きているぼくの耳には届かなかったが(著者によれば、国際的には受け入
れられているが日本ではあまりみられないと指摘している)、学界では共有されている紛争の定
義が存在する。著者はまず本書の冒頭でそれを説いてくれている。
その紛争分析の専門家は、「複数の人間(集団)が、相容れない目的をもっているとき」、紛争
は生まれると考える。
この定義は、欧米諸国を中心とした数々の大学の紛争解決論の授業などで、将来の研究者や政
治家や国際公務員などにたいして、教示されつづけている。
著者はここでポイントとして重要な論点を指摘しているが、それは、複数の人間が「相容れな
い目的」(incompatible goals)をもっているという状態。
この「相容れない目的」の認定によって、分析者は、客観的に紛争の存在を認定できると考え
られている。
それは「紛争当事者」が、自分たちでは紛争の存在を否定しようとも、気がついていない場合
でも、「相容れない目的」が存在する場合には、なんらかの紛争が存在すると捉えているの
が、紛争を分析する学術・実務の世界の共通認識。
さらに紛争分析の業界では、「立場」(position)と「利益」(interest)を厳密に区別する。
しかもその区別の方法はかなり国際的に共有されている。
「立場」では、当事者が公式に表明している認識のことであり、「利益」は、より実質的な目
的の達成に関わるもの。
そして、紛争当事者の利益の認定こそが、紛争分析および紛争解決において、つねにもっとも
重要な論点となっている。
紛争分析の手腕がもっとも厳しく競われるのも、紛争当事者の「相容れない目的」を目指す
「利益」の内容の認定をめぐってであるという。
交渉術の世界では、お互いの「立場」を否定せず、水面下で双方の「利益」の調整を図ること
が、基本的な考え方となっている。
著者が鋭く指摘しているのは、この「立場」と「利益」を誤認したり、混同すると、まとまる
交渉もまとまらないということだ。
もう少し視点を高くし、もっと大きな枠組みの中で、紛争分析業界の考え方を示してくれてい
る。このままのペースで進むとかなりの長さになってしまうが、重要なので載せたい。
それは大きく三つある。
①紛争は、人間と人間のあいだに存在する矛盾から生まれる。
ある人間が求めているものが、別の人間が求めているものと完全に一致しないとき、矛盾が生
まれる。そして人間社会のなかに存在するさまざまな矛盾が、紛争を引き起こす。
②複数の人間集団のあいだに継続的に存在する矛盾は、紛争の構造的な原因と呼ばれるものに
なる。紛争の構造的原因とは、つまり社会のなかに存在している構想的な矛盾である。
③世界的規模で存在する紛争の構想的原因は、国際的な制度と、制度に収まりきらない現実と
のあいだの矛盾から生まれる。
したがって国際的な紛争の構造的原因となっている矛盾を知るためには、じつは国際秩序をつ
くっている制度的枠組みを知ることも重要になってくる。
紛争分析の理論からすれば、国際制度が世界に完全な調和をもたらすことはないとしている。
なぜなら、すべての人間の「利益」が完全に一致することなどありえないと考えているから。
しかし、集合的利益の調和の度合いを高めることが不可能だとは考えていない。
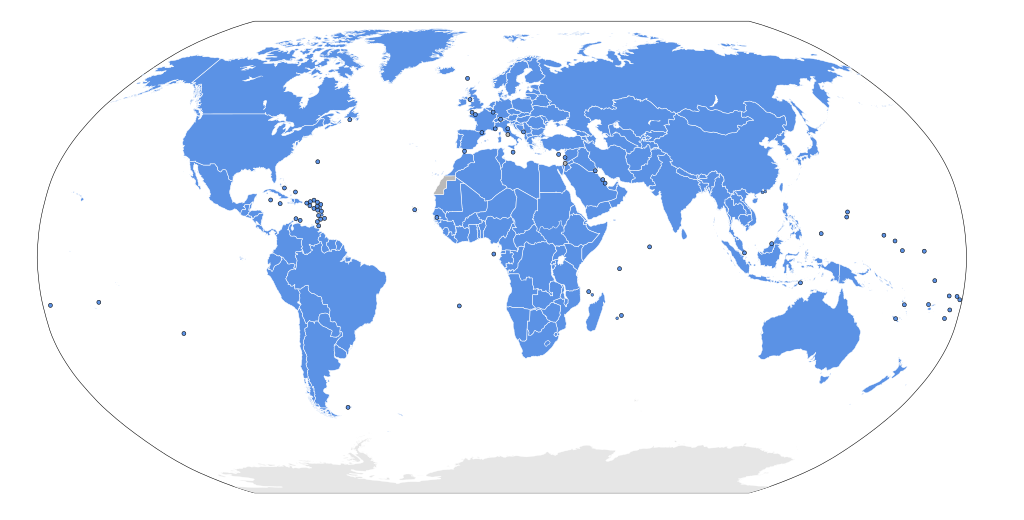
2019年1月時点での国連加盟国は196ヵ国となっている
そして、それらを踏まえた上で出発点として、数々の矛盾を抱えた現代世界が、そもそも基準
として確立してきた秩序の枠組みは、どのようなものなのか、という問題に分け入っていく。
簡潔にいえば、ホップス、ルソー、ウィルソンの流れを捉え「主権国家」という制度から説き
起こし、「主権国家」と表裏一体となっている「自由主義」の来歴を、ロック、スミス、ベン
サム、ミルの流れを説明(この流れは第六章でアメリカを論じるときにより深く詳述されてい
る)。
キッシンジャーやモーゲンソーが抱いていた、十七世紀のヨーロッパにおいて国際政治は完成
し、その後の三世紀以上の間はただ非欧州地域の人々による欧州の模範が広がったに過ぎない
という「ウェストファリア体制の神話」を「ヨーロッパ中心主義」的で「非歴史的」な「物
語」であると篠田節全開で批判を展開する。
他にも、現在では国際連合憲章に導入されて国際秩序の支柱となった諸原則は、アメリカが非
ヨーロッパ圏でつくりあげ、二十世紀になってヨーロッパにもちこみ、世界的規模に広げてい
ったもの、であるということも説明されている。
具体的には書かないが、篠田氏の結論は以下のようになるだろう。
「われわれが生きている現代の国際社会の秩序は、数世紀にわたって変化もなく維持されてき
たものなどではない。実際には、つい百年ほど前から生まれてきて、ようやく二十世紀に原則
として確立されたものにすぎないことは、どんなに強調しても強調しすぎることはないような
重要な点である」(本書)
一方では覇権的な価値規範に依拠した国際秩序があり、他方では画一的な秩序に対抗する勢力
も日々発生するという現象が、今日では起こっている。
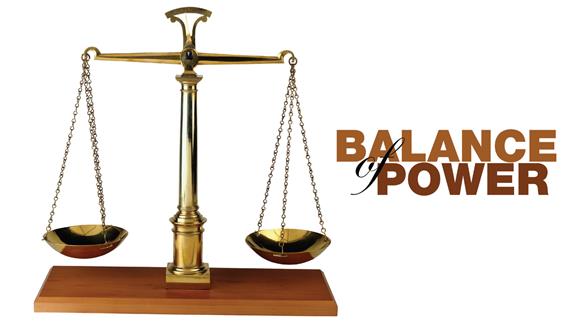
第ニ章では、勢力均衡という文脈から緊迫する東アジアの情勢を読み解いていく。
勢力均衡とは、複数の行為者(政治主体)の間で形成される力の均衡状態を意味している。
国際政治では、超越的な権力が不在であるため、複数の力の均衡を達成することによって社会
的安定を図っていかなければならない要請が強く、勢力均衡が重要な原理として認識される度
合いも高い。
結局のところ、勢力均衡理論の効力は、諸国が勢力均衡を信じて行動する程度によって左右さ
れということであり、東アジアこそが、今日の世界でもっとも強く勢力均衡の理論が意識され
る場所であると指摘する。
特に東アジアにおける勢力均衡の進展を理解するためのポイントとして、「二極から一極へ」
ではなく、「二極から二極へ」でもなく、「三極から二極へ」の流れであることを念頭に置い
ておく必要があると論じている。
モーゲンソーやケネス・ウォルツの洞察、直接的対抗パターンや競争パターン、バンドワゴン理
論、中国の経済や軍事費、十九世紀以前の東アジア情勢や大日本帝国、冷戦初期と後期におけ
る東アジア、日本の位置から現代の東アジア情勢は、第一次世界大戦前のヨーロッパに似てい
ることなど、が論じられている。
篠田氏が結論として導出されていることは、中国が、アメリカにとっての西半球世界に限りな
く近い「裏庭」の領域を東アジアにつくりあげたうえで、アメリカとの間の世界的な勢力均衡
を求めるのかどうかは、現代世界の勢力均衡のゆくえを占う一大トピックであり、東アジア全
域が中国の覇権の下に置かれるというのは、いかにも急激な変化であるかもしれないが、少な
くとも中国大陸を囲む地域にはそのような領域をつくることができるかどうか。
今後数十年で、その帰趨が決まってくるだろう、ということ。
そのような文脈で捉えた場合に、韓国に対しての日本は、歴史認識問題のみを気にして韓国と
の接しかたを決めるような余裕のある立場にはない、と喝破している。
最近、東洋経済のサイトで篠田氏は論文を書いているが、次のように言及している。
「私見では、冷戦時代の国際政治学におけるリアリズムの世界観、つまり国家と国家がビリヤ
ード台の上のボールのように相互にぶつかりあう「ビリヤード・モデル」の見方が、時代遅れ
になっている」
 “The Geographical Pivot of History”
“The Geographical Pivot of History”
最も目に留まり、かつ巧みに説明されてもいる第三章では、地政学の視座を用いてヨーロッパ
情勢を分析する。
ご存じの通り、「地政学」はGeo-politics(地理政治学)の略称であり、地理学と政治学を融合
させた学問的視点を指している。
篠田氏は、「地政学」の理論の構図がもっとも重要な意味をもつのは、ヨーロッパを中心とす
るユーラシア大陸の国際政治であり、ここで「地政学」と呼ぶのは、ふつうに日本語で流通し
ている、実質的意味を失った言葉の「地政学的な」云々ではない、と強調して指摘している。
したがって地理学的な要素を含めることなく、国家間関係のようすを描写したとしても、本来
の言葉の意味からすれば、それはまったく地政学的なものではない、とまで言い切っている。
個人的な観察だが、日本では奥山真司氏以外の言説は間違っているということになるのかもし
れない。

ハルフォード・マッキンダー(1861年2月15日-1947年3月6日)
狭義の意味において「地政学」とは、イギリスの地理学者であったハルフォード・マッキンダー
(一八六一~一九四七)を始祖とする特定の学問的伝統のことを指している。
マッキンダーの地政学を世に知らしめたのは、一九〇四年に王立地理学協会で行なわれた講演
録「地理学からみた歴史の回転軸」(“The Geographical Pivot of History”)であった。
マッキンダーによれば、「回転軸(pivot)=ハートランド」とは、ユーラシア大陸の中央部に位
置するロシアのこと。
そのロシアに関しては、ロシアがもつ比類なき地理的特性は、ロシアが歴史を動かす回転軸と
なる特別な性格をもった国である、とマッキンダーは論じた。
マッキンダーの見立てによれば、ユーラシア大陸は、その面積と人口の大きさから、「世界
島」と呼ぶべき大陸のなかの大陸であり、アフリカ大陸もユーラシア大陸の一部だと位置づけ
た。
この「世界島」に位置するユーラシア大陸の中央部を、「ハートランド」(中心地帯)と呼んで
いる。
ハートランドは、大陸の中央に位置している場所というだけではなく、外界からの侵入者を遮
断する閉ざされた場所としての性格ももっている。
その背後には、北極の無人地域があり、それは基本的に人間が交通路として考えることができ
るハートが存在しない、地球上でも稀有な地域。
ただ、近年は温暖化の影響もあって北極海が航行可能になってきているが、まだ制限的で、今
日であっても条件の根本的な変化は起こっていない。
ハートランドを流れる河川は、ことごとく北極海側に流れこんでいくものであり、こうした状
況から、海上覇権を握る勢力は、河川沿いに上流地域のハートランドに侵入することができな
い。さらに、ゴビ砂漠の存在は、ハートランドの遮断性をさらに高めている。
しかし、ヨーロッパ側の東欧にかけて広がる大平原だけは、ハートランドとヨーロッパを結ぶ
広大な交通路となりうる。
対してハートランドの東・南・西側には、大きな半円弧の形(三日月形)をした諸地域があり、そ
れは海上交通路に開かれている地域でもある。
そして、この温暖多湿な地域でもあるユーラシア大陸外周部分に、地球の人口の大多数が暮ら
している。
この大陸の外周部分を「インナー・クレセント(内側あるいは縁辺の半円弧)」と呼んでいる。
「半円弧(crescent)」=「リムランド」。
さらにその外側には、大陸を取り囲むイギリス、日本、大陸というよりも巨大な島としてのア
メリカ、カナダ、オーストラリアなどが構成する「アウター・クレセント(外側あるいは島嶼性
の半円弧)」があり、「海洋国家」の領域を形成している。
マッキンダーによれば、フランス、イタリア、エジプト、インド、朝鮮半島などは、有力な
「橋頭堡」(Bridge Head)と呼ぶべき存在としている。
中国は「橋頭堡」ではないが、インド亜大陸の先端に属するインドは「橋頭堡」だとされる。
マッキンダーはハートランドのランド・パワーは歴史法則的に拡張主義をとるという洞察を示
し、外洋に向かって勢力圏を拡大させる「海洋国家」群は、実際には大陸中央部からの「回転
軸」の拡張に対して抑えこむ政策をとっていかざるをえないという洞察も示した。
このように地理的状況が政治状況を規定するという考え方が、マッキンダー理論にしたがった
きわめて伝統的な地政学の発想であった。
この文脈で捉えた時に初めて、ヨーロッパという「世界島」の「半島」部分の「付け根」にあ
たり、同時に「世界島」の中央部で「シー・パワー」と「ランド・パワー」の確執の最前線とな
ると規定される、東欧の比類なき地政学的な重要性を感じることができるようになる、と篠田
氏は指摘する。
マッキンダーには有名なテーゼがある。
東欧を支配する者はハートランドを制し、ハートランドを支配する者は世界島を制し、
世界島を支配する者は世界を制する。
ただ篠田氏は念を押して、マッキンダーのテーゼは、東欧から世界を支配する政治勢力が生ま
れる、という洞察を述べたものはなく、東欧は、海洋国家と大陸国家の力と力が相克する地域
であり、それだけにどちらかの勢力か東欧を完全に掌握したときには、世界島の運命が決定づ
けられる、と指摘してもいる。
その後の本章では、マッキンダーのテーゼをめぐる論争点「はたして東欧はそれほど重要なの
か?」という疑問を検証し、スパイクマンが「東欧」の重要性を低く見積もっていたことや、日
本ではマッキンダーの議論を「ランドパワーとシーパワー」と短絡的な対立の構図だけに着目
して解釈し、あえて「東欧」に注目しない議論が多いことや、マッキンダーのテーゼは安易な
解釈を許さない深遠なものである、ことなどが展開されている。
しかし、両世界大戦や冷戦体制も、マッキンダーのテーゼの重要性に関心をもつ者たちによっ
て開始されたものであるかのように見えることは、多くの人びとにとって、マッキンダー理論
がいかに重要な洞察を含んでいるのかを確信させるのに十分な事実であり続けたと論じてい
る。
さらに、冷戦終焉後の世界において、マッキンダーは依然として関連性が高いと言えるのだろ
うか、とマッキンダー理論を現代世界に置き換え検証していく。
冷戦が終わり、東欧諸国がソ連の支配から解放された際、アメリカを中心とする西側世界諸国
にはふたつの選択肢があった。
ひとつは、東欧諸国を、事実上の緩衛地帯として位置づけ、中立に近い性格をもたせること。
もうひとつは、東欧諸国を今度はアメリカを中心とする軍事同盟の側に組み込み、旧敵対勢力
を圧倒することであった。
最終的には、前者は第一次世界大戦の誤りを招きかねないと懸念する勢力が勝ち、アメリカを
中心とする勢力が旧敵対勢力を圧倒し、自由主義の価値規範に依拠した新しい国際秩序を構築
すべきだと考える外交政策が選択された。
東欧を支配するために冷戦時代の軍事同盟であるNATOを拡大させるという行為は、マッキン
ダー地政学の理論にしたがえば、世界支配をめざした行為であった。
ケネス・ウォルツなどの「現実主義者」たちは、NATOの拡大・強化に反対していたのは有名。
二十一世紀に入り、とくにプーチンが大統領に再任してから、ロシアは自国の影響力の維持を
目的にした対外的行動を積極的にとっている。
篠田氏によれば、しかしロシアが独自の野心的な計画にもとづいて拡張主義的な対外政策をと
っていると考えるのは、必ずしも実態に沿った理解ではなく、より決定的かつ構造的な問題
は、むしろNATOの東方拡大であった、と捉えている。
さらには、ロシアの対外政策は、NATO拡大を不可避的に起こっている現実として受けとめつ
つも、旧ソ連圏へのNATOの拡大は自国の死活的利益にかかわる深刻な事態とみなし、それを
防ぐためにあらゆる努力を払う、という考えかたを機軸にしている、と述べている。
マッキンダーの理論にしたがえば、冷戦終焉時に「回転軸」であるロシアが影響力を収縮させ
たのに呼応して、「半円弧」地帯は同盟関係を拡張していった。「半円弧」の同盟拡張は、ロ
シアが黙認するかぎりとどまることなく進みつづけた。
しかし、それは旧ソ連共和国のウクライナをめぐる攻防をめぐって、クリミア併合というロシ
アの反転攻勢を招き出してしまった。
こうした「回転軸」の動きに、こんどは「半円弧」が過敏に反応していくことになった。
篠田氏はそのような文脈の中で「中国」についても明快に論じている。
日本の言論界ではよく、中国は「ランド・パワー」の雄として、ロシアと同じ位置づけであるか
のように語られることがあるが、それも短絡的な見方であると説明している。
ロシアは巨大な内陸国として定義され、内陸国であるがゆえに、海を求めて拡張する自然的欲
求をもちあわせている。しかし、中国はこのような地理的条件をもっていない。
中国は大海に面した大国、あるいは大陸の反対側に位置するヨーロッパと対をなす大陸の東端
を占める超大国であり、現在のEUの全体がもつ地政学的立場を一国でもっている「両生類」の
超大国。
中国が背負う地政学的宿命は、歴史的実例に照らすと、大陸の反対側でドイツが経験してきた
宿命に酷似している。
地政学的な要衝に位置しながら、海洋にも大陸にも絶対的な基盤がない。東アジアというかぎ
られた空間では覇権国であっても、世界大の「グレート・ゲーム」においては、つねに挟み撃ち
にあう危険を孕んだ地政学的環境に置かれている。
ただ、歴史を通して中国は、海上からの脅威をあまり認識してことはなく、ルトワックのいう
とおり、そのメンタリティは「ランドメンタリティ」が顕著だということだろう。
しかし、中国とロシアの共同勢力が、ユーラシア大陸全域で影響力を行使しはじめるとすれ
ば、事態はマッキンダーを参照すべきものになってくるとも篠田氏は洞察している。
さきほど東洋経済のサイトでの篠田氏の言説を紹介したが、地政学に関しても次のように述べ
ている。
「「新しい地政学」の時代の到来を、19世紀や20世紀の「古い地政学」の復活と誤認する間違
いは、犯してはならない。
古い「ビリヤード・モデル」型の発想は、時代遅れだ。そのような発想法に基づく「古い地政
学」もまた、時代にそぐわない」
第四章では、ハンチントンの「文明の衝突」という観点を点検・参照して、中東の紛争と対テロ
戦争の帰趨が論じられている。
「「文明の衝突」が「対テロ戦争」を引き起こしたのか、あるいは「対テロ戦争」が「文明の
衝突」を引き起こしたのかは、もはや誰にもわからない。だが今日の世界では、「対テロ戦
争」が「文明の衝突」としての様相を呈していることは、否定しがたいものとなっている」
第五章では、ウォーラーステインの「世界システム論」を手掛かりとして、アフリカの現状を
考察する。
「アフリカの紛争問題を分析することは、甚大な格差社会としての国際社会について分析する
ことであり、人間社会で弱者が苦しめられる構造的な矛盾について世界的規模で分析すること
である。そして弱者が悪循環から抜け出せないときはけっして強者に挑戦したりせず、むしろ
弱者同士の痛めつけあいをすることのほうが多いという現象について知ることである」
第六章では、まずアメリカの拡張主義の要因を「自由主義」の思想の観点から検討し、それを
踏まえた上で、ローマ・クラブのレポートとして出版された『成長の限界』(一九七二)が問いか
けた問題は、現代ではいまだに克服できていないとして論じられている。
「アメリカの特別な地位と、「成長の限界」の問題とは、密接に結びついている。
「成長の限界」が来るのであれば、アメリカの衰退というよりも、「アメリカが占めているよ
うな特別な国の地位の衰退」こそが、問題にされるべきだからである」
五つの視座である理論を読み込むだけでも大変な作業なのに、それらを駆使して諸地域にあて
はめ、読み解いている著者の卓越した能力に脱帽させられる。
ぼくの認識している範囲では、著者以外の日本人には描けないことだったろうと思っている。
著者も本書の中で度々、日本人は紛争の背景となる構造の分析が苦手、だと指摘している。
本書はそういった意味でも、外の世界の分析が苦手な日本人が打ち立てた“金字塔”だと思う。
当然のことだが篠田氏は、本書はけっして理論の万能性を唱えたわけではなく、また、ひとつ
の地域情勢を説明する際に、複数の理論的視座を適用することが有効になる場合があることを
否定したわけでもない、とも述べている。
「本書がなんらかのメッセージをもっているとすれば、それは、日本人が自分自身を客観的に
見るために、さまざまな理論的ツールをもって、構造的分析の視点から見ることが大切だ、と
いうことであった」(本書)
本書の出版は2015年だが、まったく色褪せていない。むしろ輝きが増している。
是非多くの方に本書を手に取っていただき、著者のメッセージを受け取って欲しいと心より願
っている。
明治日本の外交を主導した陸奥宗光は、
外交の要素に三つあり、一つは国民自然の位置也。二は武力の強弱也。
三は外交に関する国民智識の多少、是也。
と述べていたんだがね。
今日の日本社会には、そのような緊張感は失われているように思われる・・・
日本の外の世界には紛争があふれているが、「自分たち」の日本は関係がないと
言わんばかりの雰囲気のなかでは、緊張感のある分析が生まれないのは当然だろう。
『国際紛争を読み解く五つの視座 現代世界の「戦争の構造」』篠田 英朗


