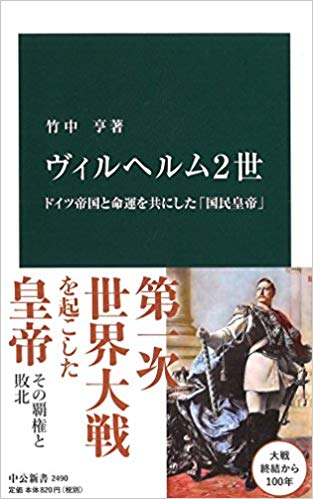
「黄禍」を口にする者は誰であるか。
支那が日本の援助によつて大軍を以て欧羅巴に猛攻撃を加へるかも知れないといふ考えは、
黄禍を口にすることによつて注意を他に外らそうとする事情がなかったならば、
あまりに馬鹿げてゐて一顧にも價しないであらう。
「黄禍」といふ言葉は獨逸が山東の海岸を併合せんとしてゐた時に獨逸が初めて作られたのだ
といふことは、或いは一般には知られてゐないかも知れない。・・・
『日本の目覚め』岡倉覚三(天心)
岡倉天心の『日本の目覚め』は、日露戦争(1904年)のさなか英文で書かれたもの。
「「黄禍」を口にする者は誰であるか」、「「黄禍」といふ言葉は獨逸が山東の海岸を併合せ
んとしてゐた時に獨逸が初めて作られたのだ・・・」というのは、当時のドイツ皇帝だったヴィル
ヘルム2世のことを指している。
その「黄禍論」というのは、「同じ黄色人種の国家である日本と中国が同盟を結び、欧米の勢
力をアジアの植民地から駆逐して西洋世界に迫るという、「アジアの覚醒」への懸念が語られ
た」(『黄禍論と日本人』飯倉 章)もの。
他にも、黄色人種の移民や異人種間結婚などに対しても、西洋キリスト教文明、支配人種であ
る白色人種を弱体化させる可能性があるとも考えられていた。
その中でも、黄色人種の勃興の脅威を説いて、国際的なプロパガンダの道具として活用したの
が、ドイツ皇帝(カイザー)ヴィルヘルム2世だった。
本書は、そのヴィルヘルム2世の評伝。著者はドイツ近現代史、日独文化移転史が専門の竹中
亨(たけなか・とおる)氏。ヴィルヘルム2世との付き合い(研究)が長い(四〇年来)という。
「ドイツの傲慢な「国民性を体現していると見られたのがヴィルヘルム2世である。
彼は日本ではとみに悪評が高かった。黄禍論を唱えたり、とくに日本への攻撃的な言辞が多か
った。― 彼は、日本人を悪魔だと言ったことがある―ためだろう」(本書)
当時、ドイツに留学していた姉崎嘲風(あねさき・ちょうふう)は、この皇帝が生きている間は二
度とドイツの地は踏むまいと誓っていたという。

ヴィルヘルム2世 (第9代プロイセン王国国王・第3代ドイツ帝国皇帝)
「1888年にドイツ皇帝として即位したヴィルヘルム2世(1859~1941)。
統一の英雄「鉄血宰相」ビスマルクを罷免し、自ら国を率いた皇帝は、海軍力を増強し英仏露
と対立、第一時世界大戦勃発の主要因をつくった。
1918年、敗戦とともにドイツ革命が起きるとオランダへ亡命、その地で没する。・・・」(本書)
ヴィルヘルム2世のフルネームは、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ヴィクトール・アルベルトとい
い、フリードリヒとヴィルヘルムは、ホーエンツォラーン家で歴代君主に多く見られ、
ヴィクトールとアルベルトは、母方の祖父母であるイギリス女王ヴィクトリアと夫君アルバー
ト公から来たもの。
ヴィルヘルム2世の母ヴィクトリアは彼らの長女であり、ロンドンからプロイセン王太子フリ
ードリヒ・ヴィルヘルム(後のドイツ皇帝フリードリヒ3世)のところに嫁してきた。
ヴィルヘルム2世が生まれた時は、難産であり、左腕に運動障害というハンディキャップを背
負った。
「ヴィルヘルム2世は、自分のなかにイギリス的本質が深く根ざしていると考えていたし、
しかもそれを大きな誇りにしていたのである。
たとえば寵臣のオイレンブルクに対して、彼はこう言ったことがある。
「イギリスにいると、自分はほんとうにわが家にいるような気分になる。
・・・実際、イギリスは私にとって故郷なのだ。田舎者のドイツ人には、このことはむろん理解で
きまいが」」(本書)
ヴィルヘルム2世は、イギリス王室の洗練と優雅さ、大英帝国の隆盛と栄光に強く魅せられ、
本格的な英国風紅茶を好み、あまり新聞や本などを読まなかったが、キプリングやトウェイン
などの英米系の作家やイギリスの新聞は読んでいた。
少年の頃には、両親に連れられてイギリスを訪問した時、海軍基地でイギリス艦隊の威容を見
て魅入られた。
その経験が皇帝に即位したときに帝国海軍を創設させた契機となる(イギリスを刺激することに
もなるが)。内心は「イギリス人」でありつづけ、それに誇りをもちつづけていた。
しかし、父母とはそりが合わず、その反発からプロイセン的なもの、ドイツ的なものへと向か
わせることにもなった。
「ヴィルヘルム2世のなかでは、相反する二つの人格理念が併存していた。
英国風のジェントルマンと東ドイツのユンカーである。彼はそのなかで引き裂かれ、揺れつづ
けた」(本書)
そんな父に代わり、頼りにするようになるのが、祖父のヴィルヘルム1世だった。
ヴィルヘルム1世はロシア王家のロマノフ家とは深い縁戚関係にあったこともあり、根っから
の親露派であり、ロシアとの提携こそが、ドイツのとるべき道だと考えていた。
その祖父のヴィルヘルム1世を支えていたのが「鉄血宰相」の異名をもつオットー・フォン・ビ
スマルクだった。
「ビスマルクが内閣首班に任命されたのが一八六二年、ヴィルヘルム2世が三歳のときであ
る。当時、内閣と議会が軍制改革をめぐって正面衝突し、政治が完全に麻痺するという深刻な
事態が生じていた。「プロイセン憲法紛争」とよばれる事件である。
事態のあまりの閉塞ぶりに、もはや退位もやむなしとヴィルヘルム1世も一時覚悟を固めたほ
どであった。そのとき最後の切り札として登用されたのがビスマルクである。(中略)
ついには反政府派の拠る議会を圧倒し、事態打開に成功する。こうして彼はヴィルヘルム1世
の政治生命を救ったわけだが、それだけではない。
ビスマルクはドイツにおけるプロイセンのヘゲモニーを確立するため、その後対戦争を三度た
てつづけにひきおこした。
そして、そのうちの最後の普仏戦争(一八七〇~七一年)でフランスを破って、宿願のドイツの
統一をなしとげたのである」(本書)
ビスマルクは、ドイツ統一で攪乱したヨーロッパの国際秩序を再建するために、ドイツを中軸
にして諸国間に同盟条約を張りめぐらせた。
その意図は、フランスからの報復戦争を防止するための現状維持の機能をもったもの。
著者は、「外政においてはビスマルクの念頭につねにあったのは、ロシアとの協調であった」
と指摘する。
すぐに辞意をちらつかせるビスマルクに対して、ヴィルヘルム1世がこぼした有名な愚痴があ
る。「ビスマルクの下で皇帝を務めるのは容易なわざではない」。
一八八八年三月九日、皇帝ヴィルヘルム1世が世を去った。
その後を息子のフリッツがフリードリッヒ3世として継ぐが、即位してからわずか九九日後の
六月五日に逝去する。
そして即日、皇太子のヴィルヘルムが即位し、ドイツ皇帝にしてプロイセン国王、ヴィルヘル
ム2世が誕生した。二九歳の時であった。この年を「三皇帝の年」とよばれている。
二〇年近く、政治の中枢にあり、国家の舵取りをあずかってきたビスマルクだったが、王子時
代のヴィルヘルム2世を次のように評している。
「王子ヴィルヘルム2世は短気な性で、また口先だけの人物だ。それにおべっか使いに弱い。
この人物が将来、気づかないうちに、望まないままドイツを戦争に陥れることになるかもしれ
ない」
即位してからヴィルヘルム2世は、ビスマルクと正面衝突し、強引に解任することになる。
ビスマルクがとっていた外交方針は、第一に、他国の対独警戒を刺激しないように、ヨーロッ
パ内での領土拡大の動きを慎む、第二に、フランスを国際的に孤立させること。
しかし、ビスマルクを下野させたことにより、この国際関係は崩壊していく。
ヴィルヘルム2世は、自国の命運を他国と渡りあうことこそ、君主たる者の天職だと考え、
何ごとにつけても自ら采配をふるった。
「外務省だと?なぜだ?朕が外務省なのに」、「貴下らはみな、何もわかっていない。わかって
いるのは朕のみだ。だから、朕が決定を下すのだ」という言葉も残している。
「大きな契機となったのが一八九一年の露仏同盟である。
ロシアはそれまで、再保障条約(一八八七年)を介してドイツと結んでいたが、同条約の失効
後、フランスとこの同盟を結んだ。
これは、ビスマルク期の国際秩序の柱が一本潰えた。フランスの国際的孤立が解消されたから
である。
しかも、フランスの相手がロシアだったから、ドイツは東西から脅かされる立場に置かれた。
ドイツにとっては憂慮すべき事態である。
そこでこの事態を解消すべく、ドイツはその後、くりかえしてロシアに働きかけた。
たとえば、日清戦争後の三国干渉(一八九五年)はその一例である。
これは、日本が下関講和条約で清から遼東半島を獲得したことについて、ロシア、ドイツ、フ
ランスが共同歩調をとって干渉し、日本に同半島を還付させた事件である。
干渉の音頭をとったのは、満州進出を狙っていたロシアである。しかし、それを強く後押しし
たのがドイツであった。東アジアで何か具体的な利益を、と考えてのことではない。
ロシアがアジア進出の矛先を向けてくれれば、ドイツとの国境でのロシアの軍事的プレゼンス
が減り、ドイツにとって脅威が減じるからである。
フランスが参加したのも、このドイツの動きに連動していた。
ロシアとドイツがこれを機に接近するようなことがあれば、せっかくの露仏関係が薄まってし
まう。それを危惧したのである」(本書)
三国干渉の後、ヴィルヘルム2世は、黄色人種の脅威を外交で利用することが有益であると信
じ始め、ロシアのニコライ2世などに説き始めるようになる。
後のドイツは、英仏露の三強国に取り囲まれる形になるのだが、この当時は、露仏の脅威を中
和しつつ、英露の対立という大きな地政学的状況のかで一定のフリーハンドを得ていた。
さらに、ヴィルヘルムが即位するとまもなく、帝国海軍省を創設させ(マハンの著作に親しんで
もいた)、大海軍の建設を急ピッチで進め、「世界政策」のスローガンの下に積極的な海外拡張
を唱えてもいた。黄禍論を唱えることは、ドイツの「世界政策」の目標に合致していた。
ロシアを東アジアでの冒険に従事させることができれば、東アジアにおいてイギリスとロシア
を対峙させることができる。
そしてこの頃に、悪名高い寓意画『ヨーロッパの諸国民よ、汝らのもっとも神聖な宝を守れ!』
のスケッチを自分で描き、それを基にお気に入りの宮廷画家へルマン・クナックフスに絵を仕上
げさせている。この寓意画は、「黄禍の図」と呼ばれるようになり、西洋世界に黄禍思想が流
布するきっかけとなった。
ヴィルヘルム2世は、ロシアのツァーに原画を贈呈し、複製はヨーロッパの王室やフランスの
大統領、アメリカの大統領といった欧米の政治指導者に贈り、一九世紀の終わりにもっとも話
題を集めた政治的なイラストとなったという。(『黄禍論と日本人』飯倉章に詳しい)

ヨーロッパの諸国民よ、汝らのもっとも神聖な宝を守れ! (1904年) 「黄禍の図」とも呼ばれた
さらにヴィルヘルムは、頻繁にニコライに手紙を書き、日本と戦争をするように煽ってもい
た。
「日本との戦いは、キリスト教徒と仏教徒の文明間戦争であり、ロシアはアジア人種の西漸か
らヨーロッパを防衛する天命を負っているのだと。ニコライの反英感をあおることも忘れなか
った。日英同盟で日本と組むイギリスは、ロシアの戦争努力を陰に陽に妨げ、ついには敗戦に
よってロシアが弱体化するのを待っているというのである。(中略)
ドイツは公式には中立を保ったが、背後ではロシアの戦争体制を積極的に支援した。
一例を挙げるなら、バルチック艦隊がヨーロッパから遠路はるばる極東に回航する際、その
先々で燃料を手配したのがドイツの巨大海運会社である。
同社の社長アルベルト・バリーンはヴィルヘルム2世の知己だった」(本書)
日露戦争は一九〇五年九月五日の講和条約締結で終わるが、その約二ヵ月前の七月にヴィルヘ
ルムは、フィンランド南部にある小さな島ビョルケで、ニコライ2世と密約をしている。
前年に防衛条約をヴィルヘルム2世は、ニコライ2世に提案していたが、ロシアは同盟相手のフ
ランスに遠慮して乗ってこなかった。それを再度試みたのがビョルケでであった。
しかし、ビョルケでの密約は、ロシアのドイツへの不信感を強める結果となり、対露関係の
悪化を加速させた。
さらに、ロシアとの関係悪化に加えて、イギリスとの関係もぎくしゃくしてしまう。
その最大の原因は、ヴィルヘルム2世が進めたドイツの海軍建設であった。
「海洋帝国としてのイギリスの覇権を支える柱は、その比類ない海軍力にあった。
その戦力は、海軍力第二位と第三位のフランスとロシアが束になってかかってきても持ちこた
えられるという、いわゆる「二国標準主義」の高い水準にあった。
それが今、ドイツの台頭で危うくなってきた。ドイツが、その企図どおりにイギリスの三分の
二まで戦力を高めたらどうなるか。
自国の覇権に対する真っ向からの挑戦とイギリス側が見たのは当然である。
その結果、独英関係はそれまで小康状態が続いていたのが、世紀転換期前後より、次第にあや
しい雲行きとなった。
はっきりした転回点となったのは、一九〇四年の英仏協商である」(本書)
新興国であったドイツの海軍増強の根幹にあったのは、経済発展の結果であり、覇権国であっ
たイギリスは反発と焦燥を感じていた。
「ドイツが経済大国化したのがまさしくこの時代であった。
一九世紀前半に点火した工業化は世紀半ばに本格化し、テンポを速めていった。
その結果、世紀半ばから第一次世界大戦までの半世紀強の期間―これは、ほぼ帝政ドイツの時
代にあたる―に、ドイツの経済規模は四倍弱に成長し、ことに工業の伸びは六倍近くにおよん
だ。人口構成も変化した。
帝国建国のころは、ドイツ人の半数強が農業で生計を立てていたのが、世界大戦前夜には国民
の三分の二が商工業に従事するようになっていた。
・・・ドイツの輸出入の伸びは著しく、その結果一九世紀には、ドイツはイギリス、アメリカに続
く貿易大国にのしあがる。この経済的興隆の極点にあたるのがヴィルヘルムの時代である。
一八九〇年代半ばから第一次世界大戦前夜は、ドイツ経済がとりわけ好調な時期だったからで
ある。言い換えれば、彼の治世には好景気に沸きつづけた時代であった」(本書)
その結果、ドイツ製品はイギリス本国にも大量に流入し、世界各地でイギリスがおさえていた
市場もドイツに侵食された。
それは汎用品にかぎらず、ハイテク(電機と化学)部門でもイギリスの劣勢が目立ち、特に化学
の分野はドイツの独壇場で、当時の世界で生産される合成染料のうち、九割がドイツ製だっ
た。
「ドイツの経済的躍進は、ドイツの側でも人びとの心性に大きな変化をもたらした。
ドイツ人には元来、イギリスやフランスに対する劣等感が根強い。
これら西欧諸国の文明的洗練に比して、自分たちの生活慣習や文化は粗野だという引け目であ
る」(本書)
経済的に成功した当時のドイツの人びとは、諸外国からも賛嘆され、次第に傲慢な態度になっ
ていった。実際にこの頃のドイツ人の評判はよくないという。
「ドイツはロシアに続いて、イギリスとも関係が悪化した。いうまでもなく、フランスは積年
の対立がある。
英露協商の締結(一九〇七年)によって、これらの三国間の提携はちょうど三方からドイツを囲
む形を整えた。第一次世界大戦の構図がここに生まれる」(本書)
「ヴィルヘルム期のドイツでは、ビスマルク時代に比べて、思いきった外政行動が目立つ。
大戦前に続発した外政的危機も、ほとんどはドイツの冒険的行動が原因であった」(本書)
ヴィルヘルム2世自身も、協商を対独包囲網だと認識していた。ただ、英国王エドワード7世の
陰謀だと堅く信じていたらしい。ちなみにドイツは、オーストリアとイタリアの三国同盟があ
った。
ドイツの国民の方も、ヴィルヘルム2世が進めた海軍建設にも熱狂的に支持し、イギリスがド
イツに嫉妬し、その国運発展を邪魔しようとする旧秩序の権化だ、という見方をするものが多
かったという。
さらに厄介だったのが、ヴィルヘルム2世が「国民皇帝」を目指していたこともあり、世論の
動向に敏感になっていた。
「ヴィルヘルムは国制を「帝国」の下に均一化し、人びとを単一の「国民」に一体化したいと
考えた。そして自らは、その統一国家の頂点に立つ君主として、全国家機構の上に君臨し、
またあらゆる国民から等しく敬慕される支配者となるのである。
言いかえれば、「国民皇帝」になるのが彼の宿願であった。」(本書)
第一次世界大戦が終わると、ヴィルヘルム2世が大戦勃発の張本人と目された。
しかし、ヴィルヘルム2世は武力解決には消極的であり、開戦前夜には、戦争を回避したいと
して、ロシアやイギリスに対して工作にも動いていた。
その後、ドイツ革命も重なり、オランダに亡命したヴィルヘルム2世だったが、戦犯法廷への
出廷という悪夢はまぬかれた。
亡命先のオランダでは、静かな生活をおくっていたが、自分の潔白を証するストーリーを考え
ていた。
「・・・いわく、諸悪の根元はユダヤ人、フリーメーソン、イエズス会である。(中略)
これら悪の勢力は、秘密のネットワークを通じて連合国の政治を牛耳り、無辜のドイツに世界
大戦をしかけさせた。ドイツ国民を瞞着して大戦末期に革命をおこさせたのも彼らである・・・」
(本書)
なかでも、ヴィルヘルム2世が敵視したのはユダヤ人だった。
「ヘブライ人種は、国内でも国外でも朕の宿敵である。
彼らは昔も今も、つねに虚説を振りまき、騒擾、革命、体制崩壊を黒幕として演出してきた。
・・・彼らにはしかるべき罰をくださねばならない」
こうした思考風土から育ってきた政治勢力の一つがナチズムだった、と著者は指摘する。
一九三八年にナチスがユダヤ人迫害を実行した(水晶の夜事件)のときにヴィルヘルム2世は、
「故国でおこっていることは恥辱だ」と憤激しているが、一方では、ユダヤ人を片づけるのに
最良の手段は毒ガスだ、とも言辞も残している。
一九四一年六月四日、ヴィルヘルム2世は世を去った。八二歳であった。
「ヴィルヘルム2世は諸々の矛盾に満ちた複雑な人間であった。
これらの矛盾はむろん、まずは彼個人の人格に根ざしたものではある。
だが他方で、この複雑さは一九世紀半ば以降のドイツの歴史的な変貌を反映したものであり、
あるいはそれに強められたものでもあった。
その意味では、ヴィルヘルム2世の人生は、近現代ドイツ史の一つの縮図だったのである」
(本書)
中世の皇帝や三十年戦争を戦った君主からウィルヘルム2世やヒトラーに至るまで、
この中庸性の欠如という面は、ドイツ国民性のひとつの宿命的な弱点となっていた。
ドイツ人は、可能な限度内において目標と行動を抑制するということができず、
他の物的・人的要因を基礎として築かれたドイツの国力を何度となく浪費し、
とうとう最後にはこれを破壊してしまったのである。


