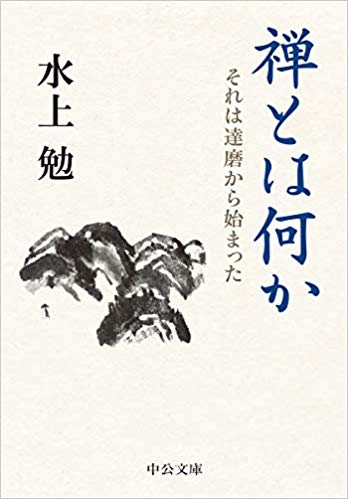
この本は、諸先輩の研究書や祖師語録注釈の書をふところに、
中国洛陽、西安から黄梅、岳陽、成都、昆明、広州、蘇州、杭州、福建に旅して中国純禅の
人々の由縁の地に佇み、さらに日本国内では、応、燈、関をはじめ一休、白隠、沢庵、桃水、
正三、盤珪、良寛と、その生誕地や、終焉の地をたずねて心にうかんだことどものノートを整
理したものである・・・
『禅とは何か-それは達磨から始まった』水上勉
新年、あけましておめでとうございます。
ぼくの年末年始は、ひたすら本書を読み浸っていた。
本書は、幼くして禅寺に預けられ、十九歳で勝手に禅門を飛び出した、直木賞作家の水上勉
が、達磨から良寛までを追った著作となっている。
その系譜は、世俗を否定し、超越する本来の禅を、著者は「純禅」と呼んでいる。
「はじめに、日本禅宗の源流を中国にさかのぼってみるのは、
ここに登場する一休和尚も良寛和尚も正三和尚も、よく中国祖師禅に還れ、純禅にもどれとい
い、中国高僧たちの行実や語録をふまえて己の詩偈(しげ)に、歌に托されたからである」
(本書)
禅は古代インドに発生し、中央アジア、中国を経て最終的に日本に来て集大成されたのだが、
中国に禅を正式に伝えたのは達磨大師。
達磨は西域の胡人であるとか、南インドの香至国の国王の第三子などとの説があるが、インド
の地で生まれたのは間違いないようだ。
出家の後、般若多羅の法を嗣ぎインドで教化の後、六十歳ごろ海路で南北朝時代の中国に渡っ
て来た、といわれている。

達磨図 河村若芝筆 (江戸時代)
一説によれば、現在の広州とハノイの間のあたりに上陸し、その後、北に進み、有名な梁の武
帝との問答を交わし、黄河流域の嵩山少林寺に入って、終日壁に向かって坐禅していた。
その梁の武帝との有名な問答が『続高僧伝』に出ていて、本書でも孫引きされている。
「貴僧はどんな教法をもって、衆生を済度されるのか」
「一字の教えももってきていません」
「朕は、即位以来、寺を建て、人を救い、写経もし、仏像もつくったが、いかなる功徳がある
だろうか」
「無功徳」
達磨はさらに言い足す。
「それらのことは、みな形にあらわれた有為の善行ではあるが、真の功徳とはいえません」
「真の功徳とはどういうものか」
「廓然無聖(かくねんむしょう)」
廓然とは、からりとして何もないことをいい、無聖とは、聖なんていうものはない、という。
「朕に対する者は誰だ」
「不識」
と達磨はこたえただけであった。
武帝は、達磨のいったことが理解できず、達磨は梁都を去って揚子江をわたって洛陽に行く。
洛陽につくと、近くの嵩山少林寺に入って、終日壁に向かって坐禅していた。
インドから来てただ座っているだけの毛むくじゃらの僧の噂は、人々の間に広まるが、皆理解
できなかった。しかし、勉強家だった沙門の神光(じんこう)は面白がった。
「孔子や老子は礼の風規だ。荘子も易経も妙理をつくしていない。
きくところによると、少林寺の岩窟で座ってばかりいる僧がきたという。
彼にあって玄境をきわめてみたい」
雪の降る夜、神光は少林寺に行って教えを乞うが、達磨は面壁端座するのみで、何もいわなか
った。夜明けまでずぶぬれで門前に立っていると、達磨がようやく口をひらいた。
「お前さん、雪の中に夜通し立って何を求めているのか」
「和尚さま、慈悲を以て甘露門をひらいて、迷える人々を度して下さい」
「諸仏の妙道は精勤して行じ難きをよく行じ忍び難きをよく忍び、小智、小徳、軽心、慢心を
もって、真実の道を求めようと願うなら、いたずらに苦労するばかりだ」
突然、神光はかくしもっていた刀で、左臂(さひ)を断った。達磨は関心して、
「諸仏ははじめに道を求めるにあたって、真理のためには身命をわすれられた。
今、お前さんは私に臂(ひじ)を斬ってみせて道を求めている。その求道心はよろしい」
その後、神光は弟子になり、慧可(えか)という名をもらった。
慧可がある日、達磨に向かって、
「諸仏の法印は得聞することが出来ましょうか」
ときいた。達磨は、
「諸仏の法印は人から得聞することは出来ない」
とこたえた。
魏の考明帝は達磨の徳を聞いて使者を三度もつかわすが、達磨は山を降りなかった。
慧可とのやりとりは、道原の『景徳伝燈録』に書かれているという。
「当時の僧たちはみな帝王に招かれることを望んでいた。達磨には名聞心はなかったのであ
る。そのため、いっそう道俗の帰依を得た。しかし、達磨は慧可ひとりをみとめただけで、
嵩山に九年間端座した」(本書)
慧可のほかに三人の弟子がいた。道育、尼総持(にそうじ)、道副。
道副がいった。
「私は、文字にとらわれず、また文字をはなれないで、仏道を行じます」
「汝はわが皮を得たり」
と達磨がいった。尼総持がいう。
「私が理解しておりますところは、愛欲も怒りもしずまって、よろこびは、仏国を見るようで
す」
「汝はわが肉を得たり」
と達磨がいった。道育が、
「物を構成する地水火風の四大も、因縁がつきますと空となり、またすべての事物は、
色受想行識の五蘊が仮に和合してできているので、もともと有ではなく、一法として得るべき
ものはありません」
「汝はわが骨を得たり」
と達磨がいった。
最後に慧可が、ただ黙って達磨に礼拝して、もとの位置についた。それをみて、
「わが髄を得たり」
と達磨はいう。
「むかし、如来は正法眼を迦葉大士(かしょうたいし)に付し、転々としてわたしに至ってい
る。いま、お前に付すから護持しなさい」
達磨は袈裟を慧可にあたえて、
「法信とする」
といい、伝法の偈を示す。
我本慈土に来り 法を伝え迷情を救う
一華五葉を聞き 結果自然(じねん)成
これが有名な皮肉骨髄の訓戒というものであり、この時、『楞伽経(りょうがきょう)』四巻も
慧可にあたえ、千聖寺(せんしょうじ)へゆき、三日目に示寂した。
永安元年(五二八)十月五日のことだといわれ、唐の代宗から、円覚大師と諡号された。
「達磨の行状をふりかえっていると、この行実に、禅の核のところが語られている気がする。
慧可の命がけの入門も、ほかの弟子との問答も、のちの祖師たちが、形式はかえるけれども躊
躇するところだし、また、武帝や考明帝に対した態度も、さすがは始祖だけのことはあって、
純禅の源流に泰然と端座している」(本書)
達磨の思想は、『二入四行論(ににゅうしぎょうろん)』(真理にいたる方法に、二つの立場と四
つの実践)でつきるようだ、としている。
「二入の一つは、原理的ないたり方で、経典をよく学んで、仏法の大意を知って、生きとし生
けるものすべては、平等な真実をもっているけれど、外来的な妄念にさえぎられて、本質を実
現できないでいることを確信せよ、というのである。
もし妄念を払って、本来の真実にかえって、身心を統一して壁のようにしずかな状態を保って
いたら、自分も他人も、凡人も聖人もひとしく一なるものであることがわかってくる。
分別を加えるまでもなく、しずかに落ちついてきて作為がなくなる。これが原理的ないたり方
だ。
もう一つの実践的ないたり方には四つの実践方法がある。
第一は前世の怨みに報いる実践である。第二は因縁にまかせる実践である。
第三は、ものを求めない実践である。第四は、あるべきようにある実践だ」(本書)
達磨のこの『二入四行論(ににゅうしぎょうろん)』は、禅宗の宗旨の根元だ、として次のよう
にも述べている。
「梁の武帝に、いくら寺を建て、写経をしても「無功徳」とこたえた達磨の考えの根がここに
ある。
達磨はつまり、壁のように座って不動の心で生きよ、と説いた。物事を対立的にとらえない
で、直覚的に見つめてとらえよという。
むずかしい理論のようだが、何どもかみしめていると、わかってくる。中国の風土に、この達
磨の思想はよく根づいた」(本書)
さらに論述を進めて、禅は老荘の学に通じる人々によって理解された、として簡単に説明され
ているが、まとめると、
「インド由来の仏教思想は、中国に入りて、こうした老荘思想の「無心」から影響を受けるこ
とによって、禅を生んだ」(西平直)
「釈尊から伝えられてきたインドの坐禅に、中国の老荘の思想を融合させ、
「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏」という禅門独特の、そして最も大切な思想が生
まれた」(枡野俊明)
ということだろう。
その後、達磨から二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘任、禅宗の基盤を確立したといわ
れている六祖慧能や、北宗禅や南宗禅の背景、南嶽懐譲、馬祖道一を経由し、臨済義玄にペー
ジを割いて中国禅の一連の流れを説明し、日本禅の良寛に至るまでの流れを説明している。
「栄西、道元のつたえた禅は、唐代がすぎ、五代の動乱期も終え宋代に至って栄えていた禅で
あった。
唐代のように貴族や王候の信仰にのみよるのではなく、地方に生まれた新興武士階級や豪族の
加護帰依で隆昌をみていたものだ。(中略)
日本の山上仏教を脱して、新宗教に接すべく渡宋した栄西と道元は、中国仏法の主流としてあ
ったこの純禅の道に魅きこまれた。ふたりとも六祖慧能の禅流に没入してゆく」(本書)
日本に禅が浸透してくると、宮廷、公家、武将などの知識階級などに魅力をもってむかえら
れるが、権力的な色彩の濃いものになってしまう。
江戸時代になると僧侶は、宗派ごとに厳密な本寺末寺関係でしばられ、上下の関係は士農工商
と同じように厳しかった。
形骸化したそれらの禅に反旗を翻し、「純禅」(世俗を否定し、超越する本来の禅)を志向した
僧侶らをフォーカスしている。
「応・燈・関の純禅の流れは一休、桃水、良寛のように地を這って生きる乞食頭陀生活型と、
正三、沢庵、白隠のように、宗派内にあって、立宗の初心にもどれと叫びつつ日本の純禅を開
拓しようと闘った型の二つに分かれる。(中略)
いずれにしても沢庵、正三、白隠、盤珪には武家の加護があった。一休、桃水、良寛には権力
の加護はなかった。
あったとすれば民衆の加護をうけて風狂を生きただけだった」(本書)
それは、鈴木大拙が『禅と日本文化』の中で、禅の特徴を七つあげているが、それを実践しろ
ということなのかもしれない。
1、禅は精神に焦点をおく結果、形式(フォーム)を無視する。
2、すなわち、禅はいかなる種類の形式のなかにも精神の厳存をさぐりあてる。
3、形式の不十分、不完全なる事によって精神がいっそう表されるとされる。
形式の完全は人の注意を形式に向けやすくし、内部の真実そのものに向けたがたくするからで
ある。
4、形式主義、慣例主義、儀礼主義を否定する結果、精神はまったく裸出してきて、その孤絶
性、孤独性に還る。
5、超越的な孤高、または、この「絶対なるもの」の孤絶がアスセチズム(清貧主義、禁欲主義)
の精神である。
それはすべての必要ならざるものの痕跡を、いささかも止めないということである。
6、孤絶とは世間的の言葉でいえば無執着ということである。
7、孤絶なる語を仏教者の使う絶対という意味に解すれば、それは最も卑しと見られている野
の雑草から、自然の最高の形態といわれているものにいたるまで、森羅万象のなかに沈んでい
る。
大拙は「禅は仏陀の精神を直接に見ようと欲するものである」と述べているが、
「本来本法性、天然自性身」ということなのかもしれない。
ぼくの要約ではわかりづらいかもしれないが、本書では達磨から説き起こし、中国で禅が確立
した背景、日本に来て集大成された背景が綴られている。
日本の僧侶は、大応、大燈、関山、道元、一休、正三、沢庵、桃水、白隠、盤珪、良寛などの
生涯と思想が掘り下げて語られている。
本書を読めば、一連の禅の流れがかなり理解できるし、直木賞を受賞しただけあって文章も読
みやすい。
日本はアジア文明の博物館となっている。いや博物館以上のものである。
なんとなれば、この民族のふしぎな天性は、この民族をして、
古いものを失うことなしに新しいものを歓迎する生ける不二元論の精神をもって、
過去の諸理想のすべての面に意を留めさせているからである。
世の塵をぬぐうて匂ふ初日かな
井月


