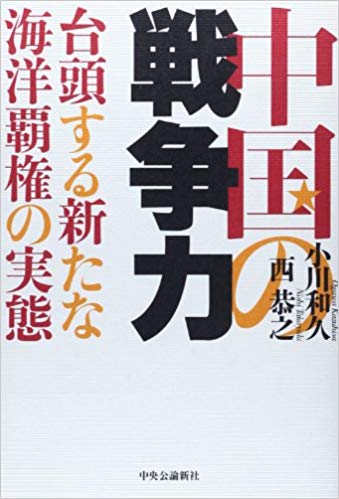
先人たちが折りに触れて口にしてきたように、国境を接する日本と中国は「引っ越しできない
関係」にある。
相手のことを嫌おうとも、憎もうとも、いやでも付き合わなければならない間柄である。
そこにおいて日本に求められるのは、軍事面で中国を安全な状態にし、経済面においても日本
企業が正当な利益を追求できる環境を、国家を挙げて戦略的に構築することである。
それにもかかわらず、中国の軍事的動向については、いまにも日本を攻撃しそうな印象ばかり
が先に立ち、危機感を募らせた日本の世論が政府の冷静な政策判断を妨げかねない兆しさえ感
じられる。・・・
『中国の戦争力』小川 和久
本書は軍事アナリストであり、静岡県立大学特任教授である小川和久氏(以前に『日米同盟のリ
アリズム』をご紹介した)と、シカゴ大学大学院で政治学博士を取得、同じく静岡県立大学グロ
ーバル地域センター特任教授である西恭之(にし・たかゆき)氏による共著。
本書の構成は、小川氏が主宰するミニ・シンクタンク「国際変動研究所」が発行しているメール
マガジン『NEWSを疑え!』の中から、中国関係の安全保障や軍事の動向に関する記事を編集
し、データなどを更新して単行本にまとめたものとなっている。
プロフェッショナルの視点から中国の軍事的動向を分析し、中国の軍事力の実像を等身大で浮
き彫りにしている。
出版は二〇一四年三月なので、時事問題を扱っている箇所に関しては、多少時間の経過を感じ
させるが、それでもプロフェッショナルな視点から多角的に掘り下げて論じられているので、
時間の経過に関係なく参考になる部分はかなりある。
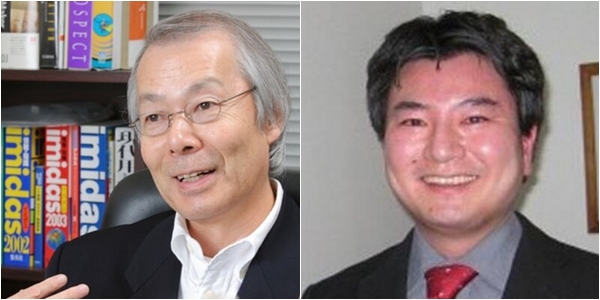
(左) 小川 和久 (右) 西 恭之
ご存知の方も多く今更な感もあるかもしれないが、本書冒頭で中国の大戦略として「三戦」(孫
子の兵法を戦略化したもの)を実行していると指摘し、論じられている。
これは中国共産党が二〇〇三年一二月に「中国人民解放軍政治工作条例」を改定し、
「三戦」という戦略を公式ドクトリンとして取り入れたものとされている。
駐シリア臨時代理大使(現在は知らないが)の松本太氏の『世界史の逆襲』の中でも指摘されて
いることでもある。
その「三戦」とは、輿論戦(よろん)、心理戦、法律戦の総称。
本書では「三戦」について、防衛省防衛研究所編『中国安全保障レポート』(二〇一一年三月)
を転載しているが、それを要約して載せる。
大枠については言及されることはあるが、具体的に論じられることは意外と少ないので。
【輿論戦】
輿論戦とは、自軍の敢闘精神を鼓舞し、敵の戦闘意欲を弱めるために内外の輿論の醸成を図る
活動をいう。
新聞、書籍、ラジオ、テレビ、インターネット、電子メールなどのメディアと情報資源が総合
的に運用される。
常用される戦法については、敵の指導層や統治層の決断に影響を及ぼす「重点打撃」、有利な
情報を流し不利な情報を制限する「情報管理」などがある。
【心理戦】
心理戦の目的は敵軍の抵抗意志の「破砕」であり、敵軍に対する「宣伝」、「威嚇」、「欺
騙」、「離間」による認知操作と自軍の「心理防護」を主な形態としている。
「宣伝」は、ラジオ、テレビ、インターネット、投降勧告、印刷物の散布といった手段を通じ
て敵側の思考、立場や態度の変化を狙う。
「威嚇」は軍事演習などの軍事圧力、有利な戦略態勢および先進兵器装備の誇示を通じて、
敵軍の認識、意志への影響を狙う。
「欺騙」は「真実」を「偽装」することで敵に錯覚を生じさせ、敵軍の決定と行動を誤らせる
ことである。
「離間」は指導者と国民、指導官と部下の間に心理的な猜疑、離心を生じさせ、自軍が乗じる
隙をつくることである。
「心理防護」は士気低下の予防、督励、カウンセリング、治療などによって心理防御線を築
き、敵の心理戦活動を抑制・排除することである。
人民解放軍は、部隊の訓練に心理戦を取り入れるばかりでなく、心理戦専用の装備も開発して
いる。
【法律戦】
法律戦は、自軍の武力行使と作戦行動の合法性を確保し、敵の違法性を暴き出し、第三国の干
渉を阻止する活動をいう。
それにより、軍事的には自軍を「主動」、敵を「受動」の立場に置くことを目的とする。
法律戦は法律上の勝利を目指すのではなく、あくまで軍事作戦の補助手段と位置づけられる。
近年、国際法の遵守という消極的な法律戦ばかりでなく、独自の国際法解釈やそれに基づく国
内法の制定など、自ら先手を打って中国に有利なルールを作るという積極的な法律戦への志向
が顕著になっている。
この三戦を中国側は「砲煙の上がらない戦争」と呼んでいる。
これがエドワード・ルトワックの指摘する自滅する中国の一因なんだけれどね。
そしてこの三戦を、尖閣諸島をめぐる中国の行動に照らし合わせ、小川氏は論じている。
「中国は、尖閣海域に盛んに海警局所属の公船や航空機を出し、ときに領海や領空を侵犯し、
日本に圧力を加えている。同時に国際社会に対して心理的な影響を及ぼしている。
日本を威嚇し、国民の不安や猜疑心を募らせ、日本国内の世論の分断を図っているともいえる
だろう。心理戦である。
日本が抗議すると、今度は中国外務省の報道官が「尖閣諸島は中国の領土である。日本側の抗
議は受け入れられない」と述べ、これが中国でも日本でも大々的に報道される。
中国国内では、尖閣諸島を不法に占拠しているのは日本だ、という認識が強固になってくる
し、日本国内にも中国は一歩も引かないというイメージが広がっていく。輿論戦だ。
領海侵犯する公船や領空侵犯する海警局航空機も、わざわざ白く塗装し、非武装であることを
明示している。
非武装なら攻撃されないことを見越して、中国は平和的に領有権などを主張しているのだとア
ピールしているわけで、これも輿論戦の一面である。
中国が公船を盛んに送り出すのは、一九八二年に採択された国連海洋法条約を逆手にとっての
動き、つまり法律戦だ。
同条約は「国が所有または運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるもの」に軍艦
なみの法外法権を与えている(三条、三二条、九六条、二三六条など)。
この種の船舶を「公船」といい、領海内の無害通航に関する規則に違反しても、沿岸国は退去
を要求することしかできない。
もちろん、日本の「領海等における外国船舶の航行に関する法律」も同条約に基づいているか
ら、海上保安庁の巡視船艇は退去を呼びかけるしかできない」(本書)
一九九七年十一月に署名され、二〇〇〇年六月に発効した日中漁業協定は、北緯二七度以南の
東シナ海の日本の排他的経済水域について棚上げにしている。
日本はこの海域を排他的経済水域(EEZ)漁業法適用特例対象海域にしているから、中国漁船は
操業でき、それを監視すると称して中国当局の船舶がうろつくことになる。
中国側は、日本の法律がザル法だということも見抜いているのである、と日本側の問題点も指
摘する。これらを小川氏はまとめているが、次の通り。
尖閣諸島をめぐる中国側の動きは、尖閣諸島の領有権が中国にあることを世界と自国民にアピ
ール(輿論戦)し、言動に法的根拠を持たせるために防空識別圏を設定(法律戦)し、無人攻撃機
の試験飛行によって日本とアジア諸国に無言の圧力を加える(心理戦)ことを実戦していると。
これらの中国側の戦略に対して、日本側に戦略的姿勢が存在していない点が気がかりでならな
い、日本としても、輿論戦、法律戦、心理戦についての取り組みを構築して、肉薄してくる中
国の圧力を跳ね返さないことには、尖閣諸島周辺を含む南西諸島の安全を、日本に有利な形で
安定させるのは難しいだろう、とも指摘している。
最近では、尖閣諸島に対しての中国の圧力は軽減されているが、国際情勢の変化に伴って、再
度圧力を加えてくる可能性も否定できないので、日本人は受身になりすぎないで、主体性を持
ってしっかりと戦略を練ろ、ということだろう。
その日本側の戦略の無さに関しては、様々な要因があると思われるが、「海洋資源大国」を自
覚していないこともその一因であり、そこにも疑問を投げかけ「海洋資源大国」としてのあり
方を指摘している。
地政学には、「マーレ・ノストロ」(Mare Nostro)というイタリア語の言葉があり、mareは
「海」、nostroは「われわれ」という意味で、もともとは「われらの海」という言葉。
海を国境とする国の多くが、この「マーレ・ノストロ」という考え方を推進して自国の利益を図
っている。
だが、日本は島国であり海洋国家であるにもかかわらず、海洋地政学が根付かなかった。
隣国と排他的経済水域や大陸棚で接する場所では、最終的には互いに協議のうえで勢力範囲が
決まる。
そのとき自国の領域をギリギリまで広く解釈して海底資源を確保し、その領域を自国の安全保
障上の緩衝地帯にしていこうという発想は、まともな国家であれば持つのだが、日本にはその
発想は無く、むしろ、中国のほうが日本近海でそれを実行していると指摘する。
「つまり日本は、やるべきことをやらずに、中国の海洋権益拡大に立腹してきたにすぎない。
明確な海洋戦略を持たずに、「沖ノ鳥島は、中国のいう岩ではなく、日本の島である」などと
主張しても限界がある。
日本は、海洋国家としての戦略を打ち出し、海洋資源大国として振る舞っていかなければなら
ないだろう。
日本近海を中国の艦船がウロウロするのを牽制するためにも、まずは海洋資源大国としての自
覚を持たなければならない」(本書)
ちなみに、日本の領海および排他的経済水域(EEZ)は446.9万平方キロメートルで第六位とな
っている。
アメリカの通商会議委員長(現在は知らない)ピーター・ナヴァロがその著『米中もし戦わば 戦争
の地政学』の中で、
「中国の「対艦弾道ミサイル」の登場は、アジアにおける力の均衡全体をひっくり返しかねな
い衝撃的な出来事である」
「中国の対艦弾道ミサイルの画期的な点は、地表へと落下しながら、空母や駆逐艦などの大海
原の中の比較的小さな目標を速やかにロックオンすることができるとともに、
非常に正確に目標を追尾しながら回避行動まで取れることである。中国の指導者らがこの画期
的新兵器を公然と「空母キラー」と呼ぶのも理由のないことではない」
「中国の軍事力のこの非対称性こそがまさに、航行中の空母を弾道ミサイルで攻撃する能力と
いった技術の進歩と相俟って、自国の防衛をアメリカの空母艦隊に依存しているアジア諸国や
ペンタゴンを慌てさせているのである」
と書いているが、中国の指導者が公然と「空母キラー」と呼び、アメリカ側が危機感を抱いて
いる、その対艦弾道ミサイル(DF21/東風21)について西氏は冷静に分析している。

DF21 / 東風21 アメリカ国防総省コード:CSS-5
DF21は中国初の移動式固体燃料型の弾道ミサイルで、核弾頭型(射程二一五〇キロメートル)は
一九八五年に試射に成功し、九〇年代に実戦配備されたもの。
通常弾頭型(射程一七五〇キロメートル)のDF21Cは二〇〇二年に初めて試射に成功し、〇九年
十月一日の中華人民共和国建国六〇周年記念パレードで公開された。
このDF21Cは、アメリカが一九八三年から八八年まで旧西ドイツに配備していたパーシング
Ⅱ(射程一七七〇キロメートル)をモデルに開発されたとみられる。
パーシングⅡは飛行の最終段階において、飛行方向の地形レーダー画像をデジタル地図と照合
し、方向を修正する能力を備えており、地上の固定目標に対する平均誤差半径(半数必中
界:CEP)は五〇メートルだった。そのDF21Cを対艦弾道ミサイルとしてさらに改良したのが
DF21Dであるという。
ナヴァロの指摘は、アメリカ国防総省の報告書でも指摘されており(本書ではその2011年版を
引用されている)、そのアメリカで宣伝されているのを西氏は分かりやすくまとめている。
①西太平洋に展開する米空母に向けて、一五〇〇キロメートル以上の彼方から弾道ミサイルを
発射可能で、
②通常の弾道ミサイルとは異なり、対艦弾道ミサイルは飛行中も空母を追尾することができ、
音速の五倍以上のスピードで落下する弾頭を常に空母に向けて軌道修正し、
③核弾頭を使うことなく空母を撃沈したり、無力化することができる、
「これが事実ならば、アメリカにとって大変な脅威である。一五〇〇キロメートルといえば、
中国内陸部から沖縄東方海上に届く距離である。
このエリア内にアメリカの空母機動部隊が入れなくなり、中国の対艦弾道ミサイルの射程圏外
でしか行動できなくなるとすれば、現有の空母艦載機の戦闘行動半径では役に立たず、アメリ
カが日本列島周辺で行使できる軍事力のかなりの部分が殺がれることになりかねない」(本書)
だが西氏は、攻撃する中国側、防御するアメリカ側の能力を冷静に同時に眺め、弾道ミサイル
による移動目標への攻撃には、まず原理的に難しい点があり、対抗手段もないわけではないと
して、索敵、追尾、終末誘導と機動、ミサイル防衛の四点について独自に整理している。
(以下要約して載せる)
①索敵: 対艦弾道ミサイルの発射には、米空母を発見し、位置と進路を特定する必要がある。
偵察衛星については、中国も一定レベルで配備している。
しかし、米空母の位置と進路の特定には高高度飛行船や長距離無人偵察機も必要となる。
それが中国には備わっていない。
中国が索敵手段を備えたとしても、米軍は冷戦中のように偽のレーダー反射波などを用いて空
母を隠そうとするかもしれない。
それだけでも、対艦弾道ミサイルの発射は容易ではなくなる。
②追尾: 飛翔中の弾道ミサイルの弾頭を、空母が移動する予測位置に向けて落下させるには、
中国は対艦弾道ミサイルの誘導に必要なシステム(衛星)を米軍の攻撃から防衛できなければな
らない。
アメリカには、一九八五年に実証実験を終えた空中発射衛星攻撃ミサイルという選択肢もあ
る。
実験では、高度一万一六〇〇メートルを飛行中のF15戦闘機から、重さ一一八〇キログラムの
三段式ミサイルを発射し、高度五五五キロメートルの軌道上にある衛星を破壊した。
アメリカは、この衛星攻撃ミサイルを空母艦載機に搭載し、弾道ミサイルが発射されたら、誘
導に使われる中国の衛星を破壊することができる。
目下のところ、中国側には対抗手段はない。
③終末誘導と機動: 対艦弾道ミサイルの弾頭は大気圏に再突入してから、移動する空母を追尾
していかなければならないが、以下のような技術的な課題が指摘されている。
それは、弾道ミサイルが大気圏に再突入した段階で、弾頭の周りの空気が過熱されて電離現象
が発生、弾頭のレーダーで目標を探すことも、地上からの指令を受信することも、一時的に不
可能になるという問題である。
これについては、アメリカはパーシングⅡに関して解決していたし、中国も有人宇宙飛行の経
験から問題解決の方法を手にしている可能性は否定できない。
④ミサイル防衛: 中国の対艦弾道ミサイルは、米空母を護衛するイージス艦によるミサイル防
衛システムという強固な防壁を突破しなければならない。
横須賀を母港とする原子力空母「ジョージ・ワシントン」の場合、護衛するイージス艦は九隻に
のぼる。
このうちミサイル防衛能力を備えているのは半数ほどだが、これを見ても明らかなように、
米空母と機動部隊は陸上の施設と比べても最も濃密かつ強固なミサイル防衛システムに守られ
ているといってよい。
これをかいくぐって空母を直撃するのは至難のわざと言わざるを得ない。
それでも中国の対艦弾道ミサイル能力が向上し、ミサイル防衛システムの強化が必要になった
場合、アメリカは多弾頭型迎撃ミサイルの開発凍結を解除するという選択肢も残している。
アメリカがこの多弾頭型迎撃ミサイルを配備する可能性を中国とロシアに伝えれば、
中国に対艦弾道ミサイルを大量に配備することを断念させられる可能性が出てくる。
以上を見ても、米空母が対艦弾道ミサイルの攻撃目標として相応しいかどうか、明らかだろ
う。そうした問題点が語られず、対艦弾道ミサイルの脅威のみが独り歩きしているのは、
アメリカ政府の情報戦略が奏功している結果かもしれない、として見事に分析している。
「中国が対艦弾道ミサイルを有効だと思い込むほどに、中国は費用対効果がよくない兵器シス
テムに莫大な資金と技術者を投入するという陥穽にはまっていく。
これは、中国がアメリカにとって本当に脅威となる軍事力を備えることを防ぎ、また遅らせる
ための高度な戦略といってよい」(本書)
その他にも、中国の「接近阻止・領域拒否(A2AD)」戦略に対して、アメリカは空軍と海軍を一
体的に運用する統合エアシーバトル構想を進めたが、本書の中で西氏は、その一連の流れを説
明し、そこから新たに浮上してきた「オフショア・コントロール」戦略も説明されている。
「エアシーバトル」は、中国本土への報復攻撃を認めるものであり、
「オフショア・コントロール」は、海上封鎖と経済封鎖によって中国の攻撃に対抗しようとする
もの。
「オフショア・コントロール」は、T・X・ハンメス元海兵隊大佐が提案したものであり、米中間
の戦争は年単位の長期戦となるとの認識から出発している。
そこでは、米軍は中国上空に進攻するのではなくて、オフショア(沖合)の第一列島線(日本、台
湾、フィリピン)で中国軍の太平洋進出を阻止し、東シナ海と南シナ海でも自由に行動させない
「日米版A2AD」戦略をとる。
これによって中国のA2AD戦力はほとんどが無力化され、中国は米海軍の攻撃型原潜と日本列
島を守る自衛隊の双方に対抗する戦力が必要となる、と指摘している。
「停戦に持ち込む論理まで準備している点で、オフショア・コントロール戦略は統合エアシー
バトル構想と異なっており、戦略的に優れたものだ。
中国と隣接している日本こそ、こうした戦略的な構想を提案すべきだろう」(本書)
日本国内では、中国の国防費が大幅な伸びを示すたびに、中国脅威論が声高に叫ばれることが
多く、小川氏の言葉に直せば「木を見て森を見ず」の議論なってしまっているが、
本書では、多角的に中国はどんな状態にあるのかなどを冷静に見きわめている。
それは台湾に対してでも同様であり、中国が武力解放するのではないか、という声も多く聞こ
えてくるが、中国には台湾に大規模な軍事攻撃をかけて占領するほどの軍事力は備わっていな
い。しかも、この中国の軍事的オプションに対しては、在日米軍のうち沖縄の海兵隊が抑止力
を発揮している、と小川氏は指摘し、さらに後述して具体的に説明されている。
ここでは省くが(これは『日米同盟のリアリズム』の第Ⅲ部でも説明している)。
確かに中国は国防費を増やし続け軍事力の近代化を進めてきているが、その間、アメリカや
日本、台湾が何もしていなかったといえば、そんなことはなく、それぞれ軍事力の近代化を
着実に進めてきており、とくにアメリカは中国との差をいっそう広げている、とも指摘してい
る。これはエドワード・ルトワックも指摘していたことでもある。
両国の口先だけのタカ派たちに問いたい。軍事力だけで相手を制圧できるのか。
罵詈雑言や虚勢で問題は解決するのか。
主張すべきはする、譲れない点は譲らないが、それでも険悪にならず、自国の国益を追求でき
る道を探る。それしかないではないか。
幼児的な発想では自国の安全と繁栄を実現できないことに思いを馳せるべきなのである。
『中国の戦争力』小川 和久
本書は、中国の戦争力を分析しているのだが、日本側の問題点にも言及し、浮き彫りにしてい
る。
自らを客観視できない日本人の短所は、とりわけ安全保障問題に現れている。
集団自衛権の問題、普天間問題をはじめとする在日米軍基地の問題、オスプレイ問題などを語
るときも、日本は戦略的な根拠地をアメリカに提供しているという大前提に立ち、
そこから国益に沿った議論を進めなければならない。
とりわけメディアには、客観的、論理的、科学的な報道を心がけてほしいものだ。
『中国の戦争力』小川 和久
日本より自滅しているのは中国なんだけどね。
第1章 輿論戦・心理戦・法律戦 日本は中国の「三戦」の渦中にいる
第2章 尖閣諸島、南シナ海に広がる中国の海洋戦略
第3章 中国はアメリカと戦争できるレベルか
第4章 中国を凌駕するアメリカの新兵器・新戦術
第5章 変貌するアメリカの戦略構想と日本・アジア同盟国


