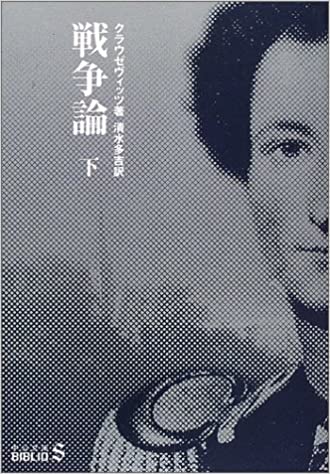

『戦争論』の中には、二人のクラウゼヴィッツが矛盾を抱えたまま同時に存在している。
一人は「観念主義者のクラウゼヴィッツ」であり、もう一人は「現実主義者のクラウゼヴィッ
ツ」である。そのことがより一層『戦争論』を読み難くしている要因でもある。
クラウゼヴィッツが『戦争論』を書くきっかけとなったのは、一八〇六年にプロイセンがナポ
レオンに惨敗したからだといわれている。クラウゼヴィッツはナポレオンによってヨーロッパ
にもたらされた戦争の新たな時代の幕開けを、直接目撃した人物でもあった。ナポレオンの指
揮下で展開された戦争は、規模の大きさや恐ろしから、クラウゼヴィッツにとって「観念上の
戦争」、暴力と破壊が妨げられることのない純粋な形の戦争であり、ほぼ完璧な戦争として映
った。クラウゼヴィッツはこれを「絶対戦争」と呼んだ。フランス革命とナポレオンの狙いは
「敵国の転覆」や、相手の政治体制を根こそぎ取り払うことにあり、政治的な狙いには限界が
なかったように、ナポレオンの軍事的な狙いにも限界はなかった。その暴力も無制限に見え
た。そしてそこから導出されたのが、「敵を打倒することが戦争の目標であり、敵の戦闘力を
壊滅させることがその手段である」などの概念であり、戦闘において敵戦力の殲滅を強調し、
「主戦」の重要性を説いた「観念主義者のクラウゼヴィッツ」である。
そのクラウゼヴィッツには誰もが知っている有名なテーゼがある。それは「戦争とは、異なる
手段をもってする政治の延長にほかならない」というものであり、戦争は「政治の道具」にす
ぎないと捉えたことである。この政治によって戦争の狙いが決定されるという考えは、最晩年
の一八二七年から一八三〇年に主張または導入したものである。さらにクラウゼヴィッツは、
自身の戦争の理論を「絶対戦争」だけでなく、多くの限定された形での現象も含んでいると歴
史の中に発見した。これらに気がついた晩年のクラウゼヴィッツを「現実主義者のクラウゼヴ
ィッツ」と呼ぶ。
この『戦争論』の中での表裏一体の絶対矛盾的自己同一のクラウゼヴィッツを明確に的確に指
摘し、鋭く浮かび上がらせたのが英国レディング大学教授のベアトリス・ホイザーである。
専門は戦略論や欧州の安全保障体制などであり、多言語を操るマルチリンガルでもある。
生まれはタイでドイツ系イギリス人だ。
以下はそのホイザーが著した『Reading Clausewitz』(2002)、邦題は『クラウゼヴィッツの
「正しい読み方」』(2017)に依って、クラウゼヴィッツの生涯やその二面性、そしてそれが
『戦争論』にどのような形で影響を及ぼしたのか、またはクラウゼヴィッツ以降の時代にどの
ように『戦争論』が読まれ、解釈をされていったのかを覗いてみたい。

ベアトリス・ホイザー(1961-)と『Reading Clausewitz』(2002)とその邦訳(2017)
皆さんもご承知の通り『戦争論』は未完であるが、全八部から構成されている。
以下は中公文庫版から列挙したものである。
第一部 戦争の性質について 第二部 戦争の理論について 第三部 戦略一般について
第四部 戦闘 第五部 戦闘力 第六部 防御
第七部 攻撃(草案) 第八部 作戦計画(草案)
先程も触れた通り、クラウゼヴィッツに『戦争論』の草稿を書かせる一番のきっかけとなった
のはナポレオンが及ぼした衝撃である。そしてクラウゼヴィッツは、初期の第一部の初稿と第
二部から第六部までの中で主に「絶対戦争」、つまり大規模な決戦において敵を完全に打倒し
て、国家を崩壊させ、領土を占領し、抵抗する意志をくじくような戦争を想定しながら書いて
いた。これが「観念主義者のクラウゼヴィッツ」。しかし、一八二七年以降(ホイザーはこの年
を「大覚醒」と呼んでいる)第七部、第八部、そして第一部を書き直し(第七部と第八部は他の
部より「絶対戦争」に偏ってなかったみたいだが)、クラウゼヴィッツは自身の戦争の理論を
「絶対戦争」だけではなく、歴史の中に発見した、多くの限定された形での現象をも含んでい
るものとして広義に捉えるようになる。「戦争は政治目的のための道具である」とするクラウ
ゼヴィッツの代名詞が展開されているのはこの部分からである。これが「現実主義者のクラウ
ゼヴィッツ」。しかし、クラウゼヴィッツが書き直して唯一満足していたのは第一部だけであ
った。それは一八二九年に友人に送った手紙に見て取ることができるという。
かなりややこしいのだが、まとめると次のようになる。
クラウゼヴィッツは異なる二つの教えを残した。一方は、一八〇四年と一八〇八年の草稿や
『皇太子殿下御進講録』、その他の歴史分析や、『戦争論』の第二部から第八部までのもので
あり、これらはすべて一八二七年以前に書かれた「観念主義者のクラウゼヴィッツ」によるも
の。もう一方は『戦争論』の第七部と第八部、そして修正された第一部であり、これらは一八
二七年から一八三〇年の間に書かれた「現実主義者のクラウゼヴィッツ」によるもの。
しかし、不幸なことに、この二つの考え方についての混乱は、書き直しを行おうとしていたに
もかかわらず、後者の原稿の中にまだ残され、主に敵軍の打倒の必要性を論じた、いくつもの
「観念主義的」な例が混在してしまっている。
そしてもう一つ、ここにややこしい話を付け加えよう。クラウゼヴィッツは一八二七年の大覚
醒の後でも、「絶対戦争」を戦争の本質に近いものであると考えており(クラウゼヴィッツは真
相:Begriffという言葉を使っている)、政治、摩擦、状況などにより、特定の戦争は「絶対戦
争」にはならないと考えていた。
そこで気になるのは、クラウゼヴィッツの考えは、いつ、どのようにして変わったのかという
ことである。ホイザーは二人の歴史家であるハンス・デルブリュックとエイベルハート・ケッ
セルの説明を賛辞を贈りながら紹介している。なかでもケッセルの指摘が参考になるが、クラ
ウゼヴィッツがナポレオン戦争終結の一二年後の一八二七年に、これまで自分の分析があまり
にも「絶対戦争」に偏っており、その分析がすべての戦争には適用できないことを悟ったとい
う。ではなぜその他のほとんどの戦争は「絶対戦争」のようにはならないのか。その答えは、
クラウゼヴィッツの士官学校時代の同僚であるルール・フォン・リリエンシュターン(一七八〇
−一八四七)を見れば容易に理解できるという。リリエンシュターンは幹部向けの手引書を書い
ていたがクラウゼヴィッツもそれを読んでいた。さらにリリエンシュターンは、「戦争とは国
家が内的条件と外的条件を考慮しつつ定めた、政治目的の実現のために遂行される」というこ
とも書いていた。ホイザーによれば、リリエンシュターンと同じようにクラウゼヴィッツも戦
争は政治のための一つの手段であり、政治が制限を設けなければ戦争は持てる力をすべて発揮
してしまうことになると気がついたという。この「政治」に眼目を置いた新しい考え方は、一
八二七年の一二月の友人に宛てた手紙にも記されている。
そしてクラウゼヴィッツは、それまでに書いた『戦争論』の原稿を書き直す必要があることに
も気がついた。戦争は政治の働きによるものであり、それまでクラウゼヴィッツが述べていた
ほぼすべての中で、この重要な要素を考慮に入れていなかったからであった。そこでクラウゼ
ヴィッツはすでにこの考えが反映されている第七部と第八部を書き直し、その他の六部分も書
き直し始めた。ところが悲劇的なことに生前すべてを書き直すことはできなかった。先程触れ
たように、書き直して満足していたのは第一部だけであった。ここまでが『戦争論』の前後関
係やその内容を少し踏まえた上での近視眼的に捉えた様相である。そしてここでクラウゼヴィ
ッツの生涯が気になってくる。以下は簡潔にクラウゼヴィッツの生涯を追ってみたい。そのよ
うにクラウゼヴィッツの生涯を総体的に眺めると『戦争論』の違った一面も見えてくる。

カール・フォン・クラウゼヴィッツ(1780-1831)
クラウゼヴィッツの人生は二つの非常に異なる時代にまたがっており、その精神性においても
特徴が明確に違っていた。クラウゼヴィッツは旧体制時代(アンシャン・レジーム)に生まれ、
そこでは兵士や芸術家やその他の職種の人々が、多くのヨーロッパの宮廷で認められて雇われ
ようと努力しており、そこでの共通言語と政治思想はフランス製のものであった。
そして人々が忠誠を誓うことを求められていた対象は君主であり、同業者組合(ギルド)であ
り、都市国家であった。ところがクラウゼヴィッツ自身の動きはそのものは、旧体制のコスモ
ポリタンの香りを残した、新しい時代精神によって作り上げられたものであった。その精神は
「一君主義」の代わりにナショナリズム(民族主義)が台頭してできあがったものであった。
この矛盾性も『戦争論』に表出していると感じられなくもない。
カール・フィリップ・ゴトリブ・フォン・クラウゼヴィッツは一七八〇年六月一日に、プロイ
センが統治していたマグデブルグの中の小さなサクソニーの街、ブルグに住む大家族に生まれ
ている。父方の祖先は北部シレジア地方(現ポーランドのシュレジエン地方)の出身であった
が、貴族の出自かどうかは疑われていたという。なぜなら、祖父はハレ大学で神学部の教授で
あったが、貴族であることを示す「フォン(von)」という称号を使っていなかったからだとい
う。その称号を復活させたがったのはクラウゼヴィッツの父であり、プロイセン王国のフリー
ドリヒ大王に再び「フォン」を使わせてくれるよう嘆願している。王はクラウゼヴィッツの父
を自身の連隊に雇っており、そこで士官としてそこそこの経歴を残している。
そんな父は「七年戦争」(一七五六−六三年)の軍士官であり、自身の職に誇りを持っていた。
クラウゼヴィッツは両親の家で軍の士官しか見たことがなく、クラウゼヴィッツ自身も「プロ
イセン軍の中で育った」と記しているという。そんなクラウゼヴィッツも一二歳になると兵士
となり、一七九三年から一七九四年の対フランス戦(ライン戦役)に参加している。クラウゼヴ
ィッツは青年時代から何もわからない状態で戦争を目撃し、その全体的な印象は心の中に一生
残ることになったとホイザーは洞察している。ちなみに、クラウゼヴィッツは三人兄弟であっ
たが、自身を含めて二人は陸軍士官になっており、共に将軍の地位まで上り詰めている。
二一歳になったクラウゼヴィッツは、ベルリンの陸軍士官学校に入学する。
そしてここでは「生涯の師」と仰ぐゲルハルト・ヨハン・ダーヴィト・フォン・シャルンホル
スト(一七五五−一八一三年)将軍と出会っている。シャルンホルストは陸軍士官学校で校長を
務めていたが、シャルンホルストはクラウゼヴィッツにフランス社会で起きた革命と新しいフ
ランスの戦争方法とのつながりに注目するように諭したという。シャルンホルストとその弟子
たちはプロイセンの軍事体制の大改革を推進していたこともあって、上官や王族は彼らに反感
を感じていた。もちろん、クラウゼヴィッツもその改革精神を共有していた。

ゲルハルト・ヨハン・ダーヴィト・フォン・シャルンホルスト(1755−1813)
そんなクラウゼヴィッツが最初に戦場で対峙した「生涯の敵」はフランスであった。
最初の戦争の時からフランスの戦争方法を恐れ、ナポレオンの下でヨーロッパ征服に乗り出し
たフランスに対して、強烈な憎しみを抱いていたという。一八〇三年には好戦的な論文を書
き、その中で、フランスと古代ローマの帝政・独裁時代を比較している。さらにクラウゼヴィ
ッツは、当時のあらゆるステレオタイプを使って、フランス人に対する非難を行っていた。
対してドイツ人の方は、知的かつ道徳的な意識の高いギリシャ人であるとの認識であった。
クラウゼヴィッツは死の直前まで反仏感情や嫌仏感情を吐露しており、『戦争論』を完成させ
ようとしていた一八三〇年にはフランスで起きた「七月革命」に対して、「フランスでは最初
の革命から新たな革命が生まれ、それが平和を乱すことになる」と恐れていた。
クラウゼヴィッツはフランス革命の平等主義的な理念を嫌悪していたが、特に極端な反動主義
者というわけではなく、むしろプロイセンには寡頭政治体制が最適であると考えていた。
クラウゼヴィッツの「フランス嫌悪感情」や「フランス恐怖症」は、妻であるマリー・フォ
ン・ブリュール、後のフラウ・フォン・クラウゼヴィッツからも来ている。マリーの母親はイ
ギリス人であったが、この母親もナポレオンに対する憎しみによって動かされていたという。
ベルリン社交界の名士の一人であった人物からは、この親子に対して「フランスへの憎しみと
いう政治的情熱の中で生きていた」と評されている。ブリュール家は極めて高い階層の貴族で
あり、クラウゼヴィッツは一八〇三年、二三歳の時にマリーと出会っているが、社会的な地位
があまりにも違っていたため、結婚するのに七年間も待たなければならなかった。
妻マリーの母方の家族は英国のロシア領事を務め、イギリスに対して尊敬の念を抱いており、
クラウゼヴィッツのフランスに対する憎しみにも一致していた。マリーは教養も高く、死の直
前までクラウゼヴィッツの考えに広く影響を与えたと考えられている。

マリー・フォン・ブリュール、後のフラウ・フォン・クラウゼヴィッツ(1779-1836)
軍人としてのクラウゼヴィッツはどうかといえば、一八〇六年の「アウエルシュタットの戦
い」に参戦しており、ここでクラウゼヴィッツはナポレオン式の戦い方を初体験することにな
った。プロイセンは敗北し、ナポレオンはベルリンに入城、隣国のザクセン王国と講和条約を
結び、ここからロシアとの戦いへと移っていった。クラウゼヴィッツはプロイセンのアウグス
トゥス親王の副官を務めていたが、この敗戦後にフランスまで連行され、捕虜として紳士的な
扱いを受けた生活を送っている。しかし、この体験がクラウゼヴィッツのフランスに対する憎
しみをさらに強めてしまった。
本国に送還された後のクラウゼヴィッツは、一八一〇年から一一年にかけて「小規模戦争」と
いう講義をプロイセン陸軍大学で担当している。この戦い方は、スペインがナポレオンに対す
る抵抗を「ゲリラ」という名前で呼んだことで後に有名になる。さらにこの頃のクラウゼヴィ
ッツは、皇太子(後のプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム四世)に講義を授けることにな
り、この準備のために戦争に関する多くの問題について考えをまとめる。これが『戦争論』な
どの著作を著すための基礎となったという。戦争そのものを理論化し始めていった。
しかし、クラウゼヴィッツの反仏的な感情は、プロイセンにおいては出世の妨げとしかなら
ず、一八一二年四月にはフリードリヒ・ヴィルヘルム三世がフランスに対してあまりにも恭順
的であったことに腹を立て、プロイセン軍を辞めて過激な建白書を書いたという。ちなみに、
同時代の伯爵や大使、軍人などのクラウゼヴィッツの評価は決して芳しいものではなく、「不
快な人物」「恥ずかしくなるような事件を起こす」「痛烈な皮肉を言うことこの上ないため
に、多くの敵を作った」「冷酷で冷ややかな態度」などと蔑まされていた。ホイザーは「クラ
ウゼヴィッツは気難しい性格を持っていたようであり、ベルリンの派手やかな社交界や仲間の
士官たちと一緒にいるよりも、図書館にこもっているほうが性に合っていたようだ」と総括し
ている。
ナポレオン衰退の時期にジョミニはフランス軍を去ってロシア軍に入り、ライプチヒなどの戦
いにロシア軍将軍として、またツァーリの軍事顧問として連合軍司令部で勤務したが、クラウ
ゼヴィッツもロシア語を一切話せなかったにもかかわらず、ロシア皇帝アレクサンドル一世に
対してロシア軍につくことを申し出て、ロシア軍士官として働いている。
一八一二年九月七日にはナポレオンの戦いの中でも最も凄惨であるとされる「ボルジノの戦
い」を直接観察し、これが後にナポレオンのロシア侵攻全体についての著作を記すことにつな
がる。さらにその年には、交渉役の一人として人生で唯一の外交の舞台を経験し、ロシアとプ
ロイセンの和平協定である「タウロッゲン協定」につながった和平交渉に臨んだ。これは後に
対仏大同盟となり、「解放戦争」(一八一三−一四年)の基盤となった。
そしてクラウゼヴィッツはロシア帝国軍の士官として、「グロースゲルシェンの戦い」と「バ
ウツェンの戦い」(共に一八一三年)に参加もしている。
ナポレオンが一八一四年に敗れるが、ヴィルヘルム三世はプロイセンがフランスにあからさま
に反旗を翻す前にプロイセンを離れ、他国の軍隊でフランスと戦ったクラウゼヴィッツのよう
な士官たちを快く思っておらず、疑いの目で見ていた。クラウゼヴィッツが帰国してプロイセ
ンの参謀本部に大佐として復帰できたのは、一八一五年になってからであった。将官の地位に
付いたクラウゼヴィッツだったが、その後、陸軍大学の校長に任命され、その仕事はほとんど
事務仕事であり、教えることはたまにあるだけで、あとの時間は研究と執筆に費やされること
になった。クラウゼヴィッツはこの扱いに対して侮辱的だと感じていた。しかし、このおかげ
で『戦争論』を執筆する時間が与えられ、この作業は一八一八年から一八三〇年まで続けられ
ることになった。ところが原稿を見直す前の一八三〇年に、ロシアの占領者に対するポーラン
ドの暴動に対処するために現地での勤務を命ぜられる。飛び火してくる可能性があった。
クラウゼヴィッツは反乱鎮圧が終わった後に、当時は東プロイセンの一部であったポーゼン(現
在のポーランドポズナン)に到着し、その後ブレスラウ(現在のヴロツワフ)に第二の師であるア
ウグスト・フォン・グナイゼナウと一緒に翌年まで留まった。しかし、不運なことにクラウゼ
ヴィッツとグナイゼナウの二人ともコレラに罹ってしまい、一八三一年一一月一六日にブレス
ラウの地で、突然その生涯を閉じることになった。
そして気になるのは『戦争論』であるが、このクラウゼヴィッツの未完の原稿は、一八三二年
から三四年にかけて、『戦争および戦争指導に関するカール・フォン・クラウゼヴィッツ将軍
の遺稿』としてマリーによって手を加えられない形で出版され、そのうちの第一巻から第三巻
までが『戦争論』となった。

『戦争論』タイトルページ(1832)
クラウゼヴィッツは誰の思想を基に壮大な体系を構築していったのか。
ドイツのクラウゼヴィッツ専門家であるシェリングなんかはヘーゲルとの共通点を指摘し、ソ
連の研究者たちはクラウゼヴィッツがヘーゲルに影響を受けたと確信するまでに至っている。
さらには、クラウゼヴィッツの「絶対戦争」というアイディアが、ヘーゲルの「絶対精神」か
らヒントを得たものだとレーニンは思い込んでいたふしがあるという。
ただ、ホイザーの分析によれば、クラウゼヴィッツがヘーゲルから影響を受けたということは
明確ではないと指摘している。そしてホイザーが示しているは、クラウぜヴィッツはマキャヴ
ェリから影響を受けているということである。クラウゼヴィッツはマキャヴェリを読んだだけ
ではなく、哲学者フィヒテとの手紙のやりとりの中で、マキャヴェリについて集中的に議論を
していたことまで突き止めている。クラウゼヴィッツはマキャヴェリの『君主論』『ディスコ
ルシ』『戦術論』を読んでおり、戦争を論じるにあたって、マキャヴェリの道徳観念から離れ
た議論を行うやり方を踏襲しているという。クラウゼヴィッツは「マキャベリほど政治家必読
の書はない」などと書いている。ちなみに「絶対戦争」という概念は、マキャベリについて論
じたフィヒテによって最初に記されたものだという。フィヒテはこの言葉を、フランス革命で
も見られたような「国民の領主に対する戦い」と同じ意味で使っていた。
一口に、誰々の影響を受けているということを明確に示すことは不可能であるが、クラウぜヴ
ィッツは「生涯の師」と仰いだシャルンホルストからモンテスキュー『法の精神』を読むよう
にも勧められている。ホイザーによれば、クラウゼヴィッツは『法の精神』を『戦争論』を書
く上でかなり意識していたとも指摘している。
シャルンホルストは、過去の戦争のデータから特定の原則が導き出させると信じていたみたい
だが、自分の学生たちに対して、戦争における心理的・政治的な要素や、部隊における士気、
卓越した指揮官などの重要性に注目するよう促してもいた。それらの教えは『戦争論』の中で
展開され、シャルンホルストからの影響も窺える。しかし、クラウゼヴィッツに限らず、他の
同僚も同じように論を展開し、また強調しているという。
では、同時代人やその同僚たちとクラウゼヴィッツの違いは何か。ホイザーによれば、それは
同僚たちとは違って、クラウゼヴィッツはかなり高いレベルでそれらの抽象化を行っているこ
とだという。そして、クラウゼヴィッツが詳細に研究した、一三〇例にも及ぶ歴史上の戦闘の
実例から導き出した結論に由来するものであり、同世代の作者と違って、クラウゼヴィッツは
歴史を通じて戦略と戦術の本質の変化を最も強調していたと説明している。
クラウゼヴィッツの同時代の人間や、その前後の戦略家たちは、行動についての厳格なルール
を設定するような傾向を持っていたが、クラウゼヴィッツ自身は戦争の理論、このテーマにつ
いて熟考したものをつくりだそうとしており、特定の状況で従うべきドクトリンのようなもの
を導き出すことは想定していなかったという。もちろん、クラウゼヴィッツも単純化されたル
ールを打ち立てる寸前のところまで行っているが(覚え書で見れる)、それでもクラウゼヴィッ
ツは、当時の他のいかなる戦略家よりも単純化した機械的なルールから逃れようとしており、
クラウゼヴィッツの目的は、読者に対して「戦いのための道具」を与えるというよりも、「戦
争をどのように考えればいいのか」を教えるところにあった。これはプロイセンの君主となる
ヴィルヘルム四世を念頭に置いたものであり、クラウゼヴィッツはこの生徒に対して、自分が
何かを決断しなければならない際にその「答え」を教えるのではなく、どのような心構えをす
べきなのかを教えようとしていた、とホイザーは指摘する。したがって多くの意味から、クラ
ウゼヴィッツは軍で実務を経験してきた人間たちがほとんど関心を持っていなかった問題を取
り上げ、それは主に「戦争の本質」についての哲学的考察を行っており、これは単純で覚えや
すいような行動原則のようなものには移し替えづらいものでもあった。
『戦争論』が後の時代にどのように読まれ、またどのような影響を及ぼしたのか。
以下は簡潔に記したい。『戦争論』の初版は一八三二年から一八三四年にかけて一五〇〇部刷
られたが、売り切れたわけではなかった。そしてその初版が出版されると、本家のドイツ語圏
では議論を巻き起こすことになった。中には肯定的な意見も少数ながら存在したが、クラウゼ
ヴィッツを賞賛する者たちでさえ、その難解な内容に批判的な態度を示していた。ドイツ語圏
の出身ではないが、ジョミニはクラウゼヴィッツの深厚な学識は肯定的に評価しつつも、その
筆運びは簡潔を旨とする学術的討議にとって、多少行き過ぎである、と書いている。
ところが、同時代人から不評だった『戦争論』は、プロイセンの軍教育において確固たる地位
を確立することになる。それに貢献したのが、ヘルムート・フォン・グラーフ・モルトケ(大モ
ルトケ)であった。この大モルトケは、自分がプロイセン軍の参謀総長になった時に、自国の士
官たちに優れた教育を受けられるようにすることだけではなく、『戦争論』がカリキュラムに
加えられるように軍部に強く働きかけたという。さらには、フランス人の記者に向かって、ク
ラウゼヴィッツは聖書、ホメロスなどに続くほどの多大なる衝撃を自分の人生に与えた、と語
っていた。その結果として、プロイセン軍の士官教育のための教科書となり、これによって一
八六四年、一八六六年、一八七〇年から七一年(デンマーク戦争、普墺戦争、普仏戦争)の勝利
はクラウゼヴィッツの様々な影響によって成し遂げられたと宣伝されていった。
『戦争論』を読んだのは、軍の士官だけではなく、マルクスやエンゲルたちもクラウゼヴィッ
ツを読んでおり、渋々ながらもその価値を認めていた。そして、マルクスとエンゲルスを受け
継ぐ形で、レーニンもクラウゼヴィッツを大いに崇拝した。
フランス語圏では、クラウゼヴィッツの名が浸透するまでに時間が掛かっている。
その理由は、クラウゼヴィッツの難解な文章も挙げられるが、ナポレオンの戦い方についての
最大の理解者であるとされたジョミニの影響が大きかったという。ジョミニはプロイセン以外
では一九世紀末になるまで、クラウゼヴィッツよりもはるかに大きな影響力を持っていた。
フランスやアメリカでは、ナポレオンの戦略の解説者として最も読まれた人物であり続けた。
マハンも陸軍出身の父親から影響を受け、その一人であることは有名な話だ。
最初のフランス語の完訳版は、一八四九年から五一年にかけて出版され、これはベルギー人の
手によるものであったという。フランスの職業訓練的な国防大学にも、クラウゼヴィッツの影
響は広がっていったが、フランスの戦略家のほとんどは、クラウゼヴィッツに疑念を持ったま
まであったという。その後『戦争論』の第二版が、一八八六年から八七年にかけて出版される
が、フランス人のクラウゼヴィッツへの情熱は長続きせず、フランスではその現象はエリート
の中だけに存在するものであり続けた。
英語圏でのクラウゼヴィッツを最初に大々的に賞賛したのは、のちに英陸軍少将となるジョ
ン・ミッチェルだという。ミッチェルは模範的な形で解説したみたいだが、それでもイギリス
士官学校は軍の幹部たちの影響もあって、一九世紀の末までジョミニの影響に染まっていた。
『戦争論』は一八三七年にイギリスで最初の英訳版が出版されている。間接的ではあったが、
イギリスでクラウゼヴィッツが有名になったのは、オックスフォード大学の戦争史の教授であ
ったスペンサー・ウィルキンソンの著作の中で興味をもって書かれたことによる。
そしてボーア戦争の直後にクラウゼヴィッツへの興味が盛り上がり、それが第一次世界大戦前
の十年ほどの間にピークを迎える。ところがクラウゼヴィッツは第一次世界大戦から、当時非
常によく読まれたバジル・リデルハートの著作のおかげで、「忌むべき人物」となってしま
う。リデルハートはその戦争における無駄な戦略を生み出した人物としてクラウゼヴィッツを
非難した。リデルハートの次に有名なフラーなんかは当初はクラウゼヴィッツを批判的に捉え
ていたが、第二次世界大戦後には掌を返して肯定的な評価に変わっている。以後の時代のクラ
ウぜヴィッツ叩きの伝統を受け継いだのは軍事作家のジョン・キーガンであり、熱心な崇拝者
になったのはレーガン政権にアドバイスしていたコリン・グレイであった。
アメリカでのクラウゼヴィッツの評価もイギリスと似たような状況だったという。
ウェストポイントの米陸軍士官学校では、ジョミニはナポレオンの戦略を教えるための主要教
科書となっていた。南北戦争の将軍たちは一同にジョミニ・ナポレオン式の主戦を必死に追求
していた。リーに関しては明確に指摘されているが、グラントもそうだろう。
アメリカでは一八七三年に、イギリス版の『戦争論』が発売されたが、生粋の米国版は一九四
三年のジョルズによるものまで待たなければならなかった。九〇年代に書かれた著作ではある
がジョージ・ケナンは、ジョミニやクラウゼヴィッツなどの著作は手に入ったし、米軍の様々
な大学でずっと以前から研究されてきたに違いないが、ワシントンの政治支配層に、それらの
著作が何らかの有意義な感銘を与えたとはいえまい、と書いていたことを思い出す。
そんなアメリカの戦略家たちがクラウゼヴィッツの考えに本格的に向き合ったのは、一九五〇
年後半から一九六〇年前半のことであり、米軍の中でクラウゼヴィッツが完全に見直されるき
っかけとなったのが、ベトナム戦争であった。そして『戦争論』は、一九七六年に海軍大学、
一九七八年には空軍大学、一九八一年には陸軍大学で必読文献となっていった。
クラウゼヴィッツの「主戦」を強調した部分はとりわけ人気となり、一九八〇年代のアメリカ
の戦略や、九〇年から九一年にかけての湾岸戦争の遂行にも影響を及ぼしたといわれている。
そのアメリカの「新クラウゼヴィッツ主義者」に触発され、冷戦期のフランスではクラウゼヴ
ィッツの盛り上がりが復活したという。
ロシアで最初にクラウゼヴィッツが有名になったのは、トルストイ『戦争と平和』の中で地味
な人物として登場したことによる。将軍の中にもクラウゼヴィッツを信奉したものも存在し、
『戦争論』をロシア語ではなくフランス語に翻訳している。それでもレーニンが亡命先のスイ
スから知識として持ち帰るまで、ロシアではほんとど広まらなかった。
そのレーニンは共産党の幹部にクラウゼヴィッツを読むように強く勧めている。
『戦争論』のロシア語版の第二版と第三版は、一九三二年と四一年にそれぞれ出版されてお
り、第二版のまえがきでは、クラウゼヴィッツの弁証法的なアプローチが賞賛されていたとい
う。ソ連の著名な戦略家たちもクラウゼヴィッツの著作を賞賛していた。
ところが、一九四五年以降にスターリンがクラウゼヴィッツを研究対象とすることを禁止し、
ソ連の軍関係者の間ではクラウゼヴィッツに対する情熱は一時的に冷めてしまった。
中国で『戦争論』の最初の翻訳が出版されたのは一九一〇年であったが、これは日本語版をさ
らに中国語に翻訳したものであった。一九三七年までには二つの中国語版が出版されており、
毛沢東はこの版を手にとって研究していた可能性が高いという。
その毛沢東は我々の想像以上に、『戦争論』について相当な知識を有しており、その思想にク
ラウゼヴィッツの影響を確認できる。日本が中国大陸の大部分を占領していた一九三八年に毛
沢東は『戦争論』を読み、政治勉強会を開催して、主に第一編を集中的に研究していたとい
う。晩年の毛沢東は、中国に最初に訪問した西ドイツの首相に向かってクラウゼヴィッツは天
才であると賞賛している。クラウゼヴィッツは毛沢東の戦争観に深い影響を及ぼした。
『戦争論』の中国語版は、一九三七年から七六年までの間に本土と、それから台湾で六回も版
を重ねているという。
第一次世界大戦が勃発する数十年前の西洋社会では、軍に対する過大評価や、戦争をロマンチ
ックに見る傾向が広まっていた。このような雰囲気の中で軍事作家たちが活躍し、それによっ
てクラウゼヴィッツへの関心が国際的に高まった、とホイザーは指摘する。
ご覧の通り『戦争論』は次第に軍学校の基本書となり、広く引用されるようになっていた。
戦間期の第三帝国では、ナチスがクラウゼヴィッツの著作に大きく触発されて、自分たちの政
策の根拠としたり、プロイセンの軍事的な精神を受け継いでいるために、そこから選択的に言
葉を引用しているという。ヒトラー自身もクラウゼヴィッツに言及することが多かった。
しかし、同じ枢軸国であったイタリアでは、クラウゼヴィッツの関心はほとんど高まっていな
い。ところが、イタリアと同様に枢軸国であった日本では、クラウゼヴィッツの著作は長年に
わたって知られていた。日本軍の幹部たちは一八八五年から九五年にかけて日本を訪れて軍を
教育したドイツ人の士官たちを通じてクラウゼヴィッツの存在を知っており、同時期に『戦争
論』はフランス語版から日本語版に翻訳されている。ただ全文が翻訳されて出版されたのは、
日露戦争直前の一九〇三年であった。明治三六年には森鴎外が訳しているのは有名な話だ。
日本語版は二〇世紀前半に版を重ね、新たなクラウゼヴィッツへの関心の高まりは一九六〇年
代半ばに訪れ(清水多吉訳はこの頃だ)、アメリカの戦略文書の影響が大きかった。
さらに日本ではビジネスに応用することに大きな関心を向けていた。
そして第二次世界大戦以後からは、イスラエルやオーストラリアに至る西側諸国のほとんどで
広まっていった。このトレンドを推進したのは、安全保障問題について論じた民間人によるも
のであった。
そんな二一世紀の今日では世界の隅々にまで知れ渡り、現在では戦略・軍事思想を学ぶ上での
必読文献として崇められ、さらには古典的名著としての地位を獲得しているクラウゼヴィッツ
『戦争論』。しかし、その抽象度の高さ故に誤読や、それに伴っての誤用の連続の歴史でもあ
った。その状況は今もさして変わらないだろう。それらを明確に浮き彫りにしているのが本書
の真骨頂である。以下からはどのように誤解・誤用されてきたのかその一部を取り上げたい。
しかし、長くなってしまったので、簡潔に触れるだけになる。
クラウゼヴィッツだけが戦いにおける政治の重要性に気づいたわけではないのだが(しかもそれ
を強調したのは晩年になってからであった)、戦争を「政治の道具(ツール)の一つ」と主張した
ことはクラウゼヴィッツの代名詞になった。その当初はクラウゼヴィッツが説明した、政治や
社会と戦争の結びつきについては注目されなかったが、エンゲルスのような共産主義者たち
は、この政治と戦争との結びつきに目を開かされている。先述の通りレーニンはスイスに亡命
中に『戦争論』を読み込んでいたのだが、レーニンもこの部分に目が留まり、一九一七年のモ
スクワでの演説で「戦争は他の手段による政治の継続である」と述べている。同じく共産主義
者である毛沢東もクラウゼヴィッツから「戦争を政治から片時も切り離して考えてはならな
い」という教訓を得ている。ただホイザーも指摘しているが、『戦争論』にはクラウゼヴィッ
ツ自身の「政治的な理想」というものがほとんど描かれていないし、『戦争論』で完全に欠如
しているのが、倫理や道徳などについての考えである。
クラウゼヴィッツが唱えたとされ、巷で吹聴されている有名なテーゼがある。
それは、戦争の理論は「国民」「軍隊」「政府」という三つの要素の相互作用を考慮に入れな
ければならないというものである。これが「三位一体」と呼ばれているもの。
しかし、これは「二次的な三位一体」として主張されたものであり、「一次的な三位一体」で
ある、①盲目的自然衝動と見なし得る増悪・敵愾心といった本来的激烈性、②戦争を自由な精
神活動たらしめる蓋然性・偶然性といった賭けの要素、③戦争を完全な悟性の所産たらしめる
政治的道具としての第二次的性質、に付随する要素としてクラウゼヴィッツは説明している。
毛沢東はこの「二次的な三位一体」の考えに感銘を受けて、その関係性を研究するようにな
り、クラウゼヴィッツに欠けていた大衆の動員について考えを補っているという。
アメリカのベトナム戦争での失敗をクラウゼヴィッツの観点から分析したハリー・サマーズも
「一次的な三位一体」ではなく、「二次的な三位一体」の方を強調しているという。
クラウゼヴィッツは「最高司令官を内閣の一員として加え、それによって軍の重要な行動の決
断の際に内閣を参加させること」などを主張していたのだが(文民政府が軍の最高指揮官のやり
方を決定すべきだと)、一八三五年に出版された『戦争論』の第二版ではブリュール伯爵がその
他の修正とともに、「最高司令官を内閣の一員として、主要な評議や決議に参加させることで
ある」としてしまった。このブリュール伯爵による修正は、プロイセンをはじめとするドイツ
諸侯で当時盛り上がりつつあった軍国主義的な文化が反映されているという。しかもこの書き
換えが判明したのは、第二次世界大戦後のことであったという。軍の最高指揮官と文民政府と
の関係に関する議論は、百年間にわたってドイツ国内の政治の議論で活発に取り上げられてい
た。あのビスマルクでさえ、軍服を着ていなければ多くの場所で無視されていたという。
そのビスマルクはクラウゼヴィッツを一度も読んだことがなく、何も知らなかったことを恥じ
ていた。ところが軍の参謀長を務めたモルトケは読み込んでいた。これも先に触れた。
しかし、モルトケが読んでいたのは第二版だけであり、本来の意図とは正反対の政軍関係を学
んでいた。さらにモルトケのクラウゼヴィッツ解釈は「観念主義者のクラウゼヴィッツ」のも
のに近かったが、ビスマルクは普仏戦争の時に王と軍の指揮官たちの間の会合には呼ばれなく
なってしまっていた。それ以前までは軍の会議に参加していたのだが、モルトケにとって非常
に目障りな存在であったという。ビスマルクはモルトケに対して、継続的に情報が受け取れる
ように要求しているほどであった。そして、モルトケの影響力は時を経て増すことになり、そ
れが戦争の遂行において敵国の社会まで狙った、より包括的なものへと変化してきたという。
シュリーフェンが作成した有名な「シュリーフェン・プラン」があるが、これも政治的な機関
に相談なく進めたものであり、壊滅的な結果を生み出した。
第一次世界大戦の終盤に、実質的に政治と軍の両方のリーダーシップを担うことになったエー
リヒ・ルーデンドルフがいる。一九三五年に『総力戦』を著しているが、そちらの方で著名
だ。そのルーデンドルフもクラウゼヴィッツに言及した文章も残しているが、『総力戦』の中
ではクラウゼヴィッツの考え方から完全に背を向けた主張を展開した。
一九世紀後半の欧州における軍国主義的な世界では、非軍人の政治家が軍を支配すべきである
といった考え方は受け容れられなかった。
その他にも「観念主義者のクラウゼヴィッツ」が主張した「主戦」(その効果は敵の兵士を殺害
するよりも敵の勇気を挫く点にあった)「重心」「兵力の集中」などの用語や概念が伝えるアイ
ディアが二〇世紀に広まり(クラウゼヴィッツだけではなくジョミニなども主張していたが)、
クラウゼヴィッツへの直接的な言及もなく使われるようになっていった。
「敵国家の意志を武力によって変える」という考えは、初期のエアパワーの信奉者たちの目標
の一つともなり、これは結果として第二次世界大戦における航空戦の実践における一つの指針
ともなった。イタリアのドゥーエ将軍やイギリスのトレンチャード卿が含まれる。
二〇世紀末にはクラウゼヴィッツの「意志の戦い」という考えも広く浸透し、戦略を考える際
の大前提となっていった。「摩擦」という概念もそうである(清水訳の中公文庫版『戦争論』で
は「障害」と訳されている)。ちなみに、エドワード・ルトワックも主著『戦略論』の中で、こ
の摩擦という概念は、クラウゼヴィッツ『戦争論』に由来すると説明している箇所がある。
そしてクラウゼヴィッツは、攻撃よりも防御の優位性を主張していたのだが(攻撃性が含まれる
防御)、プロイセンではクラウゼヴィッツの防御優勢の考え方はあまり歓迎されなかった(驚く
ことにモルトケはクラウゼヴィッツの考えに近かったという)。しかし、これはドイツの軍事関
係者に限らず、一九世紀末当時の全ヨーロッパの政治文化がそのような状況になっていた。
フランスのギルベール大尉なんかは、『戦争論』の書評の中で「観念主義者のクラウゼヴィッ
ツ」の部分を強調し、殲滅戦やナポレオン式の大規模戦、敵に対する飽くなき追撃などを書い
た箇所を取り上げた。クラウゼヴィッツはひたすら攻撃を好んでいると勘違いされることが多
かった。くどいようだが、これはクラウゼヴィッツが「観念主義者」だった頃に、戦闘におい
て敵戦力の殲滅を強調していたからであった。クラウゼヴィッツが「主戦」と呼んだもの(後に
他者は決戦や殲滅戦と表現)の重要性を説いた文章は、一九世紀後半から二〇世紀初頭にかけて
最も人気が出た。第一次世界大戦の大虐殺の後に、リデルハートはクラウゼヴィッツの殲滅戦
の予言者として批判した。これらの事は気になった箇所を諸々に拾い上げたものだが、本書で
は理路截然とした文脈の中で詳細に説明されている。多くの者は「観念主義者のクラウゼヴィ
ッツ」だけを見て、それを誤用して失敗したケースが多いという事であり、大変危険だという
事だ。「観念主義者のクラウゼヴィッツ」の理論は間違っているとは一概にはいえないが、そ
れは「現実主義者のクラウゼヴィッツ」と表裏一体の関係にあるので、正解ではないというこ
とだけは確実にいえることだ。『戦争論』は矛盾した両面を同時に捉えることが重要なのだ。
そのもう一方の「現実主義者のクラウゼヴィッツ」の記述の方に目が留まり、さらにそれを乗
り越えるかのように巧みに援用した人物が二人いる。それは海洋戦略に応用したジュリアン・
コーベットであり、ゲリラ戦に応用した毛沢東である。
以前の記事の中でコーベットの『海洋戦略の諸原則』は紹介したが、コーベットは海軍同士の
戦闘というのは常に必要であるわけではなく、常に決戦を必要とするわけでもない。「戦力の
集中」というのは時代遅れのスローガンであるなどと主張し、「制海権」とは「主戦における
勝利」という意味ではなく、自らが選んだ時に行動できる能力のことを意味していると主張し
た。詳細には説明しないが、コーベットの海軍戦略というものは、経済や外交、陸上部隊な
ど、海軍以外の大きな枠組みの中で考えることの重要性を説き、そのためには、敵を徹底的に
打倒するような殲滅戦は必ずしも必要ではなく、むしろ場合によっては「敵が海を使おうとす
るのを阻止する」という重要な狙いにとっては障害になるほどだと論じた。
コーベットはクラウゼヴィッツの攻撃と防御というアイディアに関しても、それをポジティブ
とネガティブという言葉に置き換えることも提案した。さらにコーベットが活眼なのは、クラ
ウゼヴィッツの「限定戦争」と「絶対戦争」についての新しい考え方が示されているのは『戦
争論』の第八編のみであるということを理解していたことだ。その『戦争論』の知的欠如に関
しても、クラウゼヴィッツが念頭に置いていたのは、大陸国家どうしの戦争である、というこ
となども見抜いていた。
クラウゼヴィッツは、一八一〇年から一一年にかけて「小規模戦争」という講義をプロイセン
陸軍大学で担当し、この戦い方は、スペインがナポレオンに対する抵抗を「ゲリラ」という名
前で呼んだことで後に有名になる、と先程書いた。かなりややこしい話だが、クラウゼヴィッ
ツは「国民の武装」「国民戦争」「小規模戦争」という概念を時に混同した形で使っている。
実際のところ、クラウゼヴィッツの時代には「国民戦争」(ぼくは「国民の武装」「小規模戦
争」も含まれていると捉えている)がいくつか発生していた。一七九三年にはフランスで「三〇
万人募兵令」があり、「ヴァンデの反乱」(革命派が市民を大量に動員)があり、一八〇八年に
はナポレオンに対するスペイン人におけるゲリラが始まっていた。それに一八〇九年の「チロ
ルの反乱」と一八一二年のフランスの大陸軍によるロシア領内への侵攻の際のパルチザンによ
る攻撃もあり、これはクラウゼヴィッツも直接目撃している。
そして、クラウゼヴィッツは「国民戦争」という言葉を使い続けていたが、「ゲリラ」の使用
の仕方について、極めて詳細に語り、その特徴のようなものを五つ示している。
①戦争が国内で遂行されること、②戦争がたった一回の決戦で決定されないこと、③戦場がか
なりの大きさの空間にわたって広がりをもつものであること、④国民の性格がこの種の戦争に
合致していること、⑤山岳、森林、沼沢、あるいは農民の性質によって国土が断絶し、通過に
困難である場所が多いこと、などである。
二〇世紀のゲリラ戦の思想家たちの多くは、クラウゼヴィッツの著作からインスピレーション
を受けている。T・E・ロレンスもその中に含まれる。しかし、国民戦争についての考え方を新
たな高みまで導いたのは、共産主義系のクラウゼヴィッツの継承者たちであった。レーニンも
そうだったのだが、さらにその上をいっていたのが毛沢東であった。毛沢東にとって、あらゆ
る革命戦争では人民を動員すべきであることになり、「大衆を動員出来た場合にだけ戦争を遂
行できる」という。ところが毛沢東は、クラウゼヴィッツと同じように動員された大衆を正規
軍の補完的な存在として見ており、この点からクラウゼヴィッツのアイディアをやや発展させ
つつ、戦いを「動員された人民の抵抗」という段階から、正規軍のものへと徐々にシフトさせ
ているという。中国出身の学者によれば、毛沢東の考えていた「ゲリラ」という言葉の意味
は、民兵やパルチザン部隊、もしく正規軍の中の一部である特殊部隊が、人民全体と連携しな
がら、特定の指示を受けず、もしくは特定の前線を維持せず、敵の小規模な部隊に対して戦う
ような戦争の形であったと指摘する。
毛沢東の教えは、上述したクラウゼヴィッツの五つの要点と多くの共通点を持っていた。
そしてクラウゼヴィッツの思想が、その毛沢東を通して共産主義の思想家に伝わっていった。
毛沢東の思想をラテンアメリカに紹介し、『ゲリラ戦争』を著したチェ・ゲバラもそうであっ
た。同書の中ではクラウゼヴィッツに言及されている。ただ、クラウゼヴィッツ自身の「国民
戦争」や「小規模戦争」などの分析は参考にしていない。北ベトナムの共産主義の思想家であ
るチュオン・チンは『人民戦争は勝利する』の中で、クラウゼヴィッツ式の戦争と政治の密接
なつながりについて繰り返し言及しているという。
ホイザーは「核時代のクラウゼヴィッツ」とする章を設けて、この時代の西洋の戦略家が、
「絶対戦争」という概念のおかげでクラウゼヴィッツが、「大惨事の予言者」や「全面核戦争
による第三次世界大戦という滅亡的な未来を見通した歴史家」として論じられたことや、クラ
ウゼヴィッツが否定的な意味で引用されることも多くなったことなどを詳らかにしている。
さらにクラウゼヴィッツの「エスカレーション」という概念によって、核時代において極めて
興味深いアイディアを提供した存在となったことや(クラウゼヴィッツはエスカレーションの可
能性を考慮すべきであると強調していた)、限定戦争と西洋の新クラウゼヴィッツ主義者の一連
の流れ、ベトナム戦争に対するクラウゼヴィッツ主義者たちからの批判などを緻密に追ってい
る。トマス・シェリングはクラウゼヴィッツの「戦争を商取引としてとらえる方法」を、ゲー
ム理論を使って発展させたと喝破している。
そして最後には、クラウゼヴィッツの問題点や現在に生きる我々はクラウゼヴィッツから何
を、どのように学べば良いのかが論じられている。私たちがクラウゼヴィッツを読む上で頭に
入れておくべきなのは、クラウゼヴィッツが『戦争論』を書いた目的は、あるゆる戦争に応用
できるようなドクトリンを作り上げることではなく、むしろ戦争をさらに批判的に考察したり
「研究」するところにあったということだ。ホイザーが導き出しように、クラウゼヴィッツは
一八二七年の時点で、暴力、軍事的天才、軍隊の士気・精神力、重心への戦力集中、そして敵
の打倒を狙うことなどが含まれた初期の理論は、「政治的な狙い」という最も決定的な要素が
欠けているために不完全であることを悟った。そして一八二七年から三〇年にかけて『戦争
論』を書き直した際に導入した要素が、この「政治的な狙い」であった、ということも常に意
識しなければならない。
クラウゼヴィッツはニュートンとは違って「普遍的な原則」というようなものを生み出すこと
はできなかったが、それでもクラウゼヴィッツはその原則の一部となるような、数多くの「変
数」を正確に特定した。ホイザーはそれを七つにまとめている。これはクラウゼヴィッツを正
しく読み解く上でとても参考になるので要約して載せたい。
①暴力がその中心にあり、そのエスカレーションを抑えることに難しさがあるという点
②軍事的な狙いを形成する上での政治目的の重要性
③良好な政軍関係の必要性や、いかなる目的であっても国民からの支持が必要である点
④非常に複雑な状況を直感的に理解できる意思決定者(軍の最高司令官)の才能
⑤軍隊と国民の士気や、両者が障害に打ち勝つ決意(意志)
⑥重心への戦力集中の必要性
⑦どこにでも常に摩擦があるという認識

若き日のクラウゼヴィッツ
「戦争の真の本質は不変であるが・・・」という文脈の後にクラウゼヴィッツは「戦争はカメ
レオンである」と矛盾した考えを表明している。これがクラウゼヴィッツの本質を表している
と感じる。さらにクラウゼヴィッツはとても大切なことを理解し、主張してもいる。それは、
相闘う両者を分析している文脈の中で、「人間とはもともと不完全な存在なのであって、常に
絶対的完全性とはほど遠いところにある」ということを書いていることだ。
この「人間とはもともと不完全な存在である」と見抜いたクラウゼヴィッツにもっと着目すべ
きである。
『戦争論』を援用するにしても否定するにしても、ベアトリス・ホイザーの『クラウゼヴィッ
ツの「正しい読み方」』を一緒に読まなければならない。
なぜなら、あなたが捉えているクラウゼヴィッツはその一面にすぎないからだ。
「観念主義者」「現実主義者」としてのクラウゼヴィッツの両面を鮮やかに浮かび上がらせた
ホイザー女史は傑物だ。
クラウゼヴィッツはそのシステムの中のすべての「変数」を発見したわけではないし、それら
を探究しようとしたわけでもない。しかしわれわれにあらゆる戦いの本質や、ある戦いの事例
の特殊性を決定づける「関数」と「変数」を見つけるように教えることによって、クラウゼヴ
ィッツはわれわれが戦争をどのように考えるべきかを示したのであり、こうすることによって
実質的に他の変数を見つけやすくしてくれたのだ。そしてこれこそが、彼の最も偉大な功績で
あり、自身でもそのように主張している。
この「戦争をどのように考えるべきか」を説くという目的に関していえば、クラウゼヴィッツ
はそれ以前やそれ以降の、どの戦略家よりも優れているのである。
『クラウゼヴィッツの「正しい読み方」』ベアトリス・ホイザー
武を『説文』には「止戈(しか)を武となす」、すなわち武力を抑制するのが武であるという。
この説は、卜文・金文の字形が、戈(ほこ)をかかげて進む形に作ることからいえば、明らかに
誤りであるが、しかしこのような解釈のうちに、戦争否定を願う人類の希望が、託されている
ように思う。兵法書の『孫子』は、その巻頭に「兵は国の大事、死生の地、存亡の道なり。察
せざるべからざるなり」と述べている。兵は斤(まさかり)をふりあげる字であるが、戒は戈を
両手でさしあげている形である。武力は本来防衛的に用いるべきものである。
戰(戦)は、單(単)と戈とに従う字である。單は円形あるいは楕円形の盾で、上に飾りをつけてい
る。未開社会では、盾に羽の飾りなどをつけることが多い。
『漢字』白川静




