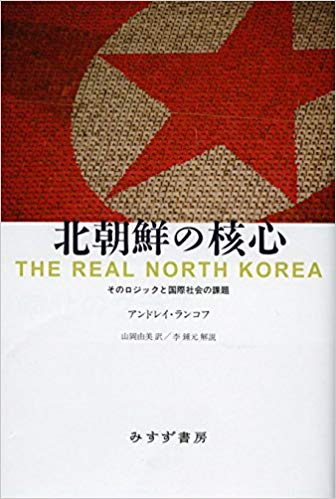
しかし平壌では依然として、金一族の政権が主人の座にとどまっている。
政治の物理学的法則を無視するこの国は、まさに四面楚歌の立場におかれている。
資源が乏しく、経済も瀕死の状態だ。
それでもなんとか生きながらえて、大国の足並みの乱れを最大限利用している。
理性を欠く国にできることではない。指導層は自分たちが何をしているか、実際には完全に分
かっているのだ。
頭がおかしいわけでもイデオロギーの虜になっているわけでもなく、むしろ冷徹な計算のでき
る有能な人々である。
あるいは、現代世界で最も非常なマキャべェリ思想の実践者といえるかもしれない。
『北朝鮮の核心――そのロジックと国際社会の課題』アンドレイ・ランコフ
著者のアンドレイ・ランコフは、1963年のレーニングラード(現サンクトペテルブルク)生まれ
で、レーニングラード国立大学在学中の1984年に語学研修生として金日成総合大学に留学し、
1年ほど平壌でも暮らしている。なのでかは知らないが、著者は北朝鮮への対応について、
「圧力も譲歩も、核のない豊かな北朝鮮という目標を早期に達成する役には立たない」
「タカ派がどういうおうと、武力行使をほのめかすのはよい方法ではない。
倫理面からいえば武力行使は侵略行為以外の何ものでもないが、それを脇においても得策とは
いえない」
「外交で譲歩したり、軍事的圧力や経済的圧力を加えたりしても、北朝鮮の政権に影響を及ぼ
すことは難しい」
「短中期的な政策として筆頭にあげられるのは、核開発計画に対し事実上の承認を与えるとい
うものだろう」
「六者協議が機能するよう維持していくことが望ましい」
と主張している。(本書は英米で2013年に出版され、その後韓国でも出版、2015年に日本で出
版されたもの)
しかし、トランプが大統領に就任してから、シリア攻撃、大規模爆風爆弾(MOAB)によるアフ
ガニスタン爆撃、カール・ビンソン打撃群の展開などの(中国の裏切りも)、武力行使をほのめか
したチキンゲームが功を奏して(経済制裁も)、シンガポールで会談したのは明らかだろう。

アンドレイ・ランコフ
韓国・国民大学教授。レニングラード(現サンクトペテルブルク)生まれ。
金日成総合大学に留学した経験もある。
本書は、「北朝鮮の行動の内部にある論理をみていく。この論理は北朝鮮社会の特異性によっ
て形づくられ、その特異性には長い歴史がある。この国はどんな経緯で国際社会の問題児とな
るにいたったのか、また、問題視されるようなことを北朝鮮の指導層が好きこのんで行ってい
る、というよりそうせざるをえなかったのはなぜなのか」を解き明かすために著している。
ソ連の従属国としてつくられた北朝鮮だが(韓国の左翼系知識人は自生的な民衆革命という見方
をしている)、ほどなくして民族的スターリン主義政権に変わり、外部から来るどんな課題にも
この体制を維持しながら取り組み、一九九〇年代前半まで大きな変化を経験せずにきた。
その数十年は金一族の政権が成長し成熟を遂げた時代、敵対的な環境のなかで生き残り、環境
を操るすべを体得していった時代だった、と著者は指摘する。
「金日成時代の公式思想をみると、そこにはレーニン主義と毛沢東主義が奇妙な形で混在して
いること、そしてやや極端な民族主義と儒教的伝統が濃厚に残っていることが分かる」(本書)
一九六〇年代はじめごろは、毛沢東主義の理想は金日成が建設したいと考えていた朝鮮像にピ
タリと合っていたが、毛沢東の起こした凄惨な文化大革命に対して、金日成はブレジネフとの
会談のなかで、「とほうもない愚行」だと述べている。
中ソ両国に対する自律性を揺るぎないものにするため、北朝鮮の政権は独自の思想をつくりだ
す必要に迫られた。
それが「主体思想(チュチェ)」と呼ばれるもので、現在の韓国の大統領である文在寅にも影響
を与えている、といわれているもの。
「主体」という概念が最初に登場したのは、一九五五年に金日成が行った演説のなかでであ
り、はじめのうちはさほど重視されていなかったが、六〇年代半ばになると国家の公式思想に
仕立て直された。
短い期間、北朝鮮の国内外における宣伝活動の一環として、「主体思想」を世界に広める運動
が積極的に進められた。そのほとんどが第三世界で行われたという。
『朝鮮新報』によれば、最近では沖縄で「チュチェ思想新春セミナー」が開催されている。
「金日成はひとりで体制の礎を築いた。
「永生不滅の主体思想」の創始者、朝鮮五千年の歴史における最も偉大な人物なのである。
政権が維持してきた世界観のなかでも重要な要素が「民族的独我論」、つまり朝鮮というもの
が世界全体をかたちづくるうえで決定的重要性をもつという思考である。
この考え方によれば朝鮮五千年の歴史における最も偉大な人物は、人類の歴史における最も偉
大な人物となる」(本書)
金日成時代のメディアは、北朝鮮を人民の楽団と形容してもいて、全人民が、このうえない幸
福をいつも享受している国である、としていた。
「金日成(キム・イルソン)が北朝鮮に築いた体制は、経済が持続不可能という致命的な欠陥を抱
えていた。ソ連と中国からの定期的な援助がなければ機能しないシステムだった。
そのため冷戦に突如として終止符が打たれると、「民族主義の特徴を備えた金日成のスターリ
ン主義」も息絶え、北朝鮮は重大な危機に蝕まれるにいたった」(本書)
一九九四年以後の北朝鮮は、金日成がつくり治めてきた国とは大きく異なるとして、
「金正日(キム・ジョンイル)の時代」と著者は呼んでいる。
個人的にだが、本書で最も参考になったのは、韓国との関係を詳述している箇所であり、今話
題の文在寅にも繋がってくる。その所が気になって本書を手にした、という側面もある。
北朝鮮は、六〇年代までは、統一問題に関しては消極的な姿勢だったが、韓国で四月革命が発
生し、その姿勢を考え直す契機となった。
四月革命によって李承晩政権が崩壊し民主的な政権が成立したが、軍の介入により一年もたた
ないうちに倒された。
これは韓国で革命が発生する可能性を示すものだと金日成は考えた。
さらには、六〇年代と七〇年代の韓国では民衆による反体制運動が幾度も爆発的な高まりをみ
せ、ソウルでは大規模なデモが起きていた。
このことも北朝鮮政府の楽観的な見方を助長したという。
それに加え、ソ連の北朝鮮への影響力が低下したことも、統一への希望を燃え立たせた、
と著者は指摘する。
そして、金日成は一九六〇年代後半に、統一のための試みを再び実行に移した。
これが非常に熾烈な活動だったため、「第二の朝鮮戦争」と呼ばれることもあるという。
「おおまかな説明になるが、北朝鮮の統一計画は「統一戦線」戦略を使ったものといえるだろ
う。共産主義運動においてはすでに定着した方法である。北朝鮮は南に広範な左翼反体制運動
をつくることを考えた。
これをいくつかの秘密組織(というよりも主体思想信奉者)が指導・操作し、まずは親米軍事政権
を転覆する。次に親北朝鮮の中核組織が運動内の他の勢力を切り捨て、必要ならば打倒し、真
の共産主義革命を推進する、という計画である」(本書)
その中でも、一番大きな成功を収めたのが「統一革命党」で、「創党準備委員会」なるものも
結成されるが、一度も勢力を得ることなく、韓国当局に解体されている。
主要メンバーの一部は処刑され、他の幹部は懲役刑に服したという。
北朝鮮に同調的な地下組織をつくり、有望な若者を取り込む試みはその後も繰り返された。
二〇一三年には極左的な政党の統合進歩党に所属する李石基(イ・ソッキ)議員が、北朝鮮に同調
的な地下組織のリーダー格だったことが明るみに出ている。
しかし、北朝鮮の指導部は、一九七〇年代半ばに、韓国での革命は当分期待できないという結
論にいたった。
「朝鮮戦争の休戦から一九八〇年ごろまで、韓国の政治とイデオロギーは右翼がほぼ独占して
いた。韓国の右翼は強烈な反共主義に凝り固まっていた。アメリカとの長期的な同盟関係を外
交政策の基軸に据え、資本主義・自由主義政権のもとで南北統一を遠い将来における第一の目標
に掲げていた」(本書)
だがしかし、「三八六世代」が台頭してくるとその状況は一変する。
「三八六世代」というのは、六〇年代に生まれて八〇年代に大学へ通い、九〇年代には三〇代
になっていたことからあだ名がついた。
「三八六世代」は自国の成し遂げた経済成長にあまり価値を認めず、その程度のことは優秀な
韓国人ならできて当然と考えていた。軍事政権を嫌悪し、市場経済には懐疑の目を向けてい
た。
「飢えを経験した親たちが成長と繁栄と安全を見ていたその場所に、彼らは格差と不正と
大国への従属を見ていた。
この世代、というより政治に積極的に関わろうとするその一部は、権威主義に強く反発すると
ともに反米的で、民族主義を掲げつつも左翼的だ」(本書)
「民族主義と強烈な左翼思想、そして韓国の軍事政権に対する深い嫌悪感。
こうした潮流は当初、三八六世代の少なからぬ人たちを親北朝鮮派にした。
一九八〇年代はじめごろには、韓国の知識人のあいだでマルクスやレーニンの著作が熱心に読
まれた。一部には主体思想に関する論文を読んだり、北朝鮮の出版物を回し読みしたり、
北から流れてくるラジオ放送の内容を書き取って回覧したりと、さらに上を行く人たちもい
た。もっとラディカルな反体制派にいたっては、北朝鮮が朝鮮らしさをそのままに保っている
社会正義の国であるとか、なぜかは分からないが民主主義の国であると考えていた。
一九八七年の民主化運動では左翼の活動家(平壌の政権に思い入れをもつ人は少数派だった)が
大きな役割を果たし、何十年ものあいだ韓国に君臨していた権威主義に終止符を打った」
(本書)
今でも自称「進歩派知識人」たちは、韓国の軍事独裁政権が犯した人権侵害には容赦ない非難
を浴びせるが、北朝鮮の政権が抱える欠点には目に余るほど寛大だと、著者も指摘している。
この世代より少し上だが文在寅も同じようなものだろう。
それでも、主体思想の楽園に対する初期のころのような熱は、九〇年代半ばには冷めていたと
いう。
「三八六世代の世界観において、統一は大きな位置を占めていた。
一九八〇年代後半に学生運動のラディカリズムが最高潮に達したころ、声の大きな少数派は、
当時北朝鮮で採用されていた制度に幾分か似た、ある種のレーニン型社会主義に基づいて南北
は統一すべきだと考えていた。
しかし多数派はそこまでラディカルではなく、南北がそれぞれの特徴を維持しつつ、社会や政
治の分野で妥協を探っていくという連邦制を主張していた」(本書)
一九九七年の暮れの大統領選挙で、半生を反体制活動と民主化運動に捧げ、社会保障の拡充、
大企業に対する規制、北朝鮮政策の柔軟化、右派エスタブリッシュメントに対する批判を軸に
選挙戦を戦った、金大中(キム・デジュン)が当選すると、三八六世代は親と同じ世代に属する金
大中を熱狂的に支持した。
二〇〇二年の大統領選挙でも、左翼民族主義運動と関わりを持つ、人権派弁護士で民主化運動
の活動家である、盧武鉉(ノ・ムヒョン)が当選する。
「いずれの政権でも三八六世代に属する人が一部の重要なポストを獲得し、この世代のイデオ
ロギー的傾向が部分的に反映された。―こうした背景のなかから太陽政策が生まれた―
太陽政策の根底にあるのは、柔軟路線によって北朝鮮が中国やヴェトナムと似たような改革に
着手するようになり、両国は実現可能な、おそらくある種の連邦制へと段階的に進むことがで
きるようになるという考えだ」(本書)
文在寅も重要なポストを獲得していたことは有名な話。
若い人ほど統一に対する関心が低い、近頃は統一を支持する人ですら、民族主義や理想主義を
持ち出して語ったりはしない、とも著者は書いているが、どうだろうか。
その他にも北朝鮮(金日成時代)の外交政策を論じているのもかなり参考になった。
「一九七〇年代はじめごろから北朝鮮は「等距離」外交に方針を転換し、それは一九九〇年代
初頭まで続いた。
これは基本的には、互いに対立支援者、つまり中国とソ連のあいだでバランスをとるという政
策である。
北朝鮮の政治家や外交官は中ソ対立がもたらす不安定性の根深さを認識しながらも、そこにす
ばらしい政治的チャンスがあることに気づいた。
奸知を使えば、たいした見返りを与えることなく両方の支援者から援助を引き出すことができ
たのだ」(本書)
「ソ連」を「アメリカ」に変えれば、今の金正恩がやっている事と同じだ。
韓国は同じ事をやろうとして失敗したが。
・・・状況が好ましくなく、しかも外国から援助と譲歩を搾り取ることができるなら、そうすべき
である。
政策担当者がこう考えれば、いつも同じ手順が始まる。はじめに危機をつくりだし、可能な限
り緊張を高めるのだ。
ミサイルを発射する、核実験を行う、特殊部隊を使う、威圧的なほのめかしをする等々の手段
を訴える。
朝鮮半島が戦争の瀬戸際に来たとの見出しが各国の新聞の一面に踊り、世界の外交関係者たち
が一抹の不安を覚えるようになったころが潮時で、北朝鮮政府はこのタイミングで交渉を提案
し、外国の外交当局者は胸をなでおろす。
これによって北朝鮮の外交官は強力なカードを手にすることができる。
危機が生じる前の状態に復する意思を示し、その見返りに交渉相手から最大限の譲歩を引き出
すのだ。たいていは、この方法でうまくいった。
北朝鮮は一九六〇年代と七〇年代にも、この手法をソ連と中国に行使した(もちろんこのときは
ミサイルではなく、もっと穏やかな手段を使っている)。
『北朝鮮の核心――そのロジックと国際社会の課題』アンドレイ・ランコフ
著者は、隣に豊かな韓国が存在する現状で、政治的安定の維持という目的と両立しうるもの
は、高度に集権化され統制されたスターリン主義経済以外にない。政府首脳は今後もこうした
考えを捨てないだろう、としているが、どうだろうか。
拉致被害者奪還のためにも、ぼくたち一般人も北朝鮮への認識を深めていかなければならな
い、と痛切に感じる。


