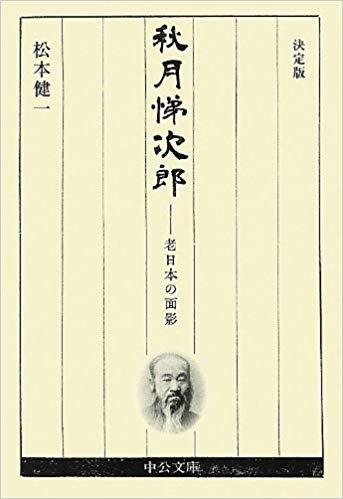
輸城後述懐 城を輸(わた)した後の述懐
至 今 忠 孝 道 方 虧 今に至り忠孝の道まさに虧(か)く
四 十 余 年 何 所 為 四十余年、何の為す所ぞ
独 恨 宝 刀 未 全 試 独り恨む、宝刀いまだ全く試さざるを
松 城 門 外 植 降 旗 松城門外、降旗をたつ
―今に至って忠孝の道を尽くしたかと考えてみると、
四十数年のあいだ何にも為すところがなかったのではないか、と恨みのみ残る。
今日、わたしは若松城の門の外に「降旗」を立てた。
秋月悌次郎(あきづき・ていじろう)は、会津戊辰戦争で会津藩の主戦派であり、敗戦にさいして
は軍事奉行添役(副奉行)をつとめ、開城の責任者だった。

秋月悌次郎 文政7年7月2日(1824年7月27日)- 明治33年(1900年)1月5日
文政七年(一八二四)、七月二日、会津藩士の丸山胤道(かずゆき)の第二子として、会津若松米
代二ノ丁で生まれた。字(あざな)は子錫(ししゃく)、韋軒(いけん)と号した。
諱(いみな)を胤永(かずひさ)といい、後年はもっぱらこれを用いたという。
永年の友人であった南摩綱紀(なんまつなのり)の撰した墓碑銘に拠れば、秋月の姓は平氏で、
その遠祖は葛原親王であると伝えられる。
その子孫に千葉兼胤(かねたね)という人物がおり、兼胤の第二子が丸山重次で、これが中興の
祖である。
重次の九世のちの頼堅が会津藩主の保科正之に仕え、その五代目が丸山胤道すなわち秋月悌次
郎の父。
丸山家は百五十石だったが、貧しく、第二子だったこともあって、悌次郎は秋月家を別に立て
た。長子の名は胤昌、第三子の名は胤家で幼名を三郎といった。
悌次郎は、幼少より学問を好み、十歳のときに藩校日新館に入った。南摩とはこのころからの
友人。十五歳のとき藩士の高津平蔵について「詩」を学び、以後、詩文を生涯最大の楽しみと
した。
天保十三年(一八四二)、十八歳のとき挙げられて江戸に上り、藩儒牧原只次郎について経術を
学び、幕府の儒官である松平謹次郎(慎斎)の麴渓書院に入って漢学を究めた。
慎斎は、学問の要は「道」を知るに在り、詞章訓詁には在らず、と教えている。
麴渓書院時代の秋月は、学資は乏しかったが、史を好み、文をよく作っていた。
慎斎にまなぶこと四年、秋月は弘化三年(一八四六)、二十二歳のとき、幕府の昌平黌(しょうへ
いこう)に入る。
昌平黌では佐藤一斎と安積艮斎(あさかごんさい)のふたりに師事し、黌外では経義を金子霜山
(そうざん)、国史令格を栗原又楽に、詩文を藤森天山に、古学を安井息軒に学んだ。
四年後の嘉永三年(一八五〇)、二十六歳のとき昌平黌の奇宿寮の寮長となり、幕府から微禄を
もらうようになる。
秋月が昌平黌にいたのは、足掛け十一年であったが、そのときの同窓生の俊才が、水戸の原市
之進、薩摩の重野安繹(しげのやすつぐ)であった。
秋月は昌平黌を卒えて西国巡遊をしたときに薩摩の重野を訪ね、そのあと藩命で水戸を訪れた
ときには原市之進を頼っている。
原市之進は帰藩後は弘道館訓導、のち徳川慶喜の懐刀といわれた。
幕末史に初めて姿をみせるのは、長岡藩の河井継之助が諸国巡遊中に記した日記『塵壺』のな
かでだという。
場所は、備中松山藩の松山にあった文武宿「花屋」。河井はここに宿をとって山田方谷のもと
で藩政を学んでいた。
秋月も同じ「花屋」に泊まっていたらしく、河井の部屋を訪ねてきたという。
その後、河井とは長崎で再会し、出島の唐館やオランダ館、幕府の海軍伝習所などを一緒にま
わっている。
さらに、その九年後には、戊辰戦争において、秋月は長岡城に入り、河井に献策している。
河井は長岡藩軍事総督であり、秋月は会津藩奉行添役だった。
秋月は重野を訪ねに薩摩にも入るが、会うことができなかった。重野は奄美大島に流されてい
た。そして、このときに大山綱良に会い、その交遊の席で西郷隆盛をみかけた、という伝説が
残っている。
しかし、西郷も奄美大島へと亡命している時期であり、このときに西郷をみかけた、というの
は疑問が残るとしている。
ただ、いつかはわからないが、西郷と会っているのは間違いないようだ。
後年、秋月は五高の生徒とともに鹿児島へ行っているが、そのときに、城山で自刃した西郷と
鹿児島県令で反乱軍を支援したという理由で死刑になった大山の墓を詣で漢詩をつくってい
る。
文久二年(一八六二)八月、会津藩主の松平容保が将軍家から信任をうけ、京都守護職に任ぜら
れると、秋月は京都守護職の下で、公用役につく。
公用人としての秋月が、最初に名をあげ、「会津に秋月あり」という噂をまきおこしたのは、
文久三年二月、足利氏三代の木像梟首(さらしくび)事件においてであった。
平田系の尊攘派の浪士たちは、京都の等持院にあった足利尊氏以下三代の将軍の木像の首を引
き抜き、これを三条大橋の下に「逆賊」として梟首にした。
京都守護職となったばかりの松平容保は、公用局にその犯人を探らせ、犯人を逮捕した。
このとき、三条実美ら尊攘派の公卿は、浪士一味の罪を赦すべきだと主張したが、それに対し
て、朝廷に説得したのが秋月だった。
秋月はこれら尊攘派浪士の「志」を否定したわけではなかったが、「志」を表現するにも
「法」を破っては国家は成り立たぬ、と考えていた。
会津藩は佐幕派というのが京都でも常識であったが、秋月の幕末の国家構想は、公武合体派に
ちかく、権力は幕府に、権威は天皇に、というものであり、尊王論それじたいに対しは好意的
だった。
そのことと関係してか、文久三年(一八六三)八月十三日の夜、京都鴨川のほとり三本木町の秋
月の宿所を、薩摩藩士であり十二歳下の高崎佐太郎が密かに訪ねてくる。
その内容は、攘夷親征路線を押し進めた急進尊攘派の公卿と長州勢力を、会薩の同盟によって
駆逐しようという提案であった。
秋月と高崎は中川宮をたずね、会薩同盟の成立を述べ、同意を得る。
文久三年八月十八日、中川宮は勅を宣べて、三条実美中納言ら尊攘派公卿の失脚と、長州藩の
駆逐を明らかにする。公武合体派のクーデター宣言。
この会薩同盟は、二年後の慶応二年(一八六六)一月、坂本龍馬が仲介者となって薩長同盟が成
立することで終焉をつげるが、著者は、もし公武合体派の新政府がつくれていたなら、そのさ
いには秋月は新政府の功労者ということになったろう、と指摘している。
秋月はこのクーデターのあと、中川宮ならびに二条関白太政大臣の顧問にあげられる。
しかし、元治元年になり、急進尊攘派の駆逐によって勢力を増した会津藩内の佐幕派は、
尊王思想に対して理解を示す公武合体派の秋月を京都から追い払う。
さらに、秋月を一年間の非職にしたあげく、慶応元年(一八六五)九月には蝦夷地代官に任命す
る。秋月四十一歳の時。
蝦夷地に居ること一年あまり、慶応二年(一八六六)十二月、京都から至急帰ってこいという手
紙が届く。
この年の一月二十一日に、二年半まえの会薩同盟を覆す薩長同盟が成り、幕府の第二次征長も
失敗に終わったことから、佐幕派の会津藩の勢力が衰退していた。そこで、かつて会薩同盟を
成立させた秋月を改めて必要とした。
しかし、秋月が戻った頃には、会津藩が「朝敵」と目される道まではほんの一歩のところであ
った。
慶応四年(一八六八)一月三日、鳥羽・伏見の戦いによって戊辰戦争の火ぶたが切って落とされる
と、一月七日には徳川慶喜追討令が出され、四月十一日には江戸が開城された。
会津藩は薩長の動きに対して、東北列藩同盟を組織し、徹底抗戦を叫び、鳥羽・伏見の戦いに敗
れて会津に帰ってきた秋月を軍事奉行添役(副奉行)にあげる。
会津藩は一カ月の籠城作戦を展開するが、九月二十二日に降伏することになる。
籠城作戦のさいには、いくつもの会津悲話が生まれている。婦女子の自刃、白虎隊の自刃。
白虎隊をはじめとする会津家臣の子弟たちは、藩校の日新館にあっては秋月の教え子であり、
戊辰戦争中にあっては秋月の政治的な指導の下にもあった。
秋月はこのような状況の中、軍事奉行添役として降伏の使者として立たねばならなくなった。
それは誰かが引き受けねばならぬ役割だった。
そして秋月は、手代木勝任(てしろぎかつとう)とともに、九月十六日、猪苗代口から若松城に
迫った板垣退助に降伏の議を申し入れた。
「秋月・手代木の二人は、この役を引き受けたことによって、白虎隊と娘子軍(じょうしぐん)の
悲壮な戦いを会津魂の華と考える会津人士から、長い間「裏切り者」にちかい扱いをうけた。
その事情は、戊辰戦争から百年以上をへた現在でもさして変わっておらず、かれら二人は嫌わ
れるというほどではないにしても、疎んじられる存在となっている」(本書)
降伏式が行われたのは、明治元年(一八六八)九月二十二日正午。
午前十時に、秋月ら降伏の使者は追手門のまえに、白い降伏旗三旒を立てた。
冒頭に載せているのは、その時のことを後に振り返って漢詩にしたもの。
秋月は明治二年六月に、手代木とともに終身禁錮を命ぜられる。
幽閉場所は、東京の熊本藩邸へ半年、美濃の高須藩へ二年、そのあと名古屋へと移され、
明治四年の末には青森県下北郡の斗南藩に移る事が許され、その一カ月後に恩赦の命に接す
る。戊辰戦争の敗北から数えて三年四カ月ほどたっていた。
その後、秋月は老母を養うために学校の先生になったらどうか、とすすめられ若松県の副教授
になる。
学校に席をおいたばかりの秋月だったが、明治新政府は左院少議生の椅子を用意し、明治七年
に秋月は左院五等議官になる。
明治八年には左院が廃止され、秋月は高崎正風の下で、内務課勤務になる。
これらは何を意味しているかというと、薩摩、長州、会津などの関係者を政府のもとにおい
て、地方行政の管理、内乱の鎮圧を担当させるということ。
秋月は新政府に仕えることじたいを「厚顔」ととらえていた。その時の漢詩に「厚顔」という
字がでてくる。
「明治以後の秋月は、心の奥でいつも戊辰戦争の砲声と吶喊(とっかん)の声とをきいていた。
長岡攻防の死者、戸ノ口原の戦死者、白虎隊の集団自決、城下の悲劇、白河口の屍、・・・。
新政府に出仕したかれが、みずからを「厚顔」と称さなければならなかったのも、この死者の
声、死者の目を意識していたからである。
そして秋月はついに、この死者の声、死者の目に同一化し、その静かな時間にみずから着地し
てゆこうとしていた」(本書)
明治十三年(一八八〇)一月に母を八十八歳で失うとふたたび上京し、家塾や大学予備門、第一
高等学校などで教鞭をとった。
秋月が教えるのは、あくまでも国家のための学問であった。秋月にとってその国家は、死者た
ちに見守られ、次の世代の生者たちが引き継いでゆくものであった。
明治二十三年(一八九〇)九月、秋月は熊本第五高等中学校(明治二十七年、第五高等学校に改
称)の漢学、倫理の教授を五年間つとめる。
そして、ちょうど同じ時期に松江から九州の熊本へと移ってきたのが、ラフカディオ・ハーンで
あった。
ハーンは、明治二十四年(一八九一)十一月から明治二十七年十一月までの三年間、五高で教鞭
をとった。
ハーンにとっては、熊本や新生日本の青年らには好ましい印象を残さなかったみたいだが、秋
月との心的交流だけは別だったという。
ハーンの秋月に対する親和の感、敬愛の情は深く、「彼は老いて、甚だ老いて、神様のように
見えて来た」とまで書いている。
ハーンにとって、秋月は「老日本」の面影を伝える人だった。それは明治二十六年に撮られた
五高の記念写真のなかにもあらわれている。
ハーンはバジル・ホール・チェンバレン宛の手紙でも「昔風な日本」を「神々の国」と捉え、
そのエトスを保持している秋月を「神々しい」人、「カミサマ」と敬愛している。
著者に拠れば、秋月はハーンのなかの「神々の国」である出雲へと連なる存在だったのだろ
う、と指摘している。
「ハーンが秋月悌次郎に対して親和の感を示すのは、秋月が「過去」に対して感謝の念を抱き
つづけたからであり、いいかえると、秋月が「死者の霊」に対する畏れと敬いとを持ちつづけ
ていたからなのではないか。すなわち、秋月のなかにある「常民の心」に対する敬意である。
「常民の心」が「常」でありうるのは、それが永遠に変わらない「死者の霊」を根底にふまえ
ようとするからであろう」(本書)
五高の学生寮である習学寮は、五十年にわたる寮の『習学寮史』を刊行し、そこには「三先
生」という回顧録が特別に作られているが、その「三先生」というのは、ラフカディオ・ハー
ン、夏目漱石、秋月悌次郎だった。
秋月はいつも紫の風呂敷に古い大判の論語などの和本をつつんで講義にのぞんでいた。
その授業は、「治国平天下」をなすべき有為の青年に「聖賢の道」を教え説くというものだっ
たのだろうと。
五高生の「鹿児島行軍」という名の修学旅行があり、秋月もこれに同行しているが、往きの海
路とは異なり、帰りは陸路で加久藤の峠を越えて熊本に戻る予定であった。
しかし、加久藤越えのさい、一行は強い雨に見舞われ、山道は雨にぬかってドロドロになって
いた。しかも、五高生たちは、大きな火銃と長い剣とを携えていた。
そんな状況の中、七十歳の秋月は先頭に立ち、道傍の枯草を「エイ〱」と声をかけながら峠の
下り坂にまきちらし、道を滑りにくくこしらえている。
みずからを励まし、後から来るものたちが坂道をすべらぬようにと、枯草をまきちらしてい
た。
著者に拠れば、その秋月の行動は、幕末から維新の動乱にさいしての戦闘や行軍から得た知識
であり、その知識を、秋月は後から来るもののために、かれらが気づこうがきづくまいが、い
ま活かしていたのである、と指摘する。
そして、この「後から来るもの」のために滑りやすい坂道に枯草をまいている秋月の姿にこ
そ、「老日本の面影」があり、それこそが、先に生きた秋月が守り、「後から来るもの」に伝
えんとした「常民の心」があったろう、と。
秋月悌次郎は、明治三十三年(一九〇〇)一月五日、七十五歳で亡くなっている。
「これが「残骸」であろうか。
たしかに、維新以後の秋月には「明治の耐えて」いる姿勢がある。
それはしかし、滅んでいったものに忠義を尽くすというのでなく、そういった政治的な変革と
か価値観の変化を超えて守るべきもの、つまり「常民の心」とでもいうべきものが人間の世界
にはあり、秋月はそれを伝えるために一身を投げだして幕末から明治の政治的な変革とか価値
観の変化に耐えていた、ということではないだろうか。
耐えて、かれは「老日本の面影」を伝えた」(本書)
本書は全Ⅲ部構成で、Ⅰ部とⅢ部は秋月悌次郎を論じているが、
第Ⅱ部は「非命の詩人 奥平謙輔」となっている。
奥平は長州藩士であり、漢詩人でもあり、萩の乱の首謀者として刑死した人物。
三十五歳の秋月が西国巡遊の旅にでて、長州に立ち寄り、その時に十七歳の奥平に出会ったと
いわれている。戊辰戦争の時の奥平は、長州軍の最前線にいて、長州干城隊参謀だった。
会津藩が降伏し、秋月が猪苗代へ立退いて謹慎していてときに、奥平は秋月に名文の手紙を書
いている。
秋月と奥平は越後で面会するが、その時に秋月は、藩公父子の助命や会津人士たちの将来につ
いても頼んでいる。
著者は、奥平は秋月に出会うことによって、詩文の才を発揮するようになったのではないかと
し、奥平は生涯の重要な三つの時点で、秋月とむかいあったとしている。
漢詩人としての自覚、戊辰戦争、刑死のとき。
著者が、秋月悌次郎を最初に論じたきっかけは、萩の乱の首謀者ともいえる奥平謙輔との関わ
りであったという。
奥平謙輔は革命的ロマン主義者であったが、その歴史のうえで正しく位置づけるためにも、対
極にある保守的な現実主義者、もしくは政治的理性の持ち主を正しく把握しなければならな
い、と考えるようになり、それが秋月悌次郎に結実した。
秋月悌次郎は偉大な政治家ではなかったのかもしれないが、会津が生んだ「偉大な教育者」で
あり、明治を耐えて過ごした「老日本の面影」であり、「神様みたいな人」だった。
本書は、長らく「裏切り者」に等しい扱いを受けていた秋月悌次郎の汚名をそそぎ、再評価の
きっかけとなっている。
著者は『秋月悌次郎 老日本の面影』(作品社、一九八七刊)をきっかけとして司馬遼太郎氏と
付き合いが生じたという。
歴史を云々と批評するのではなく、思想やその精神を説いているので、心に響く。
松本健一氏の他の著作も同様だ。
かれは、自我を主張することを価値とした近代日本のなかでは永遠に失なわれてゆかざるをえ
ないような、伝統を守って生きる人間の生き方の正道を踏もうとした懐かしい人であった。
『秋月悌次郎 決定版 – 老日本の面影』松本 健一


