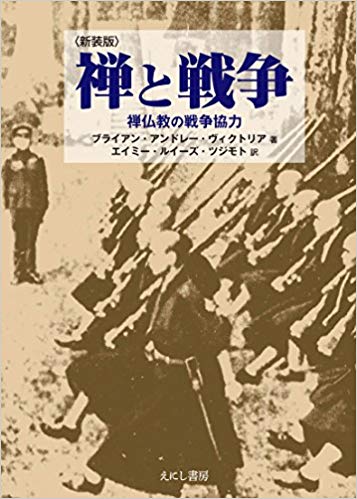
本書はかなり辛口に「禅と戦争」(近代の廃仏毀釈から戦後に至るまで)の関係を書いている。
著者は徴兵忌避者としての結果、一九六一年に日米の親善をすすめるべく宣教師として来日し
た。その後の経過は詳しく記述されていないが、禅に興味を持ち、どこでかは知らないが禅を
学んだ。
一九七〇年の春、著者は東京永平寺別院であった丹羽廉芳(にわれんぽう/一九〇五~九三)の部
屋に通される。
正座する著者の前で監院は、「あなたは曹洞宗の僧、さらに駒澤大学で仏教学を専攻する大学
院生でありながら、日本でベトナム反戦運動に加わるとはなにごとか!」と叱咤する。
さらに「禅僧たるものは一切、政治運動に関わるべからず」と警告される。
さらにもうひとつ「この警告を無視するようなことがあらば、僧籍剥奪ということもやむをえ
まい」と重ねて言われる。
その後、反戦運動はつづけたものの、僧籍を剥奪されることはなかった。
それには、何人かの後ろ盾があってのことだった。
しかし、その警告は、その後の著者の人生に大きな影響をもたらす結果となり、一つの重要な
意義を生み出していったという。
なぜなら「禅僧と国家の関わり」に始まって、政治、社会、ひいては禅と戦争の関連へと、次
第にその姿、実体を追求する方向へと視点が広がっていた。
「その焦点は一八六八から一九四五年の日本における既成仏教教団、特に禅宗の歴史を中心に
あてている。
また、この時期に限定した背景については、禅仏教と戦争との関係が代表的であったのではな
く、逆に極端な状況であったゆえに、この時期を選んだのである」(本書)
なので、かなり「左」寄りの歴史観なので(近代化した日本が始めから領土拡大を計画していた
ような記述だし、家永三郎を時々引用している)、読んでいて少し辟易させられるが、
それでも参考になる箇所も多々あり、楽しく読ませていただいた。
まず、廃仏毀釈から説き起こしているが、徳川時代には既成仏教教団が幕府から支持を得てい
たが、明治になると、神道と仏教を切り離す手段として「神仏判然令」が新政府により発布さ
れ、窮地に立たされる。
しかし、欧米視察団が帰ってきたころに、不平等条約を改善するには、国内での宗教の自由を
認めるべきであると主張し、キリスト教と共に仏教も次第に認められるようになる。
このような状況のもと、制限はされはしたものの新たに宗教の自由を経た日本の仏教者たち
は、一八八〇年代の終わり頃になると、「新仏教運動」なるものを生み出そうと動き始める。
新仏教とは、明治の初期から中期において出現した反仏教的な批判にこたえるべく誕生してい
ったもの。
その目的は三つあると指摘する。
第一の目的は、僧侶と寺院が国家の社会、経済に大きな貢献ができるということであった。
第二は、仏教は外国で誕生した宗教とはいえ、天皇に対する忠誠、愛国心、国家の統一に大い
に発揮させることができるものであること。
第三には、新仏教たるその基本的教理は、当時急速に広まった西洋科学や技術に十分相容れる
ものであったこと。
その後、日本の仏教者たちは世界(主に西洋)でも活動してゆくが、ヨーロッパでは大乗仏教は
堕落・腐敗したもので、テーラワーダ仏教(上座仏教)のみが純粋なものと主張していたことに出
会う。
鈴木大拙らはそのとらえ方を改めようと尽力する。『大乗仏教概論』はその流れにあり、大拙
の初期段階での多くの学術書は大乗仏教を讃えるために書き上げられたもの。
その話は置いといて、仏教側も四苦八苦していた中、日清戦争が起きるが、著者に拠れば、仏
教者の中で平和運動のような形はほとんどなく、慈善活動、たとえば負傷者の手当、戦死者が
残した遺族の貧困を手助けなどを始めたのは、日本のキリスト者たちであり、日清戦争を正当
化しようとする仏教指導者たちはかなりの数にのぼり、その裏づけの一つにアジアの仏教にお
ける日本仏教の優越性が説かれた、と批判的に指摘する。
さらに日露戦争が起こると、既成仏教教団の指導者たちは軍に対する支援がひきつづき必要で
あると認識し、二十六歳の若き鈴木大拙も、この運動に大きく貢献していたと指摘する。
そして、この頃に書かれた大拙の論文をとり上げて、日本の敗戦に至るまで仏教指導者たちが
総じてとった基本的立場を明白にしていると指摘する。それは五つある。
(1)日本は自国の商業及び貿易の拡大に集中すべし
(2)万一、他国の「邪魔外道」がそれを妨害するようなことあらば、彼らは全人類の進歩を妨げ
るものとして戦わざるえない
(3)その戦いとは日本の宗教界より全面、かつ無条件の支援をうけるであろう。なぜならその戦
さたるもの、正義が成り立つように存在するゆえである
(4)兵士たるもの、その宗教によって認められた戦さたるものは少しもためらうことなく、後悔
せず、自らの命を国家に捧げざるをえない
(5)有事の際、国家に対する義務を戦場において果たすことが宗教的行為であること
日露戦争は一九〇五年に終結するが、この時すでに既成仏教教団では、日本の軍事行動に関す
る基本的な姿勢は完成していた、と指摘する。
さらに、先の大拙の五つの原則に加え、宗演や円了の言葉をとり上げ、三つの原則が生じてい
るとしている。
(1)日本の戦争は正義の戦争であるばかりでなく、仏教の慈悲の表われでもある
(2)戦争において死ぬまで戦うことは釈尊と天皇に対する報恩の機会でもあった
(3)日本の軍隊は常時、命を投げ出す用意のある何万人もの菩薩でなされている
彼らの目的は自国を防衛するのみならず、同じモンゴロイドの同胞たちを、西洋で白人のキリ
スト教者たちの帝国主義者から救い出すことにあると説いていると。
そして、このような思想を述べてきた仏教学者や僧侶たちが、再び宗教と政治、すなわち政教
一致の政策へと実現させるべく道を切りひらこうとしたことで彼らは政府の手先となり、
神道の神主と共に政府を美化し、賛美し、政府の目的が達すべく努力を惜しまなかったのであ
る、と糾弾する。
さらに、日露戦争の戦場で禅の力をより発揮した人物として、乃木希典をとり上げている。
乃木は児玉源太郎に紹介され、有名な臨済宗の南天棒の指導で修行を重ねていたという。
初めて目にしたので少し驚いた。
南天棒いわく、乃木があれだけの実績を上げることができたゆえは、禅の修行に他ならないと
いう。勿論、著者は批判的にとり上げている。
その一方、一九一〇年に起きた大逆事件で、三人の僧の中で唯一死刑となった、無政府共産主
義運動に活発に活動していた、曹洞宗関係の内山愚童を革新的仏教僧として、著者は高く評価
している。
次のことも初めて目にしたことで、余り言及されることはないが、真宗大谷派は一八七六年、
上海に寺院を建立し、翌年には朝鮮にて布教活動を開始している。
その後、日清・日露戦争の勝利で大陸経営にのりだした日本だったが、それと同時に真宗の開拓
者的活動は何倍にも拡大したという。
一九一八年までに本願寺派が朝鮮の三十四ヵ所に布教所を設立、真宗大谷派が五十八ヵ所に布
教所を設置した。
一九四一年までにこの両宗派は、それぞれ満洲において五十三ヵ所と八十三ヵ所の布教所を設
けているという。
曹洞宗の場合は、一九〇四年に初めて朝鮮に設立し、一九一二年には二十一ヵ所に広がり、太
平洋(大東亜)戦争終結時には百ヵ所以上になっていた。
満洲では曹洞宗は一九〇七年に布教を開始し、一九〇四年になると三十七ヵ所となっている。
日蓮宗なども一九〇七年、満洲に最初の布教所ができ、終戦時には二十ヵ所となっていた。
浄土宗は一九〇五年、中国で最初の寺を建立し、真言宗では満洲をはじめ中国で三百人以上の
僧侶を、戦時中に送り込んでいるという。
大陸での仏教布教所、そして僧侶たちは、大日本帝国の代表者でもあった、と著者は糾弾して
いる。
そして、一九三〇年代にかけて、暗殺がはびこったこの時期の禅との関係にも言及している。
二・二六事件(一九三六年)の前年に、軍務局長永田鉄山が暗殺されるという事件が起きているが
(相沢事件)、その犯人である相沢三郎は、長年在家人として参禅し、臨済宗円覚寺管長の今北
洪川の指導を受けるなど禅に凝っていた。
相沢は輪王寺(仙台)の住職だった福定無外老師に弟子入りし、雲水のごとく僧堂でも起居して
いる。
無外は暗殺事件後に相沢について、「立派なる精神」「確固不動の信念」と讃えた文を残した
りしている。
著者は、禅の指導的な立場にあった無外をはじめ、他の禅のリーダーたちがとらえた禅とは、
一定の条件のもと、国内での暗殺、外国侵略を支援せんばかりの性質を持っていた、と指摘す
る。
それは血盟団事件の首謀者だった井上日召の師でもあった山本玄峰老師にも向けられている。
井上日召は、日蓮主義のイメージが強いが、最後に禅を選んだという。
無外も玄峰も、直接的に行動はしなかったが、自分たちの弟子の行動を肯定したことは事実だ
としている。
その後の時代に著者は、「仏法」を完全に「王法」の指導のもとに置く皇道仏教が誕生し、
既成仏教教団は国家とその政策に一切の異議を唱えることなく従順そのものであったと指摘す
る。
禅では、先述のように、明治以後の禅者たちが、いかに禅と武士道の関連性を説いたか、
明治以降の禅者たちがこの関係において、自分たちの強大な戦争支持をいかに正当化したかを
指摘する。(「皇国禅」)。
日中戦争に入ると、大法輪が主催して座談会が開かれるが、そこに参加したのが、陸軍大将林
銑十郎や中将堀内文次郎、海軍では、小笠原長生中将らで、座談会の内容とは、禅が軍人の精
神や国民に対していかほどの貢献ができるのか、としていたという。
大法輪社長の石原俊明は曹洞宗の僧侶でもあった。
さらに、当時陸軍大臣だった東条英機によって発布された「戦陣訓」は、編集するにあたり、
総責任者であった今村均(時の陸軍大臣、のちにスマトラ方面の司令官)は、回想録の中で「自
身と禅」の関わりについて書いてあり、その影響も指摘している。
この頃の禅の老師たちは、将校たちに何度となく五日間の坐禅会を開き、この会は各部隊の武
道館で行なわれ、将校たちは自分の陸軍用毛布をたたみ坐布の代わりをしていたという。
著者はこの時期の禅を「軍人禅」としている。
戦後になって鈴木大拙は、禅僧 が悟りを開いていないゆえにいうのではなく、悟りはあったか
もしれないが、公の時代では悟りだけではすまされない、と指摘していたという。
そして、「皇国禅」「軍人禅」という言葉自体は今日では消えたものの、その精神は今もって
なお生きつづけていることは紛れもない、とも指摘し、それは「企業禅」にとってかわったこ
とにすぎなこと、と指摘する。
戦後日本の奇跡的な経済復興の一端に、「死に至るまで働く」ことを暗に承知した形があっ
た。つまり、無我の境地における死の価値観は一貫するものであった、と。
ざっとぼくの気になった箇所を簡単にとり上げた。
著者は「エピローグ」で、いうまでもなく歴史上、仏教だけが「聖戦」に参加したものではな
い、とも述べている。
確かに著者の歴史観は「左」に寄っているとはいえ、この時代の仏教者の印象はあまりいいと
はいえない面もある。
勿論、仏教界に限った話ではなく、日本画家の横山大観も同じように糾弾されていたことも思
い出す。
この時代は帝国主義の時代でもあり、食うか食われるかの恐ろしい時代でもあった。
今以上に危機感を抱いていたということも頭に入れておく必要があるだろうし、
そのような時代の雰囲気の中で、国を思う気持ちからそのような行動に至った、というように
汲みたい気持ちはある。
しかし、キリスト教に関しても、マッカーサーはプロテスタントの一人として、
日本人にキリスト教を広めることに大変熱心な軍人キリスト教徒だったし、
原爆投下時にはチャプレンが、エノラ・ゲイが出撃する直前に、お祈りをしてから送り出してい
る。
一七世紀初頭のジェイムズタウンが建設されたばかりの頃から、聖職者が住民たちによる戦闘
の訓練、実戦に対する攻撃も牧師の説教や祈りで始められるのが普通であったし、殺戮を正当
化し、戦死者の名誉を称えるのも、教会と牧師の仕事だった。
伊藤博文を暗殺した安重根もカトリックの信者で、神父から洗礼を受けてトマスという洗礼名
をもらっている。
ハルピン駅で伊藤を暗殺した時には、「天主よ、ついに暴殺者は死にました、感謝いたしま
す」と言ったと伝えられている。
あまり揚げ足をとりたくはないが、そのような事実もある。
いずれにしても、過去にこだわりすぎるのではなく、未来に向けて何ができるのかを考え、
偽善ではない平和をいかにして実現できるのか、を追求されることを心より願う。
ちなみに、本書は一九九七年にアメリカで出版され、ドイツ、フランス、イタリア、ポーラン
ドでも出版されている。
日本語版は二〇〇一年に出版され、長らく絶版になっていたが、二〇一五年に新装版として再
販されたもの。
韓国や中国でも出版準備中(二〇一五時点)ともしているので、まためんどくさいことにならな
ければいいが。
ぼくが本書を手に取った理由は、宗教学者の正木晃氏がすすめていたからだった。


