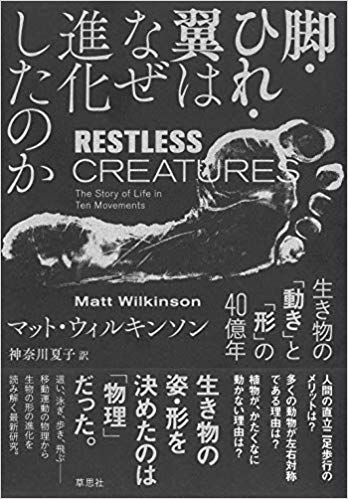
イギリスの物理学者で原子物理学の父と称されるアーネスト・ラザフォード(1871-1937)は、
「物理だけが科学だ。ほかはみな切手収集みたいなものだ」と言い、もう少しニュアンスは控
えめだが、アメリカの古生物学者・進化生物学者のスティーヴン・ジェイ・グールド(1942-
2002)は、仮に進化の過程を再現したならば、今見えている生物界とは全然違うものが目の前
に現れるだろうと断言し、基本的にはラザフォードと同じ立場を表明した。
グールドが言いたかったことは、大きな枠組みで考えると、進化とは複雑怪奇のようなもので
あり、科学をもってしても明確に見渡すことができない、ということだったと言われている。
本書では、これらの考えとは別の捉え方・見方を提案している。
わたしたち人間とほかの生き物について深く理解するための方法が、なさそうでいてじつは1
つある。進化が始まって以来、進化の実現性を支配してきたテーマ、それは「移動運動」であ
る。ある場所から別の場所に移る、という一見単純な行為だ。
とケンブリッジ大学の生物学者であるマット・ウィルキンソンは表明する。
そんなウィルキンソンにひらめきを与えたのは、動物学の研究を始めた頃に興味を持った翼竜
だったという。
「進化の歴史において移動運動がもたらした結果から判断すれば、間違いなくこれは生命が生
まれて以来、歴史上もっとも意義深い転換だ。
移動運動能力が進化する以前には、生命はいわば異常に複雑な化学物質といったところだっ
た。
しかし生命体はひとたび動き出すと、ほかの個体と出会うようになり、捕食、寄生、生殖行
為、共生などの関係を持ち始める。
言葉を変えれば、移動運動のおかげで生命は生命としての特徴を帯びるようになったのだ。
以来、移動運動は進化が繰り広げるドラマの主役を張っているのである」(本書)
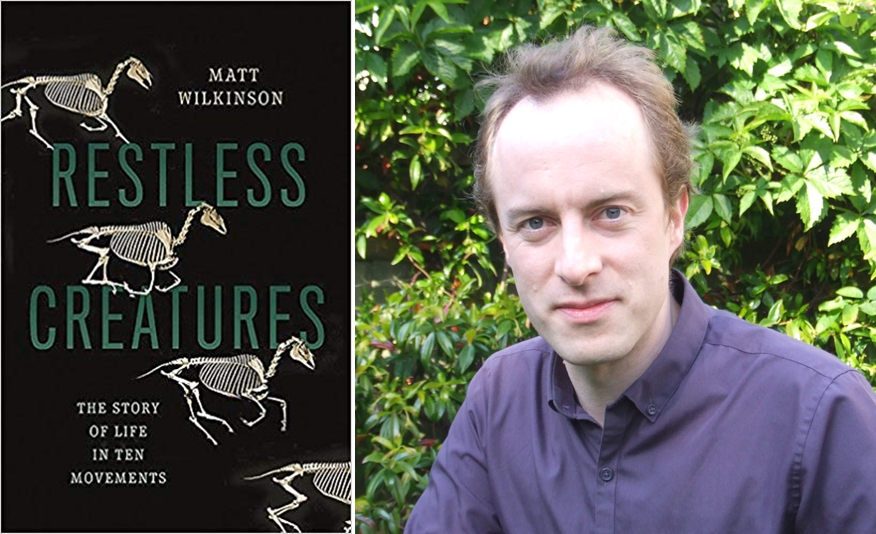
『Restless Creatures The Story of Life in Ten Movements』とマット・ウィルキンソン
本書では進化生物学は勿論のこと、物理学や航空力学、人類学や動物行動学、分子生物学や脳
神経学や人体構造学、そしてアンドレ・ルロワ=グーランが研究していた「力学的な均衡」のよ
うなものも入っていて、それらの知見を用い、移動運動の物理から生物の形の進化が書かれて
いる。著者の構想の雄大さと知識・調査範囲の広さには圧倒される。
なのでかなり難解で、本書を一から十まできちんと把握できる人間は限られる。
さらに原著はどうか知らないが筆がはやい。The Royal Institution(王立研究所)での講演の動
画も観たがしゃべりはもっとはやい。
本書は全10章で構成されており、マクロからミクロな視点に下りていく。物理学がメインだっ
たものから生物学に移行していく。外から中に入っていく。
最初の章では、「人間はどのように歩き、走るのか」を検証し、人間の移動運動の過去の歴史
を学ぶにつれて、生物の世界をより広い背景のもとで理解し、移動運動の普遍的な特徴を考察
している。2章では、樹上生活者であったわたしたちの祖先が、どのように二足歩行を始め、
森を去ったのかを。3章では、空に目を向け、今も大空を自由に飛び回っている幸運な動物た
ちの誕生のいきさつを。4章では、水の世界に飛び込み、自然選択の結果、泳げるものだけが
残り、脊椎が発生した経緯について。5章では、ひれを手足に変えて陸上に這い上がってき
た、魚に似ているが人間にもう少し近くなってきた祖先の話。
6章では、進化のより深い世界に踏み込み、生物はみな、移動運動に即した身体を目指して、
前後左右という対称性のある身体構造を持つにいたった過程を。
7章では、神経系統の発生のおかげで、動物が無駄のない造りの身体をコントロールして移動
できるようになった道のりを。
8章では、移動運動を放棄した生き物を。ただし、放棄というのはうわべだけの言いかたであ
り、移動運動は動物の進化だけでなく植物の進化をも支配してきたとして植物を。
9章では、単細胞生物における移動運動の適応改善が、のちに現れる巨大な多細胞生物の基礎
作りにどのように貢献したのかを。
最後の10章では、移動運動の恩恵は、身体に関する事柄だけではないとして、人間の心につい
て語られている。
粘液による推進力を使っていた原核動物から人類へと続く系統の進化を大まかに辿ると、
動物界の黎明期、最古の這うようなアメーバ運動から繊毛の誕生へ、そして繊毛に取って代わ
って神経系が登場した。
次に、細胞骨格の再編成が内部で行なわれて筋肉が形成された。筋肉は最初は移動運動の舵取
りのような役割を果たしていたが、次第に推進力を担い始めた。
これらと並行して、放射相称性の身体構造が破綻し、繰り返しのモジュールが前後軸に沿って
発達した。
このような進化の背景には、筋肉によって這う移動運動が可能となり、メキシカン・ウェーブが
再び活用された。そしてこれが、左右相称動物の時代を告げた。
カンブリア爆発は動物門のさまざまな祖先がそれぞれの体制を発達させた時期だが、わたした
ちの属する脊索動物門の起源は、脊索の誕生と水中での推進力を生むうねり運動の出現による
という。これらの特徴はのちに、脊柱と対になったひれの発達に取って代わられる。
そして、数百万年後、最初の空気呼吸が始まったときから、さまざまな出来事が展開してい
く。脊柱とひれの骨格の骨化、ひれの水底歩行への適応化、陸上への移動。
わたしたち人類に連なる系列に関しては、安定性を犠牲にはしたが、四つの足での歩行や走行
のエネルギー効率は次第に改善され、腹部を地面につけた姿勢から、地面から垂直に浮いた姿
勢に変わった。そして樹上生活が始まる。
もっとも近い霊長類の祖先は不安定な枝に生える果実をとって食べるのを好んだため、拇指は
対向して生え、足の指は大きく発達した。
類人猿が直立歩行を始めると、前肢と後肢の進化的な運命はきっぱりと分けられた。
このときからヒト族は地上に戻り、わたしたちの祖先は二本足での走行など陸上生活能力を磨
いた。
そして、走れるようになった人間は獲物を襲撃することにかつてないほどの力を発揮し、これ
が脳の拡大を促した。
「新しいエネルギー補給方法の発見は、生命が向かう未来に移動運動があたえた影響力の始ま
りに過ぎない。
ひとたび動き回り出せば生物は否応なく互いに接触し、邂逅のたびに新しい選択の機会が訪れ
る。
相手を攻撃するか、相手から逃げるか、遺伝物質を交換するか、何らかの形で協力するか。
言い換えれば、移動運動の開始によって、生態系は今わたしたちが見ているような様相を帯び
てきたのだ。
生産者がいて消費者がいる。捕食者がいて獲物がいる。そして生殖や共生が行なわれる。
そして進化は、生命体が環境に適応するためだけではなく、自分以外の生命体に適応していく
ためのものになった」(本書)
この壮大な物語を振り返ってみると、生物の移動運動がきっかけではないエピソードなどない
に等しい、とウィルキンソンは言う。
もっとも近い脊索動物の祖先は、脊索が進化する前にすでにうねり運動を行なっていたし、
原初の四肢動物はひれが体肢になる以前から川底を這っていた。
原初の霊長類は手足で完璧にものをつかめるようになる以前から、細い木の枝の上をうろつき
まわっていた。
彼らがこのような冒険を試みたことで、その物理的な帰結が選択圧を与え、最終的に身体構造
の適応化が起きたのであり、このプロセスが強く思い起こされるのは、人が歩くことを習い覚
えるときの方法だ、とウィルキンソンは指摘する。
初めは試行錯誤で、そのうちやっとまともに歩けるようになる。歩行を習得すれば、移動運動
にしろそうでないにしろ、あらゆる種類のことを新しく学ぶ可能性が広がっていく。
それと同じで、祖先から何かを選択すると、それに呼応してふさわしい身体構造が形成され、
子孫たちにおいてはさらに進んだ試みが行なえるようになると。
ウェイフェアリング(元来は徒歩旅行の意)という言葉がある。
ウェイフェアリングは、現在の狩猟採集生活にとっての行動原理でもある。
伝統文化に関する人類学の研究では、移動中の狩猟者や採集者が、ほんのわずかな手掛かりに
も、絶え間なく注意力と敏感さを示していることが指摘されている。
狩猟採集生活者にとっては必須の行動様式。
ウィルキンソンによれば、今を生きる私たちの心理にも、このウェイフェアリングの痕跡が残
っていると見ている。特にその痕跡は“物語”にみられると指摘する。面白い仮説だ。
物語はナビゲーションという用途からかけ離れているが、人間が一連の出来事から意味を汲み
取るのが得意だからこそその機能を果たすし、物語は出来事の前後の順によって特徴ある一定
の心的イメージをつくり出す。どちらに進むのが自分にとって意味があるのかを、次々と現れ
る一連の展望から見出している。
そして、まさに人はウェイフェアリングをしながらこれを実践している、とウィルキンソンは
考えている。
「人間がよくできた物語を好むのは、究極的には、移動運動用に設計された脳の造りのせいだ
といえないだろうか?」(本書)
ばらばらの音に分解されたメロディは何の意味も持たないが、これらの音を編み上げて1つの
まとまった曲にすると、力強く心に訴えかける意味を帯びる。
人間が音楽を好むのも、移動運動用の心理設計の副作用か何かかもしれない、とウィルキンソ
ンは理解している。
それらを乱暴に言い換えれば、人間は“線形”に捉える傾向がある、ということであろう。
トール・ノーレットランダージュが『ユーザーイリュージョン』で、
「線形と非線形の均衡をいかに保つかは、文明の抱える大きな難問だ・・・
これは意識と無意識のバランスを見出す難題と密接に絡んでくる。
意識と無意識の違いは、意識にはごく少ない情報しかないというところにある。
そのため、意識は直線しか理解できず、膨大な情報を含む曲線は持て余してしまうのだ・・・
文明がともすると直線性に傾きがちなのは、意識が無意識に力をおよぼすからにほかならな
い・・・
直線は計画と意思と決定の媒体、曲線は感覚知覚と即興性と自由奔放の媒体だ」
と述べているが、ウィルキンソンがいう“移動運動用に設計された脳の造り”は、それらとどの
ように関係しているのか、していないのか。無理やり並べたきらいもあるが、気になるところ
ではある。
今後のマット・ウィルキンソンの活動には注目したほうがいいと思うし、存在感も今以上に増し
てくるだろうと思う。
本書は、先史学者・社会文化人類学者だったアンドレ・ルロワ=グーランの『身ぶりと言葉』に
連なるような印象を受ける。
具体的に踏み込まず“さわり”しか書かなかったけれど、気になる方は是非、自身で紐解いてみ
てください。
人々の注目が、生命の生化学の中核をなすDNA、RNA、タンパク質、細胞膜、そしてこれらの
要素が具現化している代謝と生死プロセスの出現に集まることは正しいことだ。
しかし、それだけで止まってしまう生物圏は、生物圏の名に値しない。
移動運動が生物圏に登場して初めて、生命体の世界は十分に発達し、たんなる生化学以上の何
かになったのだ。
自己推進力が進化していなかったら、生命は、数個の散在した、短命の、ひどく複雑な化学物
質の破片でしかなかっただろう。
死の惑星の海底にあるちっぽけな存在で終わったに違いないのだ。
『脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか:生き物の「動き」と「形」の40億年』マット・ウィルキンソン


