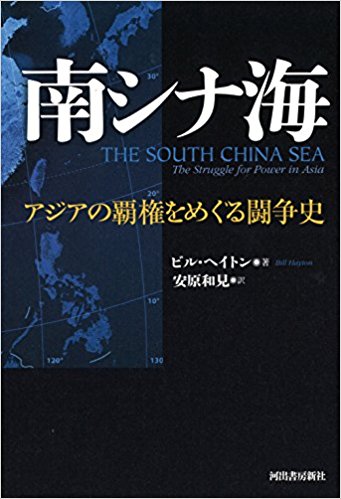
「この時代、南シナ海で起こることが世界の未来を決めることになるだろう」(本書)
「南シナ海では二種類の対立が起こっているということだ。
ひとつはアクセスをめぐる中国とアメリカの対立、もうひとつは領有権をめぐる中国と近隣諸
国との対立だが、このふたつがどんな相互作用を起こすか予測がつかないのである」(本書)
世界の海上貿易の半分以上がマラッカ海峡を通じておこなわれており、
世界の液化天然ガスの半分、原油の三分の一がここを通って運ばれている海域でもある。
ここでの問題は、日本も他人ごとでは済まされない。
著者は、ロンドンのBBCワールドニュースに勤務するジャーナリスト。
ベトナムやミャンマーで仕事をし、著書には『ベトナム―ライジングドラゴン』がある。
本書は、南シナ海の先史時代から説き起こし、将来の展望までを綴っている。
「一六世紀前半まで、東南アジアの海を支配していたのは、インドの影響を受けた「マンダラ
国家」群だった。と言っても、覇権国から次の覇権国へというように、権力がきれいに移譲さ
れていったわけではない。国はだんだん衰退していく。
共存している時期も長い―ときには平和的に、しかしたいていはそうではなかった。
メコン河口の扶南は後一世紀から四世紀まで支配権を握っていた。いまのベトナム中部にあっ
たチャンパは六世紀から一五世紀まで。
スマトラのシュリーヴィジャヤは七世紀から一二世紀まで。メコン河下流のアンコールは九世
紀前半から一四三〇年代まで。
ジャワのマジャパヒトは一二世紀から一六世紀まで。そしてマレー半島のマラッカは一五世紀
の前半から、ポルトガルがやって来る一六世紀前半まで、それぞれ支配権を握っていた。
南シナ海の北岸、すなわちいまの中国と呼ばれている地域を治める勢力が、その他の政治勢力
のやることに介入することがなかったわけではない。
しかしそのような例はまれで、また長続きもしなかった。
どんな意味においても、この海を「所有」していた国も人も存在しなかった」(本書)
著者は、この海上ネットワークを「マンダラ」体制と呼び、当然だが、中国が主張する物語と
はまったく異なる南シナ海の姿を提示している。
2014年6月1日にシンガポールで開催された、シャングリラ・ダイアローグ(アジア安全保障会
議)で、中国側の代表の王冠中(人民解放軍副総参謀長)は「南シナ海は2000年以上も前から中
国の支配下にあった」と発言しているが、上述の通り、そんな事実はないし、その会議の出席
者から失笑も買ったみたいだ。
そして、特に著者が懸念を示しているのが、この「マンダラ」体制から「ウェストファリア」
体制的な考え方に移行したことにより問題が複雑化したこと。
「ウェストファリア体制の影響力はあまりに大きく、固定的な国境と領土主権という概念は、
まるで何千年も前から存在したかのように当然視されている。
しかし東南アジアでは、このような考えかたにはわずか一世紀強の歴史しかないのだ。
「マンダラ」体制のもとで存在したであろう境界を根拠に、現代の国境を想定するのは無意味
であり、また危険でもある」(本書)
「マンダラ的体制からウェストファリア的体制への移行が、歴史的混乱という遺産を残し、
「U字型ライン」が公表されてからの年月に、南シナ海における領土獲得競争を生み出したの
である」(本書)
中国は一九五三年から「U字型ライン」(九段線)、断続する九つの破線の連なりを地図上に引
き、南シナ海全域にわたる権利を主張してきている。

それに加えて厄介なのが、現在の南シナ海の国境線が、植民地時代における列強によって引か
れていること。
「列強は国を作り、国と国の国境を作り、それをもとに海上の境界線が引かれた。
フィリピンとインドネシアは、一五二九年のポルトガルとスペインの合意によって分割され、
マレーシアとインドネシアとの国境線はだいたいにおいて、一八四二年に英国とオランダによ
って決められた。
中国とベトナムの国境は、一八八七年にフランスが一方的に中国に押しつけたもので、
フィリピンの国境線は全体に、一八九八年にアメリカとスペインによって定められ、
フィリピンとマレーシアの国境は一九三〇年にアメリカと英国が決めたものだ」(本書)
数千年の歴史上、南シナ海全域が一国の手に落ちたのは、一九四二年五月にフィリピンのアメ
リカ軍が降伏してから一九四五年一月までの短い期間でしかなく、それは日本によってなされ
た。中国もそれを狙い、最近では国内経済の行き詰まりから一帯一路を上にかぶせて主張して
きてもいる。
著者は、中国が南シナ海を「中国の湖」にすることによる利益は、四つの要素があると指摘し
ている。
第一は、国威発揚を望む感情と結びついた、南シナ海は歴史的に中国のものだという意識。
第二は、中国の沿岸部の都市を守るための「戦略的縦深性」の必要性。
第三は、インド洋および太平洋の公海域への戦略的アクセスを確保すること。
第四は、南シナ海そのものの資源―特に水産資源と石油ガス資源―を押さえること。
以前に取り上げた『米中もし戦わば』でピーター・ナヴァロが、第一次世界大戦前のドイツ帝国
と現在の中国に類似点が見られる、と指摘していたことを思い出す。
第一の類似点は、「マラッカ・ジレンマ」と同じようなものを抱えている。
第二の類似点は、急成長する産業基盤を支えるために外国からの天然資源の輸入に大きく依存
している。
第三の類似点は、海洋封鎖を恐れている。
上の要因もあり、東シナ海、南シナ海を「中国の湖」にしようとしているのだろう。
(大方予想がつくが)
それが有名な「A2/AD Anti-Access Area Denial」(接近阻止・領域拒否)と呼ばれる戦略で、
二〇〇九年に米国防総省が議会に提出した中国の軍事力に関する年次報告書で示した概念。

軍事アナリストの小川和久氏が『日米同盟のリアリズム』のなかで次のように説明している。
「A2/ADとは、九州・沖縄・台湾・フィリピン・ボルネオを結ぶ第1列島線の内側で米軍を軍事的
に排除し、伊豆諸島・小笠原諸島・グアム・サイパン・パプアニューギニアを結ぶラインを第2列
島線として、その内側でも米軍から行動の自由を奪おうというものだ。
このA2/ADに沿って、中国は海軍、空軍、ミサイルを統合運用する能力を増強している」
(日米同盟のリアリズム)
この戦略思想のもと、近海である南シナ海では管轄権を主張するための岩礁埋め立てなどの活
動を活発化し、大規模な軍事演習を繰り返している、とも指摘されている。
中国は一四年以降に確認されただけでも、スビ礁、ファイアリークロス礁、クアテロン礁、
ミスチーフ礁、ヒューズ礁、ジョンソン南礁、ガベン礁の七つの岩礁と干潮時に砂州が現れる
エルダド礁(安達礁)で埋め立てと施設建設を進めてきている。
本書のなかで著者は、係争対象の島々の軍事基地は、ほとんどがミサイル一発で破壊できるか
ら、とくべつ「戦略的」要所というわけではない、としている。
先ほどの小川氏に話を戻すと、とりわけ中国が重視しているのは南シナ海東部であるとし、
「南シナ海はかなりの海域が水深200メートル以下であり、透明度も高い。
そのため、中国が核弾頭搭載の弾道ミサイル原潜(SSBN)を遊弋させようにも、すぐに発見さ
れてしまう。
しかし、東部には平均水深が3500メートルもの海域があり、SSBNを遊弋させられる深度を確
保できるのだ。
SSBNの役割は、報復核戦力にある。例えば米国が中国を先制核攻撃したいと考えても、
海中に潜んでいて居場所がつかみにくいSSBNから報復の核ミサイルが米国の主要目標に向け
て発射されるのがわかっていたら、米国も核攻撃に踏み切れない。
これによって中国は核抑止力を確保できる」(日米同盟のリアリズム)
それでも中国は日米同盟によって抑制的に動いている、と小川氏は指摘されている。
著者は、南シナ海では、ふたつの戦略上必須の要件と多くの地域的利害が衝突している。
この対立がきわめて危険なのは、ふたつの国の自己像のちがいがそこにくっきりと現れている
からだ、として次のように指摘している。
「アメリカ合衆国も中華人民共和国も、その建国の基盤には強烈な目的意識がある。
そしてその目的意識は、両国のどちらのエリートの意識にも深くしみこんでいる。
中国共産党にとって、かれらの支配の正統性を担保するのは、帝国主義との戦いの歴史であ
り、また現在継続中のキャンペーン―植民地主義者や売国奴によって、国体からむしりとられ
た領土を回復するという―である。
歴史的に見ればいかにまちがっていようとも、その奪われた領土には南シナ海も含まれるとか
れらは信じているのだ。
いっぽうアメリカのエリートも自国の「自明の運命」を絶対的に確信している。
アメリカは「例外の国」であり、世界の「最後にして最善の希望」であり、「なくてはならな
い大国」であり、国際社会の規範やルールの守り手なのだ。
南シナ海は、その規範とルールが脅かされつつある初の場所なのである。
もしこの海域へのアクセスを失えば、アメリカはグローバルな大国としての役割を失い、ふつ
うの大国になってしまう。
そうなったら生半可なショックではすまないだろうし、アメリカのアイデンティティ、繁栄、
安全保障に壊滅的な影響が及ぶだろう。
とすれば、そのために戦う価値があるということになってもおかしくない」(本書)
「大成は欠くるが若(ごと)く」「大国は下流なり」
老子の言葉を思い出す。


