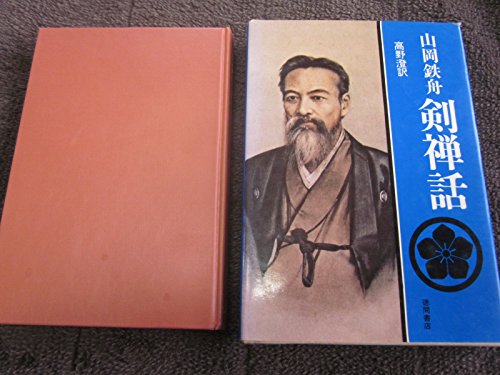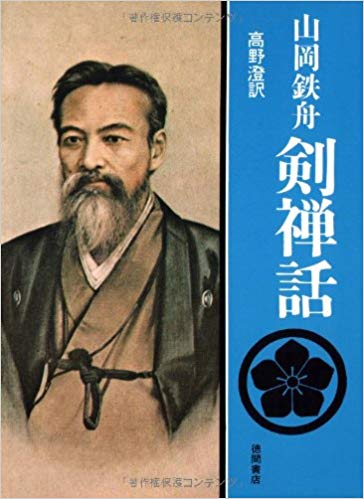
学 剣 労 心 数 十 年 剣を学び心を労すること数十年
臨 機 応 変 守 愈 堅 機に臨み変に応じて守り愈よ堅し
一 朝 塁 壁 皆 摧 破 一朝塁壁みな摧破す
露 影 湛 如 還 覚 全 露影湛如として還って全きを覚ゆ
山岡鉄舟 (一剣の極致に達せられた時)
剣・禅・書の三道を究め、明治維新のハイライトのひとつに数えられる江戸無血開城を実現する
ために身命を賭して官軍陣地を突破、西郷隆盛と直談判し、西郷・海舟会談を導いた山岡鉄舟。
そんな鉄舟の危険を顧みない行動に対して、西郷は、
「イヤ、命もいらぬ、名もいらぬ、金もいらぬ、といったような始末に困る人です。
ただし、あんな始末に困る人ならでは、お互いに腹を開けて、共に天下の大事を誓い合うわけ
にはまいりません。本当に無我無私の忠胆なる人とは、山岡さんのごとき人でしょう」
と評し、滅多にしか人を褒めない海舟も、
「山岡は明鏡のごとく一点の私をもたなかったよ。だから物事に当り即決して毫も誤らない。
しかも無口であったが、能く人をして自ら反省せしめたよ」、
「あの際、西郷を説得して、安々、維新鴻業(こうぎょう)を全(まった)からしむることは、
山岡ならでは出来ない業だよ。
回顧すれば高士山岡と叫びたくなるよ。簡単に、山岡を評せよと云うなら『誠実忠愛にして英
邁豪果(えいまいごうか)』の人物なりと評したい。
また当時、この意味からその人を探せば、山岡以上の人物は見当たらなかった」
と称賛しているのは有名な話。
維新後は、その西郷に「山岡の誠忠、山岡の剛直、かれこそは側近に奉侍せしむる資格があ
る」と求められ、海舟や大久保一翁に口説かせて明治天皇の侍従となって、子爵となる。

山岡鉄舟 天保7(1836)年6月10日~明治21(1888)年7月19日
大森曹玄の『山岡鉄舟』では、孔子の徳に進んだ順序に当て嵌め、鉄舟の生涯を五つの“節”に
分けている。
十七歳にして父を失ったときが第一節、二十四歳にして尊王攘夷党を結成したのが第二節、
三十三歳にして駿府に使いした頃から第三節、四十五歳の大悟が第四節、
四十九歳で庭の草花を見て機を応じたのが第五節の完成期。
山岡鉄舟は、天保七(一八三六)年六月十日、本所大川端四軒屋敷で、幕臣で御蔵奉行をしてい
た小野朝右衛門高福の四男として生まれた。母は磯。通称鉄太郎、名は高歩(たかゆき)。
弘化二(一八四五)年に父が飛騨高山の郡代となり、鉄舟こと小野鉄太郎もこの町で、十歳から
十七歳まで過ごすことになる。
九歳で剣の道を志していた鉄太郎は、江戸では久須美閑適斎に真影流を学んでいたが、飛騨高
山に移り、閑適斎の弟子の庄村翁助から修武場で稽古をつけられる。
しかし、父の高福は、息子の鉄太郎を鍛えるには一流の剣客を師範に迎えなければならないと
考えていた。そこで偶然にも、江戸で人気の北辰一刀流、千葉周作の高弟の井上八郎清虎が高
山に長期滞在しており、修武場で本格的な稽古をうけるようになった。井上も鉄太郎のことを
気に入っていたみたいだ。
書道もはじめたのもこの高山時代で、師は書の大家であり、弘法大師流入木道(じゅぼくどう)
五十一世の岩佐一亭に学んだ。
入木道というのは、後漢の蔡邕から始まって、衛夫人から王羲之、智永、虞世南、張旭を経た
もので、弘法大師が入唐された際に韓方明から習い、帰朝後、嵯峨、淳和の両帝に伝えたとい
う。
その入木道では、「身心ともに忘れ、おのずから天地万物、一筆に帰するのが妙」がなければ
「書道を得た」とはいわない、とされている。後に鉄舟は、入木道五十二世を継承している。
剣と書に明け暮れる日々が続いたのだが、嘉永四年に母の磯が亡くなり、翌年にも父の高福が
高山で亡くなってしまい、鉄太郎は葬儀をすませて高山を去り、弟たちを連れて異母兄の鶴次
郎のもとに身を寄せる。
江戸に戻った鉄太郎は、剣の師の井上八郎の師である千葉周作の玄武館に入門する。
この頃の鉄太郎は、道を歩いていてもどこかで竹刀の音がすれば、すぐに飛び込んで試合を申
し入れていたという。周囲は呆れて「鬼鉄」とあだ名するようになる。
さらにこの頃には、槍の達人である刃心流(じんしんりゅう)の山岡静山にめぐりあい、深い影
響をうけることになる。
静山は、ボロ鉄とあだ名されていた鉄舟と同様に貧乏だったが、「人となり剛直、阿(おもね)
らず、質朴を重んじ気節を尚(たっと)び、人倫に篤い」とされ、その人柄を慕って食客がたく
さんいたという。まるで晩年の鉄舟みたいだ。
しかし、静山が若死してしまい、望まれて山岡家の養子となり、静山の妹の英子と結婚する。
静山の実弟が「幕末三舟」のひとりであり、高橋家へ養子に行っていた高橋泥舟。
そして、禅と本格的に出会ったのもこの頃であり(以前から興味を持っていた)、願翁、星定等
の諸禅師に参じ、最後に天竜の滴水禅師に参じた。
安政の大獄の頃の鉄舟は、清河八郎らと虎の会(尊王攘夷の秘密結社)をつくり、さらに幕府が
募集した浪士組の取締役となり京都にのぼろうとするが、浪士組の分裂ですぐに江戸に帰り、
何度も挑んでも手も足も出なかった、一刀流の達人である浅利又七朗に出会う。
そしてこの頃に、「鉄舟浮水上」の句に因んで、「鉄舟 山岡高歩」と署名している。
鉄舟は幾日も浅利の幻影に悩まされていたが、ある商人と滴水禅師からヒントを得て、剣禅一
如を見出してから浅利を凌駕するようになる。
大政奉還から戊辰戦争にかけては、精鋭隊歩兵頭取格や若年寄格として過ごし、その間に冒頭
で言及した通り、駿府での談判をこなした。
維新後は、静岡、茨城、伊万里での要職を歴任し、明治五(一八七二)年に宮内侍従となり、
以後、十年間、明治天皇の側近として宮内省につとめた。
しかし、宮内省つとめが終わっても、天皇の特命によって終身宮内省御用掛の身分にはあっ
た。
明治十三(一八八〇)年の四十五歳の時に、滴水和尚の印可を受け、剣も無敵となり一刀流正伝
を継ぎ、無刀流の一派を開く。
廃仏毀釈が吹き荒れる中、仏教再興にも尽力し、明治二十一(一八八八)年には、紀元節に最後
の参内をし、従三位を贈られる。その一カ月後の七月十九日に、坐禅のまま大往生を遂げる。
行年五十三歳。
かなり抜かした箇所もあるけど(詳しく知りたい方は『山岡鉄舟』小島英記がおすすめ)、ざっ
と鉄舟の生涯を追うと、やはり鍛えに鍛えた結果、身命を賭して官軍陣地を突破したことがよ
くわかる。(当然のことだけど)
本書『剣禅話』は三部構成になっており、大悟して無刀流を開くにいたる経過を記しているの
が「剣法と禅理」などの明治十三年以後の剣法論、二十歳代に書いた文章を集めた修養論、
維新渦中における記録「西郷氏と応接之記」などからなっている維新覚書。
「剣法と禅理」では、何度も手も足も出なかった浅利とのくだりが記されている。
浅利をこえられず、その秘訣を知ることができないでいた鉄舟は、以前から滴水禅師に、
「剣法と禅理とは一つのものではないか」という考えをくわしく述べていた。
すると滴水禅師は、
「おまえのいうことは正しい。しかし、自分らの考え方にしたがって遠慮のないところを批評
するとすれば、現在のおまえは眼鏡を通して物を見ているようなものだ。
たしかにレンズは透き通っているから、さほど視力を弱めることはないとはいえる。
しかし、もともと肉眼になんの欠点もない人は、どんなによいレンズであろうとも、
ふつう物を見るときには使う必要がないばかりか、使うことが変則であり、使わないのが自然
というものなのだ。現在のおまえは、このことを問題とするところにまで進んできている。
もし眼鏡という障害物を取り去ることができるならば、たちまち望みどおりの極致に到達でき
るにちがいない。ましておまえは、剣と禅との二つの道ともに進境いちぢるしい人物である。
いったんはっきりと道のあるところを悟ったならば、殺活自在神通遊化ともいうべき境地にい
たるのはわけないことであろう」
さらに、「つまるところ無という一字に尽きる」と励まされ、ヒントをもらっていた。
それ以来、長い間「無」の公案について取り組みつづけていたが、釈然とせず理解することが
できずにいた。そこで再び、鉄舟は滴水禅師のもとに赴き、自分の考えを述べたが、滴水禅師
はそんな鉄舟に対して、また公案を授けることになった。
それは、「両刃、鋒(ほこ)を交えて避くるを須いず、好手還りて火裏の蓮に同じ。宛然おのず
から衝天の気あり」というものであり、この公案についてよく考えろといわれる。
鉄舟はこの公案に心を惹かれ、太帯に自分で書きつけて忘れないようにし、あれこれと考えて
三年の月日が過ぎていた。
そんな時に、偶然にも商人が鉄舟の書がほしいと訪ねてきて、興味深いはなしを聞くことにな
る。
その商人は、
「・・・思いきって大きな商売をやってやろうというときに、勝ち負けや損得にびくびくしていて
は、商売にならぬものだとわかったのです。
つまり、これは必ず儲かるぞと思ってしまうと、ドキドキするし、損をするのじゃないかと思
うと、自分のからだが縮むような気分になるのです。
そこでわたしは、こんなことで心配しているようではとても大事業なんかできっこないのだと
思いなおし、それからというものは、たとえどんなことを計画するにしても、まず自分の心が
しっかりしているときにとくと思い定めておき、いざ仕事にとりかかったときには、
あれこれはいっさい考えないようにして、どしどし実行することにしてきたのであります。
その後は、損得は別にして、まず一人前の商人になれたものと思って今日までやってきたわけ
です」
という話をする。
この話を聞いた鉄舟は、滴水禅師が示した「両刃鋒を交えて避くるを須いず」という公案の語
句と照らし合わせ、さらに、自分の剣道と関連させて考えてみると、真理を感じたという。
そして、その翌日から昼は剣の稽古に励み、夜は沈思精考するというのを繰り返していたら、
ある時突然に、天地の間には何物もないのだという心境になっている自分の存在を感じ、
そのまま、浅利に向かうように剣を振り、試合をしている姿勢をとってみた。
すると、それまでとはちがい、いつも鉄舟の剣の前に立ちはだかる浅利の幻影が見えなくなっ
ていた。
鉄舟は「俺はついに無敵の極致に立ったのだ!」と感激して、そのまま門人の籠手田安定を呼び
寄せ、木刀を手にして試合をする。
試合が始まると直ぐに籠手田は、鉄舟の今までとは違う雰囲気を感じ、「勘弁してください」
と叫び、驚嘆の表情を示して白旗をあげる。
そして、次に浅利との試合を申し込み、浅利は喜んで受けいれた。
そこでも木刀を構え対すると直ぐに、木刀を捨て、面具をはずし、改まって次のように言っ
た。
「ついにやりましたね!これまでのところとは段ちがいの腕前です。
わたしといえどもかなうものではありません。秘伝を授けるのが当然というべきです」
伊藤一刀斎の「無想剣」の極意は、こうして鉄舟に伝えられたという。
冒頭で引用した漢詩が、その時の心境をあらわしている。
その後も鉄舟は、無刀流の一派を立てて有志の人士に伝授しようとし、次のように記してい
る。
「わたしの剣法はただ技術を重視するものではない。
精神のはたらきの極限にまで自分自身がつき進んで行くことだけを目標にしている。
いい換えれば、天道の発する本源というものをつかみ、同時にその正しい活用方法を追究して
ゆくことを願うのである。
一言にしていえば、見性悟道、つまり妄想を捨てて悟りを開くということである。その他にこ
とばを知らぬ。それは剣の修行にかぎったことではない。
古人はいっている―業はつとめれば明らかになり、さらにつとめれば必ず極意を得る―と。
道を学ぶ人よ、請う、怠るなかれ」
それは、別の「剣法論」の箇所でも述べられているが、
心の外に刀をおかないことであり、心をとどめないことであり、優劣の考えをもたないこと。
自然の流れに逆らわず、心の眼で見ることなど。
「軍(いくさ)の陣にのぞむ、大政に参与する、外交に当たる、教育宗教のことに従う、
商工農作に従事するなどのような場合に、すべてこの考え方をもって対すれば、
不可能ということなどあり得ないであろう」
勝海舟と同じ事を論じている。
「修養論」では、「武士道」を高らかに宣言している。
「わが国の人びととのあいだには、一種微妙な道の思想がある。
それは神道や儒教ではなく、また仏教でもなく、その三道が融和してできた思想であって、
中古の時代から主として武士の階層においていちじるしく発達してきたのである。
わたしはこの思想を武士道と呼ぶ。しかし、この思想が文書としてまとめられたり体系化され
て伝えられているものは、これまでに一度も見たことがなかった・・・」
巷ではたまに、鉄舟が「武士道」ということばを最初に使ったという説が唱えられているみた
いだが、『甲陽軍艦』という説もあることは認識している。
まあ、なんでもいいんだけれど、体系化してまとめたのは鉄舟ということだろう。
「修養論」の中から目に留まった言葉を拾ってみたい。
「わたしが剣法を学ぶのは、ただ心胆練磨の術を積み、心を明らかなものにすることによっ
て、自分もまた天地と同根一体なのだという理を釈然と理解できる境地に到達したいという目
的がある」
「水源のない流れはすぐに涸れてしまうものだし、根のない樹木は、まっすぐに立っていられ
ない。あわてふためいて決意したところで、それはそのときだけの幻影にすぎず、それが永く
続くわけはあり得ないではないか」
「明治十三年三月三十日、この日わたしは、剣と禅との二道において悟るところがあった。
そして何ごとでも本質は同じなのだとわかったので、書の筆意にも変化が生じた」
「一つ質問してみるが、貴様たちのいう「高尚の君子」とはいったい何者だ。
悪知恵ばかり達者でくどくどと理屈を並べたて、金銀財貨を貯めこんで他人を見下し、
勲章を飾りつけて豪勢な邸宅に住まい、美女を囲い、当世流の才士を傍らにつけおき、
山海の珍味を並べて美酒をあおり、西洋文明さまさまともてはやし、アメリカの自由がよいな
どとほざき、眉をあげ髪を撫でて気取りながら、アジアの堯・舜・禹・湯・文・武・周公・孔子・釈迦
の名をあげては、「こんな連中に西洋の文明がわかってたまるものかネエ」などと放言する、
おそらくはそのような者どものことであろう」
鉄舟は、死が翌年に迫った明治二十年に自邸で、門人の籠手田安定に頼まれて、四回にわたり
武士道の講義をしている。
そこに集まったのは、教育勅語の起案者である井上毅や、フランス人法学者のポアソナード、
文学博士の中村正直、陸軍少将の山川浩らがいた。
特に井上毅は毎回聴講しており、教育勅語の前段が鉄舟の講話と酷似しているので、その関係
性が云々とされていると、大森曹玄の『山岡鉄舟』で指摘されている。
「維新覚書」では、西郷との面会や彰義隊を率いていた覚王院のこと、朝廷に奉士する事など
が記されている。
維新後に、幕臣でありながら天皇に奉士したときに「不埒だ」などと周りから罵られるが、
鉄舟は、「是れ恰も仏教の小乗を知りて未だ大乗の何物たるを知らざるものゝ如きのみ」
と喝破しているのも愉快だった。
時代が移り変わり、廃仏毀釈が吹き荒れる中、鉄舟は仏教再興に尽力する。
特に、維新の際に国事に殉じた志士たちを弔うために、谷中に全生庵を建立したのは有名な話
だ。鉄舟もそこに埋葬されている。

全生庵にある鉄舟の墓
「・・・わしは禅を仏教の根源だと信じているので、その根源の強く、深く張られることを祈って
いるのだ。禅に形式的な盛大さを求めて、却ってその真精神を失うことを惧れているのだ」
明治十九年頃から、大蔵経の筆写を発願し、芝、増上寺の朝鮮版蔵経を借用して、毎晩のよう
に怠らず写経をし、午前二時頃までに及んだ、という話も残っている。
鉄舟は、十三歳の頃に父から
「人荀も斯道(忠孝の道)を極めんと欲せば、形に武芸を講じ、心に禅理を修練すること第一の
肝要なりと仰せられた」として、「故に余は、爾後斯の二道に心を潜めんと欲するに至った」
と記している。
勝海舟はこのことを評しているが、
「彼の特性は前もいう如く、長者のいう事は、真正直に之を信ずるというのが彼の彼たる所
だ。一概にものを信ずるとすれば、頗る不利なるものだということは世間普通の流言だが、
それはまだ信じようが中途だから、否、偽信だから真の的には中らぬわい」
と論じている。大変律儀な人で、世界でも稀で唯一無二の存在が山岡鉄舟。
坂本龍馬と同い歳で、あらゆる面で対極に位置しているのが、また面白い。
その他にも、清水の次郎長や円朝との関係、明治天皇との関係や、西郷隆盛の征韓論と鉄舟と
の関係、大往生を遂げる間際の勝海舟とのやりとり、近代以降鉄舟がどのように捉えられてき
たか、などには触れなかったけれど、決定版と銘打っている小島英記の『山岡鉄舟』が豊富に
論じられていてかなり参考になる。
最近の日本人は右往左往してダメだよ。沈思熟考した鉄舟の真髄を吸収して「呼吸」したい。
鉄舟と直接対話したいのであれば、『剣禅話』、
禅を案内として鉄舟を掴みたいのであれば、大森曹玄の『山岡鉄舟』、
時代や人物との関係などから詳しく鉄舟を掴みたいのであれば、小島英記の『山岡鉄舟』。