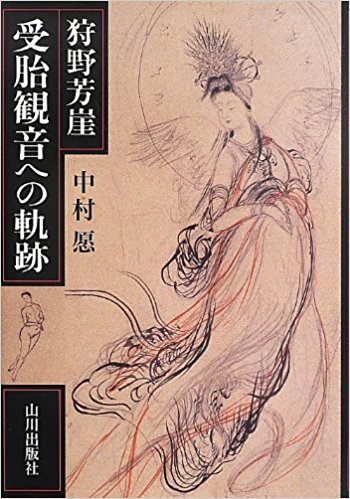
翁[芳崖]は画理[画の理論]を以て天地万物の真理を発明[表現]せんと試み、
仏家禅僧の妙悟[さとり]、儒道西哲[儒教・道教・西洋哲学]の深旨[深い道理]、
総て丹青鏡裏[絵画のなか]に昭映[うつし出]して其意義を判じ得失を論じ、
仁義道徳の大道、坐臥進退の庸行[日常の行ない]に至るまで尽く画訣となせり。
『狩野芳崖』 岡倉覚三
芳崖の新画風のごときも鎖国時代の日本画から世界の日本画へゆく一つの
道標であつたとも思われる。
『狩野芳崖について』(昭和十七年) 河北倫明
絵画に従事するもの宜しく先づ自己の志操を高尚にし、然る後、其技術を研究すべし。
狩野芳崖
本書は、その偉大な画師芳崖の伝記として、
さらに岡倉覚三(天心)の弱年の軌跡を追い、フェノロサ伝説を見直し、
覚三を受け入れ芳崖の〈受胎観音〉の被写体にもなった九鬼隆一夫人の初子もめぐり、
これらの人びとが交差する地点に、至宝と呼ばれている〈悲母観音〉が生み出され、
その先にある未完の〈受胎観音(下絵画稿)〉へ至る過程を克明に綴っている。
「岡倉覚三 生誕150年記念出版」と題して刊行されたもので、帯は金色になっている。
(今はどうだか知らないが)
多面的でもあるし、著者の独断も複数あると思われるが、素晴らしい著作となっている。
著者は中国学がご専門で、関連する著作も多数残しているみたいだ。
本書ではそれが随所にあらわれていて魅力が増している。

狩野芳崖 (1828~1888)
狩野芳崖は文政十一年(一八二八)に長門国長府の城下町で生まれた。(現在の下関市長府)
狩野家は数代前から、外様大名毛利候のお抱え絵師として禄を食んでいた。
祖父察信(あきのぶ)、伯父俊信(としのぶ)、父陽信(あきのぶ)(号は晴皐)は、
徳川幕府直属の奥絵師四家のひとつ木挽町狩野家(江戸日本橋)の画所でまなび、
祖父は法橋(ほっきょう)、狩野派の名取りになった実力者だった。
そんな環境のなか、幼い頃の芳崖は、厳しくもおおらかな父と、ゆかしい母の慈愛によって
育てられた。
著者は「晩年に、万物を生み育てる理想的な母としての観音菩薩を画いたのは、そこに由来し
ているに違いない」と述べている。
七、八歳になると藩校・敬業館(けいぎょうかん)に通うようになる。
そこでは素読を通して『論語』などの四書五経を学び、そしてこの頃から、父の晴皐から狩野
派画師の跡継ぎになるため画技を学ぶ。
その画技とは、橋本雅邦が述べているが「狩野派画学の順序は臨写を以て初め、臨写を以て終
わるもの」で、初めは簡単な瓜や茄子など画くことからはじまり、数年はただ臨写(先人の画や
模本・粉本を模写する)して用筆(筆の使い方)のみを訓練する。
父から与えられた最初期の手本の原画は雪舟だった。
さらに、この頃に父から“画の六法”を学んだ、と著者は予想されている。
画の六法
一、気韻生動(すぐれた精神が生き生きと脈動する)
二、骨法用筆(力強い骨格を形づくる用筆)
三、応物象形(対象に応じて形をうつす)
四、随類賦彩(対象にしたがって彩色する)
五、経営位置(しっかりした画面の構成)
六、伝模移写(伝統を伝えるための模写)
青木正児は「香」、渡辺崋山は「音」がするものとしている。
雪舟は享徳(一四五四)年の備中(岡山)生まれだが、京都から大内氏をたより山口にやって
くる。
大内氏のはからいで、中国に渡り水墨画の技法を学び、帰国後は日本各地を転々とし、
最終的に山口に落ち着く。(没するまで)
代々の狩野派が、中国北宗画の祖として雪舟を崇めていたが、芳崖はそれ以上に雪舟画の模写
に打ち込んでいる。土地柄が影響しているだろう。
父の晴皐は雪舟を忠実に模写したと考えられているが、芳崖は所々微妙に変化させている、
といわれている。
後年に芳崖は「夫(それ)絵画の術たる規矩縄墨を以て法を定むべきに非ず」と述べている。
長府の毛利家は代々能楽を大事にしており、芳崖も十四歳の時に〈翁図〉を画いているし、
晩年には、宝生流能楽師松本金太郎(甥に泉鏡花)に舞の指導を受けている。
芳崖十代の作品は、ほとんど臨写したもので、ほかには人物画、花鳥画、山水画、馬画などを
画いている。
そして十五歳のころから、菩提寺である覚苑寺の如沢和尚(黄檗宗)について参禅したといわれ
ていて、著者は「弱年における参禅体験は、絶筆〈悲母観音〉創作にいたる貴重な第一歩だっ
た」と述べている。
十九歳の時(弘化三年一八四六)に、江戸での十年間の藩費留学が認められ、
日本橋木挽町、諏訪因幡守(いなばのかみ)の屋敷隣りにあった狩野晴川院養信(せいせんいんお
きのぶ)の画所で学ぶ。そこでは、偶然にも同日入門したなかに橋本雅邦もいた。
晴川院はかつて芳崖の父晴皐の師でもあり、江戸狩野の中心となる奥絵師四家(鍛冶橋宗家・
木挽町・中橋家・浜町家)のなかでも、木挽町晴川院はもっとも勢力があり、塾生は五、六十人
をくだらなかった、といわれている。
しかし、芳崖らが入門して一ヵ月にして晴川院は病没してしまい、二十代の嗣子勝川院雅信
(しょうせんいんただのぶ)が跡を継ぐ。
そこでの芳崖と雅邦は、“勝川院の龍虎”と称されていた。
さらに面白いのは、入門して数年後に佐久間象山の知遇を得て、人格・知識・視野の広さなど
に影響を受けていること。
道一本へだてた向かいに象山塾があり、象山も芳崖を面白がったらしい。
著者は象山の「余、二十以後乃ち匹夫にして一国に繋(かか)ることあるを知る。…」
を芳崖に当て嵌めて考察している。
勝川院での芳崖は、伝統的一枚物の臨写に精力的にはげみ、現在、東京藝術大学に所蔵されて
いる。
特に“見覚えがき”(臨写する模本を一定時間眺め、数日後に思い出しながら描かせるという
稽古)がずばぬけて優秀だった。
当時の弟子頭で勝川院の顧問格だった三村晴山は芳崖の画を
「画中の人物・動物、画布の中より脱出するの感あり、逸群の気象あり」と評価している。
その晴山は松代藩お側絵師で、父晴皐の同期生だった。
芳崖は研鑽の日々をおくり、嘉永二年(一八四九)に師匠の一字を拝領して「勝海」と号し、
翌年には弟子頭を命じられる。
弟子頭は古画を鑑定し、証明書を発行する任務もあった。
ペリー来航前年の嘉永五年(一八五二)、芳崖二十五歳の時に修業を終え、長府藩から三十石を
給付されお抱え絵師となり、狩野派に属しているが、独立した画家になる。
江戸狩野の絵画精神と画技の堕落を痛感もし、その克服も模索しはじめる。
自由の身となり、拘束されることなく、江戸と長府を往き来もしている。
著者は「狩野芳崖にとって二十代が“古画臨写の時代”、三十代は“仏画と肖像画の時代”、
四十代は“山水画の時代”」と区分けしている。別の言い方では象山を意識し
「藩から日本国へ、日本国から海外の五大州世界へ、そしてさらには宇宙的な宗教心へ」
としている。

月夜山水図 1857年 (安政四)

鏻姫像 1860年 (安政七年)
しかし現実に生きるかれにとっては、安政四年(一八五七年、三十歳)から明治九年
(一八七六年、四十九歳)にいたる二十年間というものは、見通しのきかない貧窮と政治的激変
に見舞われるなかで、それでも止むことのない絵画創作への欲求を圧しきれずに苦悶する日々
がつづいた。
母が病没し、晴山がコレラで急逝し、松蔭が処刑され、象山が暗殺され……
やがて芳崖自身もまた貧苦のうちに肺病を病んだ。
のちに顧みれば、人生の三分の一を費やした長いながい逼塞の年月であった。
『狩野芳崖 受胎観音への軌跡』中村愿
その頃の心境を詠った歌も残されている。
苦しくも照る日に熱く成る石の
やがてぞ雪の降りもつもるか
めぐり遇わんごと笛の音の澄上る
嵯峨野の奥の秋の夜の月
我妹が待ちつつあればいといなん
田町の森にひぐらし鳴くも
妹と我と見れば長閑(のど)けし隅田川
堤の桜いまだ咲かずも
芳崖の養子廣崖(こうがい)は「父は晩年万葉の古調を愛し多く無調をとられたり」
と述べている。
維新によって大名家のお抱え画師は職を離れ困窮し、狩野家も没落。
長い不遇の時代を経験する。
この頃のことは、上述で著者の言を引用し割愛させていただくが、
芳崖は各地を旅し、思案し山水画や仏教画などの傑作を残す。
明治十年(一八七七)芳崖五十歳、妻子と姉を引き連れ、故郷長府に別れを告げ上京する。
生活は変わらず困窮していたが、明治十二年(一八七九)に転機が訪れる。
旧薩摩藩主・島津邸に明治天皇が行幸するに際し(大河ドラマ『翔ぶが如く』でもその場面が
少し描かれている)、島津家では古式の犬追物を余興にしていて、その絵巻物の制作を橋本雅邦
に依頼したが、雅邦はこれを辞し、芳崖に譲る。
月俸数十円、三年あまり、島津家に雇われることになる。
そしてこの時期に、日本近代美術史にとって重要な、
文部省入省前の岡倉覚三[天心](十六、七歳)と狩野芳崖(五十一、二歳)が出逢う。
著者は明治十二、三年ごろだと推測されている。覚三(天心)の甥の覚平(のち秋水)が、
明治十三年に芳崖のもとで画の修業を始めているからだとしている。
ちなみに、フェノロサが東京大学のお雇い教師として日本にやってきたのは、
明治十一年(一八七八)八月。他の七人の生徒とともに十六歳の覚三(天心)もいた。
そして、明治十三年の秋ごろ、覚三(天心)は芳崖をフェノロサに紹介する。
フェノロサはこの頃懸命に狩野派を研究していたみたいだ。(息子の名前もカノーとしている)
フェノロサは、誰よりも早く日本古美術を蒐集したいという自己の思惑を胸中に秘めたまま、
来日後懸命に学んだ日本美術の知識を駆使して、大官たちや画工・民衆に日本美術再興の
意義を宣伝した。
いっぽうビゲローはフェノロサの思惑に協力しつつも、岡倉が推し進めてゆく日本美術の
再創造運動に深く共鳴して、惜しげもなく資金を提供しつづけたのである。
『狩野芳崖 受胎観音への軌跡』中村愿
としているが、通説であり崇められている“フェノロサ伝説”を指摘・批判もしている。
1、フェノロサは、岡倉覚三の藝術的感性にあふれた通訳と翻訳によって日本古美術の世界
を識り、のめり込んでいった。
岡倉がフェノロサの影響をうけて日本美術復興に覚醒した、というのは伝説である。
2、龍池会での「美術真説」講演は、文部省の美術戦略にしたがってフェノロサが代弁者とな
り、日本美術振興、美術学校設立などについて話したものであり、その筆記録として刊行
された『美術真説』は、同講演にさらに文部省や龍池会の主張を加筆・整理して出版され
たものである。
したがって、それをフェノロサの美術論とするのは伝説である。
3、フェノロサが狩野永悳から永探(えんたん)理信(まさのぶ)の名と鑑定免許証を与えられた、
というのも伝説である。事実はフェノロサが要求して、手に入れたものである。
龍池会というのは、美術工藝振興を目的として、明治十二年三月不忍池の畔で結成された、
古美術品評会を中心とした半官半民の組織。
明治初年から廃仏毀釈の影響で、奈良や京都で日本美術、名画や仏像などが二束三文で売却
されるなど、脱亜入欧の欧風化が激しかった。そんな時に設立された保守的な組織。
ちなみに、フェノロサは日本の古美術品をひそかに購入し、勝手に海外に持ち出してもいた
みたいだ。著者は岡倉あってのフェノロサだったと指摘している。
長くなりすぎるので割愛するが、その後は、
芳崖は覚三の批評や示唆に耳をかたむけつつ、作品を制作しはじめる。
芳崖の妙想と画術、覚三の英知と芸術的先見の明が、その後の芳崖の少なからぬ作品を
生んでいく。
『狩野芳崖 受胎観音への軌跡』中村愿

懸涯山水図 1882年 (明治十五)

岩石 1887年 (明治二十)

暁霧山水図 1887年 (明治二十)

伏龍羅漢図 1885年 (明治十八)

仁王捉鬼図 1886年 (明治十九)
そして、「観音」を描くようになり、絶筆で至宝〈悲母観音〉(明治二十一年十一月)に
辿りつく。

悲母観音 1888年 (明治二十一)
その頃の芳崖と覚三の対話が残されている。
芳崖 去年、新治が逝ってから体調がよくない。
三年たらずの命だった……。よしも病がちで、寝こむことが多くなった。
覚三 翁(せんせい)は、〈仁王捉鬼図〉の制作で、お疲れになられたのでは。
芳崖 ははは、なんの……。そのまえに〈飛龍戯児図〉を描いた。
あれは母子(おやこ)だが、新治とわしの戯れでもある。フェノロサが持っていった
が……。
先日は〈観音〉の下図を取りだして、よしと日がな一日ながめていた。
あの児は新治なんだ。
(中略)
芳崖 『観音経』は、観音菩薩を礼拝・供養すれば、男をのぞむと男の児が、
女が欲しければ可愛いい女の児が生まれるという。新治は死ぬのがはやすぎた。
廣崖には、つぎができたらしいが……。
よしはあいかわらず毎日、〈准胝観音〉を拝んでおる。
覚三 翁(せんせい)はいつも「観音」の妙想をふかめておられます。
芳崖 〈観音〉の男顔が、どうも気にかかる。
覚三 支那の観音は宋のころから女顔になり、明は女そのものであります。
芳崖 うむ……元信の〈白衣観音像〉も女顔に近いな。
祈れば、女人も成仏できる画を創りたい。
覚三 成仏より……人はまず誕生します。西洋の宗教画で「受胎告知」という題材が
あります。
妊った聖母のまえに翼をもった天使が降りたち、あなたは神の子をさずかったと告げる
のです。
芳崖 児を孕んだ聖母の画……。
覚三 十月から一か年、欧米の美術事情を視察に行ってまいります。
美術館や教会で、よく見てまいりましょう。
芳崖 ああ、西洋の新しい絵の具も欲しいな…。
明治二十年(一八八七)に芳崖は、妊娠六ヵ月の初子[波津子](九鬼隆一男爵夫人で、覚三とは
不倫関係だった)の裸体を描写し、〈受胎観音〉として描こうとして、技巧面において、
それが〈悲母観音〉にまで繋がっている、と著者は述べている。
狩野芳崖の最後の傑作は、普遍的なる母、観音を、人間の母性の姿に描いているものである。
彼女は中空に立ち、その三重の背光は金色にかがやく清浄の空に消え、その手には水晶の瓶を
持ち、それからは創造の水が滴り落ちている。
その一滴は、落ちながら一人の赤子となり、赤子は雨雲のごとき産衣に包まれて、無心の目を
彼女に上げながら、はるか下方、蒼暗の霧の中から聳える大地に突兀たる雪の峯に向かって、
漂い降っていく。
この絵においては、藤原時代のそれのごとき色彩の力が円山派の優美さと合して、
熱情的で写実的であると同時に神秘的で敬虔な自然の解釈に表現を与えているのである。
明治二十一年(一八八八)十一月五日、狩野芳崖、病没。享年六十一。
芳崖没後七年に法要がいとなまれ、天心は、厨子のうちに〈悲母観音〉を飾り、香を焚き、
経をあげて祀った。
割愛した箇所もかなりあるが(初子のことなど)、詳しく知りたい方は、是非本書を。
藝術はつねに宗教と結びついている。藝術の最大の達成は宗教思想の装いの中にあった。
……しかし実際は、藝術は宗教の圏外にある別の独立した存在である。……
しかし、人生と藝術はいつも互いに関係があった。
藝術は人生という幹をとりまく葡萄であり、宗教は、森の中のみごとな大樹のように、
藝術をしてもっとも有効な方向により高く、その栄光を輝かせることを可能とする。
こうして宗教は藝術の歴史における最も重要な要因となる。
……東洋はもし宗教でなければ何も無い。
岡倉天心
嗚呼、宗教なくして美術を得(う)るべき、……
岡倉天心
「自己の志操を高尚にし、然る後、其技術を研究」
した芳崖は、生涯「擬」を追求し、創発させた。




