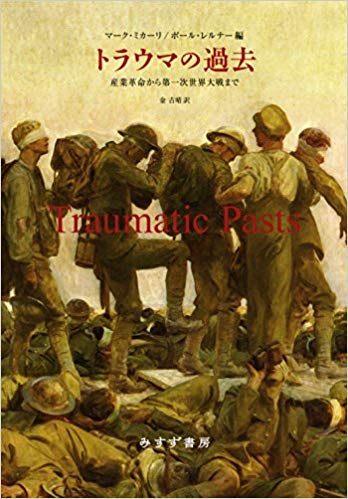
本書の目的はトラウマについての歴史的な新しい研究成果の最良のものを幅広く選び出して提
供することである。そのことによって、トラウマの研究が、実証的、分析的、概念的、方法論
的な問題を提示したい。
『トラウマの過去』マーク・ミカーリ・ポール・レルナー (編集)
本書の中心となるのは、イギリス、フランス、イタリア、アメリカにおいてトラウマが社会と
いう集団によってどのように経験されてきたのかについての11の事例検証的な論文。
近代化の悪影響が明らかとなった一八七〇年から一九三〇年頃を扱っている。
全体としては四つの別々のエピソードを通じて、心理的トラウマが政治的、文化的、医学的、
そして軍事的にどのような扱われてきたのか、それらがどのように重なり合ったのかを示して
いる。
そのエピソードは、一九世紀最後の四半世紀における鉄道網の発展、一八八〇年代に開始され
た損害保険と早期社会保障制度、世紀の変わり目における心理学的精神医学の出現、第一次世
界大戦とその社会的、文化的な後遺症など。
「本書はトラウマ的な経験とその受容の仕方が、国ごとにどのような歴史的、文化的な文脈の
中で形成されたのかを浮き彫りにしている」(本書)
「われわれは「トラウマの歴史」を書くことによって、過去に意味を持っていた言葉を発見
し、再発見し、再構築しようと考えている」(本書)
一九世紀ビクトリア朝期のイギリスでは、蒸気機関(鉄道)が経済の拡大と社会の進歩を体現
し、その世紀の象徴であった。
しかし、危険とも隣り合わせでもあり、ほんの些細な過失から事故が生じることもあった。
鉄道事故の件数と犠牲者の数が急増すると、その衝撃とともにトラウマをもたらすことが多
く、鉄道事故はビクトリア朝のひとつの主要なテーマとなり、多くの新しい不可解な症状を生
み出した。
一八六四年には、鉄道会社に乗客の健康と安全に責任を持たせる法令が議会を通過すると、医
師、法律家、保険会社の専門家たちが、新しい状態の性質、原因、予後について、激しい議論
を戦わせた。
一八六六年、ロンドン大学病院の外科学教授であった、ジョン・エリック・エリクゼンは、
「鉄道脊髄症 railway spine」と名づけた七症例について連続講演をし、それを『鉄道とその
他の事故による神経系の損傷について』として公刊した。
エリクゼンはその本で、こうした症例を「脊髄震盪症 spinal concussion」と考え、その原因
は事故による物理的な振動による衝撃と、鉄道旅行の持つ特異な性質であると考えた。
このエリクゼンの「鉄道脊髄症」という概念によって、心理的トラウマ後の諸症状が初めてま
とまって提示され、単一の診断名を与えられ、病因も単一であると認められたという。
エリクゼンについては、トラウマの歴史を扱った本の中で言及されることがある。
そして、一八八〇年代前半のエリクゼンの著作が引き金となって、事故後に生じる症状につい
ての多くの著作が出版されるようになり、やがて脊髄と脳に代わって精神が主要な病理の場所
として考えられるようになったという。さらには、この病態を巡る経済的、法的な要求は高ま
っていった。

ジョン・エリック・エリクゼン
アメリカでは、一九世紀後半の二〇年間、医師たちがトラウマ後の症状形成に関して、起源、
性質、発展などを論じていた。
アメリカの臨床家たちは、理論的な支えをヨーロッパの理論家(シャルコーやベルンハイム)に
求めることが多く、アメリカの精神療法にはフロイト以外の起源があり、一八八〇年代と九〇
年代に「鉄道脊髄症」を観察し、理論家し、治療したことが、近代的な精神療法の発展に決定
的な貢献をしたという。
アメリカについては別の章で、一九世紀末と二〇世紀初頭のアメリカ医学界を取り上げ、女性
の性的トラウマが公式に論じられていないことも指摘されている。
レイプ、夫婦間のレイプ、自傷によるものを含めた性器への虐待、などの悲惨な症例報告が理
論化されることはなく、医師たちは症例を共感的に記録することもあれば、無関心を装って記
録することもあった。
どちらの場合も、女性患者の苦しみよりも社会における性的役割の方を憂慮していた、という
点は変わらなかったという。
しかしそんな状況の中、ボストンを基盤とした精神分析的治療家のL・ユージーン・エマーソン
は公平に評価していたという。
ドイツでは、鉄血宰相ビスマルクの先駆的な国家賠償法が一八八〇年代に成立すると、
帝国保健局は「トラウマ神経症 traumatische Neurosen」の存在を認め、新しく制定された
勤労者の補償の立法による受給対象に含めた。
それは、社会民主運動による社会革命を防ぐための措置として行われたものだった。
以来、ドイツではトラウマは生産と調和、効率へのい広い懸念ととも語られるようになり、
全体としての社会福祉とその有害な影響をめぐる幅広い議論が繰り広げられたという。
当時、心理的トラウマによって実際に補償を要求する患者の数は少なかったにもかかわらず、
医師らは「賠償ヒステリー」が疫病のごとくに広まっていると宣言し、事故の病理的な作用で
はなく、勤労者の強欲と怠惰がその原因であると非難している。
一八九五年には、神経学者のアドルフ・ストゥリュンペルが神経症の症状の原因を説明するため
に、「想像による欲求 Begehrungsvorstellungen もしくは imaginative desires/願望コンプ
レックス wish complex」という概念を命名し、ドイツ語圏の新しい理論家たちはそれに言及
することが多くなった。
その後も、トラウマとその精神病理学的な影響の可能性はドイツの医学界で熱心に論じられ続
けていたが、その影響のひとつに、保険に関する近代の議論において、リスクと予測可能性と
いう概念が個人の精神にも適応されたことであった。
事故のリスクを予測の科学へと変容させ、それによって新しく生み出された市民像は、統計的
な性質を内在化させ、新しい「自己についての政治的な技術」にしたがって行動するというも
のであったという。
一九〇〇年をはさむ数十年は、トラウマを他の疾患と切り離し、医学心理学的に論じられるよ
うなっていたが、それはフロイトとジャネの影響による。
その二人ほど有名ではないが、トラウマの概念化にとって、重要な人物にフランス・パリの神経
学者ジャン―マルタン・シャルコーがいる。
シャルコーは、鉄道と職場の事故についての研究で世界的な関心を惹き、一八八〇年代、九〇
年代に出版した多くの症例をつうじて、「トラウマヒステリー hystérie traumatique」という
診断カテゴリーを提唱した。
さらにシャルコーは、トラウマを持った患者の治療を通じて、ヒステリーという名称を成人男
性勤労者にも用い、女性の精神および身体と関連するという古くからの考えに異を唱えた。

ジャン=マルタン・シャルコー
そのシャルコーの論敵でもあったのが、ドイツ系ユダヤ人の神経学者へルマン・オッペンハイ
ム。
オッペンハイムは、『トラウマ神経症 traumatischen Neurosen」(一八八九年)の出版によっ
て、シャルコーの雄弁な論敵となり、フランスとドイツの医学界のあいだの辛辣な論争に火を
つけたという。
オッペンハイムはシャルコーのヒステリーを伴った一連のトラウマ症例を批判し、
トラウマ的な出来事の直接的な神経病理学的な影響を軽視しており、患者の病的な願望と観念
を不当に強調しているとした。
さらにオッペンハイムは、シャルコーに対抗して独自の診断カテゴリーであるトラウマ神経症
を提唱し、そこに身体と心因的なメカニズムの両方を含めた。
しかし、この概念は一八九〇年代と第一次世界大戦中のドイツ精神医学からは敵意をもって迎
えられた。
オッペンハイムの理論は誤解され、賠償ヒステリーという「疫病」と関係しているとの非難を
受けたが、この「疫病」は、ワイマール時代の社会保険制度への批判から第一次世界大戦によ
る経済的疲弊に至る時代を通じて、ドイツ医学をひどく悩ませていたという。

へルマン・オッペンハイム
トラウマと精神医学のターニングポイントとなったのは、第一次世界大戦においてであった。
近代化された、かつてないほどの破壊力を持った兵器の破滅的な結果や、機械化された大量の
殺戮や塹壕の中の非人間的な状況を強いられたために、何十万人もの兵士に深刻な精神的破綻
が生じた。
戦争が始まって最初のクリスマスまでに、医師たちはヨーロッパの随所で、動員された兵士に
激しい震えや吃音、視覚、聴覚、歩行の障害が発症したことに驚き、これらの不可解な症状は
度重なる戦闘の衝撃と恐怖に関係しているのではないかと考え始めたという。
それ以前の臨床家たちは、成人・思春期の女性のヒステリーという問題に直面し、そうした患者
は主に家庭で発症し、民間人を対象とした病院や個人診療所で治療されていた。
しかし、戦争の勃発から戦後に至るまでに臨床家が直面したのは、労働者階級を中心とした成
人男性に大規模に生じた精神的な破綻だった。
そして、こうした事例を説明するためにさまざまな概念が提案されるようになった。
シェルショック(砲弾恐怖症)、戦争緊張症 war strain、ガス神経症 gas neurosis、
生き埋め神経症 buried alive neurosis、兵隊心臓症 soldier’s heaet、
戦争精神衰弱 war neurasthenia、不安神経症 anxiety neurosis、等々。
戦争と共に交戦中のすべての軍隊にシェルショックが広がり、心理的トラウマに関する議論は
新たな緊急性と重要性を帯びて再開された。
臨床家たちは身体因もしくは心因的な説明に引き裂かれたが、戦争の半ば頃には身体論者はほ
とんどみられなくなったという。
心因論者たちは、戦争捕虜や負傷者には驚くほどに神経症が少ないという証拠を集め、こうし
た病態は戦争のストレスと緊張に対する精神病理的な反応であると考えた。

ヨーロッパ中が戦争と経済力を貪欲に必要としたために、シェルショックの治療は国家的な関
心事となり、症状を説明・予防し、治療するためにさまざまな医師たちが動員された。
イギリスでは、古典的な戦争詩人たちの作品によって、影響力のある多くの学術的著作や芸術
作品が生み出され、歴史家の想像力もとらえているが、こうした事例は例外的であり、それの
みに依拠することは歴史記録を歪めてしまうと指摘する。
本書では、戦争神経症のさまざまな治療施設や治療方法をまとめ直している。
大戦の半ば頃までには、催眠、水浴法、「意識的な暗示」、説得、電気刺激が、手軽で効果的
な治療法であると考えられるようになっていた。
これらの治療法の多くが基礎を置いていた治療原理は暗示であった。
水浴や電流は直接の身体の影響によってではなく、威圧、詐術、狡知によって効果を挙げ、
地方や労働階級出身の歩兵であることの多かった患者たちへの、教育のある中級士官である医
師の支配力を強めていった。
しかし、すべてがそういった洗脳の舞台というわけでもなく、必要に応じて行われ、治療の転
帰もさまざまであったという。
変質学説と優生学説に影響を受けた、フランス、イタリア、ドイツの医師たちは、
トラウマ的な出来事の病因論的な衝撃よりも、精神疾患に対する個人の素因の方が勝ると考え
ていた。
こうした考え方は特にイタリアで強い影響力を持ち、当時のイタリアでは、精神医学の議論は
地域的、民族的な要因に支配されていた。
フランスでも医師たちは、シェルショックを意志の障害、臆病さ、遺伝的な脆弱性の表れだと
考えていた。
こうした考え方は、国の全体が、長期にわたって堕落、退廃、人口の減少、闘争心の喪失を恐
れていたことを表していた。
医師たちは「神経学的な愛国心 neurological patriotism」を抱いて傷病兵を診察し、国全体の
健康と勇猛さを守るために「ヒステリーに対する戦争」に従事しているかのように感じていた
という。
第一次世界大戦後には、精神と身体への破滅的な影響は、社会と文化にとって重要な関心事と
なっていた。
アメリカでは、一般市民のあいだで精神疾患の地位が大きく変化し、神経的、精神的に傷つい
た兵士たちは尊敬されるようになった。
戦後新しく作られた在郷軍人会は、精神疾患と精神健康の増進についての公式見解を形成し、
決定的な役割を果たした。
在郷軍人会は、神経的、精神的な傷病兵は、元々は普通の市民であり、愛国の義務を熱心に果
たした結果として苦しんでいる、と主張した。
この見解に基づいて、アメリカ政府は心理的トラウマを抱えた退役軍人の外来や入院治療費を
支払う法案を通過させた。
このような施策は同時に医師たちにも利益をもたらし、一般世論における医学の発言力を増加
させ、政府によって治療を要すると認められた患者集団を新しく作り出したという。
本書では、単一の普遍的なトラウマという概念に疑問を付し、いくつもの歴史的な事例研究を
通じて、概念の文化的、社会的な偶発性を提示している。
トラウマを研究できるのは、それが過去の特定の時代において被害者によって経験され、
科学的な指導者によって理論家され、社会集団によって解釈され、文化の中で表現されるかぎ
りにおいてである、としている。

精神医学のカテゴリーとしてのトラウマは、米国精神医学会(American Psychiatric
Association:APA)によって、一九八〇年に公式にPTSD(Posttraumatic stress disorder:外傷
後ストレス障害)として認められた。
PTSDという診断概念が打ち立てられたのは、ベトナム戦争の帰還兵のための精神医療の専門
家や一般の活動家の熱心なロビー活動の成果であり、ベトナム戦争では五万八千人以上の米兵
が死亡したが、帰国しても深刻な心理的な問題を抱えていた兵士の数はさらに多く、一説には
百万人ともいわれている。
PTSD診断はこうした兵士たちの精神的な苦悩と尊厳を認めることになり、共感と医療的関心
と賠償を(理論的には)保証した。
一九八四年には国立PTSDセンターの設置を可決し、退役軍人局の医療部門はトラウマ後の精
神状態の研究のためにアメリカ政府から巨額の研究費を得るようになった。
科学研究も急激に増加し、自伝的な報告も増えていったという。
一九九〇年以降は、トラウマ後の精神障害という考えは、戦争以外にも拡大し、自然災害、職
場での事故、家庭での虐待、その他、非常に苦しい感情をもたらすすべての種類の体験を含む
ようになっていった。
PTSDは二一世紀初頭の米国精神医学でもっとも急速に発展し、影響力を持つに至った診断だ
と指摘している。
そのような流れの中から『身体はトラウマを記憶する』のヴァン・デア・コークも出てきたとい
うことだろう。
本書は、トラウマの理解のためには歴史的な人間観がきわめて重要であるとの前提に立って書
かれている。
原題には、トラウマという概念についての過去の歴史という意味と、トラウマが社会の関心を
集めた過去の時代という意味の両方が込められている。
第1章で全体の概要が語られているので、時間が無い方はそこだけ読んでも有益。
戦略家のエドワード・ルトワックは、「戦争とは、探究であり、発見であり、テクノロジーの進
歩だ。これは、「トロイの木馬」の時代から不変の真理なのである」と語っているが、
医学の分野でもそういった一面があるのかもしれない。
トラウマの結果を認めなければ、社会の構造が台無しになりかねない。
人々が、戦争がもたらす害に直面するとことを拒み、「弱さ」に不寛容だったせいで、
一九三〇年代に世界中でファシズムと軍国主義の台頭に弾みがついた。(中略)
文化がトラウマ性ストレスの表現形式を決めるのだ。
『身体はトラウマを記憶する』ベッセル・ヴァン・デア・コーク


