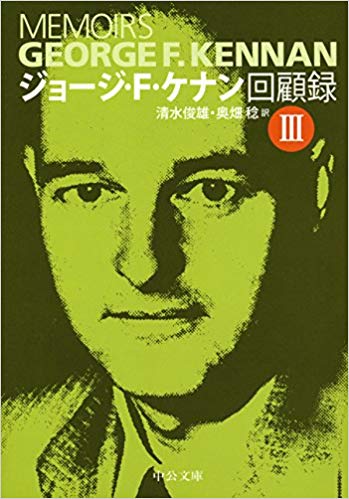
本書の目的は、これと対をなす上巻と同様に、
公共の事柄全般およびとくに外交についての考え方の発展を記述することにある。
『ジョージ・F・ケナン回顧録 Ⅲ』ジョージ・F・ケナン
本書第Ⅲ巻は、1950年~1963年までが収録されていて、朝鮮、極東、“マッカーシズム”などに
ついて語られている。
この頃のケナンは、国務省における任務を解かれ(外交官として政府の在籍者名簿には残ってい
たが)、プリンストン大学で学究生活を送りながら、なかば歴史家であり、なかば討論家であ
り、時には、著述兼歴史の教師であり、時には、政府への助言者もしくは公共の問題や危機に
関する討論の参加者であった。
さらには、再度駐ソ大使を務めるが、ソ連を批判した発言を問題視され、国外退去を命じられ
る。
その後、BBCから招請があり「リース講義」を行い、ユーゴスラビア大使とつとめた後、
外交官を引退し、再び長い学究生活に入った。

ジョージ・F・ケナン (1904年2月16日 – 2005年3月17日)
ケナンが国務省を去る頃、朝鮮戦争が勃発した時期であり、ケナンは学究生活に入るために準
備をしていたが、国務省の同僚から、ワシントンにロシアに精通した人物がいないから、ワシ
ントンに戻ってきてくれないか、として、役割は比較的小さいなものであったが、ケナンは一
時的にワシントンに戻ることになる。
「私が求められているのは、われわれが陥っている軍事的窮地からの、
一つの脱出策としてのロシアとの直接交渉に関する見通しについての意見であった」(本書)
「マッカーサーの部隊が一九五〇年に三十八度線を越えて進撃するのに反対して聴き入られな
かった後に、この馬鹿げた行為が予知しえた結果を生み出した軍事情勢を落ち着かせるため
に、ささやかな、しかし無視しえない役割を果たした」(本書)
そして、その時の教訓として、二つ指摘している。
第一は、国の政策を軍事的考慮だけで決めさせることの恐るべき危険性、
第二は、政治的な対立者、軍事的対立者の間においてさえ、国際外交の公然たる正式ルートの
陰にある、極秘の非公式な接触が、時には決定的な価値をもつということ。
さらに、ケナンは極東について総括し、アメリカ政府の極東に対する政策や認識について、批
判的に次のように述べている。
「アメリカの政治家たちはまた、センチメンタリストであった。
貧しいが高貴で、アメリカの庇護に感謝し、アメリカの美徳を崇拝していると見なされていた
中国は、彼らのお気に入りであった。
従って彼らのアメリカの政治家たちは、過去四十年間にわたって、日本の大陸における足場を
掘り崩すために一生懸命になって努力した。
日本がいなくなりさえすれば、情勢の支配者として中国がすわることになり、そうすればアメ
リカにとっては経済的浸透や貿易の機会拡大を容易にするものとかたくなに信じていたからで
ある。
その結果、日本を追い出すことは、ロシアを招きいれることだということを決して認めようと
はしなかった」(本書)
「まったくひとりよがりに、朝鮮における日本の地位を剥奪したために、戦後になってわれわ
れは、日本がこの半島において大陸の対立勢力―かつてはロシアであり、今度はロシア、中国
共産主義者の連合勢力―を封じ込めるため長い間担ってきた負担を、自ら肩代わりする事態に
直面することとなった」(本書)
その原因は、連合国を理想化させ、敵対者を非人間的な悪魔と思い込ませて、バランス・オブ・
パワー(力の均衡)を理解しなかったことであると。
当時のケナンは基本的には、アメリカ軍が大規模に海外に駐留することに対して批判的であ
り、在日アメリカ軍についても、メモに次のように書いている。
「われわれは無期限に、自分たちの力を主要な手段として、巧みに日本をソビエトの圧力に対
抗させ続けることはできない。
このための唯一適切なる“主要な手段”は長い目で見て啓発された日本人の利己心であり、日本
政府がそれを行動に移し変えることであろう。
もしわれわれが日本に兵力を維持することを固執しつづけるならば、日本におけるこれらの兵
力の強化は、不可避的に政治的争いの一つの核心となると同時に、それを共産主義者が徹頭徹
尾利用することになろう」(本書)
ただ、本書を執筆している時点では、それは誇張である、として、日本との軍事同盟を評価し
ている。しかし、負の側面もあり、
「われわれの軍事的存在は、日本における世論の分極化に、とりわけ若者を穏健で民主的な政
治制度からきわめて重大な形で遠ざけるのに大きな役割を演じた」(本書)
と、苦言を呈している。
当時の中国は、共産主義が大陸で勝利をおさめてからまだ二、三年しかたっていなかったが、
ケナンは中国についても、私は中国における二つの政権のいずれも好きではない、
として鋭く分析したメモを書いている。
第一に、私は中国を偉大で強力な国とは見なしていない。その工業力は真の大国のどれと比べ
てもきわめて小さい・・・
第二に、たとえ現在の政治的反目が克服されたとしても、米中間のより緊密な関係から何かよ
いことが生まれるとは期待していない。
ケナンがこのような見解に傾いたのは、中国の国際関係史や中国のナショナリズムと経国の才
の伝統について学んだことであり、さらに三つのことを論理的に明らかだ、としてあげてい
る。
「まず中国人は民族として非常な外国嫌いで尊大であった。
中国をもって“中華”とする考えに基づいた彼らの、外国人およびその世界に対する態度、外国
人を野蛮人とするその見方は、本質的に他民族に対して礼を欠き、きわめてよそよそしい関係
は別として、満足すべき国際関係の基礎を提供するものではなかった。
二番目に、中国人は通常その対外的行動は高度に洗練されているにもかかわらず、だまされた
と思い込んだ時には途方もなく無慈悲になりうることが明白であった。
・・・私には、彼らが西洋的―キリスト教的心情の二つの属性に欠けているように思われる。
それは憐れみの心情と罪の意識である。
三番目に、中国人はしばしば文書によらない実際的取り決めをする。
しかし普通これらの取り決めは、そうする方が彼らの目的にかなうとなれば意のままにくつが
えしうるようなものなのである。
その反面、彼らは決して原則的な事柄について譲歩する用意を示さない・・・
最後に、ここ何十年にもわたり中国人が、彼らとなんらかの関係にあったアメリカ人―とくに
長期間中国に居住していたアメリカ人の大半を堕落させたその手腕と、それに成功した事実を
見て、私は全く驚いた」(本書)
「私は、中国の国連参加について、もし他の国が欲する場合それを妨害することには反対であ
るが、以上の理由からして合衆国と中国との間に正式な二国間の外交関係を結ぶことには賛成
しなかった。私としては、アメリカ外交官が北京でその使命を首尾よく果たすのに必要な配慮
をもって所遇されるという保証を見出しえないのである」(本書)
その後ケナンは、プリンストンに戻り束の間の学究生活を送るのだが、ケナンが考えていたこ
とはソ連についてであった。
「もしも、暴力によって自由をおしつけていくのではなく、専制が腐食していくことにより、
ロシアに自由がもたらされるというのが運命の意思であるならば、われわれの政策はそれを支
持するものであり、またわれわれは予見や性急さ、あるいは絶望感をもってそれを妨げてはな
らないということができるであろう。
これらの点こそが、政府の仕事を離れてから最初の一年半の間、私の念頭にあったアメリカの
対ソ政策に関する不安であり、期待と確信なのであった」(本書)
そして、モスクワ駐在アメリカ大使として、再度モスクワに赴任することになる。
「前回ロシアに在勤した数年間と比較して、とりわけ二つの変化が強く感じられた。
その一つは、革命政権の掲げる表向きの目的に対し、民衆の内的な無関心が増大していること
であった―民衆を服従させている人たちのイデオロギー的発想に対して、奇妙にも関心が欠け
ていた。
第二は、ソビエト社会において、社会的にも官僚制度の上でも、階層形成の速度と硬直性が増
大していたことである」(本書)
しかしソ連側から、好ましからざる人物、として追放されてしまう。
ケナンもこの頃、大使という職業に急速に冷めていて、追放されたことに喜びを感じていた。
追放されてからは、CIA内の役職を引き受けて欲しい、などの誘いを受けるが、それも断り、
再びプリンストンでの学究生活に戻ることになる。
そして、この頃に“マッカーシズム”(赤狩り)がアメリカ国内で吹き荒れることになるのだが、
ケナンは批判的に次のように指摘している。
「当時は、あらゆる場所で、名声は攻撃され、傷つけられ、ブラックリストがつくられてい
た。無実の人が当然資格のある職場から解任され、あるいはその職場に就くことを拒否されよ
うとしていた。
ふだんなら人情も良識もわきまえた善良な市民が、図書の追放や、共産主義者の影響の証拠を
求めて、教科書の検閲に忙殺されていた。
教授団の記録は、過去における異端の説の兆候を熱狂的にさがす連中の手によってしらみつぶ
しに点検されていた。
「共産主義者の陰謀」の陰険な手先、あるいは無意識の同調者と疑われた人々が、講壇に立つ
のを拒否するようにするために、容赦ない努力がなされた。
何千という善良な人々が、さまざまな方法で、また新聞の多くもそうであったが、この残酷な
熱狂の中に身を委ねていたのである。
そしてこのような集団的ヒステリーの運動の常だが、先頭に立っていたのは、相手側からの自
称転向者、恐れられているものからの改宗者、悪魔と親しかったために悪魔の手口を知ってい
ると称するもの―この場合は、いわゆる転向し、悔い改めた元共産主義者―だった」(本書)
ただ、一九三〇年代の終わりに、米政府部内に浸透していたことは、でっち上げたことではな
く、共産主義の浸透はたしかに存在していた、その程度は、圧倒的とは言えないまでも、決し
て軽視できるものでもなかった、と指摘している。
そしてその後は、BBCからロンドンで講義して欲しい、と招請を受け、これを受諾して全六回
の「リース講義」を行うことになる。
さらには、ケネディ大統領から、ポーランドかユーゴスラビアの駐在大使を引き受けてくれな
いか、と申し出があり、ユーゴスラビア駐在大使を受け入れることになる。
そこでは、チトー大統領やユーゴスラビアの政府関係者などと良好な関係を築いていたが、本
国に対して無力なことを痛感し、プリンストンでの学究生活に戻りたいむねを国務省に通告し
て、冷戦初期からアメリカ外交を牽引してきたケナンだが、外交官を引退することになる。
以上までが、全Ⅲ巻におよぶ『ジョージ・F・ケナン回顧録』。
やはり、ピューリツァー賞と全米図書賞を受賞した、第一部(Ⅰ巻とⅡ巻)が読みごたえがあ
り、時間が無い人は、Ⅰ巻とⅡ巻だけでも十分に参考になる。
今現在まで続く国際秩序の形成過程もよく理解できるし、アメリカのいい加減さもケナンを通
して理解できるし、ケナンの紳士で律儀な姿勢にも感銘を覚える。
最近では「新冷戦」という言葉も聞こえてくるが、アメリカは同じ事を繰り返しているにすぎ
ない、ということも理解できるし、この先もそう思われる。
ただ、ケナンが提唱した「封じ込め」政策は軍事的なものではなく、政治的封じ込めを主張し
たものであり(マーシャル・プランなど)、ソ連との冷戦で軍事的に硬直化した状況には危機感
を抱き、懸念していた。特に核兵器については晩年まで考えをめぐらしていた。
「封じ込め」という言葉が、誤解されひとり歩きしていることについても不満を覚えていた。
本書はアメリカ外交史を理解する上での必読書とされている。
外交官は、ただ単に、外部世界の出来事を―意思決定の素材として―対外政策の神経中枢に報
告するための目や耳であるだけではない。
彼らは、神経中枢から発せられる指令が言葉や行動に移されるときの口や手でもある。
外交官は駐在国の国民およびとくに世論の代弁者と政治指導者に、自国の展開する対外政策を
理解させなければならないし、できることならそれに賛成してもらわなければならない。
対外政策を「売り込む」というこの仕事のためには、外交官の個人的な魅力、および外国人の
心理についての彼の理解力、といったものが必要不可欠の条件となるのである。
【その他のジョージ・ケナン関連の記事】
・ 人間はひび割れた器 / 『二十世紀を生きて – ある個人と政治の哲学』


