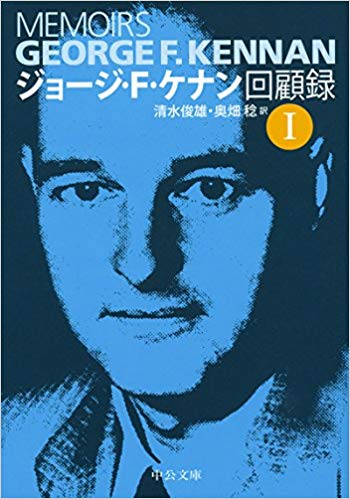
少年時代のことをはっきりと記憶している能力は、人によって大きな違いがあることはいうま
でもない。私自身、その記憶の残像がいまは薄れかかっているのではないかとおそれている。
そればかりか、このあわただしく変動する時代にあっては、あらゆる老人が、
変化のテンポが今日ほど急でなかった時代と比べて、その少年時代、
青年時代からいっそう遠くおし隔てられてしまった思いを等しくするのではあるまいか―
人口の爆発的な増加と技術的変革によって急速に進められた環境の破壊が、
過去の記憶の生々しさを傷つけてしまったのであるまいか―と疑わざるをえない。
『ジョージ・F・ケナン回顧録 I』ジョージ・F・ケナン
「まことに、人生の道をたどるのは、あたかも暗い森の中を提灯をもって通るようなものであ
る」とも書いている(原著では「提灯」と書かれているかは疑問が付くが)、二十世紀アメリカ
を代表する外交官であるジョージ・F・ケナンの回顧録(MEMOIRS)。
この回顧録は出版以来、第二次世界大戦後のアメリカ外交史やアメリカ外交論を理解する上で
の必読書としての地位を保っている、とされている。第一部は一九五八年にピューリツァー賞
と全米図書賞を受賞している。
原著では上巻下巻という構成になっているが、日本語版では3巻にまとめており、ⅠとⅡが上
巻にあたり、Ⅲが下巻にあたる構成になっている。

ジョージ・F・ケナン (1904年2月16日 – 2005年3月17日)
ケナンといえば、一九四七年七月『フォーリン・アフェアーズ』誌に、Xの匿名で書いた一文
「ソビエトの行動の源泉」、いわゆる「X―論文」で有名だが、本書(Ⅰ巻)では、その「X―論
文」に至るまでの、少年時代の薄れていく記憶から対独戦終結までが収録されている。
それはソ連(ロシア)に対して、どのように関わりをもったのか、「X―論文」の結論に如何に
して辿りついたのか、などが窺いしれる。
ちなみに当ブログでも、ケナンが八十九歳(一九九三年)の晩年の時に出版された『二十世紀を
生きて―ある個人と政治の哲学』を取り上げた。(ぼくの力量不足だったことも承知している)
ケナンは、一九〇四年二月十六日にアメリカのウィスコンシン州ミルウォーキーに生まれた。
母親はケナンを産んだあとにすぐに亡くなってしまう。このことが深いショックを受け、
生涯の傷痕になっていたと、思い込んでいたとして、後年になって知ったいくつかの状況証拠
に裏づけられた理性的な推論でこの結論に至り、思い出の中から引き出されたものではないと
している。
独特の言い回しなので理解しづらいのだが、この少年時代に感じていた悲哀みたいなものが、
ケナンの人間形成に大きな影響を与え、「人間はひび割れた器」だという認識に至った一つの
要因だったと、個人的には思っている。
父方の祖先は、十八世紀初頭に北アイルランドから一家をあげてアメリカに移住してきて、
開拓農民として一筋に生きてきたという。
ただ、その中から牧師になった者、独立戦争中に陸軍大佐の階級にまで昇進し、バーモント州
の代表議員としても選出された者もいる。ケナンの父は、その男らの中で初めて大学教育を受
けたという。その妻たちもまた開拓農民の血筋をもつものであり、皆、自主独立を求めてやま
ない情熱だけは強く持っていた。
そんな一家は浮世離れした状況だったので、後年に一世を風靡したマルクス主義に対して、
ケナンは次のように述べている。
「私は古典的マルクス主義がいうところの社会的貧困説―冷酷で腐敗した資本家と、踏みにじ
られ搾取されていても社会的に純正な労働者とが対立するというこの二分論法―を認めること
はどうしてもできなかった。マルクス主義者たちは、このような状況がどこにでも存在する現
実だと主張している。
しかしいくらかはそうした風潮や現実が確かに存在したことは否定できないが、私自身の経験
ないし家族の経験に照らして、私自身が説明できるようなことがらではなかった」(本書)
一族の中には、父のいとこであり六歳年長のもう一人のジョージ・ケナンがいて、ケナンは深い
きずなで奇妙な形でつながっている感じがするのであるとして、次のように書いている。
「同名ということを別にしても、私たちはくしくも誕生日まで同じである。
私たちは、二人ともその成人後の生涯の大部分をロシアとロシア問題に捧げた。
ところが、二人とも、その時代のロシア政府によって、それぞれ似かよった経歴を経た時に、
ロシアから追放されているし、二人ともロシアの専制政治からの亡命者を救済する団体をつく
っている。
二人とも執筆と講演には時間を惜しまなかったし、二人ともギターを弾き、よく似た構造の特
殊な帆船を所有し、愛好した。
また、二人とも晩年には全米芸術文学協会の会員になったし、二人とも日本および日本のアジ
ア大陸との地政学上の問題について、アメリカ国内での理解を深めるためにしばしば弁護の労
をとった」(本書)
ケナンは後に、陸軍士官学校からストレートにプリンストン大学へ入る。
プリンストン在学中は、恥ずかしがりやで、人にものを尋ねることができず、友達も少なく、
成績も悪かった。なので、人から認められることも少なかったという。
「私が自負できる何よりの財産といえば、明るく澄んだ知性―これは放っておかれればだらし
なく、引っ込み思案であるが、どうかして挑戦されれば、俄然活気づいてくる―であった。
また周囲の雰囲気と他人の思想の世界に対する鋭敏な感受性、あるいは知性の上では先入観を
絶対にもたないことなど、であった。
この知性は、当時の教育上の伝統からいえば、プリンストンが育成した精一杯のものであっ
た」(本書)
そのプリンストンでは、後日の心の準備をしてくれたが、大きな知的探究心は刺激してはくれ
なかった、卒業したばかりの頃は、ウィルソン流のリベラリズムの受け売りをしていたとも書
いている。そして、そのプリンストンを卒業すると、ケナンは外交官になろうと決心する。
「私がこの外交官になろうと決心した主な動機は、私の記憶に間違いないとすれば、
外に何を志望してよいかわからなかったからというにつきたと思う。大学時代の後期に、私は
国際政治の研究に熱中し、成績もよかった。
ミルウォーキーには何の未練もなかった。私はどういう職業にせよ、職業の型にはまるのがい
やで、外交官ならそれから逃れるだろうと考えた」(本書)
ケナンは幼い頃に父に随ってドイツに赴き、約一年ドイツの学校で学んだことがある。
外交官研修を終えると、ジュネーブ総領事館付として派遣される。
その後、外交官研修所の教官に、中国語、日本語、アラビア語、あるいはロシア語などの稀少
の語学の一つの専門家になる訓練を受ける気があるなら、ヨーロッパの大学で三年間の大学院
過程の勉強ができる、しかも外交官を辞職することなしに―などの誘いを受け、ケナンはロシ
ア語を選んだ。その理由は、当時アメリカはソ連と全く国交がなく、いつの日か、ソ連の言葉
を知っている人が任務につく機会がきっとあるだろう、と考えたことと、老ジョージ・ケナンを
意識したことが関係してロシア語を選んだという。
そして、ロシア語専攻生としての訓練を受けるために、ベルリンやタリン、リガなどのバルト
海沿岸諸国の首都で、ロシア語は勿論のことソ連の経済情勢などを分析して過ごし(このベルリ
ン滞在時に妻と出会う)、五年半たって、初めて正式にモスクワ在勤を命ぜられることになる。
リガ滞在時には、初めてアメリカの政策立案工作に少しだが参画し、ソビエト政府“承認”問題
がアメリカの新政権(フランクリン・ルーズベルト)によって検討されることがわかっていたの
で、ソビエト政府が過去数年間に他国政府との間に締結した通商条約について検討した。
調査結果は長文の報告書にまとめ、一九三三年四月、ワシントンに送っている。
その分析した報告書の中では、外国人はロシアの裁判所で経済スパイとして処刑されかねな
い、などの問題点を指摘した内容となっており、ワシントンの注意を喚起するために送られた
ものであった。
「ところが、一九三三年十一月、ワシントンで行われたリトビノフ外相との交渉妥結の直後、
新聞をひろげてみて、私は驚いてしまった。
アメリカがソビエトを承認する前提条件として、リトビノフに調印を承知させた保証条件の中
に、例の問題の条文が一字も変えられないで出てきたからだ。
その意味するものは明白であった。
ソビエト政府が他の場合にも同じ条文のものに調印していることを国務省に教えられ、
またその条文そのものは技術的、表面的なものらしいと見てとったルーズベルト大統領が、私
たちに心配無用といわんばかりに、その条文を文句なく受け入れてリトビノフに改めて調印さ
せたものとしか考えようがなかった」(本書)
この頃のアメリカでは(ルーズベルトが大統領となった時期)、共産主義者が工作を仕掛けてい
たことははっきりしていた、と第31代アメリカ大統領だったハーバート・フーバーはその著
『裏切られた自由』の中で書いている。
それを示す二つの大きな事件があり、一つは、一九三二年の「ボーナス行進」と呼ばれるデモ
であり、もう一つは、モスクワで作られた偽ドル札のバラマキであり、偽札は共産主義の活動
のために使用されていた。ルーズベルトはそのことを知っていた。
だが、大統領就任からわずか八ヵ月後の一九三三年十月十日、ルーズベルトは全連邦中央執行
委員会議長のミハイル・カリーニンにメッセージを送り、ソビエトに特使派遣を促し、ワシント
ンで国交を(アメリカによるソビエト承認)協議を求めている。
そのメッセージを受けた後に、ソビエトは外務人民委員のマキシム・リトビノフを特使として派
遣すると回答した。
一九三三年十一月十六日、リトビノフは国家承認の条件として次のソビエトの方針(約束)を提
示した。
・アメリカ合衆国の内政には一切関与しない
・アメリカ合衆国の平穏、繁栄、秩序、安全を傷つける行為やアジテーション、プロパガンダを
一切しない、そしてさせない。
・アメリカ合衆国の領土および所有する権利を侵したり、政治的変化をもたらした社会秩序を乱
すような行為はしないし、させない。
・アメリカ政府を転覆させたり、社会秩序を混乱させる目的を持つ団体や組織を作るようなこと
はしない。
これに加えて世界各国に対しても平和的態度を取ることも表明し、
当時の国務長官だったコーデル・ハルはすぐさまこの声明を賞賛したという。
ただ、リトビノフはその後にアメリカ共産党幹部とニューヨークで会談し、自分が署名した文
書は、ソビエト政府だけを拘束するものであり、アメリカ共産党を束縛しないものだと説明
し、次のように語っている。
「心配無用だ。あんな調印文書は紙切れ同然だ。ソビエトとアメリカの外交関係の現実の中で
すぐに忘れられる」
その国家承認したことについて、フーバーは次のように書いている。
「我が国がソビエトを承認したことは、国家としての信頼性のお墨付きを世界各国に与えたよ
うなものだった。
我が国の決定に他の国々も追随した。(共産主義者の)陰謀を抑えていた蓋がこうして開いた。
そして、その結果がもたらした状況に世界はいまでも苦しんでいる」(『裏切られた自由』)
承認前のアメリカ共産党員の数はおよそ一万三〇〇〇であったが、承認後には八万を超えてい
る(FBIの調査によれば)。
その結果、共産党はアメリカ人メンバーを政府の重要機関の職員に就かせ、国家安全保障に関
わる情報にアクセスできるようになり、国家の重要な意思決定に大きな影響を与えることにな
った、ともフーバーは指摘している。
ケナンに話を戻すと、ケナンもこの国家承認について次のように書いている。
「彼らはこの交渉で、アメリカ側の代表が用心深く、玄人であって、ソビエト側の術策も甲斐
なく、リトビノフに空手で引き揚げてゆかざるを得なくさせた、といった印象をうまく作り上
げたのである。
このエピソードは、アメリカ政治家気質最も本質的で抜きがたい特徴の一つを物語るものであ
り、私が外交官生活を通じて学ばねばならなかった多くの教訓の最初のものとして私の胸にい
までも残っている。
この政治家気質の特徴は、その神経質なまでの自意識と、内向性にあり、彼らが声明を出し、
行動を決める場合にも、表面上の対象となっている国際問題に対する効果が狙いではなく、
アメリカの世論、議会筋の見解に及ぼす効果の方を最初に、そして第一義的に考慮しようとし
ているのである」(本書)
さらに、次のようにソビエト国家承認に対しての自身の考えを総括している。
「―米ソ関係の確立が、果たして侵略的な日独両国の政略を一時的にせよ抑制する効果があっ
たかどうか―私にはわからない。
ある面ではきわめて現実主義的であるが、同時に熱烈な政治的幻想の持ち主であったソビエト
の指導者たちは、米ソ関係確立があげるはずの効果を確かに期待していたらしい。
私自身は、当時は懐疑的であった。
ソビエト連邦が、わが国にとってふさわしい同盟国、提携国―現実にも潜在的にも―であると
私は絶対に―その当時も、あるいはその後のいかなる時にも―思ったことはなかった。
われわれが、われわれ自身の力を開発し動員しても守ろうとするきにならない目的に、ソビエ
トの力を当てにしようとする考えは、私にはとくに危険なものに思われた」(本書)
ちなみにこの頃に、日本近代史上最も危険な革命思想家であった北一輝も、
「敵とすべきはアメリカではなくソヴィエト・ロシアだ、日本国内に「共産者ノ蔓延」が生じて
いるのも日本がソ連邦を承認した過ちの結果にほかならない」
と書いている。
そして、このソ連との外交関係が開かれた直後の数年間、ケナンはロシアで過ごすことにな
る。秘書兼通訳として。
しかし、赴任した年の暮れの十二月に、共産党指導者の最有力者の一人であり、スターリンの
後継者として最有候補であった、セルゲイ・キーロフの暗殺事件がレニングラードで勃発する。
ケナンはこの事件に対して、外交舞台の空気を一変させるような事件、近代ロシア史の運命的
な転換点となった、として次のように述べている。
「ともあれ、キーロフ暗殺事件前後の空気が、一九三〇年代の一大粛清事件の幕明けとなった
のは確実である。
この事件とともに、猜疑と暴力、忌まわしい何者ともわからないテロ行為とやたら滅法の非難
告発のやりあい、そういったものが暗い雲のようにモスクワの空を覆い、やがて数か月後に、
全面的な粛清事件が広がり、一九五三年のスターリンの死まで、モスクワは、多少の変化はあ
ったにせよ、暗い日々が続いた」(本書)
この事件以来、モスクワの外交界の空気は悪くなり、ソ連とアメリカの関係の蜜月時代は、
ちょっとの兆しを見せただけで終わってしまった、とも述べている。
「彼らは人間性の貴さなどまるで無視し、残酷を売り物にし、無過失を誇り、日和見主義的で
節操もなく、手段を取り替え、暗い秘密主義を守り、そして何よりも、高い精神に裏づけされ
たイデオロギー上の信念という仮面の裏に、いつでも彼らは権力欲を隠しもっていた。
それを私は嫌悪しないではいられなかったのである。
こうした見解をもっていたので、一九三〇年代の中葉にも、私は誤った願望や幻想など抱くこ
となく、恐怖の頂点にあったスターリン主義をめぐって現出される事態を一層身近く観察する
ことができた」(本書)
それは決して忘れられないものであり、この印象が政治的判断にも響き、ワシントンの公式見
解と疎隔をきたすことになった、としている。
そしてこの頃に、米ソ二国関係の長期的展開について、経済面、文化面、政治面などから独自
に研究し、米ソ関係の将来は、誤解、失望、そして双方の側での罪のなすり合いの他に、何の
希望ももてないであろう、という結論にいたる。
「三十年後の現在でも、この見通しが悲観的すぎたとは考えられない。
しかし、いまならわかるように、それはまたもや、ルーズベルトのもっていた見解とははるか
に隔たったものであり、とくに大統領が米ソ政策顧問として選ぶことになった人々の見解から
も、はるかに隔たったものであった」(本書)
その隔たりは、国務省東欧局(ソ連外交史について、ソ連外務省よりも立派な記録を揃えてい
た)に対してもあらわれており、東欧局は、ソ連に対して厳しく批判的な見解をもち、クレムリ
ンに対して断固たる態度をとるべきだ、としていたが、突如として東欧局は取り払われ、機能
を西欧局に移されることになってしまう。
さらには、充実したソ連関係の文庫は議会図書館に移管され、広範な図書の中に分散してファ
イルされ、文庫としての存在が消滅してしまう。
ケナンはその時の状況を次のように書いている。
「ホワイトハウスから圧力がかかったという確かな証拠もあった。
後日、私が驚いたのは、五〇年代初期のマッカーシー一味や右翼の連中がこの事件をどうして
嗅ぎつけて、利用しなかったのか、ということだった。
というのは、この事件にはソビエトの手、あるいは親ソビエト派の手が政府の最後部に伸びて
いた気配があったからである。
いずれにせよ、ロシア局は廃止されてしまった―アメリカの行政措置よりもむしろソビエト政
治の特徴に近い唐突なやり方で―」(本書)
その後ケナンは、プラハやベルリンで報告官として勤務、さらには、ポルトガルに赴き公使館
付法務官の任務、非公式にはスパイなどの混乱をうまく調整する仕事の責任を持つようにな
り、ポルトガル勤務を解かれた後は、ロンドン大使館参事官の身分で、新設されたばかりのヨ
ーロッパ諮問委員会のアメリカ代表の大使の政治顧問を務める。
そして、モスクワ大使館付の公使兼任参事官として再度モスクワに勤務することになる。
「私がのちに大使としてモスクワに勤務した期間を除いて、この戦争末期のロシアに戻って来
た当初の数週間ほど、ソビエト当局による外交団隔離政策が重くのしかかり、私の思想に深く
影響を与えたことはなかった、ということをはっきり言っておきたい」(本書)
この時に、ケナンはあるロシア人の友人と、ソ連のイデオロギーや独裁制下の思想などについ
て会話しているが、そのロシア人の友人が面白いことを次のように言っている
「われわれは、いまのところたいへんうまい具合にやっています。
外国の世論に注意を奪われることが少なければ、もっとうまくやれるでしょう。
ロシア人について、あなた方に是非知っておいていただきたいことがあります。
ロシア人は、もの事が万事うまくいっていれば、それだけ尊大になるのです。
われわれが、おとなしく、優しく、融和的になる時は、われわれが難儀にぶつかっている時だ
けなのです。われわれがうまくやっている時には、好きなようにやらしておいて下さい」
この頃のケナンは、カチンの森やポーランド問題にも分析して言及していたが、国際連合機構
設立についても否定的に指摘している。
「ちょうど私がロシアに再赴任する時に、アメリカ政府がイギリスとともに、平和と安全保障
のための将来の国際機構設立の準備会談に、用心深く躊躇するソビエト政府の参加を懸命に勧
誘していることを知った。
私はこんな調子でソビエトを勧誘するのは、利口なやり方ではないし、うまくないと思った
(中略)
こんなことをやれば、ソビエト側に自分の立場の強さへの自信を一層固めさせ、
われわれが欲しがっているその協力の売値のかけ引きを、一層厳しく貪欲なものとするばかり
であろう。
しかしこうした配慮のどれ一つも、当時、ワシントンの私の上官たちの頭の中にはなかった」
(本書)
さらにこの時に、アメリカ政府の戦後世界形成に対する計画が間違っている、と決定的にな
る。
「対ソ政策ばかりか、全般的な戦後世界形成に対するわが国の計画と公約が、
ソビエト指導部の個性、意思、政治情勢についての、危険なまでの読み誤りを土台としたもの
であることを知ったのは、この時であった」(本書)
それは「七年後のロシア」と題する三十五ページの論文となり、本書の付録として収録されて
いる。この「七年後のロシア」論文から二年後に書かれたのが「X-論文」である。
そして、ヨーロッパで戦争が終結し、ソビエト外交に一つの歴史的な転換点を画した、として
次のように書いている。
「ソビエト連邦の国際的地位は、ソビエト軍のヨーロッパ中心地への進駐によって生じたソビ
エト勢力圏の急激な拡大にともない、基本的に変化していた。
ロシアの西部国境沿いに防衛的緩衛地帯を確保したいというスターリンの夢は、ここに、これ
以上望めないほど大きく、いやこれ以上満足できないほどに大きく、実現された」(本書)
ヨーロッパ戦争終結以後の数日後にケナンは、頭に浮かんだことを文章にしておこうと思い、
「対独戦終結時におけるロシアの国際的地位」と題する未発表の一文を書く。
これも本書の付録として収録されたいる。
この論文は、後に「衛星国地域」と呼ばれることになる地帯の問題を対象にしている。
そして、この頃のソビエトのマルクス主義は時代遅れの教義あり、残っているのは、防衛と帝
国主義的拡大を目ざす愛国主義と民族主義的感情をあおりたてる力だけである、とも結論す
る。さらには、今までのアメリカのソ連に対しての政策が間違いであった、として次のように
総括している。
「とくにソビエトの指導者たちは、アメリカの世論が、次のようなことを信じるように教え込
まれていることを承知していた。
それは何かというと、アメリカとソビエト連邦との密接な協力は可能であり、必要であり、
もし両国間にこのような協力がなければ、今後も戦争が不可避である。
従ってその協力を得るためには、ロシア側指導者とは友好と信頼に基づいた正しい個人的関係
を結ばなければならない。
そうすれば、もしごたごたが起きたとしても、それは西側の政治家がしっかりやらなかったた
め、ということになるのであった。
(中略)
大国間の安全を確保するために実際に必要とされたものは、「大国間に現実的な力の均衡と重
大利害をもつ占領地域相互間の現実的な理解を保持すること」であった。
こんなことはロシア人だって承知していた。
しかしアメリカ人の持っていたこれらの先入観が、当然のこととして、ソビエト側の利益とつ
ながっていた。しかもアメリカ人はなお引き続いて、まんまと利用されていたのである。
大西洋憲章の素晴らしい宣言におよそ反するような、東ヨーロッパにおけるソビエト帝国の維
持に、西側とくにアメリカが道義的、物質的な支持を与えるよう誘い込むことができると、
ソビエトの指導者が望みを抱いたのは、以上のような根拠からであった」(本書)
そしてケナンは、ドイツとの戦争終結時点での、ロシアの国際的な地位についても総括する。
それを三つにまとめている。
(1) ロシア人は、彼らの権力構造に内在する理由から、彼らが東ヨーロッパで支配下におさめ
た全地域に対する支配権(ヘゲモニー)を、西側からその支配に対して祝福と援助を受けない限
り、立派に維持することはできないだろう。
西側からこの援助がなければ、彼らの政治的地位はある程度後退するのもやむえないだろう。
(2) わが国民衆が期待するよう教えられてきた、ロシアとの度の過ぎた協力などは、全く世界
の平和確保に必須なものではなかった―権力の合理的な均衡と勢力圏に関する了解などはトリ
ックにすぎない。
(3) ヨーロッパにこれ以上の軍隊の進駐を図る理由は、モスクワに少しもない。
西側にとって危険なものは、ロシアの侵略ではなく、西側諸国内の共産党であり、さらには西
側民衆が抱くよう教えられてきた偽りの希望と恐怖であった。
三つの命題の中に、二年後に発表される「X-論文」の中で指摘している「封じ込め理論」の基
本的要因を探し出すのを誤ることはないであろう、としている。
この結論に至ったのには、一九四七年に不安感と幻滅感が初めて襲ってきた時ではなく、モス
クワでの戦時下の勤務からの印象や、連合国の勝利の直後、有利な時点からソビエトと西側と
の関係の不安な将来を観察した努力などの間から生まれた見解であったことを知ってもらいた
い、とも書いている。
この意見を当時の駐ソ米国大使だったハリマンに提出したところ、何の意見も書き込まれずに
返されたという。
そして、ここで『ジョージ・F・ケナン回顧録 I』が綴じられている。
以上が、ぼくの目に留まった箇所である。
この頃からケナンは、法律主義的・道徳主義的アプローチ、国内世論(大衆)に阿る政治家などに
対して、批判をしているのも印象に残る。
アメリカは外交が苦手であり、本書を読んでいて今現在の国際情勢と重なり、同じ事を繰り返
していると思うのは気のせいだろうか、とも感じた。
本書の中での「ソ連」を「中国」と変更しても違和感なく読めてしまう。
国際政治社会は有機的なものであって、機械的なものではない。その本質は変化にある。
国際社会を規制するシステムが、長期にわたって機能するためには、関係するいろいろの国々
の利益と権力に、常に生じつつある変化に順応できる柔軟さと敏感さを持ったものでなければ
ならない。
『ジョージ・F・ケナン回顧録 I』ジョージ・F・ケナン
【その他のジョージ・ケナン関連の記事】
・ 人間はひび割れた器 / 『二十世紀を生きて – ある個人と政治の哲学』


