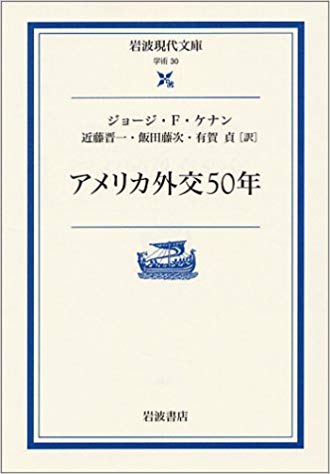
おそらく、今世紀の最初の五〇年間のアメリカ外交も、また一九五〇年以来の個々の対応を超
えた、より根本的な現実を反映している。
その現実とは、軍事的な力を政治的政策に関連づけるための、一般的に受け入れられ、長続き
するような理念の欠如であり、他国との関係において、現実的でそして切実な必要となってい
る成果を達成することよりも、むしろわれわれ自身についての自己満足的イメージを増幅させ
るために、他の国々に対する政策を形成しようとする相変わらずの傾向である。
多分この本はこれらの二つのわれわれの国民的な欠陥を意識させるという目的に役立つのでは
なかろうか。
『アメリカ外交50年』ジョージ・F・ケナン
ケナンの著作の中で最も読まれているのが本書であり、出版されてからアメリカ国内の多くの
大学で、アメリカ外交史、国際関係全般に関する科目の副読本として広く用いられているとい
われている。ケナン自身も次のように語っている。
「たまたまそうなるように運命づけられていたのではあろうが、
これまでに書いたどれよりもその売れ行きが長続きしているのである。
少なくとも二十年以上も、厚表紙(ハードカバー)のものと普及版(ペーパーバック)で次々に版
を重ねてきており、べらぼうとは言えないまでも少なからぬ印税が年々転がり込んでいる。
驚きあきれている著者にとって、これは嬉しいことに違いないが、また面くらってもいる・・・」
(『ジョージ・F・ケナン回顧録 Ⅲ』)
学究者としての生涯の、本当の意味での始まりであった、とも述べ、記念すべき一冊となって
いる。本書は全三部構成になっており、
本書のメインである第一部(六章)は、シカゴ講演(全六回)で扱った米西戦争から第二次世界大
戦までのアメリカ外交政策の形成過程を考察。
第二部は、『フォーリン・アフェアーズ』に掲載された「ソビエトの行動の源泉」(「X-論文」)
と「アメリカとロシアの将来」の二つの論文を収録。
第三部は、シカゴ講演を補う意味を持っているグリンネル大学で行われた講演、「ウォルグリ
ーン講演」と「アメリカ外交と軍部」が収められている。

(左) トルーマン大統領 (右から二番目) ジョージ・ケナン
本書のメインとして扱っているシカゴ講演というのは、ケナンが国務省の政策企画本部(ポリシ
ー・プランニング・スタッフ)の責任者として仕事をしていた時に(一九五〇年頃)、
シカゴ大学からチャールズ・B・ワルグリーン財団の後援下で毎年行われる一連の講義を、要請
されたのをきっかけとしている。
政府から離れ恩賜休暇にはいることになっていたので、ケナンはそれを気楽に引き受けた。
シカゴに行く時期が迫り、話すテーマをしぼる段階となって、アメリカ外交に関する未完成の
エッセーのテーマを基礎としながら、当時すでに到達していた結論のいくつかを説明できるよ
うに、アメリカ外交年譜の中の二、三のエピソードについて話をしようと決め、
三回分の講義内容と四回目に当てるノートを持ってシカゴへ向かった(六回の講義を予定してい
たが、残りの分は現地で仕上げられると考えていた)。
シカゴ大学での講義は、学生の娯楽室ともいうべき大きな、真四角の部屋で行われていたが、
講義が始まるにつれ参加者がかなりの数になり、数百人は収容できる大きな講堂へと移ったと
いう。
その全六回のシカゴ講演の内容は、
第一回の講演では、一八九八年の米西戦争を扱い、第二回の講演では、門戸解放政策を扱い、
第三回の講演では、一九〇〇年から一九五〇年までの、アメリカの中国と日本との関係を扱
い、第四回の講演では、アメリカの第一次世界大戦への参戦について扱い、第五回の講演で
は、第二次世界大戦を扱い、第六回の講演では、現代世界の外交を扱っている。
一貫してケナンが指摘しているのは、アメリカ人の現実感覚を欠いた「法律家的・道徳的アプロ
ーチ」で、他民族に関して判断を下してしまうこと。
もっと具体的に言えば、ユートピア的な期待にみち、その方法論に関する考え方において法律
尊重に偏し、他者に対しては道学者的な要求をおしつけ、高潔さと公正さについてはひとり自
分だけのものとしている点など。(ジョージ・F・ケナン回顧録 Ⅲ)
さらにそこに加えられるのが、盲目的愛国主義であり、戦争ヒステリーであり、領土拡張を正
当化し、膨張主義の原理を国民的使命として正当化する「明白なる運命」。
それが最もよく表れているのが、米西戦争と門戸解放政策(ジョン・ヘイ国務長官)の時期であろ
う(一八九八年~一八九九年)。
キューバの独立をめぐるスペインとの戦争に勝利し、スペインからフィリピン、グアム、プエ
ルトリコを奪い、キューバを保護国として独立させ、この戦争中にハワイも併合した。
その一方、中国に利権を得ていた列強諸国(日本、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、イタ
リア)の六カ国に対しては、「門戸解放政策(門戸解放・領土保全・機会均等)」を通告し、
中国との貿易はすべての国に開かれたものであり、独占は許されない。中国の領土は分割され
るようなことはあってはならない、と主張した。
それに対する列強諸国の反応は、熱心ではなかったのだが、国務長官のヘイは、列強諸国の中
国利権はアメリカの干渉によって阻止され挫折させられ、外交的勝利が達成された、
というような印象をつくりだし、アメリカの一般国民もこの印象を受け入れて拍手喝采した。
ケナンはこのエピソードを次のように指摘している。
「ヘイのこのようなやり口は、その後少なくとも半世紀の間もアメリカの外交的慣例を毒する
こととなり、また―私の見るところでは―まだ今後あと半世紀もなお弊害を及ぼしつづけるで
あろうところの、一つの先例をつくったのである」(本書)
その後に、義和団事件が起こり、この政策に幻滅感を抱くようになったみたいだが。
「アメリカの政治家の考え方は、道徳的ないし法律的原則の名において述べられあるいは主張
されたことはいかなることであれ、その原則が現状に適用し得るかどうか疑問であり、またこ
れを遵守した実際的影響が広範かつ徹底的なものであろうとも、その原則の主唱者にはなんら
特別の責任を負わせるものでないというのである。
われわれとして、忠告しようが、哀訴しようが、邪魔しようが、当惑させようが、それは全く
勝手だというのである。
もし他の国がわれわれのいうことを聞かなければ、われわれは、世界の世論の面前で、かれら
のぶざまな様子をあばくだけである。
他方、われわれの主張を容れたにしても、それはかれら自身の責任においてしたことであり、
われわれとして、その結果生ずる問題についてかれらを助けてやる義務はない。
―それはかれら自身処理すべき問題なのだ」(本書)
このような気持ちをもって、特に日本に対して嫌がらせをしたのである、とケナンは主張して
いる。
第一次世界大戦でヨーロッパ政治に介入を始めたアメリカだが、次のように指摘しているのも
印象的。
「勢力均衡の考慮は全面勝利に反対するものであった。
おそらくそれだからこそ、アメリカの国民は勢力均衡の主張を断乎として斥け、もっと徹底的
な仰々しい目的を追求したのであり、かかる目的を達成するために、全面勝利が絶対的に不可
欠であると、もっともらしく説くことができたのである。
いずれにせよ、ウィルソンの指導の下に、一連の考え方が育成された。
それは、戦争の徹底的遂行のためのわれわれの役割について、その理論的根拠と目標とを規定
した。その考え方は次のようなものである。
ドイツは反民主主義的であり、軍国主義的である。連合国は世界を民主主義にとって安全なも
のにする目的をもって戦っている。
われわれが希望するような平和を確立するために、プロシアの軍国主義は破壊されねばならな
い。その平和は旧い勢力均衡の上には築かれないだろう」(本書)
ブッシュの時にも、上述のパターンと同じように対テロ戦争を、自由を守る者と自由を憎む者
との戦いと位置づけていたのは、記憶に新しい。最近のペンス副大統領の演説も同様の論理だ
ろう。それらをヘンリー・キッシンジャーの言葉に直せば、
「民主主義の原理をひろめることを通じて平和を達成するのを主眼としている」
「アメリカの外交政策は、国内の原理すなわち万国共通の原理で、それを適用することがつね
に有益だという確信を反映している」
「アメリカでは、相手の信仰や信念を変えようとする精神が根付き、既成の機構やヒエラルキ
ーへの根深い不信がそれにともなっている」
とうことであろう。
新興の独立国として、移民の国として、脅迫観念のように発展しつづけることを求め、特別な
役割を担うには自分たちであるという強烈なイデオロギーをもちつづけ、第二次世界大戦以降
には世界の超大国として君臨し、理想主義とアメリカ例外論が陰の原動力となって新しい国際
秩序を築いたアメリカだが、その外交政策に対して批判的に論じられているのが本書。
実際にワシントンで勤務していた時に、政府の外交政策について疑問を感じたことが、
アメリカ外交史を調べる契機だったとしている。
ケナンはハッキリと書いてはいないが、一国の圧倒的優位の世界秩序ではなく、多様な勢力を
基盤にして、合意されたルールと限度に基づく国際秩序を理想としていたのではないのだろう
か。いわゆる「ウェストファリア体制」であり、力の均衡と安全保障を同一視し、力の行使に
あたっては抑制が安全をもたらすというもの。
なので「ウェストファリア体制」を最上位の国際秩序として評価しているキッシンジャーが、
「世界におけるアメリカの役割の議論をそれほどまでに煮詰めた外交官は、前代未聞だった」
と好意的にケナンを評しているのだろう。
いずれにしても、本書では米西戦争から説き起こし、現在まで続くアメリカの“悪い癖”を臆面
もなく指摘しているので、アメリカと付き合っていく上で参考になる。ただ訳が古臭い感じも
するが。
アメリカ人には奇妙な傾向があるように私には思われる。
すなわち、自分たちの目的や計画を妨げる複数の原因が存在しうることや、
それら諸々の原因には相互に関連はないかもしれないことを認めず、
むしろわれわれの禍いのすべての根源を、国外にある一つの邪悪な権力中枢に求めようとする
傾向である。
『アメリカ外交50年』ジョージ・F・ケナン
【その他のジョージ・ケナン関連の記事】
・ 人間はひび割れた器 / 『二十世紀を生きて – ある個人と政治の哲学』


